
JR渋谷駅と、京王井の頭線渋谷駅を結ぶ連絡通路にある、岡本太郎による『明日の神話』
米国の水爆実験で、第五福竜丸が被爆した際の水爆の炸裂の瞬間をモチーフに、核と人類をテーマに描かれた、縦5.5メートル、横30メートルという巨大壁画である。
力強い構図、インパクトのある色づかいが、いかにも岡本太郎らしい・・。
1967年にメキシコの企業家から依頼されたもので、翌年にメキシコ・シティーで開催されるオリンピックにむけて、建設が進められていた超高層ホテルのロビーに設置されるはずだったが、依頼者が倒産し、作品自体も行方不明に・・。
しかし、30年以上の歳月を経て、奇跡的に再発見され、2006年に再び公開された。

壁画のために制作した原画は5点まで確認されているそうだが、その中でも最初期に手がけられた1号原画と呼ばれる原画が、現在、広島市現代美術館で展示されている。
(カテゴリー/広島のオススメ!:「広島市現代美術館/比治山スカイウォーク」参照http://blog.goo.ne.jp/kinto1or8/e/4128888d8d250b5466027f3ce880b18e)
そのパンフレットによると・・

「画面中央には、原爆の白い閃光と炎に包まれ燃えさかる骸骨、空高く幾重にもたちのぼるキノコ雲」

「画面右下には、ビキニ環礁での水爆実験によって被爆した第五福竜丸とマグロが描かれています。」

「人類が経験した最大の惨劇ともいえる原水爆をテーマとしながら、惨状や苦しみを独自の表現で描くことによって、過去の惨劇に屈せず立ち上がり、明日へと神話を紡ぎだす人類の希望を表しているといえるでしょう。」
―とあるように、悲惨な体験を乗り越え、再生する人々のたくましさを描いたとされる。
2008年、複数の自治体での誘致運動の結果、「より多くの人の目に触れる場所に・・」というコトで、東京に設置されるコトになったが、作品テーマからすれば、名乗りを上げていた広島だろう・・と、個人的には、非常に楽しみにしていたのだが・・。
その今日的なイミ・・とゆーコトでは、震災や原発事故を経験した東日本にあるコトは、あるイミ、最もふさわしいのかもしれない。
行方不明だったこの作品が、このタイミングで再び日の目をの見るようになったコトも、今の日本のために用意されていたかのようでもある。

そういえば、この作品、ある芸術家集団が、福島原発を思わせる落書きのベニヤ板を付け加えたコトでも話題になった。
この芸術家集団、広島でも「ピカッ」という空中文字を描いて物議をかもした。
芸術家として、表現手段に工夫を凝らすのは当然だろう。
そこには余人の計り知れない深遠なテーマがあるのかもしれない。
・・が、なぜか、単に名を売って、目立ちたいだけのプロモーション的な活動に思えてしまう・・。
ちょうど、同じ時期に発売された「STEEL BALL RUN」単行本23巻の巻頭のコメントで、荒木飛呂彦がこんなコトを言っている。
(カテゴリー/マンガ・アニメ:「スティール・ボール・ラン」参照http://blog.goo.ne.jp/kinto1or8/e/235b80020b267745ae0828ba4eba23a8)
「最近、気になる事は「パフォーマンス」をする人たちの存在。その人たちの目的は『話題の中心になる事』が最大なので、本当にやりたい事の真実がいったい何なのか、わからない。その人たちは才能豊かなので色々な分野にまたがろうとして、ひとつの事を黙って極めようとしない。
芸能なのか政治なのか?救援活動なのかビジネスなのか?社会にとって非常に不気味な存在だと感じるし、相反する目的がひとつになるとは考えられない。」
―もちろん、この文章が、その芸術家集団を指したものであるかどうかは不明であるが、震災のあった仙台出身の荒木にとって、こうした「パフォーマンス」が『話題の中心になる事』が最大の目的に見えたとしても、ムリからぬコトではなかろうか・・?
”表現したいもの”を表現するのが、芸術のはずである。
だからといって、何をやってもいい・・とゆーワケではない・・。
ただ目立つため、人の目を引くため・・というだけに走ってしまったなら、もはや芸術とはいえないのではないか・・?
『明日の神話』には、そんなコトは全く意に介さないような、猛々しいまでのエネルギーに満ちているのではあるが・・。








































 「尋牛」
「尋牛」
 「見跡」
「見跡」
 「見牛」
「見牛」
 「得牛」
「得牛」
 「牧牛」
「牧牛」
 「騎牛帰家」
「騎牛帰家」
 「忘牛存人
「忘牛存人
 「人牛倶忘
「人牛倶忘
 「返本還源
「返本還源
 「入鄽垂手」
「入鄽垂手」











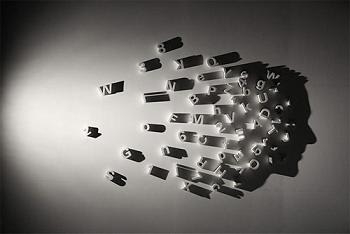











 」・・。
」・・。 )・・とゆーか、興味を持てそうなのが、このタロット占いである。
)・・とゆーか、興味を持てそうなのが、このタロット占いである。





