
「まことに小さな国が 開化期を迎えようとしている。
四国は伊予・松山に3人の男がいた。
この古い城下町に生まれた秋山真之は、日露戦争が起こるにあたって、勝利は不可能に近いといわれたバルチック艦隊を滅ぼすに至る作戦を立て、それを実施した。
その兄の秋山好古は、日本の騎兵を育成し、地上最強の騎兵といわれるコサック師団を破るという奇跡を遂げた。
もう1人は俳句・短歌といった日本の古い短詩形に新風を入れて、その中興の祖となった俳人・正岡子規である。
彼らは明治という時代人の体質で、前をのみ見つめながら歩く。
登っていく坂の上の青い天に、もし一駄の白い雲が輝いているとすれば、それのみを見つめて坂を上ってゆくであろう・・」
―という冒頭のナレーションではじまるNHKスペシャルドラマ、「坂の上の雲」第2部がスタートした。
封建の世から目覚めたばかりの日本が、そこを登ってさえ行けば、やがては手が届く・・と思い焦がれた欧米的近代国家というものを「坂の上の雲」に例えた”切なさ”と”憧憬”をこめたタイトルで、「雲」に例えたのは、やはり、つかむコトは出来ない・・とゆーコトであろうか・・?
原作も全8巻の長編歴史小説で、『竜馬がゆく』とならぶ、司馬遼太郎の代表作。
日本特有の精神と文化が、19世紀末の西洋文化に対し、どのような反応を示したかを、正面から問うた作品といえよう。
自分もずい分前に読んで、細かい内容は忘れてしまったが、ごく大まかなあらすじは、ナレーションの内容で事足りるだろう。
日清、日露戦争と大国を相手に戦い、勝利した頃の日本を舞台としているため、戦争賛美の内容になるおそれがあるとの思いから、生前、司馬は映画やドラマなど、いかなる二次使用も認めていなかったため、もちろん、初のドラマ化。
自身の戦争体験から、「どうして日本はこんな国になってしまったのか・・? 」という思いが歴史小説執筆の動機にもなっている司馬にとって、戦争を賛美するなど、もってのほかであろう。
」という思いが歴史小説執筆の動機にもなっている司馬にとって、戦争を賛美するなど、もってのほかであろう。
そこに描かれる明治の人間たちは、冷徹な目で現実を分析し、しかし、夢と希望をもって前向きに時代を生きた。
大国を相手に勝てたのは、そうした現実認識と、度重なる幸運があったからであり、当時の日本の国力で、総力戦・長期戦になったトコロで、絶対に勝ち目はない!・・という認識を、戦争をした当の政府も軍部ももっており、早い段階で有利な状況下をつくり、講和に持ち込む・・というのが、開戦と同時にあったシナリオだった。
しかし、その勝利によって、「日本は神国で絶対負けない!」、「神風が吹く!」・・という、おかしな熱病に国全体がおかされ、狂気のまま、太平洋戦争に突き進んでいってしまった・・。
まあ、「神国」、「神風」というのは、ちと行き過ぎかもしれないが、何らかの神の摂理でもあったかのような運勢が、この頃までの日本にあったのは間違いないようだ。
それは作戦参謀として日露戦争に参加した主人公・秋山真之の人生を見るコトで、なおいっそう、はっきりと見えてくる。
事実、真之はアメリカ留学中に米西戦争を観戦武官として視察、アメリカ海軍がキューバの港を船を自沈させて閉塞する作戦を見ており、この時の経験が日露戦争における旅順港の閉塞作戦に生かされたと言われる。
あたかも、幕末動乱の時代に、天が龍馬を遣わしたごとく、日露戦争を日本に勝利させるべく、秋山真之という青年を遣わした・・。
(もちろん、1人で戦争は出来ないので、その他多くの人々の力があったのは言うまでもないが・・ )
)
極東にまで、その支配力を及ぼそうとしていた欧米列強は、明治維新を経て、国際社会に躍り出た日本という国を、これを機に認めざるを得なくなった。
もし、日本がこの戦争に負けていたら、今、はたして「日本」という国は存在しているだろうか・・?
世界の果てにある、東洋の小さな島国が大国を破ったという事実は、アジア諸国にも勇気を与え、大きく影響を及ばしたコトだろう。
大東亜共栄圏は、そのリーダーシップのとり方を誤ったが、今も―特に、ここ最近のアジア情勢は、日本がリーダーシップをとり、正しい方向へ導くコトが求められていると思うのだが・・。
こう国内がまとまらないとねぇ・・。
このドラマを通して、この時代を見る時、少なからぬ”切なさ”と”憧憬”をもってしまうのである・・。


 !)・・という事実を語る最後のモノローグは、感動を新たにしてくれる。
!)・・という事実を語る最後のモノローグは、感動を新たにしてくれる。




















 」という思いが歴史小説執筆の動機にもなっている司馬にとって、戦争を賛美するなど、もってのほかであろう。
」という思いが歴史小説執筆の動機にもなっている司馬にとって、戦争を賛美するなど、もってのほかであろう。






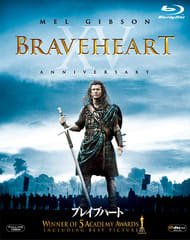








 」と、龍馬が一喝するシーンはしびれた・・。
」と、龍馬が一喝するシーンはしびれた・・。

 」
」


