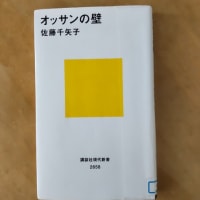近代社会の幕開けは、個人の自立から始まった。共同体のくびきを脱した市民社会が誕生した時、目的定立出来る自立した市民がその社会がその主体であった。
そこでは、もたれあい依存しあう生き方でなく、一人で自己決定する生き方が規範となっていた。ロビンソン・クルーソーこそ市民社会における市民の規範だった。
市民社会としていろいろな問題が起きてきた時、遅れてきた日本では、市民社会の成熟が足りないことが問われ、更なる市民としての自立が求められてきた。共同体の残滓を切り捨てないといけないと言われてきた。
マルクスはナロードニキとの交流を通じて共同体から社会主義への道があると思っていたようです(ザスーリッチ宛の手紙)が、レーニンはロシアが資本主義化しそのもっとも弱い環と捉え共同体の再生を顧みることはなかった。
しかし、今、資本主義が深化していく中で共同体が解体され、都市に住んでいればコンビニもあり、いろいろなサービスもあるので、個人が家族という最小の共同体なしでも生きていくことができるようになったのですが、自立自活することが出来ない個人は生き難い世になったことを実感するようになって来ました。
そんな中でのこの本なんですが、内田樹がここで言っています。
「親族を解体し、地域共同体を解体し、終身雇用の企業のような中間共同体も解体し、最終的にみんな孤独になってしまったのは、「一人でも生きていける」くらいに社会が豊かで安全になったからです。個人の「原子化」は平和と繁栄の代価なんです。でもそんな平和と繁栄は歴史的に見ても例外的なものにすぎない。もう、そんなのんびりした時代は終わってしまった。」と。

そんな時代にあって、これからの生き方をどう考えるのか、内田と岡田で示唆に富む対話が繰り広げられていきます。
贈与と反対給付のサイクルの中でパスを流し続けるというのが経済活動の本質。交易が成立するためには、様々な技術や知識が求められる。共通の言語がいるし、共通の度量衡がいるし、当事者双方を拘束する法律がいるし、通信手段や交通手段がいるし、そのうち「信用」とか「為替」が発明され、「株式」が登場してくる。こういうもろもろのことを手際よく果たせる人間が社会性のある人間だということになり、モノをぐるぐる回すことが結果的に人間的な成熟を可能にする。経済はまずは贈与から始まっているのです。ニートのお兄さんに働くきっかけを伝えるには、その人たちが誰かの面倒を見ればいいということ。親の恩は全部忘れていいので、下の世代に返してやれと。
教育と結婚についていうと人間社会が成り立つための必須の制度については設計基準が甘い。「誰でも出来る」と言う仕組みになっていないといけない。あまり高い条件が設定されるとその制度が成り立たなくなる。あまり理想論ばかり言うのでなくてもっと気楽にいい加減に考えてみればいいのでしょうか。
私たちは例外的に豊かな時代をすごす中で、「どうやって共同体を維持していくか」と言う経験知の大切さを忘れてしまっていたのですが、どうも最近の現実はもう一度共同体を再構築しなければいけない状況のようです。
対談形式なので読みやすいのですが、話されていることは結構奥が深く、いろいろ考えさせられます。
そこでは、もたれあい依存しあう生き方でなく、一人で自己決定する生き方が規範となっていた。ロビンソン・クルーソーこそ市民社会における市民の規範だった。
市民社会としていろいろな問題が起きてきた時、遅れてきた日本では、市民社会の成熟が足りないことが問われ、更なる市民としての自立が求められてきた。共同体の残滓を切り捨てないといけないと言われてきた。
マルクスはナロードニキとの交流を通じて共同体から社会主義への道があると思っていたようです(ザスーリッチ宛の手紙)が、レーニンはロシアが資本主義化しそのもっとも弱い環と捉え共同体の再生を顧みることはなかった。
しかし、今、資本主義が深化していく中で共同体が解体され、都市に住んでいればコンビニもあり、いろいろなサービスもあるので、個人が家族という最小の共同体なしでも生きていくことができるようになったのですが、自立自活することが出来ない個人は生き難い世になったことを実感するようになって来ました。
そんな中でのこの本なんですが、内田樹がここで言っています。
「親族を解体し、地域共同体を解体し、終身雇用の企業のような中間共同体も解体し、最終的にみんな孤独になってしまったのは、「一人でも生きていける」くらいに社会が豊かで安全になったからです。個人の「原子化」は平和と繁栄の代価なんです。でもそんな平和と繁栄は歴史的に見ても例外的なものにすぎない。もう、そんなのんびりした時代は終わってしまった。」と。

そんな時代にあって、これからの生き方をどう考えるのか、内田と岡田で示唆に富む対話が繰り広げられていきます。
贈与と反対給付のサイクルの中でパスを流し続けるというのが経済活動の本質。交易が成立するためには、様々な技術や知識が求められる。共通の言語がいるし、共通の度量衡がいるし、当事者双方を拘束する法律がいるし、通信手段や交通手段がいるし、そのうち「信用」とか「為替」が発明され、「株式」が登場してくる。こういうもろもろのことを手際よく果たせる人間が社会性のある人間だということになり、モノをぐるぐる回すことが結果的に人間的な成熟を可能にする。経済はまずは贈与から始まっているのです。ニートのお兄さんに働くきっかけを伝えるには、その人たちが誰かの面倒を見ればいいということ。親の恩は全部忘れていいので、下の世代に返してやれと。
教育と結婚についていうと人間社会が成り立つための必須の制度については設計基準が甘い。「誰でも出来る」と言う仕組みになっていないといけない。あまり高い条件が設定されるとその制度が成り立たなくなる。あまり理想論ばかり言うのでなくてもっと気楽にいい加減に考えてみればいいのでしょうか。
私たちは例外的に豊かな時代をすごす中で、「どうやって共同体を維持していくか」と言う経験知の大切さを忘れてしまっていたのですが、どうも最近の現実はもう一度共同体を再構築しなければいけない状況のようです。
対談形式なので読みやすいのですが、話されていることは結構奥が深く、いろいろ考えさせられます。