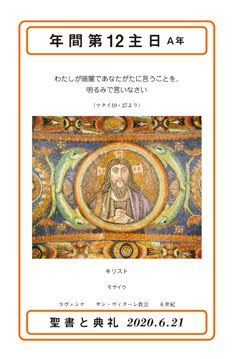第6章のタイトルは「死を超えた希望を生きる」となっている。われわれのからだが復活するとはどういうことなのか。
本章は2節からなり、第1節は死またはお迎えについて、第2節はからだの復活と永遠のいのちについてである。
どちらも重い話だが、入門講座が、教会の「葬儀の祈り」までカバーすることに驚いた。
入門講座などに出たことのない旧い信者さんは、教会の冠婚葬祭の典礼には詳しくとも、『儀式書・葬儀』は読んだことないのではないか。
小笠原師の説明を聞いてみよう。
1 死を超えて
「メメント・モーリ」 memento mori という言葉をわたしも聞いたことがる。「汝、死すべきことを覚えよ」。中世キリスト教世界で
流行ったラテン語の句だと言う。現代社会は平均寿命が伸び、超高齢化社会などと呼ばれている。だが死亡率は相変わらず100%だ(1)。
小笠原師は、マルコ8:36「人は、たとえ全世界を手に入れても、自分のいのちを失ったら、何の得があろうか」をひいて話を始める。
われわれは、あれが欲しい、これが欲しい、あぁなりたい、こぅなりたいといつも思う。若い時はいいだろう。でもその歳になって、と師は
いいたいようだ。
命(いのち)とは 「プシュケー」のことだと詳しく説明していく。プシュケーは本来は「生命の息」という意味で、人間が心(魂)を
持つ人格的主体であることを示すという。
日本語の「寿命」という言葉は「いのちを寿ぐ(ことほぐ)」という意味で、いのちは喜ばしいこととみなす考え方が背後にあると、
興味深い説明を重ねている。
そして、愛するとは、好ましい思いを抱くという通常の意味ではなく、「自分を与える、自分のいのちを与える」ことだという(2)。
この「いのち」の「中身」を師は、「自分の時間、才能や能力や言葉、体力や愛情、おもいやり、微笑み、祈り」などをあげ、
自分のいのちの中身が「豊かであることに驚きを禁じえません」という(3)。
師は、「いのちの意味」と「裁き」について説明していく。聖書の解説というより、師の現代社会論のようにも聞こえる。結局、人生の
課題とは、神の前で「自分自身を全うすること」、「神と隣人を愛する生き方」を選ぶことだという。死は、敗北ではなく、寿命を
まっとうする時、救いの時なのだという(4)。
師はさらに、浄土仏教における「お迎え」(御来迎)」が、キリスト教における「マラナタ(主よ来てください)」の祈りと同じように、
死の不安に怯える人々に深い慰めを与えていることを指摘する。マラナタは主の再臨への願いの祈りだ。師は、ミサ聖祭の「交わりの儀」で
「主の祈り」のあとに唱える「副文」を引用して本節を閉じる。これは司祭が唱えるものでわれわれが唱えるものではないが、身近な祈りだ。
「いつくしみ深い父よ、すべての悪からわたしたちを救い、現代に平和をお与えください。
あなたのあわれみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難にうち勝つことができますように。
わたしたちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。」
(葬儀)

2 「からだの復活、永遠のいのちを信じます」
師は、この最後の節で、教会の葬儀の祈りを紹介する。洗礼によって復活のいのち(新しいいのち)を地上で生き始める者は、
死をも超えて生きる。聖書はそれを「永遠のいのち」と呼ぶ。ヨハネ福音書はイエスの力強い宣言を記している。
「わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、たとえ死んでも生きる」(11・25)(フランシスコ会訳)
師の葬儀ミサの説明は興味深い(5)。二つの祈りを紹介している。
「キリストのうちにわたしたちの復活の希望は輝き、死を悲しむ者も、とこしえの命の約束によって慰められます。
信じる者にとって死は滅びではなく、新たないのちへの門であり、地上の生活が終わった後も、天に永遠のすみかが備えられています」
「慈しみ深い神である父よ、あなたが遣わされた独り子イエスを信じ、永遠のいのちの希望のうちに人生の旅路を終えた〇〇〇〇さんを、
あなたの手に委ねます。
私達から離れていくこの兄弟(姉妹)の重荷をすべて取り去り、天に備えられたすみかに導き、聖人の集いに加えてください。
別離の悲しみにある私達も、主・キリストの約束された復活の希望に支えられ、あなたのもとに召された兄弟(姉妹)とともに、
永遠の喜びを分かち合うことができますように。わたしたちの主・イエス・キリストによって。アーメン」
この祈りでは、永遠の命への信仰と、神が用意なさる新たないのちの中で「再会する」希望がうたわれている。復活の約束は
再会の喜びの約束でもある(6)。この喜びは、教会は「聖徒の交わり」という教えの基本になっているという。
3 「からだの復活を信じます」
さて、最後は難問中の難問、「からだの復活」である。からだの復活という神学を強調したのはパウロである。コリントの教会との
やり取りの中でパウロの神学は研ぎ澄まされていく。
「死者はどのように復活するのか。どんな体で来るのか」(一コリント15:35 協会共同訳)と人は問う。今でも我々の周りの人々も
問いそうな質問である。わたし自身もそう問いかけたい。だが、パウロの答えは明快である。
「(そんな質問をするあなたは)愚かな人だ」(15:36)。
これではコリント前書を読まないわけにはいかない。一コリントの1~11は「キリストの復活」、12~32は「死者の復活」、
35~58は「復活の体」について述べる。
復活論には大きく見て、キリストの復活論とキリスト者の復活論の二つがある(7)。キリストの復活論は「史的イエス問題」が
からむので第4章でふれられた。キリスト者の復活に関しては、「体の語が全体としての人間を意味している・・・体をただ実体的にのみ
とらえるのは不適切である」(8)とされる。キリスト者・信仰者の復活には、「霊の復活」と「肉の復活」の両側面がある。
北森氏は、「霊において復活した信仰者は、終末時において復活したからだを着ることになる。これが救いの成就である」という(9)。
小笠原師のからだの復活の説明も信仰者の復活に関してである。
師は、からだの復活とは「身体を持つ人格」の復活のことだという。師の説明は独特で、興味深い。
師は、からだとはギリシャ語のソーマ soma のことで、死によって朽ち果てていく肉体という意味と、身体としていまここに具体的に
生きる人間という意味の両方を含むという。師は面白い例を上げる。日本語で、「身の程を知る、身を切る、身を粉にする、身につまされる、
身に覚えがある」などなどで使われる「身」とは、「身体を持つ人格・身体としてある人格」のことをさしている。からだとはそういうもの
として、つまり「身」として、理解できるのではないかという。復活するからだとは「身」のことだということらしい。
「死をもって地上の体(肉体)の在りようが終わっても、「からだを張って」実現してきたその人自身の人格としての価値(生の質)は
滅びることなないのです」という。つまり、「霊のからだ」(10)という新しい形へと変えられ、不滅の人格として「顔と顔を合わせて」
神と向き合うのだという(11)。師は、からだの復活とはこういうことを意味すると述べて本章を閉じている。
注
1 わたしでも、身近な人の訃報を聞くと、自分の死がそこまで来ている感覚を覚えるようになった。不思議な感覚だ。証券会社や銀行が
エンディングノートの話をしてくるようになった。かれらに無責任とそしられようと、わたしはそういうことには全く関心がない。
2 教会で老人仲間はよく言う。「人様の世話をするのが、できるのが、うれしい。人様に世話されるのは、ありがたいが、うれしくない」。
3 神学的にはそうなのであろう。これは師に特徴的な表現の仕方で、そのため師をカリスマのように称える信徒もいると聞く。他方、
社会的に見れば、このいのちが画一化され、均質化され、消費の対象になっていることのほうが問題だという議論もある。
なぜか昔のベストセラーの議論を思い起こす(見田宗介『現代社会の理論』1996、加藤典洋『敗戦後論』1997)。
4 師のこういう表現を綺麗事を言っているととってはならない。司祭は、特に教区司祭は、信徒の死という極限状態に日々直面している。
焼き場(火葬場)で神父と坊さんが鉢合わせしたり、入り乱れることは珍しくないという。「死は滅びではなく、新たないのちへの門である」
という祈りがどれだけ悲しむ人々を、信者であろうとなかろうと、力づけているかを忘れてはならない。
5 教会でも家族葬が増えて葬儀ミサも変化の過程にあるようだ。ミサの式次第は、開祭、ことばの典礼、感謝の典礼、告別式と
変わらないが、聖歌など通常のミサとは異なる。
6 師はここで、法然の歌を援用する。
「先立たば遅るる人を待ちやせむ、華の台(うてな)の半ば残して」
(愛するあなたに先立って地上を去っていくわたしですが、天国での喜びに満ちた美しい席を半分あけて、遅れてやってくるあなたを
待ちましょう)
鈴木勁介師の川柳もかきとめておこう。
「いつか死ぬ 受けとめられるか よいことと」(『福音せんりゅう』A年11月2日死者の日 ヨハネ6:37-40)
7 北森嘉蔵「復活」『キリスト教組織神学事典』(2002)
8 青野太潮「体の復活」『岩波キリスト教事典』(2002)
9 北森氏のこういう表現は基督教団系のプロテスタント神学では標準のようだが、霊肉二元論を想起させる印象もある。
10 師は「理解を深めるために」欄で、「霊のからだ」について説明を重ねている。霊のからだという言葉はパウロの言葉なので一コリント
15章を使って説明していく。結局、復活とは、朽ちていく「肉」(自然の命の体)の在りようから、「霊」(神の息吹)に満たされた
「ソーマ」に変えられることだという(240頁)。肉からソーマへということのようだ。
師はここで、「自然の命の体」を「肉」と呼んでいるが、青野太潮によるとこれはギリシャ語でプシュケーで普通「霊魂」と訳されている。
ソーマはソーマ・プネウマティコンでプネウマだから聖霊とでも訳したくなる。師は「注9」の「肉体」で、聖書では「サルクス」 sarx と
呼ばれて「ソーマ」とは区別されていると説明している。肉という訳語が不適切だということのようだ。こういう細かい議論は
師の『信仰の神秘』(近刊)でも展開される。
11 われわれは自分のことは自分が一番よくわかっているとよく言う。だが考えてみると、自分で自分のことすら十分にはわかっていない
ことに気づく。師は言う。「顔と顔を合わせて神と向き合った時、われわれは自分を巡る一切のことを知り、自分と神との関わりのすべてを
知る。パウロによれば、その時人は「驚き、賛美する」だろう」。小笠原師の説明は、求道者を、入門講座の受講者を、力づける。
ロヨラハウスで館長をしておられた外川直見神父もカト研のミサのお説教で言われたことがある。神と顔と顔を合わせて向き合った時、
「ようやったね」と認めてもらえるような人生を歩みたいものだと。

にほんブログ村