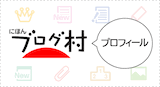2016年11月の「学び合いの会」では、「共観福音書のプロローグの意味を考える」というタイトルでS氏が報告されました。前回は、「ヨハネ福音書のプロローグ」が紹介されましたので、その続きという意味もあったようです。大変力のこもった、学ぶことの多い報告でした。
共観福音書は「共観」と言われるくらいだから各書の内容は大体同じなのは当然であろう。ガリラヤから出たイエスの洗礼から死・復活までの公生活が描かれている。ところが各書のプロローグ(冒頭部分・前書き)はどれも異なっている。各書の福音史家はここに独自のメッセージを込めていた、というのがS氏の考えであり、また、一般に聖書研究者の間で共有された命題のようだ。
福音書のプロローグというとわたしにはヨハネ福音書しか思い浮かばないが、共観福音書のプロローグとは何なのか。
「マルコ」ではプロローグらしき表現はなく、ただ一行あるだけだ。
「神の子イエス・キリストの福音の初め」
「マタイ」では1章と2章がいわゆる「幼年物語」で、一種の前書きになっている。これはユダヤ人向けだ。イエスの視点から書かれているといえよう。
「ルカ」は1章・2章で「献呈の言葉」として7つのエピソードが紹介されている。位置づけとしては前書きだろう。テオフィロ宛てなので明らかに異邦人向けだ。いわばマリアという母親の視点から書かれているように読める。
このように、共観福音書のプロローグは性格が異なっている。少し具体的に見てみよう。
「マルコ」は最初の福音書だけあって、想定されている読者は明確ではないが、一応ギリシャ人のような異邦人むけのようだ。冒頭の一行は、
「神の子イエス・キリストの福音の初め」。これだけである。が、ギリシャ語の原文では語順が逆になるのだという。「初め・福音・イエスキリスト・神の子」。「初め」(アルケー)は創世記の冒頭の一行「初めに、神は天地を創造された」を思い起こさせる。「福音」(ユアンゲリオン)とは「闘いの勝利を知らせる良きニュース」という旧訳に根ざした言葉だ。「神の子」とは「神の聖なる方」、「神の聖者」とも呼ばれている。マルコは旧約聖書の文脈の中でイエスが神の子であることを一生懸命証明しようとしている。「マルコ」が新約聖書の冒頭に置かれたら聖書はよほど読みやすいだろうに、と思わなくもない。
「マタイ」はユダヤ人向けだけあって、繰り返し「イエスは第二のモーゼである」と述べる。1・2章は、①系図②イエス・キリストの誕生③占星術学者(東方の三博士・三人の王)の訪問(ご公現)④エジプトへの避難・帰国を描くが、史的事実と言うよりモーゼの故事をなぞっている。マタイは、イエスの誕生の描写もルカに比べるとあっさりとしている。そもそもイエスがベツレヘムで生まれたというのも現代の聖書学ではすんなりと受け入れない研究者も多いらしい。ベツレヘムや出エジプトの話は歴史的事実と言うよりはその神学的意味を評価すべきなのだろう。
それにしても「マタイ」が「系図」から始まるのは、読者にユダヤ人を想定しているからだ。日本人で、初めて聖書でも読んでみようか、とふと思った人が本屋で聖書を買ってくる。勇んで新約を紐解くと、初っぱなからずらりと「イエス・キリストの系図」が始まる。2~3節読んだら「なに、これ?」となる。系図は14代×3時代の完全数の組み合わせだ、と説明されても「はい、そうですか」としか言いようがないのではないか。そしておそらくもう二度と聖書を開かなくなる。「マルコ」が最初に来ればこういうことは起こらないのではないか。
福音書の配列順序がどうして今のような形になったのかわたしにはわからないが、どうして「マルコ」を最初にもってこなかったのだろう。神父様に尋ねるのも気が引けるほど単純な疑問が頭をよぎる。
「ルカ」のプロローグ(著者の序 1・2章)は「献呈の言葉」から始まる。当時のギリシャ人の手紙の書き方に倣っているのだろうが、なにかよそよそしい感じがする。中身は、①ヨハネ誕生の予告②イエス誕生の予告③マリアとエリザベトの出会い④洗礼者ヨハネの誕生⑤イエスの誕生⑥神殿奉納⑦神殿での12歳の少年イエスの成人式、となっている。つまり、洗礼者ヨハネとイエスをパラレルに描いている点が興味深い。ルカはここで、ガリレヤからエルサレムに至るイエスの道筋をあらかじめこの幼年記で描く。エルサレムからローマへの途は、ルカは福音書の続編である「使徒言行録」で描く。ルカは、キリスト教が旧約に根ざしつつも新しい宗教として、ガリラヤ->エルサレム->ローマ という道程を経て世界的規模で飛躍していく様を、壮大に、しかも事細かに描いていく。「ルカ」のプロローグの特徴、というよりルカ福音書全体の特徴は、現代の目から見れば、女性が大きな比重を占めていることだ。ルカは、福音の普遍性が、民族(ユダヤ人とそれ以外)を超えるだけでなく、男女の性差をも超えていると言っているようだ。
教会の「聖書100週間」などに参加して旧約・新約を2~3年かけて読み通す方が増えているという。第二バチカン公会議以前は、プロテスタントの信徒は聖書を良く読むがカトリックはあまり読まない、という言説がよくなされた。現在のカトリック信者は聖書を良く読む。カテキスタや神父様など聖書に詳しい方の指導があれば、聖書はより深く味わうことができる。聖書は「続編つき」「引照つき」が望ましいが、それにしても値が高いものが多い。なんとかならないのかといつも思っている。
共観福音書は「共観」と言われるくらいだから各書の内容は大体同じなのは当然であろう。ガリラヤから出たイエスの洗礼から死・復活までの公生活が描かれている。ところが各書のプロローグ(冒頭部分・前書き)はどれも異なっている。各書の福音史家はここに独自のメッセージを込めていた、というのがS氏の考えであり、また、一般に聖書研究者の間で共有された命題のようだ。
福音書のプロローグというとわたしにはヨハネ福音書しか思い浮かばないが、共観福音書のプロローグとは何なのか。
「マルコ」ではプロローグらしき表現はなく、ただ一行あるだけだ。
「神の子イエス・キリストの福音の初め」
「マタイ」では1章と2章がいわゆる「幼年物語」で、一種の前書きになっている。これはユダヤ人向けだ。イエスの視点から書かれているといえよう。
「ルカ」は1章・2章で「献呈の言葉」として7つのエピソードが紹介されている。位置づけとしては前書きだろう。テオフィロ宛てなので明らかに異邦人向けだ。いわばマリアという母親の視点から書かれているように読める。
このように、共観福音書のプロローグは性格が異なっている。少し具体的に見てみよう。
「マルコ」は最初の福音書だけあって、想定されている読者は明確ではないが、一応ギリシャ人のような異邦人むけのようだ。冒頭の一行は、
「神の子イエス・キリストの福音の初め」。これだけである。が、ギリシャ語の原文では語順が逆になるのだという。「初め・福音・イエスキリスト・神の子」。「初め」(アルケー)は創世記の冒頭の一行「初めに、神は天地を創造された」を思い起こさせる。「福音」(ユアンゲリオン)とは「闘いの勝利を知らせる良きニュース」という旧訳に根ざした言葉だ。「神の子」とは「神の聖なる方」、「神の聖者」とも呼ばれている。マルコは旧約聖書の文脈の中でイエスが神の子であることを一生懸命証明しようとしている。「マルコ」が新約聖書の冒頭に置かれたら聖書はよほど読みやすいだろうに、と思わなくもない。
「マタイ」はユダヤ人向けだけあって、繰り返し「イエスは第二のモーゼである」と述べる。1・2章は、①系図②イエス・キリストの誕生③占星術学者(東方の三博士・三人の王)の訪問(ご公現)④エジプトへの避難・帰国を描くが、史的事実と言うよりモーゼの故事をなぞっている。マタイは、イエスの誕生の描写もルカに比べるとあっさりとしている。そもそもイエスがベツレヘムで生まれたというのも現代の聖書学ではすんなりと受け入れない研究者も多いらしい。ベツレヘムや出エジプトの話は歴史的事実と言うよりはその神学的意味を評価すべきなのだろう。
それにしても「マタイ」が「系図」から始まるのは、読者にユダヤ人を想定しているからだ。日本人で、初めて聖書でも読んでみようか、とふと思った人が本屋で聖書を買ってくる。勇んで新約を紐解くと、初っぱなからずらりと「イエス・キリストの系図」が始まる。2~3節読んだら「なに、これ?」となる。系図は14代×3時代の完全数の組み合わせだ、と説明されても「はい、そうですか」としか言いようがないのではないか。そしておそらくもう二度と聖書を開かなくなる。「マルコ」が最初に来ればこういうことは起こらないのではないか。
福音書の配列順序がどうして今のような形になったのかわたしにはわからないが、どうして「マルコ」を最初にもってこなかったのだろう。神父様に尋ねるのも気が引けるほど単純な疑問が頭をよぎる。
「ルカ」のプロローグ(著者の序 1・2章)は「献呈の言葉」から始まる。当時のギリシャ人の手紙の書き方に倣っているのだろうが、なにかよそよそしい感じがする。中身は、①ヨハネ誕生の予告②イエス誕生の予告③マリアとエリザベトの出会い④洗礼者ヨハネの誕生⑤イエスの誕生⑥神殿奉納⑦神殿での12歳の少年イエスの成人式、となっている。つまり、洗礼者ヨハネとイエスをパラレルに描いている点が興味深い。ルカはここで、ガリレヤからエルサレムに至るイエスの道筋をあらかじめこの幼年記で描く。エルサレムからローマへの途は、ルカは福音書の続編である「使徒言行録」で描く。ルカは、キリスト教が旧約に根ざしつつも新しい宗教として、ガリラヤ->エルサレム->ローマ という道程を経て世界的規模で飛躍していく様を、壮大に、しかも事細かに描いていく。「ルカ」のプロローグの特徴、というよりルカ福音書全体の特徴は、現代の目から見れば、女性が大きな比重を占めていることだ。ルカは、福音の普遍性が、民族(ユダヤ人とそれ以外)を超えるだけでなく、男女の性差をも超えていると言っているようだ。
教会の「聖書100週間」などに参加して旧約・新約を2~3年かけて読み通す方が増えているという。第二バチカン公会議以前は、プロテスタントの信徒は聖書を良く読むがカトリックはあまり読まない、という言説がよくなされた。現在のカトリック信者は聖書を良く読む。カテキスタや神父様など聖書に詳しい方の指導があれば、聖書はより深く味わうことができる。聖書は「続編つき」「引照つき」が望ましいが、それにしても値が高いものが多い。なんとかならないのかといつも思っている。