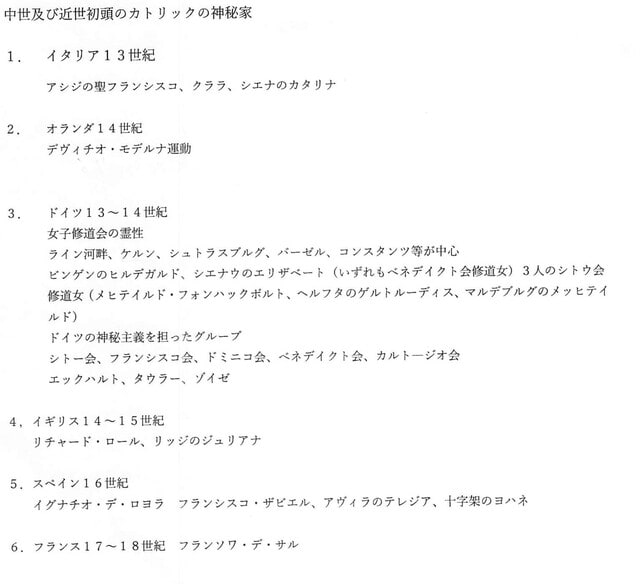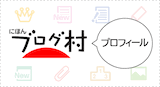ここでは、上田閑照氏の「禅と神秘主義」という論文が紹介される(1)。この論文は、西洋思想の中では禅の思想に最も近いと言われるエックハルトを禅と比較し、両者の異同を明らかにした試みだという。つまり、エックハルトと趙州従諗(じょうしゅう じゅうしん)を比較して、キリスト教神秘主義と禅がどこで類似していて、どこが異なるのかを、明らかしようとする。
【趙州従諗】 【マイスター・エックハルト】

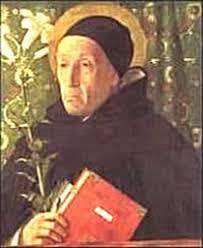
Ⅲ 禅と神秘主義
1 趙州従諗の問答
趙州従諗(じょうしゅう じゅうしん)とは、中国の9世紀の禅僧である。中国の唐の時代の大禅匠(最も偉い高僧)と呼ばれるようだ。趙州の禅問答は前回すでに紹介したが、もう一度見てみよう。
「如何是祖師西来意 庭前柏樹子」
(如何なるか是れ祖師西来意 庭前の柏樹子)
意味は、祖師(達磨大師)がインドから中国に来た目的や意義は何かと問われ、趙州従諗が「それは庭先の柏の木だ」と答えたということのようだ。すでに見たようにいろいろ解釈があるというが、普通は、仏とは何かとか、禅とは何かとか、つまらないことを考えないで、柏の木のように無心になりなさい、ということらしい。禅における無の意味を説明しているというのが上田氏の説明のようだ。
2 エックハルトの問答
上記の禅問答(公案)に対応するキリスト教の問答は、エックハルトの次のような問答だという。
「何故に神は人となり給うたか・・・神は何故なし」
この「神に何故なし」という答えは、公案の「庭前の伯樹子」や「西来無意」に対応するという。「何故に神は人となり給うたか」に対する答えは、伝統的には贖罪論にしたがって、「それは汝らをキリストと同じく神の子として生み給わんとする故である」(アンセルムス)というものであった。「神に何故なし」というエックハルトの答えはこういう伝統的な答えとは全く違う。神に(創造や存在の)理由や原因を問うても意味はないということなのであろう。
エックハルトは「何故なしに生きる」(ohne warum leben)という。何故とか、何のために生きるとか、問わない。生は生自身から湧き出る。だから生きるが故に生きるのだという。ニヒリズムに陥りかねない言説だが、エックハルトの思想の特徴がよくわかる。
エックハルトは「一人一人が神の子になる」とも言う。これも「一人一人が仏となる」という仏教の教えを思い起こさせる。エックハルトの教えはどれも禅的なトーンを持つように聞こえる。違いがあるとすればエックハルトの議論は論理的なのだという。禅の思想にはこういう論理性は見いだせないという。
3 エックハルトの神の概念
それではエックハルトは神とはどのようなものとして捉えていたのだろうか。「神に何故なし」とはどういう意味なのか。それは、キリスト教では、神は純粋存在で、つまり存在そのものであり、その行為は「充満」そのものだからだという(2)。だから、神とは何かとか、神はなぜ人となったのか、と問われても、「神は神だから」と答えるしかないというわけだ。
4 シレジゥスの薔薇(バラ)
「シレジゥスのバラ」の話(格言)は有名なたとえ話らしい Angels Silesius (1621-1677)はドイツの神秘主義詩人で、エックハルトの思想を、時代を超えてよく表現している詩人だという。これは詩の一つらしい。
Die Ros ist ohn warum;sie bluehet,weil sie bluehet.(3)
いろいろな訳があるようだ。「バラは何故なしに在る。それは咲くがゆえに咲く」。または、「バラは理由なく咲いている。誰が見ているかも気にせずに、ただ咲いている」など。私が勝手に直訳すれば、「薔薇が咲くのに理由はない。咲くから咲くのだ」とでもなろうか。
要は、バラは「何故なき神」の命の現れなので、神の内にバラを見ることができるし、バラの内に神を見ることができる、ということのようだ。
こういう説明の仕方は神と被造物(薔薇)を同一視しているように聞こえ、汎神論に無限に近い響きがある。異端視される危険性があることは否めない。だが、エックハルトは神と被造物は明確に区別していたという。
5 理(ことわり)から事(こと)へ
上田氏は、シレジゥスのバラのたとえは禅に大分近づいているがまだ幾分「理」が残っているという。まだ少し理屈っぽいということらしい。さらに単純化して単に「バラの花」という「事」にすれば、より禅的な表現になるという。つまり、「バラの花」は「庭前の柏樹子」に対応するという。宗教は哲学や思想のように「理」ではなく、「事」(体験)を重視する。神を理屈で理解するのではなく、事として、事実として理解するのだという。
ここでは上田氏は禅を宗教として説明しておられるようだ。実はこの「理」から「事」へ、という議論は先生の「言葉(ことば)」論へと発展していくという。「ことば」は「事」と交わることが(ことをめぐって話し合うことが)その原初的な事態だが、やがて「虚・実性」を持ってくると言う。ことばは、「あること 存在すること・もの」を語るが、同時に「ないこと ないもの」をも語る。こうしてことばは「虚の力」を持ってくる、という議論になるようだ(4)。
6 切捨と突破
では、結局、禅とキリスト教はどこが似ていて、どこが異なるというのか。上田氏は一言では言っておられないが、あえて言えば、禅とキリスト教は、真理を獲得する神秘主義的志向、方法においては類似しているが、真理をどう捉えるかという点で異なると言っておられるようだ。
方法論で言えば、禅の「切捨論」は、エックハルトの「離脱論」(Abschiedenheit)や「突破論」(Durchbrech)に近いという(5)。神秘体験、真理の獲得と絶対者との合一のための手法は似ているということであろう。
他方、何を真理と見なすかという点では、趙州従諗とエックハルトでは、禅とキリスト教では、異なるという。
エックハルトは、「神は何であるか」と問われ、「無である」と答える(Got ist ein nicht)。これは神はいないという意味ではなく、人間の語る有ではなく、あらゆる有をこえる有で、人間の言葉で表されるものではないという意味だという。無の背後に実体が存在するとする。 weder diz noch daz (6)(これに非ず あれに非ず)で、究極の真理を「実体」として捉えている。つまり神は実体として理解されている。
他方、仏教では、究極の真理を「縁起」として、つまり「関係」として捉える。無の背後にあるのは実体ではなく関係のみだと考える。実体論を徹底的に否定するのが禅の思想だという。「有に非ず、無に非ず、有に非ざるに非ず、無に非ざるに非ず」が禅の思想で、キリスト教と禅の根本的違いはここにあるという。実体か関係か。ここから先は哲学というよりは世界観や宗教の世界の話になるようだ。
注
1 上田閑照(1926-2019)は京大の宗教哲学者。京都学派とも呼ばれるようだ。わたしはこの論文そのものは読んでいない。ざっと読んだのは『エックハルトー正統と異端の間で』(1998)である。氏はエックハルト論を展開する中で、最後には「非神秘主義」という神秘主義を超える思想的立場を打ち出し、それは「平常心」のなかに見いだせると主張されたようだ。
氏に対するイエズス会からの批判に対しては「世界観的な強い対決姿勢を感じる」と述べている(同書493頁)。とはいえ、すでに述べたようにジョンストン師はイエズス会だが上田氏のエックハルト論を高く評価している。
なお、上田氏は14世紀の「デヴィチオ・モデルナ運動」(Devotio moderna)を「新しき信心運動」ではなく「近代的敬虔運動」と訳しておられる。中世修道院制によらない「共同生活の兄弟団」と説明しておられる。トマス・ア・ケンピスもこの運動の中で生まれたと言っておられ(同書280頁)、氏の神秘主義理解の特徴を知ることができる。。
2 これはキリスト教の充満論で、自然科学でいう真空論の対概念である充満論とは別物である。私の理解では、キリスト教では、神は完全で自己充足しているが、神が世界を創ったとき世界は存在で充満していたと考える説のようだ。
3 現代ドイツ語ではない古い表現。ohn は ohne など。
4 といってもわたしにはよくわからなかった。『非神秘主義』 2008 岩波現代文庫。実はこのことば論は、インターネットの発達の中で書き言葉と話し言葉の区別が曖昧になる中で大きな挑戦を受けていると聞く。言語学ではなく哲学のテーマなのであろう。
5 離脱論、切捨論については2018年5月の報告で少し触れている。エックハルトは「人間は被造物から離脱しなければ神に近づくことはできない」と延べ(離脱論)、趙州従諗は「如何是祖師再来意→庭前柏樹子」と述べている(切捨論)。
6 これも古い表現、表記。