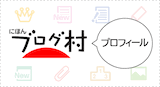日本カトリック司教協議会諸宗教部門が昨年9月22日に主催したシンポジウム「SNSと宗教――LINE・Facebook・Twitterがわたしたちに問いかけるもの」が「2018シンポジウム記録」として先日冊子として配布された。無料なので送ってもらって読んでみた。
特に目新しい話はなかったが、ここで展開された議論を自分の教会に引きつけて考えたとき、いろいろ刺激を受けたので、少し触れてみたい。
この昨年のシンポジウムは麹町教会(四谷のイグナチオ教会)で開かれたもので、出席者も100人を超えていたようだ。主催は諸宗教部門。諸宗教部門は司教協議会(1)の直轄の委員会で、「教団関連・諸部門 Sections」のひとつだという(2)。
パネリストは、中山義紹(曹洞宗熊本県第一宗務所副所長)、阿部仲麻呂(サレジオ会司祭)、志立正嗣(ヤフー株式会社執行役員会長室長)の3人。
冊子は第一部が「発題」、第二部が「対談・質疑応答」となっていて、50頁ほどのものだった。
中山師は、仏教の立場から、「禅」における「智慧」が「体感」を通してでなければ伝えられないものだと主張。曹洞宗では「不立文字」、臨済宗では「公案」を強調するが、「体感」、「皮膚感覚」の強調では共通だという。布教のためのツールとしてSNSの役割には肯定的だが、使い方を誤ってはならないという。
阿部師はインターネットに詳しい司祭として著名な方だが、ご自分の活動、体験談、SNSの問題点の指摘の三点を中心に話されたようだ。師は、イエズス会の「霊性センター せせらぎ」などSNSが宣教の上で有用なことを認めた上で、最近はご自分はSNSに少し距離をとるようになってきたと話しておられたのが印象的であった。ポイントは、SNSは個人の趣味にとどまっていると様々な危険性をはらむので、「チームとして働く」ことを強調しておられた。SNSはグループとして発信し、活用すべきと言う趣旨のようだ。
志立氏は、「キリスト教のアメリカ土着化」・「ナチスのメディア利用」・「大統領選とフェイクニュース」(トランプ大統領の話)・「ISIL(イスラム原理主義)」という4つの「例」をあげながら、メディアと宗教の関わりの歴史に言及した。宣教にはメディアと同じで「5W1H」が必要で、SNSは Where(場所)の話なのだという。5Wを考えることが大事ですということのようだ。「エコーチェンバー効果」とか、子どもに「SNS誓約書」を書かせる話とか、「Yahooあんしんネット」の話とか、興味深い指摘はやはり専門家らしいものであった。
また、ISなど悪い方向へ引き寄せられた人々がいるが、既存の宗教は逆にSNSは彼らを救える可能性を持っている証しとして肯定的に受け取るべきだという。
さらに、カトリック教会はネット利用について消極的であると言われることが多いが、「経営の観点でいうと、大きい組織は動きが鈍いのは当たり前なんですけど、大きいと何がいいかというと、大きなインパクトがつくれるということに尽きるんですよね」(41頁)と述べていた。教会のリーダーたちがSNSの重要性を理解すれば変わっていくのではないかとも述べている。最近は菊池大司教さま、岡田大司教さまをはじめFacebookやtwitterで発信される方々も増えてきており、状況は変わりつつあるようだ。今秋のフランシスコ教皇さまの訪日についての報道も教会のネット利用が望まれる。
詳しい内容としてはカトリック新聞をはじめとして、いくつかのキリスト教系メディアで紹介されているようだが、わたしは佼成新聞デジタル( 2018/10/29)がいちばん詳しい紹介をしているように見えた。
https://shimbun.kosei-shuppan.co.jp/tokusyu/24473/
第二部の対談・質疑応答では、「セキュリティ」・「カルト問題」・「チームワークと分業」・「召命などターゲットを絞ったSNSの利用」など興味深いテーマが取り上げられていた。
私が一番興味深かったのは、「ホームページ」と「SNS」の関係についての理解の違いだった。ホームページは「ストック型」で、SNSは「フロー型」なので、SNSからホームページに誘導するのが望ましいというのが志立氏の主張のようだ。
カルト問題については教会はどういう対策をしているのかという問いに関しては、阿部師と志立氏が発言していた。お二人とも、一般的な説明に終始していたのは残念だった。シンポジウムの質疑応答だから致し方ないとはいえ、「カルト」の意味や内包が歴史的に変遷してきていることを共通の理解に置かないと、「慈善活動とカルトの裏の活動が連続している場合が多いので見分けにくい状態です」(32頁)といわれても、誤解されかねないのではと思った(3)。
ということで、興味深いシンポジウムであったようだ。この「諸宗教部門」は昨年は「自死」をテーマとして取り上げてきたということで、いままでのような「平和論」一辺倒ではなくなってきているのかもしれない。今後の活動が楽しみだ。
それにしても、自分の所属教会をこういうSNS論の文脈に置いてみると、なにか別の世界の話のような気もする。SNSは教会が「外部」とコミュニケーションをとるツールだが、同時に「内部」でコミュニケーションをとるツールでもある。このシンポジウムのテーマはもっぱら外部とのコミュニケーションをとる方法、宣教の方法を扱っていたが、内部コミュニケーションの方はどうなっているのだろう。
私の所属する教会では、壮年会でも婦人会でも連絡は固定電話かファックスが中心。スマホを持っている人の割合も高齢者では高いとは思えない。キーボードが打てない(ブラインドタッチができない)と言うことでパソコンを持っている人も少ないようだ。教会委員会が躍起となってメーリングリストやスマホの利用を勧めているようだがあまり効果はないようだ。信者会館にはWiFiサービスもあるがあまり使われているようでもない。教会活動に熱心な方々から「携帯で十分」といわれると返す言葉がない。教会委員会では敬老会の対象者を85歳以上にするという話が話題に出ているというのだから、教会のメンバーの高齢化はとどまるところを知らない。そのうえごミサの最中に携帯の呼び出し音がピーピー鳴ったりする。こういう状況の中で、SNSを宣教のツールにするという課題はかなり長期的な課題なのではないかというのが、今回の読後感だった。
注
1 日本カトリック司教協議会は「カトリック教会法」にもとづく宗教組織の名称のようだ。中央協議会は法人としての名称。いわば世俗法上の名称。宗教法人としては包括宗教法人(単位宗教法人ではない)。メンバーはオーバーラップしていて、両組織は事実上同じと考えて良さそうだ。
2 社会司教委員会ののように独立した委員会にはなっていないようだ。責任司教は宮原良治(福岡教区司教)、担当司教は酒井俊弘(大阪教区補佐司教)だという。
3 現代の日本のメディアが用いるカルトという言葉は、極めて現代日本に限定的な特殊な用法であるようだ。ウエーバーやベッカーを持ち出して「キルヒェとゼクト(カルト)」論を展開してもあまり説得力はない。