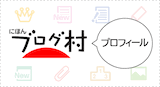教会の先輩の誕生会に招かれた。96歳の女性の誕生会である。ホテルの一室にお祝いに駆け付けたのは(招待されたのは)4組のご夫婦の方々を含む9名ほどだが、全員戦前生まれだ。つまり80歳代の人々の会食ということになる。楽しい集まりであった。
先輩のSさんによれば、誕生会の名を借りてコミュニケーションの場を持ちたいと思ったからだという。彼女は自らパソコンを操り、スマホを操作し、招待状を作られたという。感心するどころか、ただただ驚くばかりだった。
これは高齢化が進む今日のカトリック教会の一つの姿であり、印象を少し書き残しておきたい。どこの教会でも見られる姿ではないだろうが、かといって例外的な出来事とも言えないだろう。
Sさんは、教会では入門講座を担当しており、また、いくつかのグループをつくって教会のリーダー的役割を果たしておられる。Sさんは当教会では80年に及ぶ教会歴をお持ちなので、周りからは「教会の生き字引」と呼ばれているという(1)。教会歴というよりは彼女の人徳が人をひきつけ、尊敬を集めているのだろう(2)。
これは教会に限ったことではないが、高齢化社会の問題点の一つは高齢者のロールモデルが出来あがっていないことのように思える。自分の身近の周りを見わまして、自分もあういう高齢者になりたい、あの人のように年を取りたい、と思わせてくれる人が減ってきているのではないか。高齢者といえば、すぐに介護だ、看護だという話になる。健康のために歩きなさいとか寂しさを紛らわすためにペットを飼いなさいとかいう話になる。だが、健康だけではなく、広い人間関係を持ち、精神的自立を保ち、周囲に誇りと自尊心を与え続けることができる高齢者の話をあまり聞かない。Sさんはそういう意味では、信者の鑑でも、教会の生き字引でもなく、高齢者の新しいロールモデルを提示しているように思えた。
このロールモデルは当然単一のものではないだろう。地域や性別や年齢ごとに異なったモデルがあるだろう。また、どのように年を取るか、は、どのように生きてきたか、の反映でもあるので、このモデルを一律に議論するのは難しいだろう。とはいえ、高齢になることにはこのような喜びと楽しみと感謝があるのだと示せるロールモデルが欲しいものだ(3)。
【1952年ごろの聖堂】

注
1 私は個人的には心ひそかにSさんを「信者の鑑」を呼んでいるが、ご本人はこの表現を好まれない。ところが「教会の生き字引」という呼称には抵抗感がないようだ。わたしにはSさんのこの語感の違いに興味を感じるが、Sさんと私の世代の違いの反映なのだろうか。
Sさんに80年の教会歴があるということは、彼女は戦後日本のカトリック教会の歴史をほぼすべてずっと見てこられたということであろう。時々周囲の方に感想をおもらしになるということなので、一度ゆっくりとお話を聞いてみたいものである。
2 こういう表現をするとすぐに「だから教会には老害がはびこっている」みたいな批判をする人がいる。少し視点を変えるとこういう批判が如何に近視眼的かがわかる。
3 高齢者向けの議論ではしばしば、「残りの人生は短いのだから、自分の好きなように生きなさい」という言説がまかり通っている。この種の言説は一見もっともらしく聞こえるが、ひとつ大きな欠点がある。それは「自分個人の人生」のことしか念頭に置いていないことだ。ところが、なんでも好き勝手にできる自分個人の人生なんてものはなく、それはいつも集合的・共同体的ははずだ。Sさんが一つのロールモデルに見えるというのは、彼女の人生が教会という一つの共同体の中で営まれてきたからだ、と言うと言い過ぎだろうか。