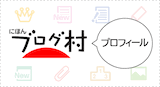真福八端はイエスの幸いの説教の中核をなしている。これは、通常、マタイ5・3-12の「山上の説教」として知られているが、他方、ルカ 6:20-23 の「平地の説教」もある。幸いの説教は「山の上」でなされたのか、「平地の野」でなされたのか。実は、問題は、どこでなされたか、山か平地かではなく、イエスは何と言っていたのか、を知ることだ。聖書学は「幸い」の説教の原型を復元しようとしてきた。
「幸い」の説教の原型はどのようなものだったのか。結論的には、それは、ルカがいうように、極めてシンプルなものだったようだ。が、マタイはそれを自分なりに内面化してなにか倫理的な教えに編集し直したようだ(1)。
1)原型の復元
a)
マタイ5・3-12の山上の説教の最初に真福八端がくる。イエスは幸いを得る基本として8項目を挙げられた。幸福とは、金持ちになること、権力を持つこと、豊かで楽な生活をすること、などとわれわれは思いがちだが、イエスはとんでもないことを言い始める。
心の貧しい人々は、幸いである、 天の国はその人たちのものである。
悲しむ人々は、幸いである、 その人たちは慰められる。
柔和な人々は、幸いである、 その人たちは地を受け継ぐ。
義に飢え渇く人々は、幸いである、 その人たちは満たされる。
憐れみ深い人々は、幸いである、 その人たちは憐れみを受ける。
心の清い人々は、幸いである、 その人たちは神を見る。
平和を実現する人々は、幸いである、 その人たちは神の子と呼ばれる。
義のために迫害される人々は、幸いである、 天の国はその人たちのものである。
わたしのためにののしられ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪口を浴びせられるとき、
あなたがたは幸いである。
喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。(新共同訳)
驚くべきメッセージである。荒井献氏はこの真福八端には二つの特徴があるという。
①精神的限定
マタイはイエスの説教を内面化・倫理化して表現する。これはマタイの表現なのだ。例えば、「心の貧しい人々」とはなんのことか。誰のことか。日本語としてはピントこないので繰り返し議論されてきた。日本語の訳語の問題もあろうが、「霊(プネウマ)において貧しい者たち」のことだ。でもこれでも分かりづらい。だから、さまざまな解釈や議論が行われてきた。「貧しさ」とは何なのか。単なる物質的貧しさから謙遜・へりくだりまで解釈は多様だ。中川師は「全人的解釈」が必要だという。
②「天の国」という言葉
マタイはここで、「神の国」とは言わない。「天の国」と言っている。これはあきらかにユダヤ教的改変なのだという。「神の国」と「天の国」の違いはすでに論じたのでここでは触れられていない。
b)
ルカの平地の説教は6・20-23である。
20 さて、イエスは目を上げて弟子たちをみて言われた。
「貧しい人々は、幸いである、神の国はあなたがたのものである。
21 今飢えている人々は、幸いである、あなたがたは満たされる。
今泣いている人々は、幸いである、あなたがたは笑うようになる。」
重要なのは、「幸い」という句らしい。ルカは二人称を使っているのに、マタイは三人称複数形を使っているのだという。これがどういう違いを意味するのかわたしにはわからないが、ルカがイエスによる「語りかけ」を強調しているのは確かなようだ。
ルカ11・28 「しかし、イエスは言われた。「むしろ、幸いなのは神の言葉を聞き、それを守る人である」
ルカ14・15 「食事を共にしていた客の一人は、これを聞いてイエスに言った。「何と幸いなことでしょう、神の国で食事する人は」
中川師はさらに、ルカが伝えるイエスの言葉、使信の迫真性を強調する。
ルカ 6・21をもう一度見てみよう。「今飢えている人々は、幸いである、あなたがたは満たされる。今泣いている人々は、幸いである。あなたがたは笑うようになる。」
ここでは、「今」と言っている。集まっている人々に向かって「いま、この瞬間、おなかを減らしている人々よ」と言っているように聞こえる。「あなたがた」と言っている。二人称だ。中川師が言う「迫真的」とはそういう意味なのであろう。
c) Q資料(語録資料)
だが、マタイの伝えるイエスの幸いの教えと、ルカの伝えるイエスの教えには違いがありすぎる。なぜこれほどちがうのか。しかもマタイ、ルカにはあって、マルコにはない話がたくさんある。それはQ資料が介在するからだ(2)。つまり、
①伝承の原型(ルカ6・20aなど)があった
②「幸い」の理由句(ルカ6・20bなど)では終末論的応報願望がQ資料段階で付加されている
③イエスの言葉(ルカ6・22-23)がQ資料段階で「ロゴス」化されて使信として提示される
(ロゴス化とは、伝承の担い手や編集者などによってイエスの使信が総括的に提示されること)
すなわち、荒井氏によると、伝承の原型は「三福」である。
幸いだ、貧しい者たち。
幸いだ、飢えている者たち。
幸いだ、泣いている者たち。
イエスの幸いの教えはこういう簡潔なものだったのかもしれない。それにしても逆説的な教えだ(3)。中川師は、まとめとして、「幸い」の説教の中心的使信は、「神の国」が「貧しい者」に開示されるということ、神の前の貧しさが要請されていること、と整理された。神の前での貧しさ。難しい課題である。
注1 荒井献『イエス・キリスト』(上下)講談社 2001
注2 「Q資料とは、前述のように、、ドイツ語のLogienquelleという語のQeulleの頭文字に由来し、邦語では、イエスの語録集という。これは定義上は、マルコにはほとんど存在しないが、マタイとルカが共有するイエスの言葉を収録したものである。たとえば、マタイ5章の山上の説教とルカ6・20以下の山麓の説教は、マルコにはないが、マタイとルカに共通した伝承である。」(三好迪『ルカによる福音書ー旅空に歩むイエス』講談社 1984 47頁)
注3 これを裕福な者への敵視ととると、そのままユダヤ人には伝えられないから、マタイのような編集が入って来るのだという。真福八端にいろいろな解釈があるのも宜なるかなである。