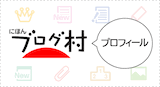先日教会の図書室で本棚を覗いていたら驚くべき光景に出くわした。
私どもの教会の図書室は図書室といえるほどの独立した部屋ではなく、集会室の壁の一部に本棚が数本置いてあるだけである。
とはいえ、この書架には、昔の聖書、カトリック大辞典、資料集、製本された過去の月報、他教会からの会報など重要なものがきちんと整理保存されている。図書室をどの程度充実させるかはその時の主任司祭や教会委員会の意向によって変わるので、時代の変化を知ることもできる。
今回、「蔵書を整理するので不要な本を処分します。ご入用の方はお持ち帰りください」との掲示とともに段ボール箱に数十冊の本が放り込まれていた。何気なく覗いてみるとそこにはなんと、「キリスト教とは何か」(カール・ラーナー)、「公会議に現れた教会」(ハンス・キュンク)が無造作に置かれていた。前者は(邦訳)は1981年、後者は1966年なので、あまりにも古いということで処分の対象となったのであろう。
それにしてもラーナーの「キリスト教とは何か」はラーナーの晩年に書かれおそらく代表作といってよい著作だろう。値段が高くて私は手が出なかった書物だ(1994年に新版がでている)。後者はパンフレット風だが第二バチカン公会議の立役者キュンクの教会論だ。私は涙を流しながら喜んでいただいてきた(また返すつもりなので借りてきたと言うべきか)。
ラーナーとキュンクが選ばれていたのは偶然なのだろうか。キュンクは一昨年訃報が伝えられたばかりだ。ラーナーは現在の日本のカトリック神学者のなかで最も影響力のある神学者だろう。『神学ダイジェスト』(1)では繰り返し特集が組まれており、正平協よりの司祭からは偶像視されているように見える。
ラーナーとキュンク。両者の比較は専門家たちがいろいろやっているようなので、私も学んでいきたいものだ。ラーナーの「匿名のキリスト者」論、キュンクの「下からのキリスト教」論、ラーナーの超越主義に基づく普遍主義説、キュンクの多様性説に戻づく教会改革論、というような言葉が脳裏に浮かんでくる。二人とも現代の混迷するカトリック教会が将来進むべき道をそれぞれ示しているようだ。
キリストを知らないで死んだ人も救われるのですか。教皇は不可謬だと聞きますが本当ですか。どうして女性は司祭になれないのですか。死んだらお寺のお墓に入ってもいいのですか・・・などなどごく普通の質問への答えは、ほとんど『カトリック教会の諸宗教対話の手引き――実践Q&A』(2)に記されているが、その神学的な意味はラーナーやキュンクにさかのぼらなければよく理解できない気がする。
蔵書整理でラーナーとキュンクが廃棄処分される時代がきている。日本社会の分裂を反映するかのようにカトリック教会にも分裂の兆しが訪れているのかもしれない(3)。教会の一致を、教会内の一致を、これからも辛抱強く祈っていこう。
【初版】

注
1 上智大学神学会誌。現在は年2回刊行されているようで、著名な外国神学者の論文を翻訳紹介している。編集長は光延一郎師。イエズス会で、元上智大学神学部長。正平協の秘書だという。
2 日本カトリック司教協議会 2009
3 キュンク風に言えば、土着派対ローマ派、ラテンミサ派対公会議派、リベラル派対保守派、正平教派対信仰派、などなど教会の分裂の線はいろいろ引くことができるだろう。しかもそれらの分裂は普通の 保守/革新、伝統/近代、右/左というイデオロギー軸できれいに線引きできない。例えば女性司祭は反対だが護憲一本やりという組み合わせもあるようだ。
それにしてもラーナーの『キリスト教とは何か』は難しい。「現代カトリック神学基礎論」とサブタイトルがついているが、これはもともと講義録のようだ。原題は Grundkurs des Glaubens:Einfuhrung in den Begriff des Christentums 1976 。キリスト教入門という意味なのだろうが、入門書ではない。ただ。論述の仕方は、神論・人間論・原罪論・救済論・キリスト論・教会論・終末論とオーソドックスな議論の進め方(章立て)となっている。