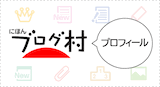2017年5月の「学びあいの会」は5月にしては珍しい猛暑の22日に開かれました。過去数回、ベネディクト16世ヨゼフ・ラッチンガー著 里野泰昭訳『ナザレのイエス』(2008・春秋社、原著2007)を読んでいます。今回はその第四章「山上の説教」第1節「真福八端(幸いな人)」に入りました。
報告者はラッチンガーの説明の要約というよりはかなり自由にまとめて話しておられました。冒頭、聖書学の研究手法としての「様式史批判」論と「編集史批判」論との違いを説明され、主に文体の比較を行う様式史批判手法の有効性を強調された。
「山上の垂訓」(共同訳は山上の説教 Sermon on the Mount)はキリスト教信仰の真髄である。キリスト教の教えは結局「愛」の教えと言われるが、「愛」とは①神を愛すること、②神を愛するとは隣人を愛すること、ということで、人を愛することが神を愛することになるという二重構造がこの教えの中核である。「山上の垂訓」は、イスラム教で言えば「五行六信」(神・天使・コーラン・預言者・来世・予定を信じ、信仰告白・礼拝・喜捨・断食・巡礼を行うこと)みたいなもので、イエスの教えの集大成である。
イエスはその短い人生において数々の奇跡とともに多くの教えを述べた。これらの多様な教えをまとめたのが「山上の垂訓」で、マタイ福音書5章から7章までに記されている。同じ話はルカ福音書6:17~49にも記述されているが、こちらは「平地の垂訓」と呼ばれ、はるかに短い話となっている。マタイ福音書は基本的にユダヤ人向けだから「山」で話したことにして旧約のシナイ山を想起させ、モーセの「十戒」の補強・完成という意味を強調したかったのであろう。ルカ福音書は異邦人キリスト者向けの性格が強かったから「山」を強調する必要はなく、イエスの教えがユダヤの世界に限定されるものではなく、むしろ普遍的な世界に向けられたものであることを強調したかったのであろう。イエスはこの長い説教を一度に行ったわけではなく、「山上の垂訓」はイエスの数多くの説教をマタイが(マタイ福音書家が)まとめて編集したものであろう。つまり意識的な編集がなされているわけだ。
「山上の垂訓」の内容は多岐にわたる。まず「真福八端」がくる。ついで「地の塩・世の光」(5:13-16)があり、「律法の成就」(5:17-20)が続く。5:21~48は「6つの反対命題」といわれ、「十戒」の掟の徹底がはかられる。反対命題とは「律法ではこうなっている。しかし私は言っておく」という表現で切り返し、いわゆる律法主義を批判している(本書では、第2節「メシアのトーラー」でさらに詳しく論じられる)。
第六章は信心業で、ユダヤ教の施し・祈り・断食についての教えがとかれ、「主の祈り」が与えられる。6:24から第七章はいわば「態度論」で、人間の「物」に対する態度、「人」に対する態度、「神」に対する態度、が示され、7:12は有名な「黄金律」となる。7:13以下は「注意事項」と呼ばれるらしく、7:24~27の「家と土台」の話で終わる。今日は冒頭の「真福八端」が紹介され、各条ごとに読み、関連する旧約部分を読み合わせた。議論しだしたら切りの無い「幸いの教え」だが、みなで静かに読んだ。
さて、「真福八端」である。「しんぷくはったん」と読む。最近はあまり聞かない言葉である。聞いたこともない、という人もいるかもしれない。昔の公教要理では良く使われた言葉だが、なぜ最近使われなくなったのか私にはわからない。カト研の皆さんには、ジョンストン師風に、英語で、Beatitudes と言ったほうがわかりがよいかもしれない。
教理でいえば、真福八端は『カトリック教会のカテキズム』の第3編「キリストと一致して生きる」第一部「人間の召命、霊における生活」第一章「人格の尊厳」第2項「至福への召命」の「1 真福八端」」(項目1716)として、「真福八端は、イエスの説教の中核をなすものです」と説明されている。(524頁) 真福八端は、幸福になることは、人生の目的であり、行為の究極目的であることを明らかにします、と書かれている。
また、『カトリック教会の教え』では、第三部「キリスト者の倫理」第一章「人間の尊厳と救いへの招き」第二節「真の幸福への招き」第二項「イエスによる至福の告知」のなかで、各条ごとに詳しく説明されている。真福八端という日本語は判りづらいが、普通は「真の幸福のための八つの言葉」という意味だ。『カトリック教会の教え』では、beatitudes を「至福」と訳し「神に祝福された幸福」のことと説明している。念のために見てみよう(新共同訳)
心の貧しい人々は、幸いである、天の国はその人たちのものである。
悲しむ人々は、幸いである、その人たちは慰められる。
柔和な人々は、幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。
義に飢え渇く人々は、幸いである、その人たちは満たされる。
憐れみ深い人々は、幸いである、その人たちは憐れみを受ける。
心の清い人々は、幸いである、その人たちは神を見る。
平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。
義のために迫害される人々は、幸いである、天の国はその人たちのものである。
わたしのためにののしられ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪口を浴びせら れるとき、あなたがたは幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報 いがある。あなたがたより前の預言者たちも、同じように迫害されたのである。
あまりにもよく知られた教えである。ちなみに英訳も見てみよう。
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
for they shall be satisfied.
Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of
God.
Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake,
for theirs is the kingdome of heaven.
Blessed are you when men revile you and persecute you and
utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice
and be glad, for your reward is great in heaven, for so men
persecuted the prophets who were before you. (Mt 5:3-12)
今日はこの八つの教えを一つづつ見ていったが、ここでは第一の「心の貧しい人は幸いである。天の国はその人たちのものである」だけを取り上げてみてみよう。「心の貧しい人」とはなんのことか。真福八端のなかでも最も難解な部分である。日本語ではそのままでは殆ど意味をなさないのではないか。心が貧しいとは心の狭い偏狭な人という意味か。そうではなさそうだ。英語ではBlessed are those who are poor in spirit という訳もある。poor in heart という訳も多い。heart のかわりに ghost も使われるようだ。そして、poorとは貧しいという意味か、乏しいという意味か、可哀想という意味か。ドイツ語聖書など、うまく訳せない言語では意訳が多いようだ。日本語訳はこれでもまだ原語に忠実に訳そうとしているのかもしれない。
フランシスコ会訳はこうだ。「自分の貧しさを知る人は幸いである」。「心」とか「霊」とかでてこない。つまり、この表現にはいろいろな解釈、説明があるようだ。ここでは最も一般的な説明を考えてみよう。ルカでは「貧しい人々は幸いである」(ルカ6:20新共同訳)とあり、貧しいとは文字通り物質的に貧しい、貧乏という意味が強い。だが、マタイでは、貧しいとは「恵みに乏しい」という意味に変えられ、いわば霊的な貧しさが強調される。ラッチンガー(の訳者は)、「霊によって貧しい人は幸いである」ととらえ(訳し)、「恩寵の貧しい者」(110頁)という意味になると説明している。貧しいとは物質的か、非物質的(精神的)か、という違いである。もちろんオーソドックスな理解はその両方を包み込むものとして、心の貧しい人とは、魂の打ち砕かれた人、自分の中に救いの可能性を認め得ず、神により頼むことしかない人、とされる。一言で言えば、心の底から「謙虚な人」という意味だ。だが、「心が貧しい」を「謙虚」の意味でとれるようになるにはかなりの勉強と人生経験を必要とするのではないだろうか。
ラッチンガーは言葉の定義ではなく、アッシジのフランチェスコ(アシジのフランシスコのこと)こそ「真福八端の精神が最も濃密な形でその実存の中にまで移し替えられた一人の人間」(114頁)だとして、詳しく検討していく。確かに、言葉に遊ぶよりは、聖人を見る方が、この教えをより深く自分のものにする途なのかもしれない。真福八端の8つの言葉はどれもパラドキシカルである。心の貧しい人こそが天国に入れる、とは、『歎異抄』(善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや)(金子大栄校注岩波文庫45頁)に劣らず逆説的な命題である。
ラッチンガーは以下7項目を逐次検討していく。ここでそのすべてに触れることはできない。それは、さらに難問が続くからだ。かれはルカにおける真福八端の思想を取り上げていく。今日の報告者はこの部分は省略されたのでここでは深いりしないが、ルカにおいて「4つの祝福の言葉の後に、4つの不幸の言葉が続く」(135頁)。「いま富んでいるあなた方は不幸だ・・・いま満ち足りているあなた方は不幸だ・・・いま笑っているあなた方は不幸だ・・・すべての人が誉めるとき、あなた方は不幸だ」という恐ろしい言葉が続く。これは真福八端の思想をルカとマタイを比較しながら理解するという作業を意味し、具体的には「Q資料」の影響力の重みの違いを検討するという大変な仕事になってくる。深入りしなかった報告者は賢明だったと思う。
次は「地の塩・世の光」の話である(マルコ4-21・49~50)。キリスト者は独特の味をもってこの世に味付けをしなければならない。キリスト者は光であり、すべてを照らす使命を持つ、という教えだ。続いて、「律法について」(5:17~20)となる。イエスは律法を否定しない。むしろ律法を完成させる。律法の本当の趣旨を貫徹させなければならないということが述べられる。(律法という言葉は日本語独特である。法とか法律という言葉と区別され、聖書的な言葉となっている。外国語ではこういう区別はないようだ。例えば英語では、律法も、法律も、法も law だけのようだ。これは律法が福音との対立概念とされ、否定的な意味が付与されてきたためのようだ。日本の聖書研究とはなんだったのか、と考えさせられるが、便利な区別、使い分けといえばいえなくもない)。
5:21~48までは「6つの反対命題」がとりあげられる。十戒の掟の徹底化といわれる。
①腹を立ててはならない
②姦淫してはならない
③離縁してはならない
④誓ってはならない
⑤復讐してはならない
⑥敵を愛しなさい
以上の命題はどれも、「~とあなた方は聞いているーしかしわたしは言う」という形になっており、「律法からの自由」が述べられる。ここで念のために「十戒」を思い起こしてみよう。
第一戒「あなたはわたしをおいてほかに神があってはならない」
第二戒「あなたはいかなる像も造ってはならない」
第三戒「あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない」
第四戒「安息日を心に留め、これを聖別せよ」
第五戒「あなたの父母を敬え」
第六戒「殺してはならない」
第七戒「姦淫してはならない」
第八戒「盗んではならない」
第九戒「隣人に関して偽証してはならない」
第十戒「隣人の家を欲してはならない」(新共同訳)
①は第六戒の徹底だし、②は第七戒、④は第九戒の徹底だ。中でも重要なのは⑤「復讐してはならない」だ。律法は同害同復をとる。それはそれでハムラビ法典にあるような復讐の連鎖・拡大を防ぐ機能を持ったが、イエスはそれだけでは不十分だとする。個人倫理の一つで、集団間の争いにはそのままは適用できないだろうが、キリスト教独自のエトスである。
⑥「敵を愛しなさい」が最も重要だ。そんなことはできっこない。そりゃそうだ。だがここでの[愛」とはアガペーのことだということを思い出そう。聖書では、「愛」には、アガペー(神愛)、エロス(情愛)、フィリア(友愛)などいくつかの意味が含まれているが、最も大事なのはアガペーとしての愛だ。「愛」という言葉も日本語としてはまだまだこなれていないが、最近使われるようになった「ご大切」という訳語は大事にしたい。キリシタン時代から使われた日本語らしい日本語だと思う。キリスト教の影響で、「愛」という日本語も「性愛」だけを意味するのではなく、もっと精神的な思いやりや慈しみを意味するようになってきていることは喜ばしい。さらに「ご大切」という訳語がアガペーの訳語として、love の訳語として、定着していってほしいものである。人を大切にすること、徹底的に大切にすることが、人を愛するということなのであろう。敵をもご大切にする。難しいことではあるが、山上の垂訓の教えの焦点といえよう。