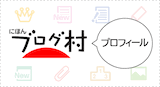Ⅴ エフェゾ公会議
1 テオトコス(神の母)論争
聖母マリアは、テオトコス(神の母)か、アンドロポストコス(人間の母)か、キルストコス(キリストの母)か、という論争。論争の発端は、コンスタンチノープルの大司教ネストリオスが428年に、伝統的な「神の母」の称号は正しくなく、「キリストの母」が正しいと主張したことにある。つまり、マリアは、キリストの人性の母であって、神性の母ではない、と主張した。これが大問題に発展した。
2 エフェゾ公会議 431年
この公会議ではキリストの神性と人性の結びつきがテーマであった。アレキサンドリア学派(キュリロス派、キュリロスはアレキサンドリアの大司教で、公会議の議長)とアンチオキア学派(ネストリオス派)が対立した。権力闘争でもあったため両派は激しく争い、結局ネストリオス派は排斥される。
マリアは「神の母」と宣言される。「キリストの神性と人性は区別されなければならないが、唯一の人格(ペルソナ)において結合され、両者とも1つの人格に帰されなければならない」とした。現在でもカトリック教会は「マリア崇拝」(批判者はMariolatoryという用語を使う)は禁止し、「マリア崇敬」(hyperdulia)を認めている。
ネストリオスはエジプトへ流刑となり、弟子たちはペルシャを経て中国にネストリオス派のキリスト教を伝える。「景教」である。空海(弘法大師)は唐で修行中にこのネストリオス派の景教に接していたといわれる(1)。
Ⅵ カルケドン公会議
1 エフェゾ強盗会議 449年
エフェゾ公会議のあともキリストの本性についての議論は終わらなかった。キリスト単性論をとるアレキサンドリアの大司教エウテュケスやその支援者はエフェゾ(第二、陰謀、強盗)会議を勝手に開いて単性論を認めた。このため新皇帝のアルキアヌスは教皇レオ一世の要請で公会議の開催を決断した。
2 カルケドン公会議 451年
これは重要な公会議である。皇帝の代理人9人、教皇使節が3人が主催。東方教会の司教500人以上が参列。
449年の強盗会議の無効を宣言。エウテュケスは排斥される。カルケドン信条が採択される。
3 カルケドン信条
これはカルケドンの思潮とアレキサンドリアの思潮を統合するものであった。「唯一かつ同一」のイエス・キリストは「真の神であり、真の人間」であり、「神性において父と同一本質の者(ホモウーシオス)であり、かつまた人性においてわれわれと同一本質の者(ホモウーシオス)」であり、「2つの本性において、混合されることなく、変化することなく、分割されることなく、分離されることがない」と宣言された。つまり、キリストの神性と人性が、「混合されない、変化しない、分割されない、分離されない」ことが宣言された。これは三位一体論の重要な教えで、現在でも生きているだ。
4 キリスト単性説
カルケドン公会議でのキリスト両性説は、西方教会では全面的に受け入れられたが、東方教会では会議後も単性説の支持者が反カルケドン派として大きな勢力となっていった。今日でも、アルメニア派、ヤコブ派、コプト派として残っている。ただ、単性説は反皇帝運動の旗印だったという説明も根強いようだ。
Ⅶ 第三回コンスタンチノープル公会議 680年
カルケドン公会議でも、キリストの「意志」の問題は残されたままだった。キリストの本性は2つ(神性・人性)であることは確認されたが、キリストの行為・行動(エネルゲイア、オペラチオ)は1つだ。それでは、キリストの意志は1つなのか、2つなのか。単意説と両意説が対立した。結局両意説が確定し、単意説は異端とされる。
「キリストは神のゆえに神の意志を有するが、同時に人のゆえに人間の自由意志も有する。人間本性の中心は理性と意志であるから、真の人であるキリストは、人間の自由意志を有するはずである。キリストは人間としての自由意志により、神の意志を受け入れ、人間の意志を神の意志に従わせ、神と一致して行動する」と宣言された。ここにキリスト両意説が完成した。
八 今回の結び
以上の古代の公会議によって、キリスト論の教義は完成した。それ以来、今日に至るまで、キリスト論についての新たな教義は制定されていない。
S氏によると、キリスト論には狭義と広義の二種類があるという。
狭義のキリスト論はキリストの本性論で、キリストは神か人か、という問いが中心だという。
他方、広義のキリスト論は、キリストはなぜこの世に来たのか、その目的は何か、を問うのだという。これは「救済論」につながる。
だが、救済論には教義はない。キリストによる人類の救済は教義として確認されることはなかった。救済は聖書で語られており、信条が信仰箇条であった。トリエント公会議では、キリストによる義認と和解、十字架上の犠牲と償い、洗礼とゆるしの秘跡などが確認されている。現代では、救済は人間だけではなく、万物におよぶ、という新約聖書の宇宙論的救済論が注目され、そのエコロジー的側面が強調されてきているという。
つまり、救済論は「終末論」という形をとる(2)。大貫隆氏によれば、イエスの終末論は「神の国」の宣教であり、「上昇の黙示録」だという(3)。イエスは「天上の神殿」が「天から降りてくる」イメージを持っていて(4)、洗礼者ヨハネの宇宙論的黙示思想とは異なるようだという(5)。
こういう救済論と終末論の関係の議論は組織神学のテーマでキリスト論からは離れていくが、S氏の次回の話がどこまで広がるか楽しみである。
注
1 もしこれが真実なら、空海はキリスト教に接した最初の日本人ということなる。ザビエルの来日に遡ること744年。真言密教に、茶道に、キリスト教の影響を見る人は多いようだ。ロマンを感じさせる話である。
2 終末論 eschatology とは、歴史には終わりがあるという思想。それが歴史の目的であると主張する。キリスト教的にはその目的は「審判」と「救済」になる。「ヨハネの黙示録」は天地創造から最後の審判・イエスの再臨まで語るが、救済への言及は少ないという。
3 大貫隆『終末論の系譜ー初期ユダヤ教からグノーシスまで』 筑摩書房 2019
4 大貫氏は、初期ユダヤ教の終末論はメシア思想と黙示思想からなり、黙示思想には宇宙史全体の行方についての言及と、「天上の神殿・玉座の幻視」への言及の二側面があるという。イエスは政治的メシア思想を避け、黙示思想から自分の「神の国」論を組み立てていったという。
5 黙示 apocalypse とは神が自らを啓くこと、つまり、真理を開示すること。日本語では 啓示 revelation と区別されるが、ギリシャ語では同じ言葉のようだ。
黙示は契約を語るが、聖書には7つの契約が書かれているという。そのうち4つは神とイスラエルとの契約(アブラハム・土地・モーゼ・ダビデ)、3つは神と人類との契約(アダム・ノア・新しい契約)からなる。大貫氏は言う。「洗礼者ヨハネは、大きく見れば、ユダヤ教黙示思想の宇宙史の終末論を背景として登場してきたと考えられる。しかし、アブラハム契約の棄却という見方においては、その宇宙史の終末論からも訣別しているのである」(133頁)。