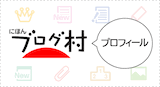Ⅲ 『現代世界憲章』のヴィジョン
岩島師は続いて現代世界憲章のなかの教会論に関する部分に簡単に言及する。この憲章の位置づけ、教会憲章との関係などについての詳しい説明は省いている。そこでここで前書き風に少し触れておきたい。
現代世界憲章が採択されたのは、すでに触れたように、第9公開会議の最終審議日(1965・12・7)だ。「教会の現代化」がモットーとして掲げられた。つまり教会が現代世界と対話することだ。これがヨハネ23世がこの第二バチカン公会議を開いた主旨であることを考えると、この憲章の重要性がよくわかる。また、それが難産の末の成果だったことがよくわかる。「憲章」ではなく「宣言」にとどめるべきという声はかなりあったようだ。この憲章は普通、教会憲章を補うもの、教会憲章の続きのように語られることが多い。だがその意義は教会論を超えてもっと広く、深いようにも思える。
現代世界憲章は第一部が4章、第二部が5章で構成されている。全部で93項あり、教会憲章よりも長い。目次を見てみよう。正式なタイトルは『現代世界における教会に関する司牧憲章』となっている。
序文
前置き 現代世界のおける人間の状況
第1部 教会と人間の召命
第1章 人格の尊厳
第2章 人間共同体
第3章 世界における人間活動
第4章 現代世界における教会の任務
第2部 若干の緊急課題
第1章 結婚と家庭の尊厳の推進
第2章 文化の発展
第3章 経済・社会生活
第4章 政治共同体の生活
第5章 平和の推進と諸民族の共同体の促進
結語
前回にも触れたように、第二バチカン公会議が「教会論」を集中的に取り上げたのは公会議の歴史の中で画期的な出来事だった。だがこれは逆に言えば、世界を取り巻く「社会問題」がほとんど取り上げられなかったことを意味する。保守的な当時の教皇庁が用意した70議案のうち社会問題を取り上げたのはただ一つだけだったという。
第4会期は1965年9月14日から開始されたが、公会議事務局が用意した議案はどれもがあまりに楽観的なトーンで書かれていたという。当時の世界が直面していた矛盾、罪と悪の現実は黙殺され、十字架の神学も十分には取り上げられていなかったという。ここにラッチンガーが登場し、原案作成に関わってきたという。後のベネディクト16世である。かれは当時は進歩派の先頭を切っていたのだ(1)。
現代世界憲章の「解説」を書いているH・J・マルクス(聖書学者)は、この憲章の「意義」を5点に整理している。
①キリスト教人間学の構想をたてた:それまで別々に論じられていた創造・罪・恩恵・終末などを総合した
②無神論へ対応した:無神論とはここでは具体的には実存主義とマルクス主義のことで、無神論を断罪するだけではなく、信者と無神論者は世界構築のため協力しなければならないとした。
③結婚と家庭についてのトリエント公会議以来の静的な見方を克服した:夫婦愛と出産が取り上げられ、夫婦間の性行為の尊さが讃えられた。産児制限については堕胎だけが弾劾されており、人工的産児制限はあえてふれられていない。
④労働の尊厳を強調した:単に私有財産の擁護だけではなく、資本に対する労働の優位を力説している
⑤戦争と平和について伝統的正戦論を乗り越えた:正当防衛権を認めながらも、原子・生物・化学兵器の使用は正当防衛の範囲を超える無差別破壊をもたらすと警告した。以後歴代教皇は第一次イラク戦争などに反対していく。
(教皇ヨハネ23世)

さて、このような現代世界憲章を岩島師は以下のように紹介している。
第二バチカン公会議における教会についての記述は必ずしも教会憲章に限定されない。16文書すべてが教会の在り方に関わっていると言っても過言ではない。特に、第1部第4章(40-45項)のテーマは「現代世界における教会の任務」である。40項は教会の課題・起源・目的・働きについて述べている。この項は、この憲章全体の発想をよく示している。教会は神の自己譲与の成果であり、現実の歴史において働く。それは教会からの一方通行ではなく、相互関係であると述べる。41-44項は教会と世界の相互関係を記述し、45項はこの相互関係のキリストにおける完成(初めと終わりであるキリスト)について記述する。
現代世界憲章に関するこういう要約の仕方は、上記H・J・マルクスの「解説」とは力点の置き方が全く異なることが解る(2)。
4 第二バチカン公会議と教会
ここは岩島師の第二バチカン公会議への評価である。師は2点指摘している。
①教会の非中央集権化が進んだ
②「完全なる社会」論から「開かれた教会」論への転換がなされた(3)
①は、絶対主義的・中央集権主義的な教会理解が解消したことだという。具体的には以下の5点が挙げられている。
a キリストこそ教会の真の主
b 教会の最高権威としての教皇中心主義は、司教の団体性指導原理により修正された(4)
c 教会は神の民 ヒエラルヒーは教会の秩序維持の手段である
d 他のキリスト教会、他宗教への開かれた見方を提示した
e 教会は自己目的ではなく、世界のために存在するとした
②では、前時代の「完全な社会」論は、典型的な閉ざされた社会のパターンである。第二バチカン公会議の教会論は開かれた社会のパターンである。変化していく世界の中で、人類全体の救いのために教会が存在するという思想を打ち出した、と述べている(5)。
注
1 現在の名誉教皇ベネディクト16世は教皇フランシスコと較べれば保守派サイドに位置づけられるだろう。ラッチンガーが変わったのか、教会が変わったのか、評価は難しい。
2 岩島師はこの現代世界憲章をあまり評価していないのかもしれない。またはこの本『キリストの教会を問うー現代カトリック教会論ー』が書かれた時代(1987)の制約かもしれない。この時期、1980年代にはいると、正平協の変質に見られるように岡田大司教の下にあった日本の神学校や司教団*は急速に「左傾化」*していく。第二バチカン公会議の「教会の現代化」は日本では「教会の左傾化」に読み替えられてしまったかのようである。日本のカトリック神学のリーダーだった岩島師のこの著作はこういう状況下で書かれたという文脈において読む必要があるようだ。
*日本では「司教団」の力が極めて強い。教区司祭は人事権を握られているし、服従が叙階の条件だから、ほとんど発言できないようだ。しかも信徒数に較べ司教の数がダントツに多い。教区も多く、細かく分かれすぎている。個々の司教にはすぐれた方がたくさんおられるようだが、組織としてはここ数十年変化していない印象を受ける。
*左傾化とは曖昧な言葉で使いたくはないが、『広辞苑第7版』によると、「社会主義・共産主義などの左翼の立場に傾くこと」と説明されている。左翼(Left)という言葉も曖昧で、党派性を右・左で類型化する思考はフランス革命まで遡らなければならないが、これは保守・革新(日本)や、リベラル・保守(米国)、進歩・保守(ヨーロッパ)という類型とは異なる。これはイデオロギー論のテーマなので改めて考えてみたい。
3 「開かれた教会」というスローガンもその中身はあまり具体的ではない。神学的にリベラル神学や福音主義神学批判のことを言うわけではなく、また、ある特定の組織形態や団体を意味しているわけでもなさそうだ。大きく見て二つの側面があるようだ。一つは、聖職者と信徒との上下関係が緩やかになるという意味だ。教会内部が開かれるという意味だ。たとえば信徒使徒職が見直された。もう一つは教会が社会に開かれるという意味だ。つまり宣教を重視するという意味だ。さて、第二バチカン公会議後の日本の教会は宣教に成功したのか。努力が成果に結びついたのか。統計で見る限りここ数十年間信徒数は減少の一途を辿っている。「アジアシノドス」(世界代表司教会議 1998)をめぐるローマとの軋轢は日本の司教団が歩んでいる道の険しさを示しているようだ(使徒的勧告『アジアにおける教会』)。
4 司教の団体性指導原理とは、全世界の司教は団体として教会全体を導く最高責任者であることをいう。この責務は明白な形では公会議において遂行されるが、「全世界に散在しているときにも、……団体的機能を行使できる」と教会憲章で述べられている(22項)。「教皇の首位性」に対して「司教の団体性」を強調しているのが第二バチカン公会議の特徴と言えるだろう。
5 岩島師の議論はここで終わっているが、本書出版35年後の現在を岩崎師はどのように見ているのだろうか。ネットでも講義を続けられる師が好んで取り上げられる現代の問題は、インカルチュレーション*・小教区の制度・女性の役割・信徒使徒職などだ。女性の叙階とか司祭による性的虐待問題とか同性愛問題とか正平協問題とかセンシティブな問題はあまり取り上げられない。教会論の視点からの発言を望みたいところだ。
*元来は文化人類学の用語で文化の受容という意味だが、教会では具体的にはキリスト教の土着化のことをさす 土着化という用語はナショナリズムとの関係を論じざるを得ないのでインカルチュレーションという言葉は使いづらく現在はあまり使われない言葉だ 教会では、谷口幸紀師のようにそのイデオロギー性を強調して言葉の使用を強く否定する人もいるが、便利な言葉なので教会にはあえて使う信徒も多いようだ