Ⅶ キリスト教の本質
シュライエルマッハーのキリスト教理解は伝統的な理解から離れてきている。だから正統派だけではなく、改革派の人々の眉をもひそめさせたという。かれの理解をキュンクは「意識・キリスト論」と呼んでいる。シュライエルマッハーは神の啓示をなにか人間的な敬虔な感情として、なにか心理的なものとして理解しているのではないかと批判されたようだ。
シュライエルマッハーはキリスト教の本質は「無限なものの観照」において見られねばならないと言っているという。つまり、キリスト教はユダヤ教とは違って「報い」という理念で規定されているのではなく、「破滅と救済」、「敵対と媒介」の関係によって規定されているという。何を言っているのかよくわからないが、キリスト教は「無限なもの」にかかわるべきだといっているようだ。つまり、キリスト教は徹底的に「論争的な宗教」だが「聖性へ突き進む宗教」である。その始まりはユダヤ教ではなく、イエスにある。イエス・キリストこそ、「唯一の einzig 」ではないにせよ、「無二の einzigartig 」の「媒介者」である、ということらしい。相変わらずよくわからないが、キリスト教は「無限なものへの感覚」なのだという。イエスを、単に神的存在ではなく、このように「意識に引きつけて」描くことは今までにはなく、独特の描き方であったようだ(1)。
Ⅷ 近代的な信仰論
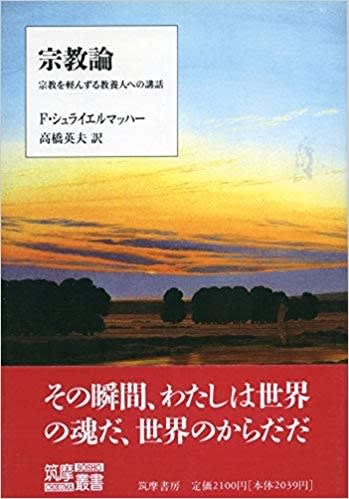
シュライエルマッハーの「意識・キリスト論」(『宗教論』)は多方面から批判された。彼の反論は『キリスト教信仰』(1821)を待たねばならなかった。この間ナポレオンがプロセインを攻撃し、シュライエルマッハーは「キリスト教的・プロセイン的愛国者」に変貌していた。この『信仰論』は独特の副題を持っている。「福音主義教会の原則に沿い、連関を持って叙述された」と訳されている。原題は、”Der christliche Glaube nach den Grundsaetzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt”。この組織神学の本は、トマス・アクィナスの『神学大全』、カルヴァンの『キリスト教綱要』に比肩する著作だという。
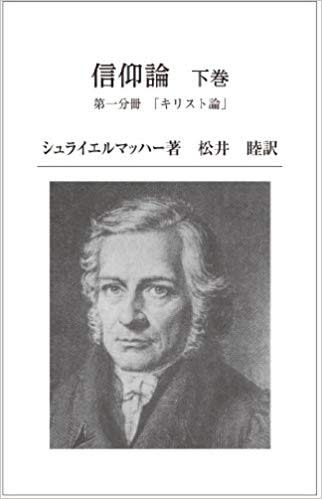
キュンクはこの『信仰論』の特徴を、「あらゆる宗教改革的・正当主義的な教義学から区別」されたものだと説明している。特徴を三点あげている。
①組織神学は「厳密に歴史的に構成されたもの」でなければならない。つまり、無時間的な、不変的な教理学ではなく、「ある特定の時代に通用した教理を、連関において扱う学」なのだという。
②エキュメニカルに形成されている。これは、カトリック対プロテスタンティズムという話ではなく、ルター派と改革派の対立には意味がないということだ。つまり、1817年の「ルター派・改革派の合同」を支持する教義学ということのようだ。
③「経験」に結びつけられていること。宗教的経験から出発すること、キリスト者の集団的・共同体的意識から出発することを主張した。かれはアンセルムスの以下の言葉を本書の扉の頁に掲げているという。「私は信ずるために知解しようと試みるのではない。むしろ知解せんがために信じるのだ」「なぜなら、信じない者はそれを経験することなく、経験しない者はそれは認識しないからである」。
ついで、キリスト教の本質規定を、「キリスト教とは信仰的心情の目的論的方向におけるある独自の形態である」としている。これも、翻訳の問題を除いても、よくわからない文言だ。キュンクは以下のように解説している。
①シュライエルマッハーは宗教の3段階の発展段階説をとっている。「物神崇拝ー多神教ー唯一神教」で、キリスト教は最後の段階だという。「目的論的」とは、目的規定的であり、それ故倫理的で活動的であるという意味だという。
②キリスト教を他の宗教から区別している「独自性」とは、その「理性的な性格」にあるのではなく、その「救済の性格」にあるという。救済とは、「仲保者」たるイエス・キリストに関係づけられているという意味だ。
③キリスト中心という性格。キリストの人格の重視はシュライエルマッハー神学に不可欠だという。
④「信仰の意識」に出発点を置く。ナザレのイエスの客観的歴史から出発するのではなく(2)、教会共同体の敬虔なキリスト教的「意識」、救済の意識から出発するということのようだ。
こういう理解は、キリストを「人」として理解することに比重がかかっているのか、それとも「神」として理解することに比重がかかっているのか。キュンクは、これはシュライエルマッハーの「意識・キリスト論」の中心的な「欠点」だという。
Ⅸ キリストー真に人
シュライエルマッハーの「意識・キリスト論」はたんなる主観的信仰の想像物ではない。それは信仰論において大規模な「非神話化」を行っている。堕罪や原罪、天使と悪魔などの非神話化に止まらず、非神話化はイエスの処女降誕、奇跡、復活と昇天などの物語にまで及んでいる。
①キリスト教はその歴史的源泉をナザレのイエスの史的形姿に持つ
②かれのキリスト中心主義はイエス・キリストの歴史の帰結である
③イエスの歴史的形姿は単なる「救済の出来事」ではなく、「物語られるもの」でもある
Ⅹ キリストー真に神?
シュライエルマッハーのキリスト論は異端的ではない。それは、仮現論(現代の超自然主義)ではないし、ナザレ人主義(現代の合理主義)でもない。前者のように、救済を「魔法」として理解するのを拒否し、後者のようにイエスを普通の人間に他ならないと見なすことも拒否する。かれは、非神話化の作業をしながらも啓蒙主義的・合理主義的なイエス論からは離れている。かれは敬虔なキリスト教的自己意識を強調する。では彼のキリスト論とはなにか。
かれは,宗教の本質を「絶対的依存感情」に求めた。宗教の本質は道徳ではなく、神に対する「直感と感情」であるという。この感情は、対象に自分が感情的に依存するという意味ではなく、自己と対象との対抗関係が統一されたものへの依存のことである。つまり、信仰のことである。
キュンクはさらにシュライエルマッハーのキリスト中心主義を詳しく紹介している。キリスト中心主義」とは、キリストは敬虔の完全な具現であるがゆえに,神意識の原型(Ur-Bild)であり,救いの原型であるということらしい。ここでは我々にはフォローしきれないほど細かい議論が続く。あえて要約すれば、シュライエルマッハーは、キリスト教を、当時の啓蒙主義思想のように何らかの倫理的理想の模範として理解するのではなく、かといって古い教会のように理解不可能な教理命題を従順に受け入れるだけではなく、歴史的イエスのなかに現臨した神による規定として理解した。
シュライエルマッハーは宗教的多元論者ではない。かれは、神の存在は排他的にキリストにのみ来たのであり、キリストとの関係においてのみ「神は人となった」という。ヨハネの「言は肉になった」は彼の教義学の根本テキストだという。
ⅩⅠ 批判的な問い返し
とはいえ、キュンクはシュライエルマッハーへの批判がなされてきたことを忘れない。以下の4点にまとめている。
①かれの意識神学は『宗教論』でも『信仰論』でも、聖書の役割が下位に置かれている。
②かれの宗教の定義(絶対的依存感情)、人間の主観から、信仰共同体の意識から出発する宗教の定義は肯定されるにせよ、キリスト論を人間論から区別しすぎている。
③かれは、神の暗闇、人間の否定的現実の経験(苦悩、罪、挫折、疎外、歴史の矛盾など)にきちんと目を向けていない
④彼の神学は、預言者的・大祭司的・王的イエスを描いているが、十字架の躓き、復活の希望には十分な目を向けていない。新約聖書の書簡など諸文書を中心に位置づけていない。
つまり、シュライエルマッハーの神学は近代の神学だったが、逆に「近代の時代精神」の囚われてしまっているという。近代社会に成立した神学なのに、同時に近代社会の限界に制約されてもいるというわけだ。
ⅩⅡ にもかかわらず、近代のパラダイム的な神学
シュライエルマッハーはヘーゲル主義者など多くの批判者にかこまれた。批判者は多かったが、かれは「希なる卓越した精神」だったという。かれの『信仰論』は19世紀にはすべての神学者に読まれたという。かれは、愛国者だったが、教会の国家からの自立を擁護した。国家教会ではなく、国民教会を擁護した。「自由な人間性とキリスト教的な神との連帯のおいて・・・彼こそ近代のパラダイム的な神学者」(281頁)だという。キュンクのシュライエルマッハーの評価は高い。
キュンクはシュライエルマッハー論を閉じるに当たって、およそ100年後に『教会教義学』(1932)においてシュライエルマッハーを批判したカール・バルト K・Barth の「賞賛のことば」を引用している(3)。
「われわれは、神学の世界にはまれにしか与えられないような、一人の英雄と関わることになる・・・この場所を一度も愛さなかった者、そしてこの場所を繰り返し愛するような状況にない者には、この場所を憎悪する資格はない」
注
1 この章の翻訳は、他の章の翻訳と比べて、同一の訳者の訳文とは思えないほど生硬というか直訳に近い。機械翻訳とも思えないが、日本語になっていない文章が散見される。
簡単に言えば、シュライエルマッハーは、「神」ではなく「信仰」を分析したということだ。「信仰論的神学」と呼ばれるらしい。これは、カント的二元論の克服を意図したものらしく、理性主義万能の風潮に対して宗教独自の世界を回復したいという思いがあったらしい。といってもこういう意識論的な自由主義神学は、20世紀に入ると、神と人間の完全な断絶を主張する二元論的な弁証法神学によってやがて批判されていくことになる。
2 よほど重要な本なのであろう。神学部や哲学科の学生の必読書なのかもしれない。われわれのなかで読んだことのある人はいないので、なんとも議論にならなかった。松井 睦 訳『信仰論 』下巻 第一分冊「キリスト論」 シャローム印刷 2013
2 とはいえ、、史的イエス研究に批判的という意味ではなく、信仰論的神学の強調という意味のようだ。むしろ批判的歴史学とは結びついており、聖書解釈に関しては伝説や物語を排して聖書を歴史文書として批判的に研究するのが自由主義神学の特徴らしい。
3 キュンクは紛れもないバルトシンパだが、よほどシュライエルマッハーが好みのようだ。
























