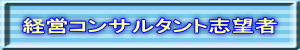■■【一口情報】 法人向けインターネットバンキングの不正送金対策
経営コンサルタントを40年もやっていますと、若かりし頃、話し下手であった自分が信じられないほど、人前でもしゃべれる様になりました。雑学をかじっていると、人が関心を持ってくれます。
■ 法人向けインターネットバンキングの不正送金対策
全国銀行協会が発表したアンケート結果に基づく過去2年間の法人口座の不正送金被害の推移を見ますと、平成26年に急増していることがわかります。警察庁によれば2014年の国内における被害額は、5月9日の時点で14億円を超え、既に昨年の被害総額を超えたとあります。
被害額急増の理由の1つに電子証明書を窃取するウイルスによる新しい手口の出現があります。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のWebサイトでは、法人口座を狙う不正送金の新しい手口と、その対策方法について解説しています。
◆1 不正送金の手口
金銭被害を食い止めるには、騙されないための注意深さと知識が必要で、利用者自身で何が正しいのかを「知る」ことが必要です。IPAでは、オンラインバンキングの「正しい画面」を知ることの大切さを強調しています。これを知っていれば、パソコンが万が一ウイルスに感染しても、異常に気付くことができます。
オンラインバンキングにおける不正送金の代表的な従来の手口は、次の通りです。
1.利用者のパソコンにウイルスを感染させることで、不正なポップアップ画面を表示させる。
2.その画面に、送金に必要な情報(ID、パスワード、乱数表の数字など)を利用者に入力させる。
3.その結果、送金に必要な情報が第三者に渡ってしまう。
4.第三者は、窃取した情報を悪用して手動で不正送金を行う。
しかし2014年3月に、窃取した情報を悪用して、その場でリアルタイムに送金処理を行う新たなウイルスが確認されました。
1.利用者のパソコンにウイルスを感染させることで、不正なポップアップ画面を表示させる。
2.その画面に、送金に必要な情報(ID、パスワード、乱数表の数字など)を利用者に入力させる。
3.入力させた情報が即座に悪用され、第三者の口座への不正送金がリアルタイムに行われてしまう。
詳しくは、以下の独立行政法人情報処理推進機構のサイトをご覧ください。
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2014/08outline.html
◆2 オンラインバンキングの正しい画面
IPAでは、オンラインバンキングの「正しい画面」を知ることの大切さを強調しています。これを知っていれば、パソコンが万が一ウイルスに感染しても、異常に気付くことができます。
「不正な画面」は既知のウイルスによって表示されるもので、ウイルスや手口が異なれば、出現する「不正な画面」も多種多様になると考えられます。そのため「正しい画面」を知っていることは、それと異なる画面が現れた際に異変に気付くことができ、金銭被害から身を守ることができます。
オンラインバンキングのサイトによっては、実際の「正しい」取引を体験できるデモページを用意している金融機関もあります。
⇒不正な画面(みずほ銀行ウェブサイト)
http://www.mizuhobank.co.jp/direct/images/start_img_01.gif
オンラインバンキングでは、このように利用者に「正しい画面」を提示している場合がありますので、利用中のオンラインバンキングのサイトで「正しい画面」が掲載されているかを確認してください。掲載されていた場合は、画面のスクリーンショットをパソコンに保存しておくかプリントアウトしておき、オンラインバンキング利用時には常に正しい画面と画面遷移に照らし合わせながら利用してください。
もしオンラインバンキング利用時に「正しい画面」と異なる画面が現れた場合、ウイルス感染が原因の場合以外にも、オンラインバンキング側のシステム変更の可能性があるため、以下の対応を取ってください。
1. 金融機関本体のサイトを確認し、オンラインバンキングの画面の変更の有無を確認する。もしくは問い合わせ窓口に確認する。
2.もしシステム変更によるものではない場合、ウイルス感染が疑われますのですぐにオンラインバンキングの利用を停止し、セキュリティソフトによる駆除や後述する感染を防ぐための対策を行ってください。
詳しくは、以下の独立行政法人情報処理推進機構のサイトをご覧ください。
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2014/08outline.html
独立行政法人 情報処理推進機構 技術本部 セキュリティセンター
Tel: 03-5978-7591 Fax: 03-5978-7518
E-mail: 電話番号:03-5978-7591
不正な画面◆3 電子証明書添付も安心するな
全国銀行協会が発表したアンケート結果に基づく過去2年間の法人口座の不正送金被害の推移を見ますと、平成26年に急増していることがわかります。警察庁によれば2014年の国内における被害額は、5月9日の時点で14億円を超え、既に昨年の被害総額を超えたとあります。
被害額急増の理由の1つに電子証明書を窃取するウイルスによる新しい手口の出現があります。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のWebサイトでは、法人口座を狙う不正送金の新しい手口と、その対策方法について解説しています。
その中の一つに「電子証明書を窃取する手口」が紹介されています。
組織内の複数端末でインターネットバンキングを利用したい場合、それぞれの端末に電子証明書が格納されている必要があります。ブラウザに格納する電子証明書の場合、インポート時の設定で、エクスポートを「可」とすることで、現在利用している端末以外の端末に電子証明書を格納することが可能となります。
利用端末が複数あることは業務効率が高く、便利な一方で、不正送金に悪用されるリスクが高まるため、利便とリスクのトレードオフを見極める必要があります。 そのため、電子証明書のエクスポート設定を原則「不可」としている銀行もあります。
最近では次のような電子証明書を窃取する新しい手口が確認されており、特にエクスポート設定が「可」となっている場合は、気付かないうちに電子証明書を窃取されてしまう危険性があります。
【1】エクスポート設定を「可」としてインポートした電子証明書を窃取する手口
【2】エクスポート設定を「不可」としてインポートした電子証明書を窃取する手口
電子証明書がついているからと言って、安心できませんね。
詳しくは、以下の独立行政法人情報処理推進機構のサイトをご覧ください。
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2014/08outline.html
◆4 不正対策法
全国銀行協会が発表したアンケート結果に基づく過去2年間の法人口座の不正送金被害の推移を見ますと、平成26年に急増していることがわかります。警察庁によれば2014年の国内における被害額は、5月9日の時点で14億円を超え、既に昨年の被害総額を超えたとあります。
被害額急増の理由の1つに電子証明書を窃取するウイルスによる新しい手口の出現があります。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のWebサイトでは、法人口座を狙う不正送金の新しい手口と、その対策方法について解説しています。
IPAでは、次の対策法を紹介しています。
1.インターネットバンキングに利用する端末ではインターネットの利用をインターネットバンキングに限定する
2.銀行が提供する中でセキュリティレベルの高い認証方法を採用する
3.銀行が指定した正規の手順で電子証明書を利用する
ただし、パソコンがウイルス感染していると、これだけでは不充分です。平素からパソコンをウイルスに感染させないための基本的な対策を常に実施することが重要です。
全国銀行協会でもインターネットバンキングの利用者に対して情報セキュリティ対策を紹介しています。
1.インターネットバンキングに利用する端末ではインターネットの利用をインターネットバンキングに限定する
2.パソコンや無線 LAN のルータ等について、未利用時は可能な限り電源を切断する
3.取引の申請者と承認者とで異なるパソコンを利用する
4.振込や払戻し等の限度額を必要な範囲内でできるだけ低く設定する
5.不審なログイン履歴や身に覚えがない取引履歴、取引通知メールがないかを定期的に確認する
法人口座は個人口座より送金限度額が大きいため、1度の不正送金が事業存続に致命的なダメージを与える可能性があります。各種のセキュリティ対策とともに、ウイルス対策という基本的なことを忘れてはならないと考えます。
詳しくは、以下の独立行政法人情報処理推進機構のサイトをご覧ください。
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2014/08outline.html
■■【時代の読み方・月曜版】 この一週間の映像 2015年5月5週 0601後半
文字数制限のため、週を前半と後半に分けて掲載しています。週の前半は、日曜日の正午頃発信しました。
 一週間の出来事・映像に見る話題
一週間の出来事・映像に見る話題
時代の流れを時系列的に見ると、見えないものが見えてきます。NHKの放送や新聞・雑誌などを見て、映像も交えて、お節介心から紹介しています。
この一週間、何があったのか、一括しましたので、見落としたニュース等をご覧下さると幸いです。


| 28日(木) |
■【今日の出来事】
政府日銀:日銀金融政策決定会合(~22日)
民間:食品スーパー売上高、パソコン国内出荷実績
米国:景気指数、景気先行指標総合指数、中古住宅販売件数
【時事用語解説】
■【今日のブログ】
午前零時 【今日は何の日】
午前発信 【今日のマガジン】
正午発信 【時代の読み方】
夜間発信 【トップ+コンサルタント情報】
■【映像に見る今日の話題】 TPP難航、EUとのEPAは前進の兆し
TPP(環太平洋パートナーシップ協定)問題で首席交渉官会合がアメリカで開催されたものの、知的財産分野で依然として対立しています。
並行して進められていますEUとのEPA(経済連携協定)は大筋合意に向かって、交渉が難航している分野での協議が加速させれています。宮沢経済産業大臣が、都内でEU貿易政策担当のマルムストローム委員と会談しました。
TPPを有利に進めるためにもEUとのEPAで成果を上げておく必要のある日本ですが、今後TPPは年内にまとまるのでしょうか? 映像
1733(亨保18)年5月28日に東京・隅田川で水神祭の川開きが行われました。享保17年(1732)の大飢餓で多くの餓死者や疫病による被害が出て、その慰霊を兼ねて悪病退散を祈願して水神祭が行われました。
■【ウェブサイト更新】
【公的補助金・助成金】を毎週増補・改訂しています。
| 29日(金) |
■【今日の出来事】
政府日銀:黒田日銀総裁記者会見
民間:電力需要実績、粗鋼生産量
米国:FRB議長講演、CPI、PMI表
【時事用語解説】
■【今日のブログ】
午前零時 【今日は何の日】
午前発信 【今日のマガジン】
正午発信 【カシャリ!一人旅】群馬
夕刻発信 【経営特訓教室】
夜間発信 【トップ+コンサルタント情報】
■【映像に見る今日の話題】 自宅でジョッキ生ビールを楽しめる時代
私は、経営コンサルタントとして独立起業する前は、商社マンでしたので、酒はつきものといっても過言ではありません。先輩が下戸の私を心配してトレーニングに、代わる代わる毎晩あちこちに連れ出してくれました。しかし、体質が受け付けないことが分かり、トレーニングを諦めました。
NHKの朝の連ドラで話題を呼んだウィスキーの最初の一口、口から鼻に抜けるあの感触は、下戸の私でも素晴らしいと思います。ビールの最初の一口、あの甘さ(”ほろ苦さ”の間違いではありません)、旨いと思います。もちろん、それ以上進むと、大変なことになります。
ビールの消費量は減少しているとは言え、生ビールは夏の風物としては欠かせないと言えます。ジョッキでぐいぐいというのが自宅でもやりやすくなるそうです。家庭向けにビールサーバーを貸し出し、作りたてのビールを定期的に宅配してくれるといいますから、ビール党の人には放っておけませんね。 映像
■ エベレスト登頂記念日 5月29日(火)
1953年5月29日に、ニュージーランドのエドモンド・ヒラリーとシェルパのテンジン・ノルゲイが、世界最高峰であるエベレスト(Everest)に人類初の登頂に成功しました。
| 30日(土) |
■【今日のブログ】
午前零時 【今日は何の日】
午前発信 【今日のマガジン】
正午発信 【セミナー情報】
夜間発信 【トップ+コンサルタント情報】
■【映像に見る今日の話題】 補正予算案と平成27年度予算案をわかりやすく
平成26年度補正予算案及び平成27年度予算案の閣議決定を踏まえ、予算案の内容について、担当者が直接、分かりやすく説明した動画が中小企業庁から公開されました。 http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2015/150123yosanan.htm" target="_blank">映像
真のプロ経営コンサルタントが、40年の経験の上に、夢を語る 映像
1968年5月30日に、「消費者保護基本法」が公布・施行されました。これを記念して日本政府が1978年に「消費者の日」を制定し、経済企画庁を経て現在では消費者庁が主催しています。
虚偽表示がまだまだ横行しています。それが発覚しても、刑が軽い ・・・・・<続き>
■【ウェブサイト更新】
「経営情報・セミナー案内」を増補・改訂致しました。

上記以前の最近の記事 ←クリック
【今月の経営コンサルタントの独善解説】 ←クリック
■■ 経営コンサルタントへの道 ←クリック 経営コンサルタントを目指す人の60%が閲覧


【小説・経営コンサルタント竹根の起業日記】は、10年のサラリーマン生活をしてきた竹根好助35歳の経営コンサルタントとしての独立起業日記です。
これから経営コンサルタントとして独立起業しようと考えている人の参考となることを願い、経営コンサルタントとしての実践を経験的に語るつもりです。
日記の主であります私(竹根)は、35歳の商社マンで、産業機械部第一課課長、2013年4月1日に経営コンサルタントという職業に関心を持ちました。
そのような中で直属上司とぶつかることが多い竹根は、商社の限界を感じたり、経営コンサルティング業による社会貢献のすばらしさがわかってきたり、ついにはヘッドハンターからコンタクトがあったりと揺れ動く竹根。サラリーマンを辞めるのか、それとも、別な道を歩むべきか、迷った挙げ句の決断は、日本を代表するコンサルティング・ファームである竹之下経営にお世話になることに決めた。
商社マンを辞めて、経営コンサルタント業界に一歩足を踏み入れた竹根である。連日、今まで体験したことのない中で、日本経営士協会のチュータリングサービスで経営コンサルタントとしての自分を磨く毎日である。
毎日20時30分頃発信しています。ただし、一部のブログでは翌朝の発行となることもあります。
【 注 】
ここに記載されていることは実在の企業とは何ら関係ありません。
 【あらすじ】 【登場人物】 【作者紹介】 ←クリック
【あらすじ】 【登場人物】 【作者紹介】 ←クリック■ 思考用具体系「ヒエラルキー・ツール」 14-5-5-1
「クリティカル・シンキングのポイントが解る本」をもとに研究を続けている。クリティカル・シンキングの思考手法の具体的な方法のうち「ヒエラルキー・ツール」が、今回のテーマである。
◇2-4 ヒエラルキー(ツール )
ヒエラルキー・ツールとは、一般に「階層制度」と訳され、主にピラミッド型組織を意味します。ツールとしてのヒエラルキーの代表は、ロジックツリーやピラミッドストラクチャーです。
ロジックツリーとは、課題FoO題の原因追求や解決方法を、MECEやWhy so?So what?などの考え方に基づき論理的(ロジカル)に階層化し、ツリー状に分解整理するツールのことです。
■ 匠製本のカタログ提案 14-5-5-2
匠製本の英文カタログ用の翻訳が出来上がったので、それを萩野専務に持参した。私が訪問するとかならず顔を見せる橋上社長は、外出中とかで、不在であった。
英文原稿を見せる前に、萩野専務に提案した。数機種のカタログを印刷するとなると、それだけで百万円は超えるだろうし、まだどの機種が、どの国に売れるかわからない状態で、それだけの投資をするのはどうかと率直な意見をぶつけてみた。
専務も、お金の問題となると、確かに苦しいが、社長は、先行投資として何とか工面をすると言っているようである。
私の提案は、見開きA3サイズで、全商品を掲載する総合カタログ的なものを作成し、詳細情報は、パソコンでやや高級感のある紙に印刷した物を使えば良いのではないかと提案した。
専務も、私の提案に甚く感動し、自分が国内向けの機種別A4リーフレットの形式にこだわっていたことを反省する言葉が返ってきた。ふたりで、その構想を具体化しようと作業に取りかかった。気がついたら夜中の十一時を回っていた。
■ 明和大学社会人講座 14-5-5-3
日本経営士協会主催の明和大学社会人講座が今日から始まる。少し早めに自宅を出たのであるが、明和大学に近い改札口とは反対側の改札口からだたために迷ってしまった。以前に行ったことがあるので、軽く見たのが誤りであった。多少余裕を見ていたのであるが、すでに講義が始まっていた。
8回シリーズの第一回目は「経営者を斬る」というタイトルで、講師は、協会の理事長という豪華メンバーである。「経営とは何か」「今日的優良企業」という点にフォーカスを当てた話に始まり、出版社の事例紹介があり、その出版社をさらによくするにはどのようなコンサルティングをするかというワークセッションがあった。
ITコーディネーターをしている人が一人いて、その人の独演会のようなワークセッションであった。時々講師が回ってくると独演を止め、他の人が話をする。講師がそれにコメントやアドバイスを出してくれる。
結局時間切れとなり、発表は、私が担当することになった。討議中に出てきた言葉を断片的に取り入れて、自分の考えを中心に発表した。すっかり上がってしまって、自分が何を話したのか覚えていない。
私の後に発表した人は、まだ大学生であるというのに、堂々と発表をしていた。発表の仕方も、まず「今日的優良企業」という講師の話をまず要約し、それをもとに、この出版社がどの様に経営すべきかを述べた。その鮮やかさに、自分が恥ずかしくなった。
■ 海外に関心がある企業 14-5-5-4
萩野専務と作業を一緒にしながら、自分のモラールが非常に高くなっていることに気がついた。匠製本以外でも、きっと同じように輸出をしたいが、やり方も、英文カタログや販売ツールも揃っていない中小企業がたくさんあるはずである。そこに、同じようなあぷろーちをしたらどうかと考えると、俄然やる気が起こった。
ジェトロの会員なら、海外販売にも関心が高いであろうということに気がつき、思い切ってジェトロの会員になろうと考えた。会員になれば会員名簿が手に入り、それをもとにアプローチを掛ければ良いだろうと思い立ったのである。
早速サイトを調べると、年会費が七万円と、クライアントのいない無収入の自分には負担が大きすぎることもわかった。妻にその話をすると、先行投資として、そのくらいは積極的に取り組むべきだと、思いもよらない返事が返ってきた。
早速、ネットから入会申込をした。
匠製本の萩野専務から電話があり、できるだけ早期に訪問して欲しいということで、来週の六月四日に訪問することにした。