2012/10/07 民数記十九章「赤い雌牛の灰の水」
詩篇五六篇 使徒の働き二十7―12
民数記の十六章から続いて参りました、祭司の役割についての教えが、今日の箇所で一段落します。次の二十章からはまたしばらく、色々な出来事が綴(つづ)られていきますので、この十九章は一つの区切りとして大切な意味を持っているはずです。それが、雌牛の灰を作って、それを混ぜた水を、死者に触れた人に振りかけて、汚れをきよめなければならない、という規程です。
新約聖書のヘブル人への手紙九章13―14節にはこうあります。
「もし、やぎと雄牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが聖めの働きをして肉体をきよいものにするとすれば、
14まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神におささげになったその血は、どんなにか私たちの良心をきよめて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕える者とすることでしょう。」
今日の民数記十九章の「雌牛の灰」を引用して、まして、キリストの血は、どんなにか私たちの良心をきよめるか、と言う。しかし、逆に言えば、そういう引き合いに出すぐらい、この規程は大事なものである、ということでもあるでしょう。
それにしても、今日の箇所は、第一印象も取っつきにくく思われるでしょうが、読めば読むほど、不思議であり、また「異例」ずくめです。まず、赤い雌牛とありますが、赤いかどうか、以前に、雌牛を屠って儀式に使う、という事例はここ以外にありません。また、3節にあるように、
「宿営の外に引き出し」
つまり、幕屋の中の祭壇ではなく、外で動物を焼くというのも他にはない指示です。
「 5その雌牛は彼の目の前で焼け。その皮、肉、血をその汚物とともに…」
焼くという焼き方も特別です。全焼のいけにえでさえ、皮は剥ぎ、血は流し、内蔵は洗った、その残りを「全焼」とするのです。
「 6祭司は杉の木と、ヒソプと、緋色の糸を取り、それを雌牛の焼けている中に投げ入れる。」
というのもここだけです。レビ記十四6でも、この三点セットは登場しましたが、焼かれはしませんでした。
そもそも、これは「いけにえ」ではありません。「焼く」という動詞が生贄を焼く場合とは別の言葉が使われています。焼かれるのも、祭壇でではなく、外で灰を作るため、なのです。
こうした雌牛の扱いそのものについての異例さと共に、目に付くのは後半11節以下の、罪の汚れの理解もユニークであることです。雌牛を焼くのは、その灰を湧き水に混ぜて、汚れをきよめる水として用いるためでした。しかし、その罪の汚れとは、
「11どのような人の死体にでも触れる者は、七日間、汚れる。」
こう言われる通り、人の死体に触れたときの「汚れ」なのです。道徳的な罪ではなくて、死体に触れた結果、触った人が担う汚れを指して、「罪」と言っているのです。道徳的なことを言えば、人の死体に触れることが罪だとは言えません。むしろ、嫌がらずに死体に触れることがその人の憐れみとか自己犠牲の精神から出ている、ということもあるでしょう。「善きサマリヤ人」の譬えで、祭司とレビ人が、強盗に襲われた旅人を見ながら、
「反対側を通り過ぎて行ってしまった」
のは、もし死んでいた場合に死体に触れたら自分が汚れることになってしまう、と考えたからでもあったのでしょう。それは明らかに非難すべき行動でした。ですから、ここで言われている「罪の汚れ/罪のきよめ」とは、死体に触れることが道徳上よろしくない、という事ではなく、もっと根源的な人間の罪を扱っているのでしょう。人道的には何一つ責められるようなことはしていなくても、人は必ず死ななければなりません。また、周りの人が突如として亡くなり、その亡骸(なきがら)に触れざるを得ない場合も起こるでしょう。そういう身近な死によって人間が思い知らされる罪-いのちの源である神に背を向けてしまっている罪の事実-をここでは問うているのです。
人間の罪の現実の、どうしようもなさ、死という冷たい事実を問うてくる。そして、それは三日目と七日目にきよめの水をかける、という形の儀式であって、その水をかければ忽(たちま)ちきよくなるというものでもないし、かえってその儀式に関わった人、灰に触ったきよい人たちさえも汚れに巻き込まずにはおれない、ということにもまた、死の現実の度(ど)し難(がた)さが現されているのではないでしょうか。
そして、それがまた、赤い雌牛だとか、宿営の外だとか、最初に申し上げたこの規程のユニークさの理由でもあるのでしょう。罪を犯すとか犯さないとか、そういうレベルとはもっと別の次元でのきよめが必要であることを、死という現実に触れるときに人間は気づかなければならない、ということなのです。祭壇や幕屋での儀式では間に合わないような、きよめの儀式が備えられなければならない、としていた意味では、旧約の儀式律法の限界をここで現しています。様々な生贄や儀式が定められてはいましたが、それが万能なのではなく、本当に肝腎な、一番の根底にある死という問題を解決することは、幕屋や神殿や儀式では出来ない、と白状しているのです。
死は人間にとって自然なものではありません。本来、神様は人間をご自身のかたちに似せてお造りになり、儚(はかな)い死すべき存在としてではなく、ご自身との永遠の交わりに生きるものとしようとされたのです。その神様に逆らい、人間が自分の力で生きようとし始めた時に、人は死すべき者となってしまって、今日に至っています。死は、それ自体が、人間が神に背いた事実の証しです。勿論、その死さえも神様は益とされて、私たちに最善をなしてくださいます。また、慰めに満ちた死に方とか、悔いのない最期という場合もあります。そうでなくとも、私たちは、死の先に、イエス様が私共を迎え入れてくださり、地上の生涯では朧(おぼろ)な幻でしかなかった祝福へと導き入れてくださる、と知らされています。それでも、その死自体は益でも喜びでもなく、神様のいのちのわざを無に帰そうとする虚しいものであり、罪の報酬であることを私たちは忘れてはならないのです。
今日、この民数記十九章で、祭司の役割について教えてきた締め括りに、このような規程がある事実を心に刻みましょう。祭司は、民に、死をサラリと流さず、そこでもう一度謙(へりくだ)り、砕かれて、神様へと悔い改めさせることを、その大きな使命の一つとしていました 。死の中にある民に、いのちの神をしっかりと仰がせることが、祭司の重要な役割だったのです。それは、今日の教会にも言えることでしょう。キリスト教の葬儀に出席して初めてキリスト教に触れる、意味が分かる葬儀という体験をする、という声をよく聴きますが、そういう場でこそ、お茶を濁したような弔辞ではなく、本当に神様の前に謙り、悔い改めるような告白を、キリスト者が自ら持つべきなのです。
最初に引用しましたように、ヘブル人への手紙九13、14では、
「もし、やぎと雄牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが聖めの働きをして肉体をきよいものにするとすれば、
14まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神におささげになったその血は、どんなにか私たちの良心をきよめて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕える者とすることでしょう。」
と言われていました。私たちは、雌牛の灰よりも遥かに優れた、イエス・キリストの血に与っています。イエス・キリストは私たちのために、都の外で十字架に殺されました。そして、私たちに水の洗礼をお命じになり、罪の全ききよめを現してくださいました。赤い雌牛ならぬ赤い葡萄液の杯を差し出されて、私たちにご自身のいのちを差し出してくださっています。私たちは、死を恐れることなく、永遠のいのちをいただいて歩んでいますが、それは死を軽んじるのではなく、イエス様の十字架の死という測り知れないみわざを心に深く留めることによってなされるのですし、また、私たちの生活が、死んだ行いから離れさせる-この地上の朽ち行くものを(責任をもって受け止めつつ)決してそこに価値の規準を置いたり耽溺したりせずに生きる-ことを伴うのです。
今日読みました使徒の働きで、パウロが死んだ者に汚れを恐れることなく触れたという行動は、死者にふれては汚れる、という律法の限界を超えて、死に優るいのちを証しした行為でもありました 。私たちも、イエス様の十字架を知ることによって、どんな死よりも強い、生ける神に仕える者として整えていただきたいと願うのです。
「私共の心に主のいのちを届けてください。死の闇を打ち破るいのちの光を輝かせてください。たくさんの死のニュースに、心を麻痺させるでも恐れるでもなく、この世界のためにこそイエス様がおいでくださったのだと、深く覚えさせてください。自分や愛する者が死すべき存在でありつつ、いのちに生かされていると心から告白させてください」?
文末脚注
1 ルカ伝十章13、14節。
2 そのためにも、祭司たち自身が、死者にふれることが厳しく制限されていました。レビ記二一1、11以下参照。
3 使徒二〇7―12。また、エリヤ(Ⅰ列王記十七19、21)、エリシャ(Ⅱ列王記四34)も、死者に身を重ねました。また、善きサマリヤ人の譬えを語られたイエス様ご自身、死者に触れられていのちをお与えになりました(ルカ八54)。
詩篇五六篇 使徒の働き二十7―12
民数記の十六章から続いて参りました、祭司の役割についての教えが、今日の箇所で一段落します。次の二十章からはまたしばらく、色々な出来事が綴(つづ)られていきますので、この十九章は一つの区切りとして大切な意味を持っているはずです。それが、雌牛の灰を作って、それを混ぜた水を、死者に触れた人に振りかけて、汚れをきよめなければならない、という規程です。
新約聖書のヘブル人への手紙九章13―14節にはこうあります。
「もし、やぎと雄牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが聖めの働きをして肉体をきよいものにするとすれば、
14まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神におささげになったその血は、どんなにか私たちの良心をきよめて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕える者とすることでしょう。」
今日の民数記十九章の「雌牛の灰」を引用して、まして、キリストの血は、どんなにか私たちの良心をきよめるか、と言う。しかし、逆に言えば、そういう引き合いに出すぐらい、この規程は大事なものである、ということでもあるでしょう。
それにしても、今日の箇所は、第一印象も取っつきにくく思われるでしょうが、読めば読むほど、不思議であり、また「異例」ずくめです。まず、赤い雌牛とありますが、赤いかどうか、以前に、雌牛を屠って儀式に使う、という事例はここ以外にありません。また、3節にあるように、
「宿営の外に引き出し」
つまり、幕屋の中の祭壇ではなく、外で動物を焼くというのも他にはない指示です。
「 5その雌牛は彼の目の前で焼け。その皮、肉、血をその汚物とともに…」
焼くという焼き方も特別です。全焼のいけにえでさえ、皮は剥ぎ、血は流し、内蔵は洗った、その残りを「全焼」とするのです。
「 6祭司は杉の木と、ヒソプと、緋色の糸を取り、それを雌牛の焼けている中に投げ入れる。」
というのもここだけです。レビ記十四6でも、この三点セットは登場しましたが、焼かれはしませんでした。
そもそも、これは「いけにえ」ではありません。「焼く」という動詞が生贄を焼く場合とは別の言葉が使われています。焼かれるのも、祭壇でではなく、外で灰を作るため、なのです。
こうした雌牛の扱いそのものについての異例さと共に、目に付くのは後半11節以下の、罪の汚れの理解もユニークであることです。雌牛を焼くのは、その灰を湧き水に混ぜて、汚れをきよめる水として用いるためでした。しかし、その罪の汚れとは、
「11どのような人の死体にでも触れる者は、七日間、汚れる。」
こう言われる通り、人の死体に触れたときの「汚れ」なのです。道徳的な罪ではなくて、死体に触れた結果、触った人が担う汚れを指して、「罪」と言っているのです。道徳的なことを言えば、人の死体に触れることが罪だとは言えません。むしろ、嫌がらずに死体に触れることがその人の憐れみとか自己犠牲の精神から出ている、ということもあるでしょう。「善きサマリヤ人」の譬えで、祭司とレビ人が、強盗に襲われた旅人を見ながら、
「反対側を通り過ぎて行ってしまった」
のは、もし死んでいた場合に死体に触れたら自分が汚れることになってしまう、と考えたからでもあったのでしょう。それは明らかに非難すべき行動でした。ですから、ここで言われている「罪の汚れ/罪のきよめ」とは、死体に触れることが道徳上よろしくない、という事ではなく、もっと根源的な人間の罪を扱っているのでしょう。人道的には何一つ責められるようなことはしていなくても、人は必ず死ななければなりません。また、周りの人が突如として亡くなり、その亡骸(なきがら)に触れざるを得ない場合も起こるでしょう。そういう身近な死によって人間が思い知らされる罪-いのちの源である神に背を向けてしまっている罪の事実-をここでは問うているのです。
人間の罪の現実の、どうしようもなさ、死という冷たい事実を問うてくる。そして、それは三日目と七日目にきよめの水をかける、という形の儀式であって、その水をかければ忽(たちま)ちきよくなるというものでもないし、かえってその儀式に関わった人、灰に触ったきよい人たちさえも汚れに巻き込まずにはおれない、ということにもまた、死の現実の度(ど)し難(がた)さが現されているのではないでしょうか。
そして、それがまた、赤い雌牛だとか、宿営の外だとか、最初に申し上げたこの規程のユニークさの理由でもあるのでしょう。罪を犯すとか犯さないとか、そういうレベルとはもっと別の次元でのきよめが必要であることを、死という現実に触れるときに人間は気づかなければならない、ということなのです。祭壇や幕屋での儀式では間に合わないような、きよめの儀式が備えられなければならない、としていた意味では、旧約の儀式律法の限界をここで現しています。様々な生贄や儀式が定められてはいましたが、それが万能なのではなく、本当に肝腎な、一番の根底にある死という問題を解決することは、幕屋や神殿や儀式では出来ない、と白状しているのです。
死は人間にとって自然なものではありません。本来、神様は人間をご自身のかたちに似せてお造りになり、儚(はかな)い死すべき存在としてではなく、ご自身との永遠の交わりに生きるものとしようとされたのです。その神様に逆らい、人間が自分の力で生きようとし始めた時に、人は死すべき者となってしまって、今日に至っています。死は、それ自体が、人間が神に背いた事実の証しです。勿論、その死さえも神様は益とされて、私たちに最善をなしてくださいます。また、慰めに満ちた死に方とか、悔いのない最期という場合もあります。そうでなくとも、私たちは、死の先に、イエス様が私共を迎え入れてくださり、地上の生涯では朧(おぼろ)な幻でしかなかった祝福へと導き入れてくださる、と知らされています。それでも、その死自体は益でも喜びでもなく、神様のいのちのわざを無に帰そうとする虚しいものであり、罪の報酬であることを私たちは忘れてはならないのです。
今日、この民数記十九章で、祭司の役割について教えてきた締め括りに、このような規程がある事実を心に刻みましょう。祭司は、民に、死をサラリと流さず、そこでもう一度謙(へりくだ)り、砕かれて、神様へと悔い改めさせることを、その大きな使命の一つとしていました 。死の中にある民に、いのちの神をしっかりと仰がせることが、祭司の重要な役割だったのです。それは、今日の教会にも言えることでしょう。キリスト教の葬儀に出席して初めてキリスト教に触れる、意味が分かる葬儀という体験をする、という声をよく聴きますが、そういう場でこそ、お茶を濁したような弔辞ではなく、本当に神様の前に謙り、悔い改めるような告白を、キリスト者が自ら持つべきなのです。
最初に引用しましたように、ヘブル人への手紙九13、14では、
「もし、やぎと雄牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが聖めの働きをして肉体をきよいものにするとすれば、
14まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神におささげになったその血は、どんなにか私たちの良心をきよめて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕える者とすることでしょう。」
と言われていました。私たちは、雌牛の灰よりも遥かに優れた、イエス・キリストの血に与っています。イエス・キリストは私たちのために、都の外で十字架に殺されました。そして、私たちに水の洗礼をお命じになり、罪の全ききよめを現してくださいました。赤い雌牛ならぬ赤い葡萄液の杯を差し出されて、私たちにご自身のいのちを差し出してくださっています。私たちは、死を恐れることなく、永遠のいのちをいただいて歩んでいますが、それは死を軽んじるのではなく、イエス様の十字架の死という測り知れないみわざを心に深く留めることによってなされるのですし、また、私たちの生活が、死んだ行いから離れさせる-この地上の朽ち行くものを(責任をもって受け止めつつ)決してそこに価値の規準を置いたり耽溺したりせずに生きる-ことを伴うのです。
今日読みました使徒の働きで、パウロが死んだ者に汚れを恐れることなく触れたという行動は、死者にふれては汚れる、という律法の限界を超えて、死に優るいのちを証しした行為でもありました 。私たちも、イエス様の十字架を知ることによって、どんな死よりも強い、生ける神に仕える者として整えていただきたいと願うのです。
「私共の心に主のいのちを届けてください。死の闇を打ち破るいのちの光を輝かせてください。たくさんの死のニュースに、心を麻痺させるでも恐れるでもなく、この世界のためにこそイエス様がおいでくださったのだと、深く覚えさせてください。自分や愛する者が死すべき存在でありつつ、いのちに生かされていると心から告白させてください」?
文末脚注
1 ルカ伝十章13、14節。
2 そのためにも、祭司たち自身が、死者にふれることが厳しく制限されていました。レビ記二一1、11以下参照。
3 使徒二〇7―12。また、エリヤ(Ⅰ列王記十七19、21)、エリシャ(Ⅱ列王記四34)も、死者に身を重ねました。また、善きサマリヤ人の譬えを語られたイエス様ご自身、死者に触れられていのちをお与えになりました(ルカ八54)。













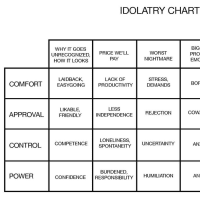
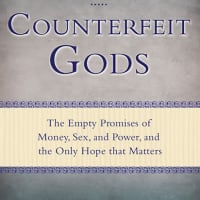













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます