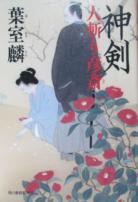
この小説は、安政7年(1860)3月3日、桜田門外で時の大老井伊直弼を暗殺した水戸浪士が、細川越中守の屋敷に自訴する。玄関での最初の応接を茶坊主の男が行う場面から始まる。この茶坊主が後に尊攘派の志士として、人斬り彦斎(げんさい)として激烈な活動をし、京洛に勇名を轟かせる。この小説は人斬り彦斎と呼ばれ、恐れられた河上彦斎の人生を嘉永3年(1850)12月、17歳の時を起点に、明治4年(1871)12月斬罪の判決により刑死、享年38歳まで描いている。
だが、読後印象としては、人斬り彦斎(げんさい)の尊攘派志士としての思想・信条および激烈な行動を描きながら、彦斎の目を通して眺めた幕末動乱期から明治新政府樹立の時代における尊皇攘夷思想の鵺の如き変転の実態を描くということにこそ、著者のテーマがあったような印象を抱く。人斬り彦斎の観点に立てば、薩摩・長州の目的は、尊皇攘夷という建前を掲げることで、江戸幕府政権を打倒し、王政復古の下で政権を行使する力を奪取することにこそあったということになる。実質的な政権担当者、支配者側になるということである。勿論、そこには清国の二の舞には陥らず、世界の列強に対抗していくという前提があってのことなのだが。
京都に住み、三条小橋の傍に立つ佐久間象山遭難碑を数え切れない位、目にしながら通り過ぎてきたが、誰に暗殺されたのかを固有名詞として考えたことはなかった。この小説を読み、私は初めて河上彦斎が象山を暗殺した人物ということを知った。これは私にとって、知識の副産物でもある。
さて、河上彦斎は、九州、肥後・熊本藩54万石の御花畑表御掃除坊主として16歳のときに召し抱えられ仕えていた。「五尺に足りない小柄な背丈で女人のようにほっそりした体つきだ。色白でととのった顔立ちの美男だが、清雅な趣がある」(p8)と描写されている。茶坊主という役目柄、頭を剃っていたために、同年配の武士からは馬鹿にされる立場であった。しかし、本人は役目として意に介さず仕えていた。そんな男が人斬り彦斎という生き様を選択したのである。なぜ、そうなったか? それがこのストーリーである。
この小説から河上彦斎に直接の影響を与えた人物が3人居ると理解した。17歳の頃から彦斎が師事した宮部鼎蔵(みやべていぞう)。熊本藩の兵学師範である。宮部鼎蔵は肥後における尊攘派のリーダーとなっていく。彦斎はまず宮部の思想を学ぶ。この宮部鼎蔵は、後に京都の池田屋事件の折りに新選組により殺される。
17歳の時、宮部鼎蔵を介し、九州遊学途中の吉田寅次郎(松蔭)を知り、吉田寅次郎の話から世界の情勢、特にアヘン戦争の清国の実情を知る。この時期、吉田寅次郎は、長州藩の藩校・明倫館で山鹿流軍学師範をしていたそうだ。吉田の謦咳に接し感銘を受けた彦斎は、その後の吉田の実践的行動力を具に知り、己の尊攘の信条を強める上で影響を受け続ける。尊攘派の一人として、吉田寅次郎の生き様から強烈なインパクトを受けるのである。著者は、彦斎が吉田松陰の「今の幕府も諸侯も最早酔人なれば扶持の術なし。草莽崛起(そうもうくっき)の人を望むほか頼みなし」に影響を受け、それを美しいことと受け止めたと描く。吉田松蔭の影響が大きいようである。
もう一人が林桜園である。国学だけでなく儒学、仏教、天文、地理、歴史に精通していた学者である。桜園は『宇気比考』を著しているという。「皇御国(すめらみくに)はそもそも言霊の佐(たす)け幸(さきわ)う国であり、言挙げすれば、天神地祇(ちぎ)の助けを蒙ることができるとする。宇気比は神事の根本義である」と桜園は唱える。この宇気比の思想を彦斎は受け止め、己の行動の基本にしていく。
驚いたのは、人斬り彦斎という勇名を轟かせ、剣の腕を振るった彦斎が剣技はほぼ独学で修得したらしいということだ。熊本藩で盛んだった伯耆流居合いの見取り稽古をして学んだ抜刀術を日夜自邸で錬磨することで、剣技の腕を磨いたとされている。一人稽古という自得の道を歩んだのだ。つまり、彦斎の基本は抜き打ちである。刀は「肥後拵(ひごこしらえ)」と呼ばれる刀身2尺1寸(約63cm)を常用したようである。
嘉永4年3月、彦斎は藩主の参勤交代の供をして江戸に赴く。嘉永7年にはアメリカのペリー提督率いる艦隊が来航し、吉田寅次郎はアメリカに行くためにペリー艦隊に近づくという行動をとるも、失敗し国許に送還され獄に投じられるという事件が起こっている。安政3年(1856)熊本に帰国。2年後、安政5年3月には、再び藩主に随従して出府。この年6月には、井伊直弼による<安政の大獄>が起こる。吉田松蔭はこの安政の大獄で刑死する。万延元年(1860)10月、彦斎は藩主慶順に従い帰国。文久2年7月、左大臣一条忠香より、熊本藩主細川慶順に国事周旋の内勅が下され、やむなく藩主の連枝である長岡左京亮が11月に上洛することになる。このとき宮部鼎蔵をはじめとする名だたる尊攘派が随従し、彦斎も供に加わる。このとき彦斎は髪を伸ばすことを許されたという。この頃、京都市中では尊攘派の志士による天誅が荒れ狂っていたのである。この11月には、井伊直弼の寵愛を受けたことがあり、長野主膳の奸計を助けたとして、村山たかが尊攘派志士によって、三条大橋傍で生き晒しにされる事件が起こっている。
このストーリーでは、これが彦斎にとって「天誅」とは何かを示す契機となる。「女人まで狙う天誅はわたしの好むものではありません」と言わしめる。つまり、「天とは清淨にして公明正大なものです。強き悪に罰は下りましょうが、弱き者を誅して快哉を上げるのは天の名を騙る所業です」という考えである。そして、「まことの天誅がいかなるものか見せねばなりますまい」と。結果的に、この瞬間から人斬り彦斎と呼ばれる生き様が始まって行く。
薩摩尊攘派に眼を掛けられ藩士とはいいがたい身分だったが、仲間に入れてもらえたことから率先して天誅をおこなった<人斬り新兵衛>、そして同様の身分だが、土佐勤王党の武市半平太弟子となり勤王党に加わり天誅を行うことで己の居場所を築いた<人斬り以蔵>。なんと、この二人の所業を天の名を騙るものとして、彼らの「誇りを斬る」と立ち向かうのだから、痛快である。
そして、彦斎の行動の結果が波紋を広げ、各藩の尊攘派の人々との様々な関係が広がり、その関係が生まれる政治的背景、時代背景が織り交ぜられて語られている形になる。だが、この背景描写を通して、当時の政治的空気の昂揚、攪乱と乱流、結束と統合のダイナミズムが書き込まれていく。それは彦斎の立ち位置から眺めたものでもある。時代をどうのようにとらえるかは、どの観点から、立ち位置から眺めるかで変化する。
このストーリーで異彩を放つのは由依という女性の存在である。国学者林桜園が、遠縁の娘で早くに父母を亡くし孤児となった由依を、本当の娘同様に育てたのである。由依は嘉永4年に、彦斎より2ヵ月遅れて江戸に着き、江戸藩邸の奥女中として努めた後、京都にて公家の三条実美邸の奧仕えの女中を務めるようになっていく。肥後の尊攘派と三条実美との繋ぎの役割を密かに果たす立場にもなっていく。そこには養父桜園の思想の一端を受け継ぐ思いとともに、密かに彦斎への思いに通じるものがあるという形で描かれて行く。 このストーリーのプロセスで、彦斎と由依は「尊攘」という立場を介して、互いの思いが織り上げられていくことになる。この二人の思いのあり方を描くのがサブ・テーマでもあるように思う。一種の忍ぶ恋である。
彦斎の信条は明瞭である。天誅とは神の下したもう罰であり、天誅をなすは神の意に従う者のみである。神の意を如何にして知りうるか。彦斎は天誅をなすべき対象であるかどうかは、懐紙を引き裂き、その一紙片に名を書き記し、それら紙片を杯洗に浮かべて、名を記した紙片が沈まずに浮いているかどうかで、神意を見極めるという方法をとる。神意を受け止め、天誅を加える者としての人斬りを己の務めとして推敲するのである。
本書のタイトルにある「神剣」は、彦斎の天誅の信条から由来するのだろう。
文久3年(1863)1月27日、京都東山の翠紅館(すいこうかん)で、水戸、長州、土佐、対馬、津和野、熊本各藩の尊攘派有志二十余人の会合に、彦斎も末席に加わる。その席で名の出た似非尊攘浪人を彦斎は斬る。真に人斬り彦斎と呼ばれる始まりだと描かれる。
この後、人斬り彦斎がどういう行動をとるのか、幕末動乱の動きはどうなのか、本書を読み進めていただくと良い。
人斬り新兵衛が公家姉小路公知暗殺事件との関わりを疑われ自決。その間接的原因が彦斎にあること。
薩摩の人斬り半次郎と彦斎が白刃を交えることになること。
彦斎は七卿落ちという事態に立ち至った時、三条実美の護衛役として随行すること。
池田屋事件後、彦斎が勝海舟に面会を求め、勝海舟という人物を見極めること。
勝海舟に佐久間象山を斬ると彦斎が宣言し、象山を斬るに至ること。
三条実美に随行していた彦斎が奇兵隊を創設した高杉晋作との関係ができること。
岩国城下を訪れた近藤勇の宿舎に彦斎は行き宮部鼎蔵の仇討ちと称し対決すること。
京の薩摩藩家老屋敷まで尊攘派の桂たちを護衛し送りとどけること。
新選組に入隊した象山の息子・恪二郎が沖田に惨殺されそうになるのを救うこと。
長州藩と幕府海軍との四境戦争で、彦斎は高杉晋作に協力して戦いに加わること。
長州藩と戦火を交えた熊本藩を救うために、肥後に戻る行動をとること。
故郷の者に向ける刃は持たぬとして、悠然と捕縛され、獄舎に繋がれること。
出獄後上京し、木戸孝允(桂)、三条実美などと面談し、情勢を知ること。
明治2年(1869)、九州・鶴崎で有終館を開設し、運営すること。
攘夷派弾圧が始まる中で、彦斎は再び明治4年、獄中の人となること。
このような彦斎の行動の軌跡が描かれて行く。
彦斎は熊本で獄中に居たにもかかわえらず、1月9日に東京で、長州出身の参議、広沢真臣が麹町の私邸で殺されるという事件が起こる。その犯人の嫌疑が彦斎にかかったという。この広沢参議殺しには様々な説・憶測があるようだ。いずれにしろ、当時高田源兵衛と改名していた彦斎は、東京に移送され、斬首されることになる。
このストーリーでは、判事と彦斎が交わした会話として以下の描写をする。
「あなたの志はわかるが、すでに世の中は変わろうとしている。考えをあらためて政府に協力していただけないか。さように言っていただけば必ず一命はお助けいたしますぞ」
「お言葉はありがたいが、私は志とはさように変えることのできないものだと思っている。いま、政府はかつての尊攘の志を捨てて得体の知れぬ化け物になろうとしている。さような化け物の仲間に入りたいとは夢思わぬ」
ここに、彦斎の思いが凝縮していると感じる。
幕末動乱期から明治維新にかけての「尊攘の志」は万華鏡の如きものだったのだ。人斬り彦斎の生き様が、結果的にそのことを読者に語っているように思う。
262ページで、著者は「河上彦斎言行録」に言及している。ネット検索で調べてみると、河上彦斎建碑事務所編『河上彦齋』が1926年9月に出版されれている。「河上彦斎言行録」、「高田玄明遺詠鈔 」などが含まれているそうである。
最後に、本書の各所に引用されている彦斎が詠んだ歌を抽出引用しておきたい。ここに人斬り彦斎の信条・心情が詠み込まれていると感じる。どのような文脈で著者がこれらの歌を織り込んでいるかを、本書を読み進めて、味読していただくとよい。
我こころ人はかくとも知ら雲の思はぬ方に立ちへだつ哉
うき名とや我が身をしらで立ちしより恋といふ路をふみにぞ初めにき
うき名とや我が身をしらで立ちしより恋しく人を思ひ初めけり
黒髪は生ひて昔にかへれどもなでにし人のいまさぬぞうし
君が代は富の小川の水すみて千年をふとも絶えじとぞ思ふ
帰らじとおもふにそひて古鄕の今宵はいとど恋しかりけり
仇波と人はいふとも国のため身を不知火の海や渡らん
濡衣に涙包みて思ひきや身を不知火の別れせんとや
そして、処刑に際し、彦斎は次の和歌を遺したという。
君がため死ぬる骸に草むさば赤き心の花や咲くらん
このストーリーは、西南戦争の勃発を記して、締めくくられている。
ご一読ありがとうございます。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
本書に出てくる事項で関心を惹かれたものについて検索してみた。一覧にしておきたい。
河上彦斎-人物伝 :「www.神風連.com」
河上彦斎 :ウィキペディア
京都の街を震え上がらせたテロリスト「幕末四大人斬り」 :「NAVERまとめ」
河上彦齋 / [河上彦齋建碑事務所編] :「九州大学附属図書館」
河上彦斎1 :「万遊歩撮」
河上彦斎 国士列伝 :「国立国会図書館デジタルコレクション」
吉田松陰の盟友「宮部鼎蔵」とはどんな人? :「NAVERまとめ」
No.073「宮部鼎蔵(みやべていぞう)」 :「ふるさと寺子屋」(熊本県観光サイト)
林桜園 :「コトバンク」
林桜園 :「熊本歴史・人物散歩道」(熊本国府高等学校PC同好会)
佐久間象山 :ウィキペディア
佐久間象山 :「コトバンク」
佐久間象山の暗殺(上) 白昼メッタ刺し、斬首…攘夷派の「憎悪」誘発した“開国攘夷派・象山”の「とんでもない計画」 2014.3.23 :「産経WEST」
有終館 :「鶴崎歴史散歩」
このページでは高田源兵衛への改名について本書とは異なる解釈があり、興味深い。
維新資料画像データベース :「京都大学附属図書館
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
徒然に読んできた作品の印象記に以下のものがあります。
こちらもお読みいただけると、うれしいかぎりです。
『辛夷の花』 徳間書店
『風かおる』 幻冬舎
『はだれ雪』 角川書店
『鬼神の如く 黒田叛臣伝』 新潮社
『決戦! 大坂城』 葉室・木下・富樫・乾・天野・冲方・伊東 講談社
===== 葉室 麟 作品 読後印象記一覧 ===== 更新4版(37+1冊)2016.1.27
だが、読後印象としては、人斬り彦斎(げんさい)の尊攘派志士としての思想・信条および激烈な行動を描きながら、彦斎の目を通して眺めた幕末動乱期から明治新政府樹立の時代における尊皇攘夷思想の鵺の如き変転の実態を描くということにこそ、著者のテーマがあったような印象を抱く。人斬り彦斎の観点に立てば、薩摩・長州の目的は、尊皇攘夷という建前を掲げることで、江戸幕府政権を打倒し、王政復古の下で政権を行使する力を奪取することにこそあったということになる。実質的な政権担当者、支配者側になるということである。勿論、そこには清国の二の舞には陥らず、世界の列強に対抗していくという前提があってのことなのだが。
京都に住み、三条小橋の傍に立つ佐久間象山遭難碑を数え切れない位、目にしながら通り過ぎてきたが、誰に暗殺されたのかを固有名詞として考えたことはなかった。この小説を読み、私は初めて河上彦斎が象山を暗殺した人物ということを知った。これは私にとって、知識の副産物でもある。
さて、河上彦斎は、九州、肥後・熊本藩54万石の御花畑表御掃除坊主として16歳のときに召し抱えられ仕えていた。「五尺に足りない小柄な背丈で女人のようにほっそりした体つきだ。色白でととのった顔立ちの美男だが、清雅な趣がある」(p8)と描写されている。茶坊主という役目柄、頭を剃っていたために、同年配の武士からは馬鹿にされる立場であった。しかし、本人は役目として意に介さず仕えていた。そんな男が人斬り彦斎という生き様を選択したのである。なぜ、そうなったか? それがこのストーリーである。
この小説から河上彦斎に直接の影響を与えた人物が3人居ると理解した。17歳の頃から彦斎が師事した宮部鼎蔵(みやべていぞう)。熊本藩の兵学師範である。宮部鼎蔵は肥後における尊攘派のリーダーとなっていく。彦斎はまず宮部の思想を学ぶ。この宮部鼎蔵は、後に京都の池田屋事件の折りに新選組により殺される。
17歳の時、宮部鼎蔵を介し、九州遊学途中の吉田寅次郎(松蔭)を知り、吉田寅次郎の話から世界の情勢、特にアヘン戦争の清国の実情を知る。この時期、吉田寅次郎は、長州藩の藩校・明倫館で山鹿流軍学師範をしていたそうだ。吉田の謦咳に接し感銘を受けた彦斎は、その後の吉田の実践的行動力を具に知り、己の尊攘の信条を強める上で影響を受け続ける。尊攘派の一人として、吉田寅次郎の生き様から強烈なインパクトを受けるのである。著者は、彦斎が吉田松陰の「今の幕府も諸侯も最早酔人なれば扶持の術なし。草莽崛起(そうもうくっき)の人を望むほか頼みなし」に影響を受け、それを美しいことと受け止めたと描く。吉田松蔭の影響が大きいようである。
もう一人が林桜園である。国学だけでなく儒学、仏教、天文、地理、歴史に精通していた学者である。桜園は『宇気比考』を著しているという。「皇御国(すめらみくに)はそもそも言霊の佐(たす)け幸(さきわ)う国であり、言挙げすれば、天神地祇(ちぎ)の助けを蒙ることができるとする。宇気比は神事の根本義である」と桜園は唱える。この宇気比の思想を彦斎は受け止め、己の行動の基本にしていく。
驚いたのは、人斬り彦斎という勇名を轟かせ、剣の腕を振るった彦斎が剣技はほぼ独学で修得したらしいということだ。熊本藩で盛んだった伯耆流居合いの見取り稽古をして学んだ抜刀術を日夜自邸で錬磨することで、剣技の腕を磨いたとされている。一人稽古という自得の道を歩んだのだ。つまり、彦斎の基本は抜き打ちである。刀は「肥後拵(ひごこしらえ)」と呼ばれる刀身2尺1寸(約63cm)を常用したようである。
嘉永4年3月、彦斎は藩主の参勤交代の供をして江戸に赴く。嘉永7年にはアメリカのペリー提督率いる艦隊が来航し、吉田寅次郎はアメリカに行くためにペリー艦隊に近づくという行動をとるも、失敗し国許に送還され獄に投じられるという事件が起こっている。安政3年(1856)熊本に帰国。2年後、安政5年3月には、再び藩主に随従して出府。この年6月には、井伊直弼による<安政の大獄>が起こる。吉田松蔭はこの安政の大獄で刑死する。万延元年(1860)10月、彦斎は藩主慶順に従い帰国。文久2年7月、左大臣一条忠香より、熊本藩主細川慶順に国事周旋の内勅が下され、やむなく藩主の連枝である長岡左京亮が11月に上洛することになる。このとき宮部鼎蔵をはじめとする名だたる尊攘派が随従し、彦斎も供に加わる。このとき彦斎は髪を伸ばすことを許されたという。この頃、京都市中では尊攘派の志士による天誅が荒れ狂っていたのである。この11月には、井伊直弼の寵愛を受けたことがあり、長野主膳の奸計を助けたとして、村山たかが尊攘派志士によって、三条大橋傍で生き晒しにされる事件が起こっている。
このストーリーでは、これが彦斎にとって「天誅」とは何かを示す契機となる。「女人まで狙う天誅はわたしの好むものではありません」と言わしめる。つまり、「天とは清淨にして公明正大なものです。強き悪に罰は下りましょうが、弱き者を誅して快哉を上げるのは天の名を騙る所業です」という考えである。そして、「まことの天誅がいかなるものか見せねばなりますまい」と。結果的に、この瞬間から人斬り彦斎と呼ばれる生き様が始まって行く。
薩摩尊攘派に眼を掛けられ藩士とはいいがたい身分だったが、仲間に入れてもらえたことから率先して天誅をおこなった<人斬り新兵衛>、そして同様の身分だが、土佐勤王党の武市半平太弟子となり勤王党に加わり天誅を行うことで己の居場所を築いた<人斬り以蔵>。なんと、この二人の所業を天の名を騙るものとして、彼らの「誇りを斬る」と立ち向かうのだから、痛快である。
そして、彦斎の行動の結果が波紋を広げ、各藩の尊攘派の人々との様々な関係が広がり、その関係が生まれる政治的背景、時代背景が織り交ぜられて語られている形になる。だが、この背景描写を通して、当時の政治的空気の昂揚、攪乱と乱流、結束と統合のダイナミズムが書き込まれていく。それは彦斎の立ち位置から眺めたものでもある。時代をどうのようにとらえるかは、どの観点から、立ち位置から眺めるかで変化する。
このストーリーで異彩を放つのは由依という女性の存在である。国学者林桜園が、遠縁の娘で早くに父母を亡くし孤児となった由依を、本当の娘同様に育てたのである。由依は嘉永4年に、彦斎より2ヵ月遅れて江戸に着き、江戸藩邸の奥女中として努めた後、京都にて公家の三条実美邸の奧仕えの女中を務めるようになっていく。肥後の尊攘派と三条実美との繋ぎの役割を密かに果たす立場にもなっていく。そこには養父桜園の思想の一端を受け継ぐ思いとともに、密かに彦斎への思いに通じるものがあるという形で描かれて行く。 このストーリーのプロセスで、彦斎と由依は「尊攘」という立場を介して、互いの思いが織り上げられていくことになる。この二人の思いのあり方を描くのがサブ・テーマでもあるように思う。一種の忍ぶ恋である。
彦斎の信条は明瞭である。天誅とは神の下したもう罰であり、天誅をなすは神の意に従う者のみである。神の意を如何にして知りうるか。彦斎は天誅をなすべき対象であるかどうかは、懐紙を引き裂き、その一紙片に名を書き記し、それら紙片を杯洗に浮かべて、名を記した紙片が沈まずに浮いているかどうかで、神意を見極めるという方法をとる。神意を受け止め、天誅を加える者としての人斬りを己の務めとして推敲するのである。
本書のタイトルにある「神剣」は、彦斎の天誅の信条から由来するのだろう。
文久3年(1863)1月27日、京都東山の翠紅館(すいこうかん)で、水戸、長州、土佐、対馬、津和野、熊本各藩の尊攘派有志二十余人の会合に、彦斎も末席に加わる。その席で名の出た似非尊攘浪人を彦斎は斬る。真に人斬り彦斎と呼ばれる始まりだと描かれる。
この後、人斬り彦斎がどういう行動をとるのか、幕末動乱の動きはどうなのか、本書を読み進めていただくと良い。
人斬り新兵衛が公家姉小路公知暗殺事件との関わりを疑われ自決。その間接的原因が彦斎にあること。
薩摩の人斬り半次郎と彦斎が白刃を交えることになること。
彦斎は七卿落ちという事態に立ち至った時、三条実美の護衛役として随行すること。
池田屋事件後、彦斎が勝海舟に面会を求め、勝海舟という人物を見極めること。
勝海舟に佐久間象山を斬ると彦斎が宣言し、象山を斬るに至ること。
三条実美に随行していた彦斎が奇兵隊を創設した高杉晋作との関係ができること。
岩国城下を訪れた近藤勇の宿舎に彦斎は行き宮部鼎蔵の仇討ちと称し対決すること。
京の薩摩藩家老屋敷まで尊攘派の桂たちを護衛し送りとどけること。
新選組に入隊した象山の息子・恪二郎が沖田に惨殺されそうになるのを救うこと。
長州藩と幕府海軍との四境戦争で、彦斎は高杉晋作に協力して戦いに加わること。
長州藩と戦火を交えた熊本藩を救うために、肥後に戻る行動をとること。
故郷の者に向ける刃は持たぬとして、悠然と捕縛され、獄舎に繋がれること。
出獄後上京し、木戸孝允(桂)、三条実美などと面談し、情勢を知ること。
明治2年(1869)、九州・鶴崎で有終館を開設し、運営すること。
攘夷派弾圧が始まる中で、彦斎は再び明治4年、獄中の人となること。
このような彦斎の行動の軌跡が描かれて行く。
彦斎は熊本で獄中に居たにもかかわえらず、1月9日に東京で、長州出身の参議、広沢真臣が麹町の私邸で殺されるという事件が起こる。その犯人の嫌疑が彦斎にかかったという。この広沢参議殺しには様々な説・憶測があるようだ。いずれにしろ、当時高田源兵衛と改名していた彦斎は、東京に移送され、斬首されることになる。
このストーリーでは、判事と彦斎が交わした会話として以下の描写をする。
「あなたの志はわかるが、すでに世の中は変わろうとしている。考えをあらためて政府に協力していただけないか。さように言っていただけば必ず一命はお助けいたしますぞ」
「お言葉はありがたいが、私は志とはさように変えることのできないものだと思っている。いま、政府はかつての尊攘の志を捨てて得体の知れぬ化け物になろうとしている。さような化け物の仲間に入りたいとは夢思わぬ」
ここに、彦斎の思いが凝縮していると感じる。
幕末動乱期から明治維新にかけての「尊攘の志」は万華鏡の如きものだったのだ。人斬り彦斎の生き様が、結果的にそのことを読者に語っているように思う。
262ページで、著者は「河上彦斎言行録」に言及している。ネット検索で調べてみると、河上彦斎建碑事務所編『河上彦齋』が1926年9月に出版されれている。「河上彦斎言行録」、「高田玄明遺詠鈔 」などが含まれているそうである。
最後に、本書の各所に引用されている彦斎が詠んだ歌を抽出引用しておきたい。ここに人斬り彦斎の信条・心情が詠み込まれていると感じる。どのような文脈で著者がこれらの歌を織り込んでいるかを、本書を読み進めて、味読していただくとよい。
我こころ人はかくとも知ら雲の思はぬ方に立ちへだつ哉
うき名とや我が身をしらで立ちしより恋といふ路をふみにぞ初めにき
うき名とや我が身をしらで立ちしより恋しく人を思ひ初めけり
黒髪は生ひて昔にかへれどもなでにし人のいまさぬぞうし
君が代は富の小川の水すみて千年をふとも絶えじとぞ思ふ
帰らじとおもふにそひて古鄕の今宵はいとど恋しかりけり
仇波と人はいふとも国のため身を不知火の海や渡らん
濡衣に涙包みて思ひきや身を不知火の別れせんとや
そして、処刑に際し、彦斎は次の和歌を遺したという。
君がため死ぬる骸に草むさば赤き心の花や咲くらん
このストーリーは、西南戦争の勃発を記して、締めくくられている。
ご一読ありがとうございます。
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
本書に出てくる事項で関心を惹かれたものについて検索してみた。一覧にしておきたい。
河上彦斎-人物伝 :「www.神風連.com」
河上彦斎 :ウィキペディア
京都の街を震え上がらせたテロリスト「幕末四大人斬り」 :「NAVERまとめ」
河上彦齋 / [河上彦齋建碑事務所編] :「九州大学附属図書館」
河上彦斎1 :「万遊歩撮」
河上彦斎 国士列伝 :「国立国会図書館デジタルコレクション」
吉田松陰の盟友「宮部鼎蔵」とはどんな人? :「NAVERまとめ」
No.073「宮部鼎蔵(みやべていぞう)」 :「ふるさと寺子屋」(熊本県観光サイト)
林桜園 :「コトバンク」
林桜園 :「熊本歴史・人物散歩道」(熊本国府高等学校PC同好会)
佐久間象山 :ウィキペディア
佐久間象山 :「コトバンク」
佐久間象山の暗殺(上) 白昼メッタ刺し、斬首…攘夷派の「憎悪」誘発した“開国攘夷派・象山”の「とんでもない計画」 2014.3.23 :「産経WEST」
有終館 :「鶴崎歴史散歩」
このページでは高田源兵衛への改名について本書とは異なる解釈があり、興味深い。
維新資料画像データベース :「京都大学附属図書館
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
徒然に読んできた作品の印象記に以下のものがあります。
こちらもお読みいただけると、うれしいかぎりです。
『辛夷の花』 徳間書店
『風かおる』 幻冬舎
『はだれ雪』 角川書店
『鬼神の如く 黒田叛臣伝』 新潮社
『決戦! 大坂城』 葉室・木下・富樫・乾・天野・冲方・伊東 講談社
===== 葉室 麟 作品 読後印象記一覧 ===== 更新4版(37+1冊)2016.1.27



















