
この本を手に取ったのは、本のタイトルがおもしろかったことと併せて、モディリアーニの絵が表紙に使われていたことによる。
「本書は、芸術家の恋愛をめぐる人生模様と作品が織り成す、華麗な物語を紹介する試みである」と、著者は「おわりに」の冒頭に記す。この一行は、「はじめに」の冒頭の一行、「美の本質は、恋愛にある」に呼応している。著者は「恋愛」というフィルターをかけて作品を選び出し、作品の裏に潜む芸術家の恋愛模様や主義を目の前に浮かび上がらせた。自分の感性・感覚だけで掲載作品を鑑賞した味わいに比べ、各章の解説を読んで改めて掲載作品を眺めると、甘み、苦み、酸味などが微妙複雑にからんだ味に一層変化してくる。
それは、手軽に実験できる。この本に所載の絵画、彫刻をまず自分の目で眺め、鑑賞しておく。まず独自に感じ、味わってみる。その後で各章のその主作品についての「恋愛」譚や、関連してさらに展開された説明を読む。そして、再びその章の絵画あるいは彫刻を鑑賞する。さて、そのお味はどう変化するだろうか。それを楽しむのには、手ごろなボリュームで各章がまとめられていると思う。
今まで様々な美術展でその作品群を鑑賞していた画家、彫刻家の幾人かについて、私はこの本からその人物の意外な人生模様を一歩踏み込んで知ることができ、一方、未見の作品にも誘われた。そして今後の作品鑑賞にひと味深みを付け加えられたように感じている。
著者は記す。「美とは、なにものかがなにものかを恋い求める際に、激しくかきたてられる感情を意味している。人がなにかを美しいと思うのは、その美しいと思われるもののなかに、自身が願ってやまないもの、求めてやまないものが結晶しているからである」と。本書に取りあげられた芸術家たちの恋い求めた姿がいかにバラエティに富んだものだったかがよくわかる。
章のまとめ方は2種類ある。一つは、特定の芸術家とその作品について、恋愛を軸に、様々な人々と作品の関わりへと展開して行く形式。つまり、モディリアーニ、ピカソ、ジェローム、ドガ、マネとモネ、ルノワール、ムンク、カミーユ・クローデルという人物名で八章がまとめられている。他の一つは、テーマ的見出し形式の下に、芸術家と作品に言及していくものである。こちらには、「ダンテとベアトリーチェ」、「モンマルトルの夜会」、「モンパルナスの娘」という三章がある。
<モディリアーニ> 最初の章がモディリアーニの恋愛である。著者はモディリアーニが35歳で病死する最後の3年ほどを共に過ごしたジャンヌ・エビュテルヌとの関係を中心に書いている。彼女は、満1歳の娘ジャンヌを残し、21歳で、妊娠8ヵ月だったが、モディリアーニの死の2日後・未明に、パリのアパルトマンの6階(注:ヨーロッパでは5階)から飛び降り自殺をした。
手許には、2008年に開催された「モディリアーニ展」の図録がある。モディリアーニをプリミティヴィスムの観点から紹介する美術展だった。本書には、「プリミティヴィスム」という用語は一切でてこない。この図録には、本書に掲載の『ジャンヌ・エビュテルヌの肖像』(1918)、『自画像』(1919)、『黄色いセーターのジャンヌ・エビュテルヌ』(1919)は載っていないので、これらの絵は来日しなかったものだ。最初の肖像画には瞳が描かれている。しかし、後の2枚には瞳が描かれていない。瞳を描写しない絵をモディリアーニは数多く描いている。なぜ、彼は瞳を描かなかったのか。著者はその謎をこの本で解き明かしている。なるほど・・・・と思った。
図録に所載のメリル・シークレストの論文「アメディオ・モディリアーニ『夢に力尽きて』」によれば、ジャンヌと出会う前に、モディリアーニには別の恋人がいた。ひとりは、モー・アブランテス、2人目はベアトリス・ヘイスティングスだったという。この論文では、モディリアーニとジャンヌが1916年の末に出会ったことと二人の死の事実に触れているだけである。そして「彼らは結婚をしていなかった」と記す。
一方、本書の著者は、「ジャンヌとモディリアーニの結婚は、私的な誓約書は交わしたものの法的には未手続きのままであった」と記している。恋人ジャンヌをこの本で初めて具体的にイメージできるようになった。
末尾の章で、ジャンヌの死について著者はこんな一文を記している。
「生きたいとの願いが強いゆえに、生きる場を見出せないという現実に絶望し、生きる希望を見出すことができなくなっていたのである」と。
この本を読み、絵を味わうにはここに書き留めることを少なくする方が良いのかもしれない。そこで、最小限の私の印象だけをメモしておきたい。
<ピカソ> ピカソの修羅のごとき愛欲遍歴と彼の示したエゴイズム、彼の屈折した感情が簡潔に記されている。その上で、ピカソの『自画像』(p53)を眺めると、一層、強烈だ。私は、この自画像を初めて見た。
<ジェローム> 接吻する男女の絵『ピュグマリオンとガラテア』は彫刻家と美神との恋。この「アカデミズム」の画風に対比して、印象派の絵が語られていて興味深い。
<ドガ> 場末のカフェの片隅に描かれた男女二人のまなざし、その表情に改めて焦点をあてさせるドガの『アプサント』。そこに近代都市に生まれる「絶望という名の親密感、不幸の居心地」-その逆説的言辞に意味が与えられる。「ドガのカメラ・アイ」という言葉がキーワードになっている。
<ダンテとベアトリーチェ> ダンテとベアトリーチェの出会いを描いた絵から、ダンテがベアトリーチェを登場させた『神曲』に話が展開する。また「見初める」という視点での絵画に話題がつながっていくのがおもしろい。
<マネとモネ> マネとモネの対比。そこにルノワールも登場する。三者の違いの描写がおもしろい。モネが妻カミーユを描いた『死の床のカミーユ・モネ』(p141)が載っている。画家の「業」のすさまじさに思いを及ぼす。
<ルノワール> ルノワールの画業の原点が陶器の絵付け仕事だったと初めて知った。近代芸術そのものの青春の聖地・モンマルトル、ムーラン・ド・ラ・ギャレットとボヘミアン精神が溌剌と描き出されている。無名のルノワールが恋したのは10歳年下のリーズ・トレオ。彼女をモデルに『ボヘミアの女』(p161)が描かれている。
<ムンク> 不安と不幸に満ちる世界を描くムンク。ムンクの生い立ちと、平穏な幸福とは無縁の男女関係に囲まれた彼の青春、ムンクの心の地獄が彼の絵の世界を紡ぎ出した。そのことがよくわかる。主観をそのまま描いたムンクの絵の暗黒性が逆に人を惹きつける。
<カミーユ・クローデル> 彫刻家としての才能を持っていたカミーユ。ロダンとの宿命的な恋愛が生まれなければ、芸術家カミーユはどんな人生とどれほどの作品群を遺しただろうか。カミーユと出会わなかったなら、ロダン芸術はどうなっていただろう・・・・そんなことを空想したくなった。それにしても、悲しいカミーユの後半生だ。
<モンマルトルの夜会> ルソーの絵を軸にして、詩人アポリネールがピカソと共に、60代なかばになっていたルソーのために<ルソーの夜会>を催したという。この描写の中にルソーの人物像が浮かび上がる。併せて「ベル・エポック」期の芸術家たちの姿が。しかし、ここでも、著者はピカソの性愛遍歴には手厳しい。その指摘には同意したくなるのだが・・・・・。
<モンパルナスの娘> モンマルトルに替わり芸術の聖地となったモンパルナス。モデル引退後、その地にイタリア料理専門の安食堂を開いたロザリ・トビア。彼女はボヘミアン芸術家のアイドル兼母親代わりになったという。「蜂の巣」と通称された芸術家共同住宅の建設を実行した彫刻家アルフレッド・ブーシェ。この二人を軸に、かつてのモンパルナスが語られる。そこには、モンパルナスの黄金時代への郷愁が込められている。そして、最後に、再びモディリアーニに戻っていく。
『恋愛美術館』には、多くの芸術家が登場する。芸術家同士のつながり、絵画観の変転、変遷がしからしめるところなのだろう。そういう人間関係の中で、筆者は芸術家の恋愛と作品を語る。各章に登場する名前を挙げてみる。
<モディリアーニ> ミケランジェロ・ブオナナローティ、ティノ・ディ・カマイーノ、ジャンヌ・エビュテルヌ
<ピカソ> グスタフ・クリムト、エドヴァルド・ムンク
<ジェローム> エドゥアール・マネ、ティツィアーノ・ヴェチェルリオ、ジャン=フランソワ・ミレー、フランチェスコ・アイエツ
<ドガ> エドワード・マイブリッジ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、北斎、D.F.ミレー
<ダンテとベアトリーチェ> ヘンリー・ホリデイ、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ、エドワード・バーン=ジョーンズ
フレデリック・レイトン、イワン・ニコラエビッチ・クラムスコイ、アレクサンドル・ブローク、ウィルキー・コリンズ、トルストイ、マネ、
ジョン・ブレット、ランボオ
<マネとモネ> ルノワール、ドガ
<ルノワール> ヤコブ・ファン・ロイスダール、ゴッホ、コロー、ルソー、マネ、ソラレス・イ・カルデナス、ボードレール、
ピエール・フランク=ラミ、ドガ、アンリ・ミュルジェール、プッチーニ、シスレー、モディリアーニ、シェイクスピア、
バズ・ラーマン、ジョルジュ・ブリエール、フランソワ・ブーシェ、ゴーギャン
<ムンク> イェーガー、イプセン、グリーク、スタニスラウ・ブシビシェフスキー、オスカー・ワイルド、ゾラ、
ジョージ・バーナードショー
<カミーユ・クローデル> ロダン、イサドラ・ダンカン、シェイクスピア、ダンテ、レーヌ=マリー・パリス、イプセン
ジャン=レオン・ジェローム
<モンマルトルの夜会> アンリ・ルソー、ギョーム・アポリネール、マリー・ローランサン、ピカソ、セザンヌ、ブラック
アンドレ・サルモン、ジェローム、ヘミングウェイ、ガートルード・スタイン、M・ジロー、M・シュバリエ、
<モンパルナスの娘> ウィリアム・ブグロー、ジェローム、ルノワール、ドガ、モディリアーニ、ピカソ、アポリネール
ユトリロ、パスキン、マン・レイ、ジャコメッティ、ジャン・コクトー、ヘミングウェイ、アルフレッド・ブーシェ、ロダン
カミーユ・クローデル、ローランサン、レオ・フェレ、ジュリエット・グレコ、金子由香利、ジャンヌ・エピュテルヌ、サルモン
スタニスラス・フュメ、ジャンヌ・モディリアーニ、
脇役として登場する様々な芸術家の素顔の一端を知るのも興味深い。
本書から私にとって印象深い文章を引用しておこう。
*美を求める人の心は、そのまま恋うること恋われることを求める心へと連なり、実現は決してしないかも知れぬ理想を求め、地上にはいないはずの神を求める情熱へとも連なることになる。 (p4)
*写実が現実を写すことを意味するのに対して、記念は理念の記憶を残すことを意味している。 (p22)
*人は、自分の欲求のままに生きたいと願うと同時に、自分の欲求を超えた大いなる使命のために生きたいと願うものである。
自由には、そうした配慮や献身の対象を、自分で発見し選択しなくてはならないという重責がともなってくる。
この重責を全うしない限り、自由には、虚空に放り出されたような孤独感がつきまとうことになる。 (p38)
*若く頑健な身に美味なものが、成熟し老成した身にも美味であるとは限らない。(p52)
*もともと恋とは、相手のなかに理想を見出す心情のこと。 (p64)
*現実というものには、つねにイデアの理想や定義を裏切るかたちでよけいなものがつきまとい、欠けた部分が備わっている。芸術は、いわばこのイデアの似姿を生み出す作業である。 (p67)
*人は皆、魂の磁石を持っている。 (p170)
*死者は生者に、生きることを教えてくれる。 (p192)
*人は、その思いのほとんどを語らぬままに生涯を終える。
思いの大半の、その真の苦しみや哀しみを、ほとんど語らぬまま生を全うしていく。
それほど人の思いの奥底にある苦しみや哀しみは深く、向かい合うには激しすぎる痛みを伴っているからである。 (p258、p264)
*むしろ気づかぬふりをして生きていくしかないような思いが無数に存在するのである。 そうした思いを抱えた人が、わずかに自身に許すことがけきるものがあるとすれば、それはおそらく、他者の痛みや苦しみに涙することをおいてはないであろう。
であるからこそ、演劇や文芸の歴史は悲劇から始まっているのであろう。(p259)
この本に記載された言葉にまつわる情報をネット検索してみた。
ダンテ・アリギエーリ :ウィキペデイアから
Beatrice Portinari :Wikipedia から
File:Dante and beatrice.jpg 拡大図
ポンテ・ヴェッキオ :italyguides から
世界で最も美しといわれる橋:Ponte Vecchioは「古い橋」という意味
サンタ・トリニタ橋 :フィレンツェ・オルトラルノ・ネットから
ピュグマリオン :「ギリシャ神話解説」サイトから
ルツ記 :ウィキペデイアから
ルツ記 :「布忠.com」から
神曲 :ウィキペディアから
ベルリン分離派 :ウィキペディアから
アポリネール :ウィキペディアから
アポリネールのオフィシャル・サイト (フランス語)
ジュリエット・グレコ パリを歌う :YouTubeから
ミラボー橋 金子由香利 :YouTubeから
最後に、一つ腑に落ちないことがある。
「ダンテとベアトリーチェ 忘れ得ぬ女」の章の最初の箇所にある本文の記述(p104・p105)とヘンリー・ホリデイ作『ダンテとベアトリーチェ』の絵との照応関係についてである。
まず、本文から著者の記述を引用する。
p104の最後の2行目以降:
「女性三人の衣の色はフランス国旗と同じ赤白青だが、青の女性が奥にいるのでダンテの衣の緑と女性の二人の衣の色で、イタリア国旗の赤白緑の配色ができあがる。・・・人物の並びも、女性三人組よりはこの赤白緑の三人の方が揃って見えるので、意図的な配色かも知れない」
p106の最初から4行目
「絵の作者は英国十九世紀の画家ヘンリー・ホリデイ。」
著者は国旗の色三色の対比の形で記述しているので、誤植とは思えない。一方本書p105に該当の絵を載せ、前者の引用文の続きに、後者の引用文を記述している。この章は、「フィレンツェで観光みやげを売る屋台の、定番となっているのがこの絵葉書。」という書き出しで始まる。「この絵葉書」がヘンリー・ホリデイの絵を意味することが、この章の本文の文脈から読み取れる。
そうすると、絵の左から二人目の女性の服装の色が「黄色」であるので、本文と照応しないのだ。「この絵葉書」が掲載された絵が別物とすると、絵葉書自体が掲載されるはずだし、そうであれば、ホリディが色違いの2枚の絵を描いたことになる。ネット検索に挙げた英文版ウィキペディアのBeatrice Portinariにも掲載されているヘンリー・ホリデイの絵は、この本のp105掲載のものと同じだ。
さてこの不可解さは何だろう。著者の思い違いなのか・・・・
フィレンツェには観光旅行で訪れたことがある。観光みやげは買ったが、定番だという「この絵葉書」は購入しなかったので、絵葉書自体をたどれない。
フィレンツェで英語版の観光ガイドブックを購入していたので、ちょっと調べて見た。橋のことは載っていたが、ダンテのエピソードや絵は載っていなかった。
ご一読いただき、ありがとうございました。















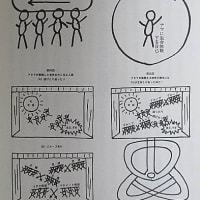




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます