
タイトルが目に止まり、「京みやこ語り」という言葉に関心を抱き、最初の数ページをペラペラと見ると、青木木米という名前が目に飛び込んで来て、この作品を読む気になった。作者については、まったく予備知識がなかった。初めて目にした作家名だった。
奥書を見ると、2010年に、「物原を踏みて」という作品で、第10回内田百文学賞優秀賞を受賞されている。
さて、本書は4つの短編が収録された短編集であり、作品のテーマはそれぞれ大きく異なり、趣がかなり違う短編を収録した小説集になっている。4つの作品に共通するのは、京言葉での会話を主体にすることと、京都を舞台にした作品であるという点である。
結果的に私が一番惹きつけられるのは、やはり一番最初に収録されている青木木米を扱った作品である。以下、各短編作品の読後印象をまとめてみたい。
<< 粟田の桐 >>
京都東山の鳥辺野に父、青木木米(もくべい)の墓があるという書き出しから始まる短編小説である。二人の死者が青木木米についてその人となりを回想して語るという形で展開する構成になっていておもしろい。
二人の語り部とは、一人が娘の「お來」であり、もう一人は、東国江戸の窯元に生まれ、伝手を頼って上方に来て、16歳で弟子入りした栄吉である。京焼の名工として名を馳せた木米の墓には、「識字陶工木米之墓」と墓石に刻まれているという。そして、その傍に誰の目を引くこともない質素な墓石が建てられていて、そこには「お來」と「俗名 栄吉」と刻まれているという。お來は冒頭部分で、「栄吉さんと一つ墓にはいりたいという身勝手な希望を、理解ある方々が叶えてくださったのです。おかげで生前には掴めなかったこのうえない幸せを、人生の幕を閉じたあとで手にすることができたのでございます」とうれしさを述べる下りがある。
なぜ、生前にお來と栄吉が夫婦になれなかったのか、それが青木木米自身とどうかかわるのか、ということが、お來と栄吉の語りの中から徐々に明らかになっていくという構成になる。
お來は娘の視点から木米を語る。そこでは木米を支えたお來の母の苦労を、お來の目を通して語ることにもなる。母の苦労を見ているところから生まれる愛憎を込めた視点で、父木米を語ることにもなる。さらに、お來は、父を介して大坂商人で初老の殿山長右衞門に引き合わされ、妾の立場になっていく。そこには、木米が窯を維持するために多額の借金をしていたことと、現在は使われていない貨幣とはいえ、古い貨幣の贋金造りで脅かされているという事情があったのだ。父のためとはいえ、身売り同然の境遇に一旦なっていくお來の心が語られる。お來は、母につらい思いをさせながら、妾を持ち子どもを作る父の有り様を見つめていく。父の私的な側面と、世に名声を得ながらも、京焼の競争の中で、絶頂と失意の振れの大きい父の陶工としての側面を、時間軸の中でともに語り続けて行く。
一方、栄吉は弟子の目に映じた木米を語る。そして、なぜ木米に弟子入りしたのか、その理由を明らかにしていく。また、その理由からすれば、栄吉がお來に何も求められないことになるという事情があった。
木米の最晩年に、木米自身の思いと行為が、お來を介して語られていく。
京焼の名工、青木木米がどんな人物だったかが浮かび上がってくる組み立てになっている。当時の京焼に関わる主要な人々の関係や仕事が点描風に織り込まれていく。窯の継承者が続いている高橋道八とは異なり、対比的に、名工木米の窯は木米一代で終わりを遂げる。木米は、三条粟田口に焼物の窯を築いていたのだ。江戸末期には粟田口一帯には20基を超える窯が稼働していたようだ。今はその痕跡すらほとんどないように思う。
表題の「粟田の桐」は、お來が生まれた時に桐の木が植えられたのだ。娘が生まれた時に、桐の木を植えると、娘が嫁ぐ頃にその木から嫁入り道具を作ることができるということによる。お來の場合、粟田の桐は桐の木のままで切られることなく終わる
最後は父・木米の生き様を理解し、それを全体として受け入れていくお來の生き方は、ふっと心やすらぐとともに、哀しく切ない。しっとりとした気持ちで読み終えさせる作品である。
「お來」の没年は「明治12年己(つちのと)卯年6月 享年79歳」
末尾の文は、こう記されている。お來の嬉しげな気持ち、はなやぎが伝わってくる。
「ああそうそう、お歯黒はきれいに洗い落としておきましょう。娘に戻ったつもりでいられるように。なにせ待っているのは『男盛り』の栄吉さんなのですから。」
<< 飛び落ちたくは候へど >>
明治維新を迎えるが、未だ行政組織が確立していない時点で、前月に京都府が創設され、「府兵」が警察事務を掌握したまなしの京都が舞台となる。主な主人公は、京都東町奉行所の同心として奉職していたが、奉行所が廃止されたとはいえ、元同心身分で、各町の自身番屋に顔を出し続けているという状態に居る元武士である。津田忠右衞門と平川宗之助の二人。彼らは一種のモラトリアム状態にいる。
元治元年夏、蛤御門の変での戦火で、京の町は大火事となる。大火事が東寺内町に達し、燃え落ちる仏具屋の猛火の中から、津田と平川が孫の救出に一役かう結果となる。しかし、そこには裏事情があった。火事場泥棒が居合わせた子供を見捨てられず、助け出したのだ。男が子供を肩から下ろしたところで、忠右衞門が火事場泥棒を押さえ込む。盗品の包みは地面に落とす。忠右衞門はその男を逃がしてやるのである。かけつけた仏具屋(彦根屋)の主人惣兵衛に、子供と包み(金箔)を手渡す。
惣兵衛は二人に必ず礼はすると述べて、子供を連れて去って行く。
話は、それから4年後の現在に繋がる。それは、清水の舞台からの「飛び落ち」の件に絡んでいく。かつて清水の舞台からの「飛び落ち」は年に4~5件あったという。観音信仰との関連があるそうだ。
飛び落ちして命を落としたのは下女として勤めていた「さよ」という女。「主人の病気平癒」を願っての飛び落ちとして適当に処理された。3歳年上で22歳の与吉がさよの遺品を整理していて、母の形見の薩摩つげの解き櫛が見当たらないのだった。そこで、与吉は番屋にその行方の調査を申し出る。与吉の申し出を忠右衞門が聴いたのだ。そして与吉があの4年前の火事場泥棒を試みた男だったことに気付く。この話を忠右衞門が平川に語ることから、話が具体的に展開していく。
平川が実はさよの飛び落ちの検屍に立ち合っていたことが、後ほどわかっることから、忠右衞門の疑心暗鬼が始まる。与吉が切られるという展開にもなっていく。幸いに命に別状がなかったのだが・・・・。忠右衞門の捜査は意外な展開をしていく。このあたりのストーリーの展開はなかなかおもしろい。
明治維新直後の雰囲気がよくわかるとともに、京都にとどまった元同心の不安定な日常生活と心の平衡を保とうとする心理状態が描き込まれていく。ペーソスが漂う作品である。明治維新直後を時代背景とした捜査追跡物語といったところである。
その中に、平川の家庭状況や用立ててという形での無心行為、ふとしたでき心などが織りなされ、忠右衞門も身の振りかたに思い悩む。そのような元武士の姿が哀調を帯びて描かれている。
(こうづる)の窓 >>
1932年3月に満州国が建国された。この話はその3年後の4月、奉天で初めての冬を迎える静代と妹・房子の姉妹のある事情から始まる。姉妹2人の生き方の違いがどちらかというと淡々と描かれて行く。
ある事情とは、妹の生んだ幼児を、静代が「奉天同善堂」の入口に近い建物に小さく開けられ「救生門」と書かれた「窓」にそっと差し入れに行くという行動を選択するのだ。救生門とは捨て児にされる赤ん坊を救う門である。なぜそんな状況に陥ったのか、姉妹の生まれと育ちの経緯を絡ませながら、「幼児」に対する姉妹の意識の差や関わり方の差が描かれる。
産めよ増やせよが奨励され、堕胎罪が重要視された1930年代という時代の一面が鮮やかに切りだされ、浮き彫りになる。ヨーロッパでは鸛(こうのとり)が人間の赤ん坊を運んでくるという伝説がある。この作品はタイトル「鸛鶴の窓」は、「救生門の窓」と同じ意味である。その後、姉妹は満州・奉天から京都に戻り、静代は助産院を開業し、「鸛鶴の窓」を自ら設けるのだ。看病婦学校時代の同級生・濱田徳子の強い勧めが帰国の一因なのだが、京都市内で助産院を営む徳子に頼まれて、考案されて間もない避妊具「太田リング」を置くことにもなる。「法律で禁止されたわけやないやろ。近々そうなるていう噂もあるけど、うちはそれでも続けるつもりや」「今でも危ないえ。軍隊に入れるため人を増やせいうのが国の政策や。産児制限はそれに刃向かうことやないか」という会話がつづく。そんな時代が描かれていく。
静代が設けた「鸛鶴の窓」から入れられた初めての「赤ん坊」をめぐって、話が急展開していく。赤ん坊を置いた母親が翌日、改めて「赤ん坊」を引き取りたいと現れるのだが、赤ん坊は消えていた。妹・房子がそこに絡んでいたのだが・・・・・。
1930年代という時代世相の中での中絶・堕胎意識が捨て児という行為と重ねて描き込まれる。静代はある事情で中絶させられ、妊娠できない体になっていることを秘している。その静代が妹の奔放な生き方を眺める視点も興味深い。「鸛鶴の窓」は、静代の生き方につながる窓でもある。「赤ん坊」の存在の意味が描かれていく短編である。
<< 三条の橋 >>
「中国との戦争に続きアメリカとも戦火を交えてすでに三年、日常の暮らしには制約が多く課せられ、外出時はモンペの着用が義務づけられていた」という時代背景で、祇園町のお茶屋の主でもあり母でもある八重と、翌年には「十三参り」を控える娘・綾子が主な主人公となる。
綾子の祖母トクの若い頃の着物を仕立て直し、綾子の十三参りのためのの小振り袖が作られる。綾子は母に訊ねる。「今晩のおけら参りには、あれ着て行くねん」「あれは今日着られへん。あれは十三参りのためにこさえたべべやないの」という母子の会話からストーリーが始まる。
「お母ちゃんの言うこと聴きよし。そやないと三条の橋の下へ捨ててくるえ。あんたはあそこで拾てきた子やさかいに」「お母ちゃん。いけず言わんといて」という会話に発展する。
この「橋の下で拾てきた子」というフレーズは、京都で生まれ育った私も子供の頃に使われた記憶がある。なつかしい言葉・・・・。久しぶりに、この作品を読み、ああそういえば、と思い出した。子供を叱る時などの脅し文句としてよく使われた。
だが、この言葉の意味するところが、この作品ではダブルミーニングになっていくというストーリー展開となる。
八重と綾子が八坂神社におけら参りに行く。その境内で、可愛らしい子を連れた祇園新橋のお茶屋の女将が、八重に軽く会釈して声をかけた。それに対する八重の見せた素っ気ない態度に、気まずい雰囲気を綾子が感じ取る。それが綾子の感性への伏線となっていく。
この短編は、八重の生き方を描き出していく。一方で、綾子は、十三参りを目前にして、「今度は自分が秘密を持つ番だ」と、一段大人への階段を上る。そこに至るプロセスで八重と綾子のそれぞれの心中の葛藤があざやかに描き出される。
そして、いつもの親子のやりとりが今日も始まるというところに戻って行く。
戦時下の祇園町の雰囲気を織り込みながら、祇園町に生きる親子の物語である。哀切感が滲む一方で、そこに一つの人間成長物語が描き出されている。
著者は、心の機微を描き出したかったのだろう。その観点が各作品に共通しているように思う。
ご一読ありがとうございます。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
本書から関心を抱いた語句をネット検索してみた。一覧にしておきたい。
青木木米 :ウィキペディア
陶匠・青木木米宅跡・弁財天社(東山区) :「京都風光」
陶工・青木木米忌日 :「今日のことあれこれと・・・」
『磁器』(石もの) 染付名花十友図三重蓋物 :「京都国立博物館」
兎道朝暾図(うじちょうとんず) 重要文化財 :「e國寶」
染付龍涛文提重(そめつけりゅうとうもんさげじゅう) :「e國寶」
京都国立博物館データベース
「館蔵品データベース」に9件の作品の登録あり。作者名で検索してください。
Aoki Mokubei :「JAPANESE CERAMICS」
Bowl in the shape od an antique Gui Chinese vessel :「MMUSEE CERUNUSHI」
奥田頴川 :ウィキペディア
仁阿弥道八 :ウィキペディア
田能村竹田の墓 :「大坂再発見!」
満州国 :ウィキペディア
堕胎罪 :ウィキペディア
避妊リング :「三宅婦人科内科医院」
じぇねれーしょんぎゃっぷ :「病院からのお知らせ」
をけら参り :「八坂神社」
京の祭礼と行事 をけら参り :「甘春堂」
法輪寺(虚空蔵)・・・嵯峨嵐山 十三参り :「ようこそ渡月橋」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
奥書を見ると、2010年に、「物原を踏みて」という作品で、第10回内田百文学賞優秀賞を受賞されている。
さて、本書は4つの短編が収録された短編集であり、作品のテーマはそれぞれ大きく異なり、趣がかなり違う短編を収録した小説集になっている。4つの作品に共通するのは、京言葉での会話を主体にすることと、京都を舞台にした作品であるという点である。
結果的に私が一番惹きつけられるのは、やはり一番最初に収録されている青木木米を扱った作品である。以下、各短編作品の読後印象をまとめてみたい。
<< 粟田の桐 >>
京都東山の鳥辺野に父、青木木米(もくべい)の墓があるという書き出しから始まる短編小説である。二人の死者が青木木米についてその人となりを回想して語るという形で展開する構成になっていておもしろい。
二人の語り部とは、一人が娘の「お來」であり、もう一人は、東国江戸の窯元に生まれ、伝手を頼って上方に来て、16歳で弟子入りした栄吉である。京焼の名工として名を馳せた木米の墓には、「識字陶工木米之墓」と墓石に刻まれているという。そして、その傍に誰の目を引くこともない質素な墓石が建てられていて、そこには「お來」と「俗名 栄吉」と刻まれているという。お來は冒頭部分で、「栄吉さんと一つ墓にはいりたいという身勝手な希望を、理解ある方々が叶えてくださったのです。おかげで生前には掴めなかったこのうえない幸せを、人生の幕を閉じたあとで手にすることができたのでございます」とうれしさを述べる下りがある。
なぜ、生前にお來と栄吉が夫婦になれなかったのか、それが青木木米自身とどうかかわるのか、ということが、お來と栄吉の語りの中から徐々に明らかになっていくという構成になる。
お來は娘の視点から木米を語る。そこでは木米を支えたお來の母の苦労を、お來の目を通して語ることにもなる。母の苦労を見ているところから生まれる愛憎を込めた視点で、父木米を語ることにもなる。さらに、お來は、父を介して大坂商人で初老の殿山長右衞門に引き合わされ、妾の立場になっていく。そこには、木米が窯を維持するために多額の借金をしていたことと、現在は使われていない貨幣とはいえ、古い貨幣の贋金造りで脅かされているという事情があったのだ。父のためとはいえ、身売り同然の境遇に一旦なっていくお來の心が語られる。お來は、母につらい思いをさせながら、妾を持ち子どもを作る父の有り様を見つめていく。父の私的な側面と、世に名声を得ながらも、京焼の競争の中で、絶頂と失意の振れの大きい父の陶工としての側面を、時間軸の中でともに語り続けて行く。
一方、栄吉は弟子の目に映じた木米を語る。そして、なぜ木米に弟子入りしたのか、その理由を明らかにしていく。また、その理由からすれば、栄吉がお來に何も求められないことになるという事情があった。
木米の最晩年に、木米自身の思いと行為が、お來を介して語られていく。
京焼の名工、青木木米がどんな人物だったかが浮かび上がってくる組み立てになっている。当時の京焼に関わる主要な人々の関係や仕事が点描風に織り込まれていく。窯の継承者が続いている高橋道八とは異なり、対比的に、名工木米の窯は木米一代で終わりを遂げる。木米は、三条粟田口に焼物の窯を築いていたのだ。江戸末期には粟田口一帯には20基を超える窯が稼働していたようだ。今はその痕跡すらほとんどないように思う。
表題の「粟田の桐」は、お來が生まれた時に桐の木が植えられたのだ。娘が生まれた時に、桐の木を植えると、娘が嫁ぐ頃にその木から嫁入り道具を作ることができるということによる。お來の場合、粟田の桐は桐の木のままで切られることなく終わる
最後は父・木米の生き様を理解し、それを全体として受け入れていくお來の生き方は、ふっと心やすらぐとともに、哀しく切ない。しっとりとした気持ちで読み終えさせる作品である。
「お來」の没年は「明治12年己(つちのと)卯年6月 享年79歳」
末尾の文は、こう記されている。お來の嬉しげな気持ち、はなやぎが伝わってくる。
「ああそうそう、お歯黒はきれいに洗い落としておきましょう。娘に戻ったつもりでいられるように。なにせ待っているのは『男盛り』の栄吉さんなのですから。」
<< 飛び落ちたくは候へど >>
明治維新を迎えるが、未だ行政組織が確立していない時点で、前月に京都府が創設され、「府兵」が警察事務を掌握したまなしの京都が舞台となる。主な主人公は、京都東町奉行所の同心として奉職していたが、奉行所が廃止されたとはいえ、元同心身分で、各町の自身番屋に顔を出し続けているという状態に居る元武士である。津田忠右衞門と平川宗之助の二人。彼らは一種のモラトリアム状態にいる。
元治元年夏、蛤御門の変での戦火で、京の町は大火事となる。大火事が東寺内町に達し、燃え落ちる仏具屋の猛火の中から、津田と平川が孫の救出に一役かう結果となる。しかし、そこには裏事情があった。火事場泥棒が居合わせた子供を見捨てられず、助け出したのだ。男が子供を肩から下ろしたところで、忠右衞門が火事場泥棒を押さえ込む。盗品の包みは地面に落とす。忠右衞門はその男を逃がしてやるのである。かけつけた仏具屋(彦根屋)の主人惣兵衛に、子供と包み(金箔)を手渡す。
惣兵衛は二人に必ず礼はすると述べて、子供を連れて去って行く。
話は、それから4年後の現在に繋がる。それは、清水の舞台からの「飛び落ち」の件に絡んでいく。かつて清水の舞台からの「飛び落ち」は年に4~5件あったという。観音信仰との関連があるそうだ。
飛び落ちして命を落としたのは下女として勤めていた「さよ」という女。「主人の病気平癒」を願っての飛び落ちとして適当に処理された。3歳年上で22歳の与吉がさよの遺品を整理していて、母の形見の薩摩つげの解き櫛が見当たらないのだった。そこで、与吉は番屋にその行方の調査を申し出る。与吉の申し出を忠右衞門が聴いたのだ。そして与吉があの4年前の火事場泥棒を試みた男だったことに気付く。この話を忠右衞門が平川に語ることから、話が具体的に展開していく。
平川が実はさよの飛び落ちの検屍に立ち合っていたことが、後ほどわかっることから、忠右衞門の疑心暗鬼が始まる。与吉が切られるという展開にもなっていく。幸いに命に別状がなかったのだが・・・・。忠右衞門の捜査は意外な展開をしていく。このあたりのストーリーの展開はなかなかおもしろい。
明治維新直後の雰囲気がよくわかるとともに、京都にとどまった元同心の不安定な日常生活と心の平衡を保とうとする心理状態が描き込まれていく。ペーソスが漂う作品である。明治維新直後を時代背景とした捜査追跡物語といったところである。
その中に、平川の家庭状況や用立ててという形での無心行為、ふとしたでき心などが織りなされ、忠右衞門も身の振りかたに思い悩む。そのような元武士の姿が哀調を帯びて描かれている。
(こうづる)の窓 >>
1932年3月に満州国が建国された。この話はその3年後の4月、奉天で初めての冬を迎える静代と妹・房子の姉妹のある事情から始まる。姉妹2人の生き方の違いがどちらかというと淡々と描かれて行く。
ある事情とは、妹の生んだ幼児を、静代が「奉天同善堂」の入口に近い建物に小さく開けられ「救生門」と書かれた「窓」にそっと差し入れに行くという行動を選択するのだ。救生門とは捨て児にされる赤ん坊を救う門である。なぜそんな状況に陥ったのか、姉妹の生まれと育ちの経緯を絡ませながら、「幼児」に対する姉妹の意識の差や関わり方の差が描かれる。
産めよ増やせよが奨励され、堕胎罪が重要視された1930年代という時代の一面が鮮やかに切りだされ、浮き彫りになる。ヨーロッパでは鸛(こうのとり)が人間の赤ん坊を運んでくるという伝説がある。この作品はタイトル「鸛鶴の窓」は、「救生門の窓」と同じ意味である。その後、姉妹は満州・奉天から京都に戻り、静代は助産院を開業し、「鸛鶴の窓」を自ら設けるのだ。看病婦学校時代の同級生・濱田徳子の強い勧めが帰国の一因なのだが、京都市内で助産院を営む徳子に頼まれて、考案されて間もない避妊具「太田リング」を置くことにもなる。「法律で禁止されたわけやないやろ。近々そうなるていう噂もあるけど、うちはそれでも続けるつもりや」「今でも危ないえ。軍隊に入れるため人を増やせいうのが国の政策や。産児制限はそれに刃向かうことやないか」という会話がつづく。そんな時代が描かれていく。
静代が設けた「鸛鶴の窓」から入れられた初めての「赤ん坊」をめぐって、話が急展開していく。赤ん坊を置いた母親が翌日、改めて「赤ん坊」を引き取りたいと現れるのだが、赤ん坊は消えていた。妹・房子がそこに絡んでいたのだが・・・・・。
1930年代という時代世相の中での中絶・堕胎意識が捨て児という行為と重ねて描き込まれる。静代はある事情で中絶させられ、妊娠できない体になっていることを秘している。その静代が妹の奔放な生き方を眺める視点も興味深い。「鸛鶴の窓」は、静代の生き方につながる窓でもある。「赤ん坊」の存在の意味が描かれていく短編である。
<< 三条の橋 >>
「中国との戦争に続きアメリカとも戦火を交えてすでに三年、日常の暮らしには制約が多く課せられ、外出時はモンペの着用が義務づけられていた」という時代背景で、祇園町のお茶屋の主でもあり母でもある八重と、翌年には「十三参り」を控える娘・綾子が主な主人公となる。
綾子の祖母トクの若い頃の着物を仕立て直し、綾子の十三参りのためのの小振り袖が作られる。綾子は母に訊ねる。「今晩のおけら参りには、あれ着て行くねん」「あれは今日着られへん。あれは十三参りのためにこさえたべべやないの」という母子の会話からストーリーが始まる。
「お母ちゃんの言うこと聴きよし。そやないと三条の橋の下へ捨ててくるえ。あんたはあそこで拾てきた子やさかいに」「お母ちゃん。いけず言わんといて」という会話に発展する。
この「橋の下で拾てきた子」というフレーズは、京都で生まれ育った私も子供の頃に使われた記憶がある。なつかしい言葉・・・・。久しぶりに、この作品を読み、ああそういえば、と思い出した。子供を叱る時などの脅し文句としてよく使われた。
だが、この言葉の意味するところが、この作品ではダブルミーニングになっていくというストーリー展開となる。
八重と綾子が八坂神社におけら参りに行く。その境内で、可愛らしい子を連れた祇園新橋のお茶屋の女将が、八重に軽く会釈して声をかけた。それに対する八重の見せた素っ気ない態度に、気まずい雰囲気を綾子が感じ取る。それが綾子の感性への伏線となっていく。
この短編は、八重の生き方を描き出していく。一方で、綾子は、十三参りを目前にして、「今度は自分が秘密を持つ番だ」と、一段大人への階段を上る。そこに至るプロセスで八重と綾子のそれぞれの心中の葛藤があざやかに描き出される。
そして、いつもの親子のやりとりが今日も始まるというところに戻って行く。
戦時下の祇園町の雰囲気を織り込みながら、祇園町に生きる親子の物語である。哀切感が滲む一方で、そこに一つの人間成長物語が描き出されている。
著者は、心の機微を描き出したかったのだろう。その観点が各作品に共通しているように思う。
ご一読ありがとうございます。
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
本書から関心を抱いた語句をネット検索してみた。一覧にしておきたい。
青木木米 :ウィキペディア
陶匠・青木木米宅跡・弁財天社(東山区) :「京都風光」
陶工・青木木米忌日 :「今日のことあれこれと・・・」
『磁器』(石もの) 染付名花十友図三重蓋物 :「京都国立博物館」
兎道朝暾図(うじちょうとんず) 重要文化財 :「e國寶」
染付龍涛文提重(そめつけりゅうとうもんさげじゅう) :「e國寶」
京都国立博物館データベース
「館蔵品データベース」に9件の作品の登録あり。作者名で検索してください。
Aoki Mokubei :「JAPANESE CERAMICS」
Bowl in the shape od an antique Gui Chinese vessel :「MMUSEE CERUNUSHI」
奥田頴川 :ウィキペディア
仁阿弥道八 :ウィキペディア
田能村竹田の墓 :「大坂再発見!」
満州国 :ウィキペディア
堕胎罪 :ウィキペディア
避妊リング :「三宅婦人科内科医院」
じぇねれーしょんぎゃっぷ :「病院からのお知らせ」
をけら参り :「八坂神社」
京の祭礼と行事 をけら参り :「甘春堂」
法輪寺(虚空蔵)・・・嵯峨嵐山 十三参り :「ようこそ渡月橋」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)















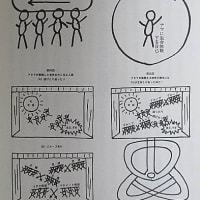




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます