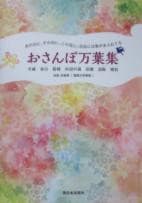本書の表紙を見ると、横書きの書名の上下にキャプションが付いている。
上には「あの山に、その川に、この花に。奈良には歌があふれてる」と。勿論、ここでの歌は、『万葉集』に収録されている歌である。下には奈良の名称が列挙されている。「平城」から「飛鳥」まで。名称は7つ。しかし、本書は8つのルートを採り上げていく。7つの名称で8ルートというのは、最後の「飛鳥」が「歩く」と「自転車」の2ルートを解説していることによる。
本書の特徴と基本はここで紹介されるコースを「線」として歩くという形の中でポイントとなる「史跡」(点)について説明を加えるというスタイルにある。そのルートという道のり(線)から見える大和の景観に触れ、万葉集の歌を採り上げて、その歌に絡めて古代の歴史や当時の人の思いへと読み手を誘っていく。そのコースに含まれる史跡ポイントでは基本的な観光ガイドプラスαの蘊蓄が加わっていく。学者の視点から観光ガイドブックのレベルでは触れない一歩踏み込んだ説明が専門的になりすぎない程度で要所要所で組み込まれている。タイトルに「おさんぽ」とあるように、その語り口は、ところどころに軽いタッチのノリが加わり、ちょっとくだけた話しぶりもあって読みやすい。
本書の構成のしかたという点にまず触れておこう。各ルートの1ページ目にはそのコースのハイライト的なワン・シーンの写真がどんと載っている。次のページには、「コースのポイント」を一行で説明。スタートからゴールまでの史跡ポイントと所要時間が図式表示され、総距離数が記されている。その下部に、「このコースの楽しみ」という要約文がある。そして、1~2ページでコースの地図が掲載され、行程表示と照応する形で歩くコースが破線入りで示されている。ページ全体を使ったマップなので、これは実際に本書あるいはコピーを持参し現地を歩く際に利用すると便利である。一方、本書を自宅などで読む際には、この地図がヴァーチャルおさんぽの友になる。
そして、本文説明に入る。本文は冒頭の行程図式に示された史跡名称を使い、そこまでのコースの「線」を語りながら「史跡」(点)に触れる。最初の「平城」コースを事例にすると、「①旧長屋王邸宅跡まで」という説明の中では、スタート地点から長屋王邸宅跡までの道順説明、長屋王がどういう歴史的位置づけにある人物だったか。そして長屋王邸宅がどういう経緯で確定されたのか、などの説明がある。「歴史と考古とのあわいを歩いた」と読者に思わせることには成功していると言える。調査や研究の経緯を含めた詳細までには踏み込んでいないが、事実を理解する助けとなる程度の要点は歴史的視点と考古学的視点の双方から取り込んでいる。そこに『万葉集』を素材にした文学的視点が加えられる。ここでは『万葉集』に収録されている長屋王の歌そのものが引用される。万葉仮名表記ではないのでご安心を。通常の文学全集に記載の歌表記である。引用の歌にはすべて著者の読みやすい訳が付されている。
引用歌が史跡の説明とコラボレーションしていく。この旧長屋王邸宅跡は冒頭からその一つの典型と言える。なぜなら、現在は碑が立つだけの点(史跡)である。その点の空間に佇み、長屋王の生きた時代という、その場所に「堆積している時間」に思いを馳せるように導いていく。そのためのトリガーが『万葉集』の歌であり、著者の解説となる。そんな感じで本文が進む。
「はじめに」の末尾において著者が記す文章に、著者の狙いがあるようだ。
”「線」にはあなたの歩いた今日の過去があり、「点」には1300年前の過去がある。そして、『万葉集』の歌はその「線」と「点」を「面」にする役割を果たしてくれるはずである”と。つまり、『万葉集』を携えて、大和の現地を歩きましょうよ、という誘いの書である。
この本文自体は一貫して文字による説明だけにしてある。脚注形式として要所要所に、系図などの図、写真、脚注説明文などを載せている。ある意味で本文は目移りせず、邪魔が入らずに文字面で読み進める形式である。文字を読み進めるときのイメージや思いの途切れを引き起こさないためだろうか。
「おわりに」を読んでなるほどと思ったのだが、本書の読みやすさは実際に案内人(講師)として講座参加者と共に歩いた経験を踏まえている故のようである。「万葉集講座のバスツアーで、共に大和をめぐって下さった泉北教養講座の皆さん、みなさんと共に歩いた記憶が本書の基礎を形成しています」と著者は述べている。その時の説明に対する参加者の傾聴反応や質問などが役立っているのではないだろうか。
上記のとおり、本書に載るコースマップを見ながら、その道のりに沿った記述と『万葉集』より引用された関連歌の説明を読み進めて行く分には「おさんぽ」気分である。まちがいなく、楽しみながら読める。だが、これらコースを自分の足で歩くとしたら、ちょっと「おさんぽ」気分ではいられないだろう。たぶんかなりの健脚の人以外は・・・・・。
本書に採り上げられた8コースの地域名称、起点と終点、歩行距離をご紹介する。
起点と終点の間は「~」、駅からのバス利用区間は「→」で表記した。
平城 近鉄新大宮駅~近鉄平城駅 総距離約7.5km
春日 近鉄奈良駅→破石町(わりいしちょう) バス停~近鉄奈良駅 約12km
葛城 近鉄御所駅→風の森バス停~宮戸橋バス停→近鉄御所駅 約12km
山の辺の道 天理駅~JR桜井線三輪駅 約15.5km
泊瀬(はつせ) JR桜井線三輪駅~近鉄長谷寺駅 約 6.6km
忍阪(おっさか) JR桜井駅→粟原バス停~近鉄大和朝倉駅 約 6km
飛鳥 近鉄橿原神宮前駅→豊浦駐車場~飛鳥バス停→近鉄橿原神宮前駅 約 7.0km
飛鳥(自転車) 近鉄橿原神宮前駅~近鉄飛鳥駅 約13km
コースの行程図式を見ていて、一点リクエストしたくなったのは、近鉄あるいはJRから起点までのバス移動の所要時間はどれくらいかを付記して欲しかった。他府県の土地勘のない者にはその部分が記されていると計画を組む上で自宅からの往復の総時間量がイメージしやすくなる。近鉄やJRの幹線はネット検索で手軽に所要時間が分かるが、バス路線などは調べづらいし、手間がかかるので。
本書には、「おまけ」として「柿本神社」と「かぎろひ」、「ちょっと豆知識」として「古代の色名」がそれぞれ1ページで、「おさんぽひとやすみ」として「二上山」「宇陀」「吉野」がそれぞれ見開き2ページで説明するコラムがついている。これも勉強材料になる。
最後に、この各コースに誰の歌が引用されているかを記しておこう。作者名を記しているものについてだけの話ではあるが。どの歌かは、本書を「おさんぽ」して、楽しんでいただければよいだろう。
平城 長屋王、大伴家持、太宰少貳小野老朝臣、山部宿祢赤人、田辺福麻呂、
磐姫皇后、額田王、柿本人麻呂、聖武天皇
春日 橘奈良麻呂、笠金村、坂上郎女、光明皇太后、藤原清河、大伴家持
葛城 丹比真人笠麻呂(記載なし、万葉集確認)
山の辺の道 柿本人麻呂、中大兄皇子、額田王
泊瀬 髙市皇子、三輪髙市麻呂、雄略天皇
忍阪 沙弥女王、間人大浦、額田王、舒明天皇、天智天皇、鏡王女、中臣鎌足
飛鳥 舎人娘子、柿本人麻呂、有馬皇子、上古麻呂、大伴旅人、志貴皇子、持統天皇
作者の明かな歌の他に、詠み人不詳の歌、『日本書紀』からの引用なども各所に組み込まれている。
机上での「おさんぽ」読書が終わったので、このガイドを利用して、コースを歩いてみたいと思っている。私にとっては「おさんぽ万葉集」になるのか、しんどいウォーキング万葉集になるのか・・・・どうだろう。
ご一読ありがとうございます。

本・書籍ランキング
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
本書掲載のコースと関係する観光案内の公のサイトをちょっと検索してみた。一覧にしておきたい。
なら記紀・万葉 :「奈良県地域振興部文化資源活用課」
パンフレット・マップのダウンロード :「奈良市観光協会」
平城宮跡歴史公園 ホームページ
平城宮跡 :「なら旅ネット<奈良県観光公式サイト>」
奈良で自転車を楽しもう :「奈良県」
葛城の道 :「御所市観光ガイド」
山の辺の道(南)コース :「天理市観光協会」
長谷寺参道へようこそ :「初瀬観光ガイド」(初瀬観光協会)
第6回忍坂街道まつり :「桜井市纏向学研センター」
既に終了2017年10月実施の情報です。
国営飛鳥歴史公園 ホームページ
パンフレットダウンロード
特集:明日香村万葉歌碑マップ :「旅する明日香ネット」(明日香村観光ポータルサイト)
調査報告等 文化財 :「明日香村」
光明宗法華寺 ホームページ
春日大社 公式ホームページ
新薬師寺 公式ホームページ
白毫寺 :「奈良市観光協会」
三輪明神 大神神社 公式ホームページ
長谷寺 ホームページ
奈良県立万葉文化館 ホームページ
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)

本・書籍ランキング
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
上には「あの山に、その川に、この花に。奈良には歌があふれてる」と。勿論、ここでの歌は、『万葉集』に収録されている歌である。下には奈良の名称が列挙されている。「平城」から「飛鳥」まで。名称は7つ。しかし、本書は8つのルートを採り上げていく。7つの名称で8ルートというのは、最後の「飛鳥」が「歩く」と「自転車」の2ルートを解説していることによる。
本書の特徴と基本はここで紹介されるコースを「線」として歩くという形の中でポイントとなる「史跡」(点)について説明を加えるというスタイルにある。そのルートという道のり(線)から見える大和の景観に触れ、万葉集の歌を採り上げて、その歌に絡めて古代の歴史や当時の人の思いへと読み手を誘っていく。そのコースに含まれる史跡ポイントでは基本的な観光ガイドプラスαの蘊蓄が加わっていく。学者の視点から観光ガイドブックのレベルでは触れない一歩踏み込んだ説明が専門的になりすぎない程度で要所要所で組み込まれている。タイトルに「おさんぽ」とあるように、その語り口は、ところどころに軽いタッチのノリが加わり、ちょっとくだけた話しぶりもあって読みやすい。
本書の構成のしかたという点にまず触れておこう。各ルートの1ページ目にはそのコースのハイライト的なワン・シーンの写真がどんと載っている。次のページには、「コースのポイント」を一行で説明。スタートからゴールまでの史跡ポイントと所要時間が図式表示され、総距離数が記されている。その下部に、「このコースの楽しみ」という要約文がある。そして、1~2ページでコースの地図が掲載され、行程表示と照応する形で歩くコースが破線入りで示されている。ページ全体を使ったマップなので、これは実際に本書あるいはコピーを持参し現地を歩く際に利用すると便利である。一方、本書を自宅などで読む際には、この地図がヴァーチャルおさんぽの友になる。
そして、本文説明に入る。本文は冒頭の行程図式に示された史跡名称を使い、そこまでのコースの「線」を語りながら「史跡」(点)に触れる。最初の「平城」コースを事例にすると、「①旧長屋王邸宅跡まで」という説明の中では、スタート地点から長屋王邸宅跡までの道順説明、長屋王がどういう歴史的位置づけにある人物だったか。そして長屋王邸宅がどういう経緯で確定されたのか、などの説明がある。「歴史と考古とのあわいを歩いた」と読者に思わせることには成功していると言える。調査や研究の経緯を含めた詳細までには踏み込んでいないが、事実を理解する助けとなる程度の要点は歴史的視点と考古学的視点の双方から取り込んでいる。そこに『万葉集』を素材にした文学的視点が加えられる。ここでは『万葉集』に収録されている長屋王の歌そのものが引用される。万葉仮名表記ではないのでご安心を。通常の文学全集に記載の歌表記である。引用の歌にはすべて著者の読みやすい訳が付されている。
引用歌が史跡の説明とコラボレーションしていく。この旧長屋王邸宅跡は冒頭からその一つの典型と言える。なぜなら、現在は碑が立つだけの点(史跡)である。その点の空間に佇み、長屋王の生きた時代という、その場所に「堆積している時間」に思いを馳せるように導いていく。そのためのトリガーが『万葉集』の歌であり、著者の解説となる。そんな感じで本文が進む。
「はじめに」の末尾において著者が記す文章に、著者の狙いがあるようだ。
”「線」にはあなたの歩いた今日の過去があり、「点」には1300年前の過去がある。そして、『万葉集』の歌はその「線」と「点」を「面」にする役割を果たしてくれるはずである”と。つまり、『万葉集』を携えて、大和の現地を歩きましょうよ、という誘いの書である。
この本文自体は一貫して文字による説明だけにしてある。脚注形式として要所要所に、系図などの図、写真、脚注説明文などを載せている。ある意味で本文は目移りせず、邪魔が入らずに文字面で読み進める形式である。文字を読み進めるときのイメージや思いの途切れを引き起こさないためだろうか。
「おわりに」を読んでなるほどと思ったのだが、本書の読みやすさは実際に案内人(講師)として講座参加者と共に歩いた経験を踏まえている故のようである。「万葉集講座のバスツアーで、共に大和をめぐって下さった泉北教養講座の皆さん、みなさんと共に歩いた記憶が本書の基礎を形成しています」と著者は述べている。その時の説明に対する参加者の傾聴反応や質問などが役立っているのではないだろうか。
上記のとおり、本書に載るコースマップを見ながら、その道のりに沿った記述と『万葉集』より引用された関連歌の説明を読み進めて行く分には「おさんぽ」気分である。まちがいなく、楽しみながら読める。だが、これらコースを自分の足で歩くとしたら、ちょっと「おさんぽ」気分ではいられないだろう。たぶんかなりの健脚の人以外は・・・・・。
本書に採り上げられた8コースの地域名称、起点と終点、歩行距離をご紹介する。
起点と終点の間は「~」、駅からのバス利用区間は「→」で表記した。
平城 近鉄新大宮駅~近鉄平城駅 総距離約7.5km
春日 近鉄奈良駅→破石町(わりいしちょう) バス停~近鉄奈良駅 約12km
葛城 近鉄御所駅→風の森バス停~宮戸橋バス停→近鉄御所駅 約12km
山の辺の道 天理駅~JR桜井線三輪駅 約15.5km
泊瀬(はつせ) JR桜井線三輪駅~近鉄長谷寺駅 約 6.6km
忍阪(おっさか) JR桜井駅→粟原バス停~近鉄大和朝倉駅 約 6km
飛鳥 近鉄橿原神宮前駅→豊浦駐車場~飛鳥バス停→近鉄橿原神宮前駅 約 7.0km
飛鳥(自転車) 近鉄橿原神宮前駅~近鉄飛鳥駅 約13km
コースの行程図式を見ていて、一点リクエストしたくなったのは、近鉄あるいはJRから起点までのバス移動の所要時間はどれくらいかを付記して欲しかった。他府県の土地勘のない者にはその部分が記されていると計画を組む上で自宅からの往復の総時間量がイメージしやすくなる。近鉄やJRの幹線はネット検索で手軽に所要時間が分かるが、バス路線などは調べづらいし、手間がかかるので。
本書には、「おまけ」として「柿本神社」と「かぎろひ」、「ちょっと豆知識」として「古代の色名」がそれぞれ1ページで、「おさんぽひとやすみ」として「二上山」「宇陀」「吉野」がそれぞれ見開き2ページで説明するコラムがついている。これも勉強材料になる。
最後に、この各コースに誰の歌が引用されているかを記しておこう。作者名を記しているものについてだけの話ではあるが。どの歌かは、本書を「おさんぽ」して、楽しんでいただければよいだろう。
平城 長屋王、大伴家持、太宰少貳小野老朝臣、山部宿祢赤人、田辺福麻呂、
磐姫皇后、額田王、柿本人麻呂、聖武天皇
春日 橘奈良麻呂、笠金村、坂上郎女、光明皇太后、藤原清河、大伴家持
葛城 丹比真人笠麻呂(記載なし、万葉集確認)
山の辺の道 柿本人麻呂、中大兄皇子、額田王
泊瀬 髙市皇子、三輪髙市麻呂、雄略天皇
忍阪 沙弥女王、間人大浦、額田王、舒明天皇、天智天皇、鏡王女、中臣鎌足
飛鳥 舎人娘子、柿本人麻呂、有馬皇子、上古麻呂、大伴旅人、志貴皇子、持統天皇
作者の明かな歌の他に、詠み人不詳の歌、『日本書紀』からの引用なども各所に組み込まれている。
机上での「おさんぽ」読書が終わったので、このガイドを利用して、コースを歩いてみたいと思っている。私にとっては「おさんぽ万葉集」になるのか、しんどいウォーキング万葉集になるのか・・・・どうだろう。
ご一読ありがとうございます。

本・書籍ランキング
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
本書掲載のコースと関係する観光案内の公のサイトをちょっと検索してみた。一覧にしておきたい。
なら記紀・万葉 :「奈良県地域振興部文化資源活用課」
パンフレット・マップのダウンロード :「奈良市観光協会」
平城宮跡歴史公園 ホームページ
平城宮跡 :「なら旅ネット<奈良県観光公式サイト>」
奈良で自転車を楽しもう :「奈良県」
葛城の道 :「御所市観光ガイド」
山の辺の道(南)コース :「天理市観光協会」
長谷寺参道へようこそ :「初瀬観光ガイド」(初瀬観光協会)
第6回忍坂街道まつり :「桜井市纏向学研センター」
既に終了2017年10月実施の情報です。
国営飛鳥歴史公園 ホームページ
パンフレットダウンロード
特集:明日香村万葉歌碑マップ :「旅する明日香ネット」(明日香村観光ポータルサイト)
調査報告等 文化財 :「明日香村」
光明宗法華寺 ホームページ
春日大社 公式ホームページ
新薬師寺 公式ホームページ
白毫寺 :「奈良市観光協会」
三輪明神 大神神社 公式ホームページ
長谷寺 ホームページ
奈良県立万葉文化館 ホームページ
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)

本・書籍ランキング
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。