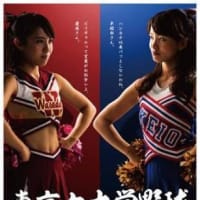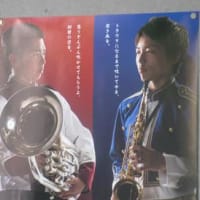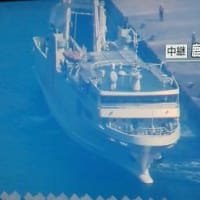こういうテーマも好きです。
見瀬丸山古墳(みせまるやまこふん)は、奈良県橿原市見瀬町、五条野町、大軽町
にまたがった地区に存在する前方後円墳。
6世紀後半に築造されたと推定されており、欽明天皇と堅塩媛の陵墓であるとの説
もある。


●北東方向からみた見瀬丸山古墳
古墳は丘陵上の傾斜地に設けられている。極めて大規模な前方後円墳であり、
全長は318メートル、前方部高さ15メートル、幅210メートル、後円部の径155メートル、高さ21メートルにおよぶ。
これは奈良県下では最大、日本全国においても6位に位置しており、古墳時代後期
後半(6世紀後半)に築造されたものの中では最大の規模を誇っている。
前方部が丘陵の傾斜でわかりにくく、円墳と思われていたらしい。
明治期に、ウィリアム・ゴーランド(ガウランド)なる外国人が
登場する。彼は奈良の古墳調査を行なう。
「日本最大のドルメン(横穴式石室)」と評価する。記録によると羨道は巨大な
自然石6枚(最大のものは16フィート)で天井を覆い、長さ約60フィート、高さ
8~10フィート、幅4~8フィート、壁は巨大な粗い自然石を積んでいる。
羨道を40フィート進んだところで、内部に4フィートほどの深さで水が溜まって
おり、玄室には進めなかったが、かろうじて水面に顔を出している二つの家形
石棺様子を観察した。
なぜか、この記述はフィート単位だ。

この測量図面が問題を提起する。
墳丘の中心と墓室の位置がズレているのである。
なぜか。
となる。
答を言ってしまう。
横穴式石室と羨道は、自然石を積んだだけであり、その自然石は徐々に
巨大化していく。
つまり、築造が無理になったということなのだ。
当時の政権トップたち(?)は、「巨大前方後円墳」か、「横穴式」かの
選択を迫られたらしい。だれに?
「横穴式」が選ばれ、
350年つづいた巨大墳丘の時代が、ここに終わる。
丸山古墳で終わった、終焉したというのである。
ちょっとあっけないのだが、そういうことでありました。
1chの“知られざる大英博物館 第3集・日本”「巨大古墳“消滅”の謎」 なんである。


おわり。