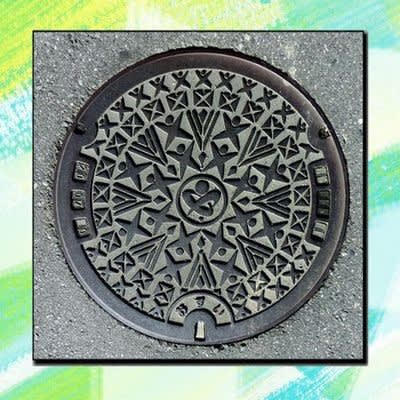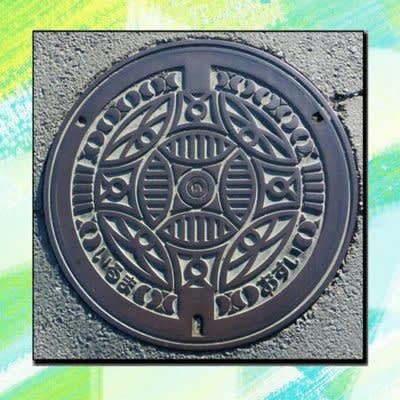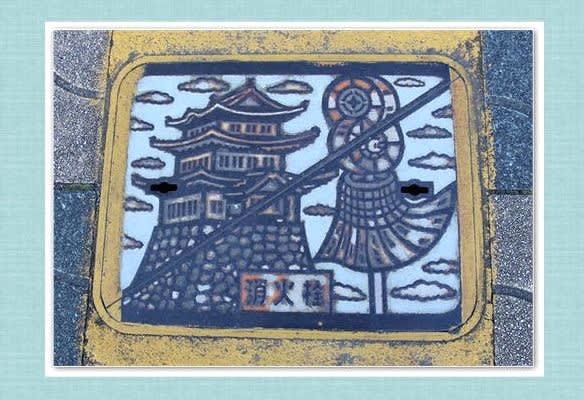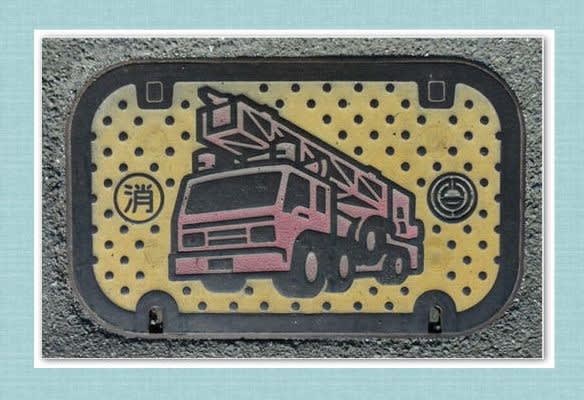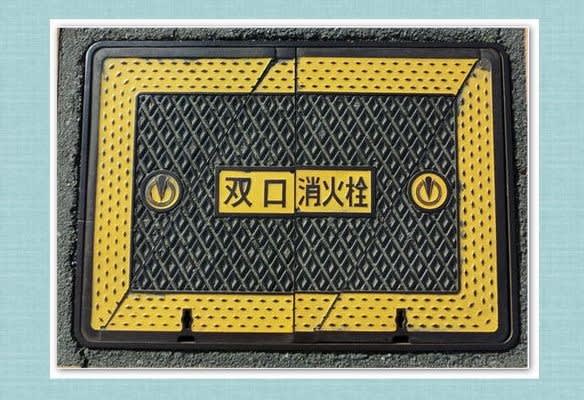社 号:八幡神社(はちまん じんじゃ)
別 称:狭山八幡神社・入間川八幡神社・新田の八幡宮
御祭神:・応神天皇(誉田別命)(おうじんてんのう〔ほむだわけのみこと〕)
・天照皇大御神(あまてらすおおみかみ)
・春日大神(かすがだいじん)
創 建:不明なるも室町時代初期と推定
社 格:旧村社
例 祭:7月15日夏季例大祭 他
指 定:狭山市指定有形文化財〔建造物〕(名称:八幡神社本殿 昭和48年〔1973〕3月1日指定)
鎮座地:埼玉県狭山市入間川3-6-14
狭山市入間川に鎮座する八幡神社は、旧入間川村の鎮守社であったと言われます。
元弘3年(1333)5月8日、上野国(群馬県太田)の御家人・新田義貞は後醍醐天皇の幕府追討の令
旨により挙兵し、討幕のため鎌倉を目指しましたた。その過程において小手指が原(埼玉県所沢市)
の戦いなどを繰り広げましたが、入間川に仮の陣所を置いたとも言われます。その折に八幡神社で
戦勝祈願をし、見事勝利を治めたところから文武・必勝の神として市民に親しまれています。新田
義貞の崇敬篤く一時期は『新田の八幡宮』と呼ばれていました。
また、新田義貞が鎌倉幕府討伐に際して元弘3年(1333)当地に勧請したとの説もあるようです。

『一の鳥居】
鳥居の右側にある『社号標』には【村社八幡神社】と刻まれています。旧社格が【村社】であった
ことを示しています。
石段を上り詰めたところに「二の鳥居」が建っていますが写真は撮っていませんので・・・

正面が『八幡神社社殿』 右の建物は『狭山東武サロン』(結婚式場・レストラン)

拝殿の『扁額』と『門帳』
扁額の「八幡宮」の【八】の文字は鳩が向き合った形 門帳の【左三つ巴】は八幡神社の神紋

左:【本殿』 右:『拝殿』 手前:『新田義貞駒繋の松』

『本殿』 狭山市指定文化財〔建築物〕
享和2年(1802)に建立された 唐破風向拝付 千鳥破風付 入母屋造り

『新田義貞駒繋の松』
義貞は、元弘3年(1333)5月、小手指ケ原の戦いにおいて新田軍は入間川の徳林寺に陣所を定め、
源氏ゆかりの八幡宮へ戦勝祈願した。そのときに愛馬をつないだのが、この松の木だったと言われ
ます。既に松の木は枯れて切り株に若い松の木が移植されていますが何代目の松の木でしょうか。
なお、看板には【史蹟】と入っていますが、国、県、市のいずれからも史跡指定はされていません。
「歴史あるもの」ということで広~く解釈して史跡と表示をしたのでしょう。

社殿の東側には駐車場が設けられています

『神楽殿』 『八雲神社』


〈境内社 以下同じ〉
『大鷲神社』 『思兼神社』


『琴平神社』 『入間川神社』
散策日:平成30年(2018)8月19日(日)
正平8年/文和2年(1353)に鎌倉公方足利基氏が武蔵国入間郡入間川に設置した宿営地「入間川
御所」の比定地(徳林寺)を訪ねた後に訪ねましたが、既に日が落ち始めていましたのでこれだけ
の写真を撮るののもが精一杯でした。しかも、みんなシルエットに近い写真ばかり・・・何とか画
像処理をして
一部写真については別記事に使っていますが、今回「狭山八幡神社」として新たな投稿です。