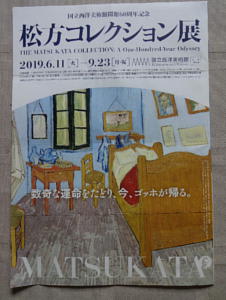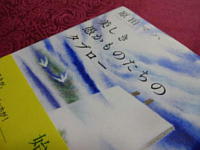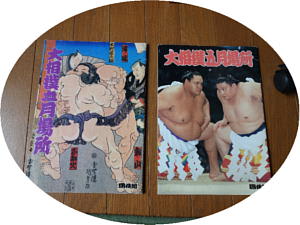実業家・大倉喜八郎が設立した日本初の私立美術館「大倉集古館」リニューアル記念特別展《桃源郷展》へ行きました。数多くの実業家が個性ある美術館を持ち公開していますが、残念ながら「大倉集古館」はあまり知りませんでしたが・・・蕪村から呉春への受け継がれたものが、蕪村は俳諧師だけでなく絵画にも長じているのを知りました。同時開催された名品展、横山大観の「夜桜」と前田青邨の「洞窟の頼朝」が美しかったです。




9月に建て替えられオープンした《ジ オークラ トーキョー》41階建ての高層ホテルです。以前の「ホテルオークラ東京」は少し敷居が高く行ったことがなかったんですが、今日はせっかくなので覗いて(見学)みました。日本の美、和の様式を再現した玄関正面の花飾りと切子玉形のオークラランタンの照明やロピー、重厚感にあふれ優雅、さすがラグジュアリーなホテルです。でも残念ながら・・・落ち着きませんでした。




別館のロビーもまた優雅,屛風型壁面に棟方志功の「鷺綴の柵」の陶板タイルが飾られています。
今回も思いがけず「オークラ 東京」も見られて一粒で二度美味しい体験をしました。




9月に建て替えられオープンした《ジ オークラ トーキョー》41階建ての高層ホテルです。以前の「ホテルオークラ東京」は少し敷居が高く行ったことがなかったんですが、今日はせっかくなので覗いて(見学)みました。日本の美、和の様式を再現した玄関正面の花飾りと切子玉形のオークラランタンの照明やロピー、重厚感にあふれ優雅、さすがラグジュアリーなホテルです。でも残念ながら・・・落ち着きませんでした。




別館のロビーもまた優雅,屛風型壁面に棟方志功の「鷺綴の柵」の陶板タイルが飾られています。
今回も思いがけず「オークラ 東京」も見られて一粒で二度美味しい体験をしました。










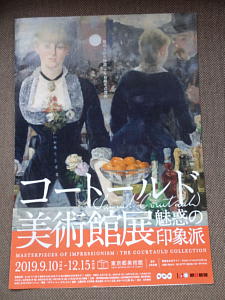

 。
。