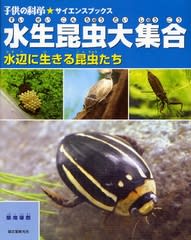昨年9月に環境省より「レッドリスト2015」が公表された。レッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)とは、日本に生息又は生育する野生生物について、専門家で構成される検討会が、生物学的観点から個々の種の絶滅の危険度を科学的・客観的に評価し、その結果をリストにまとめたもので、分類群ごとに分かれており、「昆虫類」もまとめられている。
環境省レッドリスト2015「昆虫類」では、約32,000種の評価対象種類の内、868種類が絶滅もしくは絶滅危惧種として記載され、2012年版の358種に比べて2.4倍もの種が記載されており、日本国内における絶滅(EX)は、4種になっている。
絶滅が危惧される種が増大している背景には、生息環境の消失や環境の悪化が大きな原因となっているが、昨今では、採集者による乱獲も影響を及ぼしている。
- 絶滅(EX)4種
- カドタメクラチビゴミムシ(Ishikawatrechus intermedius)
- コゾノメクラチビゴミムシ(Rakantrechus elegans)
- スジゲンゴロウ(Prodaticus satoi)
- キイロネクイハムシ(Macroplea japana)
ブログでは、機会あるごとに「絶滅危惧種」をまとめ紹介してきたが、今回、環境省レッドリスト2015「昆虫類」が発表されたので、そのリストの絶滅危惧ⅠA類、絶滅危惧ⅠB類、絶滅危惧Ⅱ類、そして準絶滅危惧種の中から、トンボ目とチョウ目(蛾類を除く)の種名をすべて記載し、私自身が撮影した種については 写真にて紹介したいと思う。
環境省レッドリスト2015「昆虫類」
絶滅危惧ⅠA類(CR) 65種
ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い種
- トンボ目
- アカメイトトンボ(Erythromma humerale)
- オガサワラアオイトトンボ(Indolestes boninensis)
- オガサワラトンボ(Hemicordulia ogasawarensis)
- ベッコウトンボ(Libellula angelina)
- ミヤジマトンボ(Orthetrum poecilops)
- チョウ目
- ウスイロオナガシジミ九州亜種(Antigius butleri kurinodakensis)
- オガサワラシジミ(Celastrina ogasawaraensis)
- タイワンツバメシジミ南西諸島亜種(Everes lacturnus lacturnus)
- キタアカシジミ冠高原亜種(Japonica onoi mizobei)
- ゴマシジミ本州中部亜種(Maculinea teleius kazamoto)
- ゴイシツバメシジミ(Shijimia moorei moorei)
- オオルリシジミ本州亜種(Shijimiaeoides divinus barine)
- ウスイロヒョウモンモドキ(Melitaea protomedia)
- ヒョウモンモドキ(Melitaea scotosia)
- オオウラギンヒョウモン(Fabriciana nerippe)
- ヒメヒカゲ本州中部亜種(Coenonympha oedippus annulifer)
- タカネヒカゲ八ヶ岳亜種(Oeneis norna sugitanii)
- ヒメチャマダラセセリ(Pyrgus malvae malvae)
絶滅危惧ⅠB類(EN) 106種
IA類ほどではないが近い将来における野生での絶滅の危険性が高い種
- トンボ目
- オオセスジイトトンボ(Cercion plagiosum)
- ヒヌマイトトンボ(Mortonagrion hirosei)
- オオモノサシトンボ(Copera tokyoensis)
- コバネアオイトトンボ(Lestes japonicus)
- ハナダカトンボ(Rhinocypha ogasawarensis)
- トビイロヤンマ(Anaciaeschna jaspidea)
- ハネナガチョウトンボ(Rhyothemis severini)
- エゾアカネ(Sympetrum flaveolum flaveolum)
- マダラナニワトンボ(Sympetrum maculatum)
- オオキトンボ(Sympetrum uniforme)
- チョウ目
- ウスイロオナガシジミ九州亜種(Antigius butleri kurinodakensis)
- ヒメシロチョウ(Leptidea amurensis)
- ツマグロキチョウ(Eurema laeta betheseba)
- ヤマキチョウ(Gonepteryx rhamni maxima)
- タイワンツバメシジミ本土亜種(Everes lacturnus kawaii)
- ゴマシジミ中国・九州亜種(Maculinea teleius daisensis)
- クロシジミ(Niphanda fusca)
- ミヤマシジミ(Plebejus argyrognomon praeterinsularis)
- アサマシジミ北海道亜種(Plebejus subsolanus iburiensis)
- アサマシジミ中部低地帯亜種(Plebejus subsolanus yaginus)
- オオルリシジミ九州亜種(Shijimiaeoides divinus asonis)
- シルビアシジミ(Zizina emelina)
- コヒョウモンモドキ(Melitaea ambigua niphona)
- ヒメヒカゲ本州西部亜種(Coenonympha oedippus arothius)
- クロヒカゲモドキ(Lethe marginalis)
- チャマダラセセリ(Pyrgus maculatus maculatus)
- ホシチャバネセセリ(Aeromachus inachus inachus)
- アカセセリ(Hesperia florinda florinda)
絶滅危惧Ⅱ類(VU) 187種
絶滅の危険が増大している種
- トンボ目
- オガサワライトトンボ(Boninagrion ezoin)
- カラフトイトトンボ(Coenagrion hylas)
- アオナガイトトンボ(Pseudagrion microcephalum)
- オオサカサナエ(Stylurus annulatus)
- ナゴヤサナエ(Stylurus nagoyanus)
- メガネサナエ(Stylurus oculatus)
- オキナワミナミヤンマ(Chlorogomphus okinawensis)
- ミナミトンボ(Hemicordulia mindana nipponica)
- サキシマヤマトンボ(Macromidia ishidai)
- ハネビロエゾトンボ(Somatochlora clavata)
- シマアカネ(Boninthemis insularis)
- アサトカラスヤンマ(Chlorogomphus brunneus keramensis)
- ナニワトンボ(Sympetrum gracile)
- チョウ目
- ギフチョウ(Luehdorfia japonica)
- ミヤマシロチョウ(Aporia hippia japonica)
- チョウセンアカシジミ(Coreana raphaelis yamamotoi)
- キタアカシジミ北日本亜種(Japonica onoi onoi)
- ゴマシジミ八方尾根・白山亜種(Maculinea teleius hosonoi)
- ルーミスシジミ(Panchala ganesa loomisi)
- ツシマウラボシシジミ(Pithecops fulgens tsushimanus)
- アサマシジミ中部高地帯亜種(Plebejus subsolanus yarigadakeanus)
- ハマヤマトシジミ(Zizeeria karsandra)
- ウラギンスジヒョウモン(Argyronome laodice japonica)
- ヒョウモンチョウ本州中部亜種(Brenthis daphne rabdia)
- オオイチモンジ(Limenitis populi jezoensis)
- ウラナミジャノメ本土亜種(Ypthima multistriata niphonica)
- タカネキマダラセセリ南アルプス亜種(Carterocephalus palaemon akaishianus)
- アサヒナキマダラセセリ(Ochlodes asahinai)
- オガサワラセセリ(Parnara ogasawarensis)
準絶滅危惧(NT) 353種
現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種
- トンボ目
- ヒメイトトンボ(Agriocnemis pygmaea)
- ベニイトトンボ(Ceriagrion nipponicum)
- キバライトトンボ(Ischnura aurora)
- モートンイトトンボ(Mortonagrion selenion)
- グンバイトンボ(Platycnemis foliacea sasakii)
- アオハダトンボ(Calopteryx japonica)
- アマミサナエ(Asiagomphus amamiensis amamiensis)
- オキナワサナエ(Asiagomphus amamiensis okinawanus)
- キイロサナエ(Asiagomphus pryeri)
- ヤエヤマサナエ(Asiagomphus yayeyamensis)
- タベサナエ(Trigomphus citimus)
- フタスジサナエ(Trigomphus interruptus)
- オグマサナエ(Trigomphus ogumai)
- イリオモテミナミヤンマ(Chlorogomphus iriomotensis)
- イイジマルリボシヤンマ(Aeschna subarctica subarctica)
- マダラヤンマ(Aeschna mixta soneharai)
- ネアカヨシヤンマ(Aeschnophlebia anisoptera)
- アオヤンマ(Aeschnophlebia longistigma)
- イシガキヤンマ(Planaeschna ishigakiana ishigakiana)
- アマミヤンマ(Planaeschna ishigakiana nagaminei)
- オキナワサラサヤンマ(Sarasaeschna kunigamiensis)
- キイロヤマトンボ(Macromia daimoji)
- オキナワコヤマトンボ(Macromia kubokaiya)
- ヒナヤマトンボ(Macromia urania)
- ベニヒメトンボ(Diplacodes bipunctatus)
- エゾカオジロトンボ(Leucorrhinia intermedia ijimai)
- タイワンシオヤトンボ(Orthetrum internum)
- チョウ目
- ヒメギフチョウ本州亜種(Luehdorfia puziloi inexpecta)
- ヒメギフチョウ北海道亜種(Luehdorfia puziloi yessoensis)
- ウスバキチョウ(Parnassius eversmanni daisetsuzanus)
- ミヤマモンキチョウ浅間山系亜種(Colias palaeno aias)
- ミヤマモンキチョウ北アルプス亜種(Colias palaeno sugitanii)
- クモマツマキチョウ八ヶ岳・南アルプス亜種(Anthocharis cardamines hayashii)
- クモマツマキチョウ北アルプス・戸隠亜種(Anthocharis cardamines isshikii)
- イワカワシジミ(Artipe eryx okinawana)
- ベニモンカラスシジミ四国亜種(Fixsenia iyonis iyonis)
- ベニモンカラスシジミ中国亜種(Fixsenia iyonis kibiensis)
- ベニモンカラスシジミ中部亜種(Fixsenia iyonis surugaensis)
- カバイロシジミ(Glaucopsyche lycormas)
- オオゴマシジミ(Maculinea arionides takamukui)
- ゴマシジミ北海道・東北亜種(Maculinea teleius ogumae)
- リュウキュウウラボシシジミ(Pithecops corvus ryukyuensis)
- ヒメシジミ本州・九州亜種(Plebejus argus micrargus)
- キマダラルリツバメ(Spindasis takanonis)
- クロツバメシジミ九州沿岸・朝鮮半島亜種(Tongeia fischeri caudalis)
- クロツバメシジミ東日本亜種(Tongeia fischeri japonica)
- クロツバメシジミ西日本亜種(Tongeia fischeri shojii)
- カラフトルリシジミ(Vacciniina optilete daisetsuzana)
- コノハチョウ(Kallima inachus eucerca)
- ヒョウモンチョウ東北以北亜種(Brenthis daphne iwatensis)
- アサヒヒョウモン(Clossiana freija asahidakeana)
- カラフトヒョウモン(Clossiana iphigenia)
- フタオチョウ(Polyura eudamippus weismanni)
- アカボシゴマダラ奄美亜種(Hestina assimilis shirakii)
- オオムラサキ(Sasakia charonda charonda)
- シロオビヒメヒカゲ札幌周辺亜種(Coenonympha hero neoperseis)
- クモマベニヒカゲ北海道亜種(Erebia ligea rishirizana)
- クモマベニヒカゲ本州亜種(Erebia ligea takanonis)
- ベニヒカゲ本州亜種(Erebia neriene niphonica)
- キマダラモドキ(Kirinia fentoni)
- シロオビヒカゲ(Lethe europa pavida)
- ダイセツタカネヒカゲ(Oeneis melissa daisetsuzana)
- タカネヒカゲ北アルプス亜種(Oeneis norna asamana)
- マサキウラナミジャノメ(Ypthima masakii)
- リュウキュウウラナミジャノメ(Ypthima riukiuana)
- ヤエヤマウラナミジャノメ(Ypthima yayeyamana)
- タカネキマダラセセリ北アルプス亜種(Carterocephalus palaemon satakei)
- ギンイチモンジセセリ(Leptalina unicolor)
- ヒメイチモンジセセリ(Parnara bada)
- スジグロチャバネセセリ四国亜種(Thymelicus leoninus hamadakohi)
- スジグロチャバネセセリ北海道・本州・九州亜種(Thymelicus leoninus leoninus)
※スライドショーはPCのみでご覧頂けます。
写真は、800×533 Pixelsで表示できますので、画面の右下にあるフルスクリーンモードをクリックして、大画面でご覧ください。
スビード設定(画面の右下のマーク、右から2番目で変更可能)は、「10」が最適だと思います。画像が表示されない場合は、しばらく時間をおいてから再度ご覧ください。
参考:環境省 レッドリスト(2015)【昆虫類】 http://www.env.go.jp/press/files/jp/28061.pdf
東京ゲンジボタル研究所 古河義仁/Copyright (C) Yoshihito Furukawa All Rights Reserved.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------