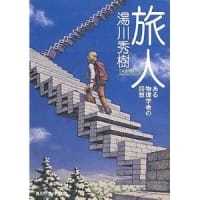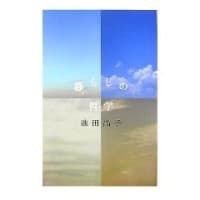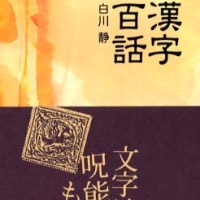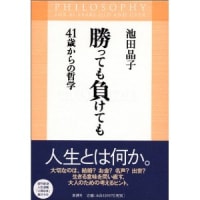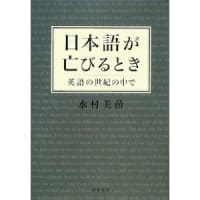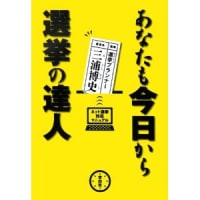p.160~
“坂の上の雲”という言い方がありますね。司馬遼太郎さんと話していて、僕は面白いなあと思ったのだけれども、『坂の上の雲』が高度成長の応援歌のように思われた時期がある。それを司馬さんは苦々しく不愉快に思っていましたよね。「違うんだよなあ」と言っていたんですよ。
『坂の上の雲』というのは、希望の象徴のように言われているけれども、そうではない。脱亜入欧のなかで、ヨーロッパに学んでアジア諸国をゴボウ抜きにして坂を駆けのぼっていく。峠のてっぺんに立って雲はつかめるか。坂の上の花とか果実だったらつかめるけれども、峠のてっぺんに立ったとき、雲は山のかなたの空遠く、向こうを流れているだけです。
つまり、“坂の上の雲”は、永遠に到達することのできない目標という意味なんですね。永遠につかむことのできない夢、ということなのです。ある意味ではニヒルな、クールな視点です。雲は永遠につかめないだろうという、深いアイロニーが背後にあるすばらしい題名ですよね。われわれ日本人は、明治以降、そうした背景にある部分を故意に見てこなかったんじゃないかと思うんですよ。
***************************************************
司馬遼太郎の一連の作品に現れている歴史観を表して、「司馬史観」と呼ばれているそうです。これは、合理主義を重んじることを前提として、具体的には明治時代と昭和時代を対置し、封建制国家を合理的な近代国家に作り替えた明治維新を高く評価する一方で、昭和期の敗戦までの日本を暗黒時代として否定する捉え方とのことです。ところが、司馬遼太郎自身は「史観」という考え方自体にそもそも否定的であり、本人を差し置いた解釈論争の側面が大きいようです。
司馬史観の特徴は、右からも左からも叩かれる点にあるようですが、司馬遼太郎の座右の銘が「中庸の徳」であったことを考えると、むべなるかなと思います。右からも左からも叩かれないのは単なる凡庸ですが、右から見れば左、左から見れば右という恐れられ方は、中庸かつ合理的でなければあり得ないことだと思います。歴史の捏造や歪曲という概念を有するか否かにより、歴史観はその入口から器の大きさが異なってくるように感じます。