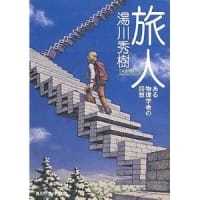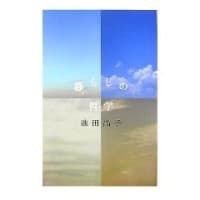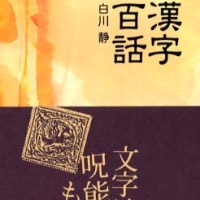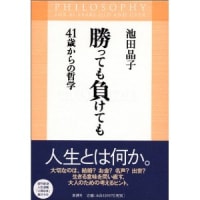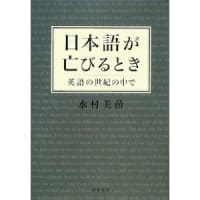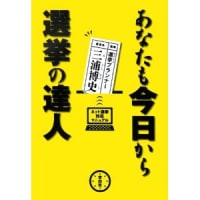p.3~
身近に政治家がおらず、みんなが政治や政治家と少し距離を置いているといういまの状態では、いったいどんなことが起きるのでしょうか。発生する問題の1つは、僕らの「声なき声」、あるいは社会的弱者の意見が、さまざまな決定のプロセスから漏れてしまうということです。届くのは組織力のある各種団体に属している人たちの「大きな声」だけなのです。
さまざまな環境の変化により、政治が果たすべき機能の一部が発揮されなくなってしまったのに、いまだ多くの政治家は従来型の組織や政治システムの維持に大半の時間を割いています。そして、「声なき声」を聞くことはムリだとあきらめてしまっているように感じます。結果的に社会的弱者の声はどんどん埋もれていきます。そうして、僕らのなかに、一向に「社会が変わらない」もどかしさが蓄積されていくのです。
p.57~
いちばん問題だと思うのは、政治家の多数派は、「強いビジョンを持った人」ではないということです。ビジョンや理念など持たない政治家のほうが成功するといってもいいかもしれません。国を治めるのに、国民一人ひとりの意見をすべて聞くことなど不可能です。だから、投票で選ばれた“国民の代表”としての政治家が利害関係を調整し、統治を行う。これが「代議制民主主義」の本質です。
ですが、多くの場合、政治家が代表しているのは、影響力の大きい組織や人、つまり、全国組織を持つ業界団体や労働組合、地元の町内会、自治会長などの声です。高邁なビジョンや理念を掲げるより、この人たちの意見をそのまま汲めば、票がたくさん集まる。そのほうが効率的なわけです。このように、ほんの一部の意見を代表しているのが、現実の政治家という存在なのです。
***************************************************
国政選挙は一般庶民から遠いのに対し、地方選挙はより身近であり、この距離関係が動くことはないと思われます。それだけに、国政選挙が「風頼み」「風向き」の選挙であり、その風の影響が地方選挙の結果まで左右していることは、社会的弱者の「声なき声」など届きようがないという状況を示していると感じます。庶民の目の前の問題が切実になればなるほど、身近なはずの地方選挙は無意味になり、切実感を失わざるを得なくなるようにも思います。
恐らく年金は今後も減額されるでしょうし、医療費の自己負担額も上がっていくでしょうし、少子高齢化の状況では消費税増税もやむを得ず、社会的弱者の「声なき声」は膨らみ続ける一方だと思います。このような状況において、庶民が何とか声を出そうとすれば、地方選挙は飛ばされて国政選挙に向かうしかありません。一番身近なはずの市町村の施策に対しては、特に不満もなければ要望もなくなり、自分の生活とあまり関連しなくなってくるからです。
私自身、自分の住む市町村から電車で通勤し、その組織でノルマに追われて朝から晩まで働いて疲労困憊し、あるいは別々の市町村から集まってきた同僚との人間関係でストレスを溜め、仕事のトラブルで頭も胃も痛いというときに、「街づくり」「地域コミュニティ」「夢が持てる街」などと駅前で演説されても腹が立つだけです。身近なはずの市町村の選挙が全く身近に感じられず、国政選挙のほうが身近に感じられるというのが、私の偽らざる感覚です。