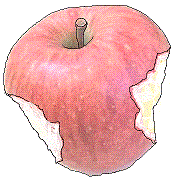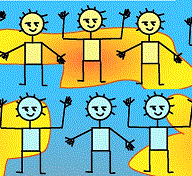学校教育と大学共通テストは区別して論ずるべきである。大学共通テストは学校教育に影響を与えるが、学校教育は大学共通テストから本来独立してあるべきである。多様性があってしかるべき社会で、共通テストがあること自体がおかしいのであって、大学共通テストで、高校や大学の教育が均一化されることを避けるべきである。
学校教育に関しては、誰もがこうあるべきという権利がある。そして、それらの意見が互いに戦わされ、学校教育に反映していく道筋があるのが、民主主義社会の教育のあり方だと思う。さもなければ、学校教育は、政府主導の洗脳教育の場となる。
共通テストがなぜあるのか、私にはわからない。国民の学力レベルの底上げを狙うものなのなら、問題は易しくて、かつ、大学入学と結び付けないようにすべきである。
大学入学共通テストの英語テストを批判する投稿が数日前に朝日新聞にあった。批判のポイントがどこにあるか、具体的には わからなかったので、語学嫌いの私も、テスト問題文を分析してみた。
英語のテスト問題は、パターン化、形式化している。そのため、問題のパターンになれた受験者は高得点がとれる。予備校に通うか、学校で同じパターンのテストを受けている者が有利である。
問題文は、主文のテキストと、それを補う図表と、選択で回答を選ばす質問文からなる。
問題文に出てくる英語の9割がたは基本的語彙といえる。残りの1割は、問題文を読めば、意味が推測できる。単語によっては、問題文の中に直接説明されている。わからない単語が出てきても気にせずに読む訓練を受けている者には有利である。
私は英語が嫌いだから、中学、高校を通して予習、復習したことはない。したがって、辞書を引かずに、英語圏の新聞、雑誌、論文を読む習慣がついている。ときたま、ある日突然、単語の意味をまったく誤解していたことに気づき、冷や汗をかく。
私がそうだからと言って、生徒が辞書を引かずに英文を読むことを、高校の英語教師は受け入れることができるだろうか。
辞書を引かずに英文を読めるには、その英文が何を対象に書いているか、わからないといけない。これは、受験者がどんな文化圏で育ったかに依存する。問題文を読んで感じたのは、都会生活の経験がある者やインターネットを日常的に使う者に有利にできている。たぶん、問題文の作成者の多くが、都会育ちであるからではないか。
問題文の理解には上記の不公平があるが、主文のテキストは単語も構文も易しいものからなる。図表の英語も易しく、主文の理解を助ける。
それに対し、各質問は、主文のテキストの高度の理解を求めるようにできている。すなわち、主文のテキストから、書かれていないことを推測して、注意深く回答を選択する必要がある。これは難しいのだ。ここで要求されていることは、自分の考えを育てることではなく、問題の作成者が意図する回答を選択する能力である。
この問題作成者の傲慢さは英語でだけでなく、国語のテストでも見受けられる。かつてNHKテレビで、東進ゼミの林修は、東大の先生というものは自分の本音の明示を避けて遠回しの表現をするが、その表現パターンを習得すると国語の試験問題が簡単に解けると言っていた。
こういう能力を大学入学共通テストで要求するとなると、トップの意図を忖度して行動する官僚や社員が社会で多くなる。こんなことを教育するのに、学校教師は我慢できるであろうか。
NPOで私の指導している子どもたちの多くは、神経発達症か神経症の傾向がある。彼らがこの共通テストをクリアして希望する大学に行くのは、非常に難しい。彼らは絶えず考える子どもたちで、考えずに機械的に質問を処理する子どもたちと異なる。せめて、問題の量を減らしていただけないか、と思う。
不公平にならないように気遣う問題作成者の苦労もわかるので、一番良いのは、大学入学共通テストを廃止することだと思う。