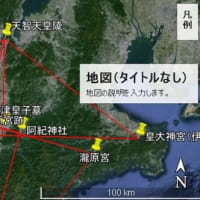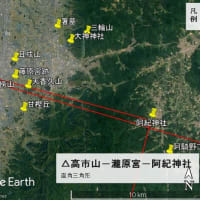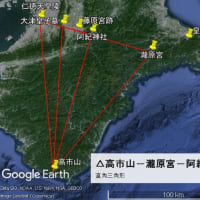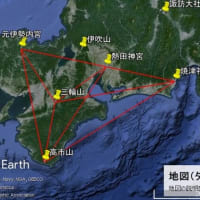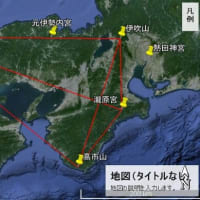天照大神・高木の神が太子(ひつぎのみこ・皇太子のこと)天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)に降臨を命じたにもかかわらず、天忍穂耳命は断って天忍穂耳命の御子の邇邇芸命(ににぎのみこと)が天降りすることになります。
邇邇芸命は天照大神にとって孫にあたります。御子ではなく、孫ということで長い時間の経過を表わしています。天孫降臨は実際には卑弥呼が死んでから二百年以上の時が経過してから、天孫に当たる方が出雲から大和に復帰したことを指します。これが根本的な意味です。
同時にもう一つの意味が重ね合わされています。「倭人伝」で過去の出来事と、現在に近い出来事が一緒くたになってしまったのと同じ事が「記・紀」では故意に実行されています。古事記は推古天皇の御代で終わっていますが、それ以降のことも書かれているのです。「倭人伝」が魏の時代が終わった後のことも書いてしまったからです。このことに関して次の解説があります。
そして、こちらのほうは一般的に理解されているようです。
「オシホミミノ命が天降る準備をしている間に生まれたニニギノ命が,葦原中国の統治者として天降る、とされていることについて、上山春平氏は次のように述べられた。天照大御神には持統太上天皇の投影が見られる。持統太上天皇は、天武天皇の皇子、草壁皇子の即位を願っていたが、草壁皇子が夭折したので、その御子の軽皇子が即位して(文武天皇)、文武天皇の後見役となったのが持統太上天皇であると、述べ、史実と神話との関係を指摘された。(『続・神々の体系』による)この説は否定しがたいものと思う。したがってこの神話の成立は文武天皇以後であろうと考えられる。」
古事記(上) 次田真幸 講談社文庫p173,4
この説は大方の共感を得ているようです。確かに(孫)という字を使用したのは持統天皇、文武天皇の祖母・孫の関係があったからであろうとは思われます。しかしそれだけだというような単純な話ではないのです。
それだけなら天照大神・高木の神-天忍穂耳命-邇邇芸命のラインは、後世の都合のいいように作られた神話というだけで、只の捏造になってしまいます。
主要なのはあくまでも、長い時間が経過した後の卑弥呼の(子孫の)復活ということなのです。ですから、この神話の骨格の成立は文武天皇以前に求められます。
ただ、初めは孫という言葉を使用していないようです。もし孫という言葉を使わなかったとしたら、どうやって長い時の経過を簡潔に表現していたのでしょうか。
(孫という字を使用しないで時の経過を表現するもう一つの方法は神功皇后が応神天皇を懐妊しながらも、石を御腹に巻きつけ、出産を遅らせるというところにあらわれています。出産の遅れで二百年以上の経過を表わしています。応神天皇も天孫です。ニニギノミコト=応神天皇=継体天皇という等式が成立します)
そして「倭人伝」の間違いのように、一つの事件として描写されている中に二つの事件を一緒くたに混同して記述したのです。二重の意味を持たせました。
なお、古事記が推古天皇の、また日本書紀が持統天皇の、それぞれ女帝の御代で終わっているのは「倭人伝」が卑弥呼の業績で終わっているからです。推古、持統天皇を卑弥呼に見立てています。特に持統天皇はみずから卑弥呼の生まれ変わりを自認されたはずです。なぜなら持統天皇は死後、皇室で初めて火葬にふされたからです。これは持統天皇の強い要望であったはずです。最後の卑弥呼トヨが火によって殺され、なおかつ(子孫が)復活したことをみずからに課したのです。
邇邇芸命は天照大神にとって孫にあたります。御子ではなく、孫ということで長い時間の経過を表わしています。天孫降臨は実際には卑弥呼が死んでから二百年以上の時が経過してから、天孫に当たる方が出雲から大和に復帰したことを指します。これが根本的な意味です。
同時にもう一つの意味が重ね合わされています。「倭人伝」で過去の出来事と、現在に近い出来事が一緒くたになってしまったのと同じ事が「記・紀」では故意に実行されています。古事記は推古天皇の御代で終わっていますが、それ以降のことも書かれているのです。「倭人伝」が魏の時代が終わった後のことも書いてしまったからです。このことに関して次の解説があります。
そして、こちらのほうは一般的に理解されているようです。
「オシホミミノ命が天降る準備をしている間に生まれたニニギノ命が,葦原中国の統治者として天降る、とされていることについて、上山春平氏は次のように述べられた。天照大御神には持統太上天皇の投影が見られる。持統太上天皇は、天武天皇の皇子、草壁皇子の即位を願っていたが、草壁皇子が夭折したので、その御子の軽皇子が即位して(文武天皇)、文武天皇の後見役となったのが持統太上天皇であると、述べ、史実と神話との関係を指摘された。(『続・神々の体系』による)この説は否定しがたいものと思う。したがってこの神話の成立は文武天皇以後であろうと考えられる。」
古事記(上) 次田真幸 講談社文庫p173,4
この説は大方の共感を得ているようです。確かに(孫)という字を使用したのは持統天皇、文武天皇の祖母・孫の関係があったからであろうとは思われます。しかしそれだけだというような単純な話ではないのです。
それだけなら天照大神・高木の神-天忍穂耳命-邇邇芸命のラインは、後世の都合のいいように作られた神話というだけで、只の捏造になってしまいます。
主要なのはあくまでも、長い時間が経過した後の卑弥呼の(子孫の)復活ということなのです。ですから、この神話の骨格の成立は文武天皇以前に求められます。
ただ、初めは孫という言葉を使用していないようです。もし孫という言葉を使わなかったとしたら、どうやって長い時の経過を簡潔に表現していたのでしょうか。
(孫という字を使用しないで時の経過を表現するもう一つの方法は神功皇后が応神天皇を懐妊しながらも、石を御腹に巻きつけ、出産を遅らせるというところにあらわれています。出産の遅れで二百年以上の経過を表わしています。応神天皇も天孫です。ニニギノミコト=応神天皇=継体天皇という等式が成立します)
そして「倭人伝」の間違いのように、一つの事件として描写されている中に二つの事件を一緒くたに混同して記述したのです。二重の意味を持たせました。
なお、古事記が推古天皇の、また日本書紀が持統天皇の、それぞれ女帝の御代で終わっているのは「倭人伝」が卑弥呼の業績で終わっているからです。推古、持統天皇を卑弥呼に見立てています。特に持統天皇はみずから卑弥呼の生まれ変わりを自認されたはずです。なぜなら持統天皇は死後、皇室で初めて火葬にふされたからです。これは持統天皇の強い要望であったはずです。最後の卑弥呼トヨが火によって殺され、なおかつ(子孫が)復活したことをみずからに課したのです。