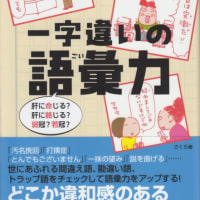真鶴(まなづる)
川上弘美 著
文藝春秋 刊
朝日新聞の「ゼロ年代の50冊」という企画に選ばれた一冊。
1位にジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』を据えたあの企画である。
企画そのものは僕にいわせれば玉石混淆。「確かに」と納得する作品もあれば「なんでこれが」と首を傾げさせられるものもある。
だもので、なんで川上弘美の『真鶴』なのか、これが10年間に出版された膨大な本の中からベスト50に選ばれたというのも、実はよくわからない。
悪い作品ではない、むしろ傑作である。しかし、だからといって、それほどのものか、とも思う。
だが、美しい魅力的な作品である。
2000-2009年のベスト50かどうかはともかく、推薦することに躊躇はない。
川上弘美という作家は、ずっと以前から気になっていたものの、1冊読んでしまったら最後、取り憑かれそうで怖かった。
内田百閒の影響を濃く受けている彼女の作品は、その向こうに内田百閒が生きているのではなくて、内田百閒そのものが「今ここ」に、21世紀に、今風の感性を持って存在している、と思わされてしまいそうな怖さがあるのだ。
本来遠くにあるものが、突然目の前に現れてしまったら、誰だって混乱する。
僕の内田百閒好きは、古本屋の店頭ワゴンで見つけた裸本の『阿房列車』にはじまって、映画『ツィゴイネルワイゼン』とその原作『サラサーテの盤』ですっかり確立してしまった。
なぜ好きかというと、それは、「へん」だからである。
内田百閒の師匠である夏目漱石には「へん」なところがない。しかし内田百閒はまぎれもなく「へん」なのだ。
そして、川上弘美も「へん」であって、その「へん」さが内田百閒とあきらかにオーバーラップしている。それなのに別物であるから、ややこしい。
僕は「弁証法的唯物論」の家庭に育ったものだから、どうしても目に見えないものを素直に信じることができない。
かといって、頭から否定もしない。世の中には科学で説明できないものがあってもよいではないか、と思うし、実際説明できないものがたくさんある。
医学一つとってみても、治療法も原因もわからない難病といわれる病気が何百もある。
科学を信じないわけではない。むしろ頼っている。
代替医療だの自然療法だのと、人から勧められても、拒否はしないが信頼もしない。
まして祈祷やおまじないで病気が治るなど、てんで信じていないし、それで治ったという人の話も聞いたことがない。
しかし、精神や意識の世界となると、これは摩訶不思議である。
「自分」はなぜ「今ここ」にいることになったのか、江戸や明治でないのはなぜか、アフリカやヨーロッパでないのはなぜか、誰が選んだのか。
こればかりは誰に聞いてもわからない。
すべてを支配する宇宙存在の指令によって割り振られたとか、天界で悪さをしたものだから、神様によって地上に降ろされて修行させられているという話もあるが、子供を脅かす話としては面白くても、いい大人が疑いもなくそんなことを信じていたら、アホである。
わずか1キロや2キロの脳で考えたことが、世界を覆すほどの影響を及ぼすこともある。
不思議である。
自然界にはまだ解明されていない不思議なことがあっておかしくないと思う。
同時に、すべてが解明されてしまったら、この世の中はなんと味気ないものになってしまうだろうとも思う。
いくら科学が発達しても、少しは「わからないこと」をとっておきたいものだ。
いわゆる精神世界と呼ばれる分野の本の翻訳者として名高い某氏は、自身では精神世界などほとんど信じていないという。
「抵抗ないですか、翻訳してて」
「だって、面白いじゃないですか」
おおかた、そんなものである。
てなわけで、「そんな世界があったら、それもまた面白いじゃないか」というような気持ちで、「妖かしの世界」を楽しんできた。
先日も、岩波文庫の江戸怪談集を古書店で手に入れた。
泉鏡花や上田秋成、京極夏彦なども結構好きだ。
内田百閒も川上弘美も、乱暴な分類をすればその仲間に入るような気がする。
以前(2008年4月29日)の記事で、川上弘美が生まれてはじめて買った百閒が『鶴』だったと紹介した。
そこで、「へ、へんなものを、み、みつけちゃったよ」とびっくり仰天したのが、どうやら川上弘美の内田百閒化の始まりだったらしい。
前置き(言い訳)が長くなった。で、『真鶴』である。
この本も、多少頭を柔らかくして読まないと混乱する。
「これはいったい何の隠喩だろうか」とか「主人公の妄想と現実をどこで分けるべきか」などと分析し始めるとますます訳が分からなくなる。
そのままストレートに読めばいい。
京(けい)の夫礼(れい)は娘の百(もも)が生まれてほどなく失踪する。
生死不明のまま十数年が経ち、「いないのに近い」夫の存在を体の片隅に残したまま毎日を送る。
夫の残した日記に書かれた「真鶴」という文字に惹かれ、目的もなく何度も真鶴を訪れる。実際には三回。
真鶴に行くと、京が行く先々に「女」がついてくる。その女は京にしか見えず、語り合いながら日常と、「よくわからないもの」の棲む異界を往き帰する。
「ついてくる女」は京自身でもあり、妖かしでもある。
この「女」は内田百閒の『鶴』(自分についてくる鶴)にかさなり、真鶴は『ツィゴイネルワイゼン』の彼岸に重なる。
『ツィゴイネルワイゼン』では彼岸と此岸が切り通し(鎌倉の「釈迦堂切り通し」がロケ地)で区切られているが、『真鶴』では切り通しと同じ役割を交通機関が担う。
そう、京は此岸としての日常と、彼岸としての真鶴をバスや電車で往き帰しているのだ。
この小説は、真実がわからない小説である。夫の失踪の原因を、不倫の果ての逃避行ともとれるが、それも京の想像の域を出ない。
夫の礼は実際どうなっているのか、それも不明のままだ。
生きているのか死んでいるのか。もしかすると京が殺したのか。
わからない。
京の喉元に引っかかるものは、単に観念的なものなのか、それとも彼女の未来を暗示する食道がんなどのシリアスな存在なのか。
夫が失踪してからの京は、生活のためにライターを始めてから親しくなった編集者の青茲(せいじ)と、長い愛人関係にある。彼には妻と三人の子供がいる。
とても近いはずなのに、夫の礼ほどの近さを感じられない。
青茲は自分が礼の代わりにされていることを認めながら、京を優しく包み込んでいる。
あるとき、京の夫の実家を二人でおとずれ、そこで京の体から礼が離れずにいることがわかったとき、青茲は京に小説の創作を勧め、元の編集者とライターの関係に戻そうとする。
青茲や礼とのベッドシーンは、短い言葉で綴られているのに、艶かしく淫靡である。
「した」…「はいった」…「流れ出ないようにすぼめて」…
心地よい「嫌らしさ」がにじみだしてくる。
京という女性一人を通してみた一人称的な文体は、センテンスが短くてひらがなが多い。しかし、決して読みにくくはない。それが京のつぶやき、心の中の言葉だと感じさせる効果がある。
ところどころ接続助詞を省いた、こなれていない文章にかえってリアリティを感じさせる。
読み終わって、やはりもう一冊読みたくなった。
しかし、もう一冊読んでしまったら、この妖しい世界から離れられなくなりそうだ。だから、間を置くことにする。
リンク→「へんな本 内田百閒・稲垣足穂」
◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆
(PR)【GALLAPからのお知らせ】
★ライティング & エディトリアル講座 受講生募集中★
●個別コンサルティング承り。当オフィス、またはスカイプ利用でご自宅でも受講できます。
*1ヵ月2回コース~12ヵ月24回コース。(1回60~90分)
*現在、1名空きあり。定員オーバーの場合、お待ちいただく場合があります。
●出張講座承り(1日4~5時間)
■ご相談・詳細はメールで galapyio@sepia.ocn.ne.jp まで。
●自費出版、企画出版、書店流通。
*坂井泉が主宰する編集プロダクション“GALLAP”が、編集から流通まで、責任持ってすべて引き受けます。
■ご相談・詳細はメールで galapyio@sepia.ocn.ne.jp まで。