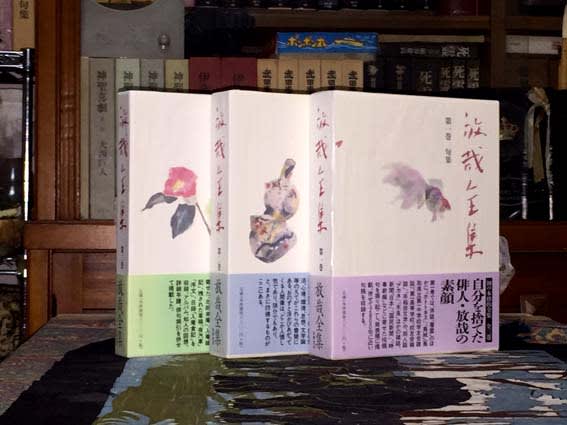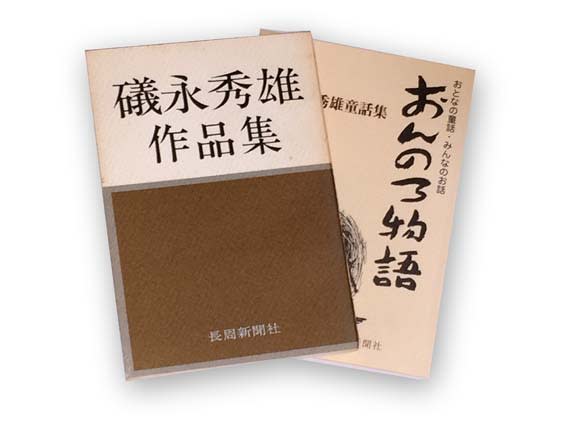すっかりご無沙汰してしまった。ずっと更新していなかったのに、その間もたくさんの方々にご訪問いただいた。
感謝、感謝!
サボっている間に実にさまざまなことがあって、ぼつぼつと紹介させていただく。
自分は編集者なので、話題はほんのことが中心異なる。まずは書評から。

この直木賞は、正直びっくりした。
直木賞(芥川賞も)は文藝春秋社という出版社が主催する文学賞であるから、会社の方針やポリシーなどがまったく影響しないとはいえない。ご存知のように、新潮社とならんで、保守的な傾向が強い大手出版社のひとつである。そんな出版社が、よくぞまあこの作品に賞を与えたものだと驚いた。
『宝島』は戦後から返還までの、アメリカ支配下の沖縄が描かれていて、著者はかなり綿密な調査をした上で執筆していることが感じられる。主要な登場人物は創作だが、屋良朝苗や瀬長亀次郎、悪名高いキャラウエイ高等弁務官など、実在人物は実名で描かれている。
「戦果アギヤー」「Aサイン」など、ヤマトンチュにはあまりなじみのない用語もふんだんに登場する。とくに、軍用機が墜落して大惨事を引き起こした宮森小学校のシーンは、まるで現場にいたかのようにリアルである。
作者の真藤順丈さんは、沖縄の人ではない。自身、「沖縄人でないものが沖縄のことを書いていいのか」と自問自答したそうだ。しかし、本土の人間が書くことにこそ意味があるのではないかと決断し書き進めたという。
最近、本土の人間が沖縄の問題を語るのを嫌うウチナンチュに出会うことがしばしばある。言葉尻を捉えて「本土の人間が勝手なことを言うな!」と怒鳴りつけられたこともあった。
はて、そうしたウチナンチュは、真藤さんの小説にどんな反応をするのであろうか。
----------------------------------------------------------------------------------------
一生に一度の記念
卒論・学位論文を本にしよう
人生の節目の記念として、卒論や学位論文を本にする方が増えています。
出版社の目にとまれば、企画出版として一般に流通することもあります。
もちろん、ご自身や身近な人に蔵書していただくための少部数の出版も可能です。
出版にはさまざまな目的があります。
・ご自身の仕事や経営している店舗・企業をPRすること。
・書きためた原稿の整理と保存。
エッセー、詩、俳句、和歌
自分史、日記、ブログ、旅行記
写真集、画集、その他作品集
などなど。
せっかく書きためた原稿も、そのままでは散逸してしまいます。しかし本にして、複数の人に蔵書してもらえれば、数十年、ときには数百年、末代までも保存されます。
上記に該当するものがございましたら、ぜひご相談ください。
◆ご相談お見積り無料
E-mail:galapyio@sepia.ocn.ne.jp
電話:03-5303-1363
感謝、感謝!
サボっている間に実にさまざまなことがあって、ぼつぼつと紹介させていただく。
自分は編集者なので、話題はほんのことが中心異なる。まずは書評から。

この直木賞は、正直びっくりした。
直木賞(芥川賞も)は文藝春秋社という出版社が主催する文学賞であるから、会社の方針やポリシーなどがまったく影響しないとはいえない。ご存知のように、新潮社とならんで、保守的な傾向が強い大手出版社のひとつである。そんな出版社が、よくぞまあこの作品に賞を与えたものだと驚いた。
『宝島』は戦後から返還までの、アメリカ支配下の沖縄が描かれていて、著者はかなり綿密な調査をした上で執筆していることが感じられる。主要な登場人物は創作だが、屋良朝苗や瀬長亀次郎、悪名高いキャラウエイ高等弁務官など、実在人物は実名で描かれている。
「戦果アギヤー」「Aサイン」など、ヤマトンチュにはあまりなじみのない用語もふんだんに登場する。とくに、軍用機が墜落して大惨事を引き起こした宮森小学校のシーンは、まるで現場にいたかのようにリアルである。
作者の真藤順丈さんは、沖縄の人ではない。自身、「沖縄人でないものが沖縄のことを書いていいのか」と自問自答したそうだ。しかし、本土の人間が書くことにこそ意味があるのではないかと決断し書き進めたという。
最近、本土の人間が沖縄の問題を語るのを嫌うウチナンチュに出会うことがしばしばある。言葉尻を捉えて「本土の人間が勝手なことを言うな!」と怒鳴りつけられたこともあった。
はて、そうしたウチナンチュは、真藤さんの小説にどんな反応をするのであろうか。
----------------------------------------------------------------------------------------
一生に一度の記念
卒論・学位論文を本にしよう
人生の節目の記念として、卒論や学位論文を本にする方が増えています。
出版社の目にとまれば、企画出版として一般に流通することもあります。
もちろん、ご自身や身近な人に蔵書していただくための少部数の出版も可能です。
出版にはさまざまな目的があります。
・ご自身の仕事や経営している店舗・企業をPRすること。
・書きためた原稿の整理と保存。
エッセー、詩、俳句、和歌
自分史、日記、ブログ、旅行記
写真集、画集、その他作品集
などなど。
せっかく書きためた原稿も、そのままでは散逸してしまいます。しかし本にして、複数の人に蔵書してもらえれば、数十年、ときには数百年、末代までも保存されます。
上記に該当するものがございましたら、ぜひご相談ください。
◆ご相談お見積り無料
E-mail:galapyio@sepia.ocn.ne.jp
電話:03-5303-1363