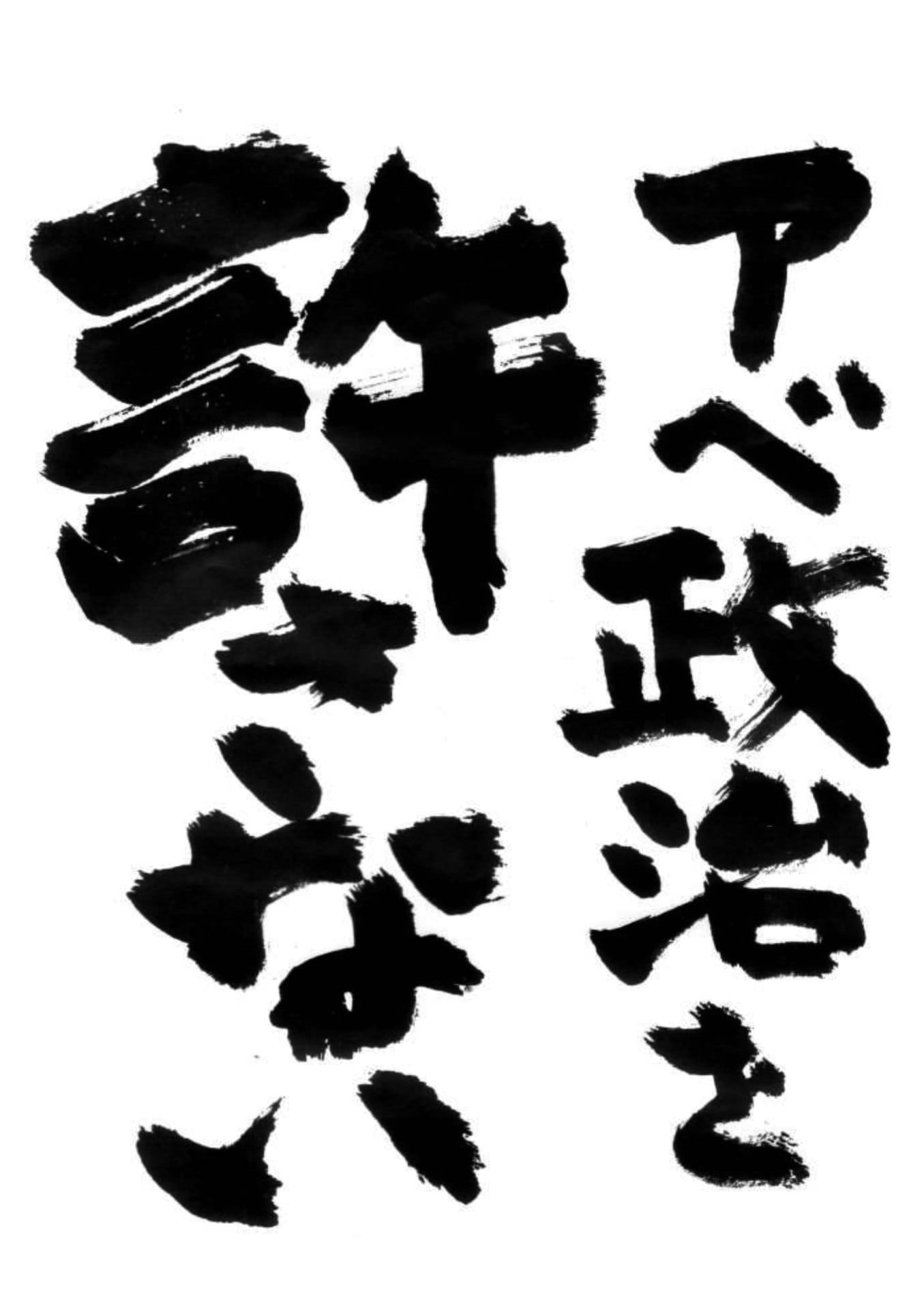「通販生活」という雑誌がある。知っている人は、この雑誌がただの買い物雑誌でないことをよくわかっている。がしかし、知らない人は存在そのものすら知らない。そういう雑誌だ。
だいぶ前になるが、歴史学者の林博文教授を囲んだ集いがあって、その席上で、「通販生活」が憲法九条についてアンケートをとった話が出た(記憶に間違いなければ、林教授が記事を書いたとかなんとか……)。「通販生活」の影響力について語り合ったのだが、知ってる人のあいだでは評価が高かった反面、参加者の半数以上が存在を知らないか知っていてもほとんど読まれていないマイナーな雑誌だと思っていた。
これほど評価が分かれる雑誌も珍しい。
で、その「通販生活」が今年の夏号で、「自民党支持の読者の皆さん、今回ばかりは野党に一票、考えていただけませんか」という呼びかけで参院選特集を掲載した。
もちろん、詳細なその理由も含めての記事なのだが、それに対して一部の読者から、政治色が強すぎる、買い物雑誌にふさわしくないなどの批判がよせられた。「左翼雑誌か」という意見もあったらしい。
それに対して、冬号で批判への回答を掲載した。
「買い物雑誌に政治を持ちこむな」という意見に対しては、暮らしのすべてが政治の影響を受けているとし、したがって、平和だからこそ買い物ができることを説く。
「お金もうけだけ考えて、政治の話には口をつぐむ企業にはなりたくないと考えます」と結んだ。
「左翼雑誌か」という意見に対しては、「通販生活」のスタンスは、戦争と原発、沖縄差別は「まっぴら御免」だとした上で、「こんな『まっぴら』を左翼だとおっしゃるのなら、左翼でけっこうです」と答える。
「良質の商品を買いたいだけなのに、政治信条の違いで買えなくなるのが残念、と今後の購読を中止された方には、心からおわびいたします。永年のお買い物、本当にありがとうございました」と締め括った。
じつに潔いではないか。
この件は、東京新聞の11月10日付けで紹介された他、テレビのニュースにもなった。
そいう自分は、過去に「通販生活」は購読していたのだが、購読料を払い忘れていたら送られて来なくなってしまった。定期購読の読み物が山ほどあって、とても手が回らないのでそのままになってしまっている。さて、継続を申し込むべきかどうか、少しだけ迷っている。
先日、「アジア記者クラブ」のボランティアをしている女性が、「集団的自衛権反対」などのステッカーを貼ったバッグを持って、お孫さんを保育園に迎えにいったところ、母親の一人からステッカーを見とがめられ、「あなた、アカですか?」と言われたそうな。
今時そんなこという人いるんだってビックリしたと言う。どうも日本人はレッテルを張って批判したり評価したりする傾向にある。人間にはさまざまな側面があることを認めようとしない。
どんなによいことでも、それが自分と信条的に合わない人間が関わっていれば賛成できない、ということだ。どんなに良い品物でも、買わないということだ。実にくだらない。
だいぶ前になるが、歴史学者の林博文教授を囲んだ集いがあって、その席上で、「通販生活」が憲法九条についてアンケートをとった話が出た(記憶に間違いなければ、林教授が記事を書いたとかなんとか……)。「通販生活」の影響力について語り合ったのだが、知ってる人のあいだでは評価が高かった反面、参加者の半数以上が存在を知らないか知っていてもほとんど読まれていないマイナーな雑誌だと思っていた。
これほど評価が分かれる雑誌も珍しい。
で、その「通販生活」が今年の夏号で、「自民党支持の読者の皆さん、今回ばかりは野党に一票、考えていただけませんか」という呼びかけで参院選特集を掲載した。
もちろん、詳細なその理由も含めての記事なのだが、それに対して一部の読者から、政治色が強すぎる、買い物雑誌にふさわしくないなどの批判がよせられた。「左翼雑誌か」という意見もあったらしい。
それに対して、冬号で批判への回答を掲載した。
「買い物雑誌に政治を持ちこむな」という意見に対しては、暮らしのすべてが政治の影響を受けているとし、したがって、平和だからこそ買い物ができることを説く。
「お金もうけだけ考えて、政治の話には口をつぐむ企業にはなりたくないと考えます」と結んだ。
「左翼雑誌か」という意見に対しては、「通販生活」のスタンスは、戦争と原発、沖縄差別は「まっぴら御免」だとした上で、「こんな『まっぴら』を左翼だとおっしゃるのなら、左翼でけっこうです」と答える。
「良質の商品を買いたいだけなのに、政治信条の違いで買えなくなるのが残念、と今後の購読を中止された方には、心からおわびいたします。永年のお買い物、本当にありがとうございました」と締め括った。
じつに潔いではないか。
この件は、東京新聞の11月10日付けで紹介された他、テレビのニュースにもなった。
そいう自分は、過去に「通販生活」は購読していたのだが、購読料を払い忘れていたら送られて来なくなってしまった。定期購読の読み物が山ほどあって、とても手が回らないのでそのままになってしまっている。さて、継続を申し込むべきかどうか、少しだけ迷っている。
先日、「アジア記者クラブ」のボランティアをしている女性が、「集団的自衛権反対」などのステッカーを貼ったバッグを持って、お孫さんを保育園に迎えにいったところ、母親の一人からステッカーを見とがめられ、「あなた、アカですか?」と言われたそうな。
今時そんなこという人いるんだってビックリしたと言う。どうも日本人はレッテルを張って批判したり評価したりする傾向にある。人間にはさまざまな側面があることを認めようとしない。
どんなによいことでも、それが自分と信条的に合わない人間が関わっていれば賛成できない、ということだ。どんなに良い品物でも、買わないということだ。実にくだらない。