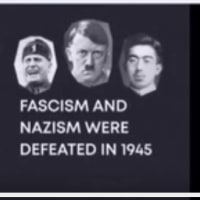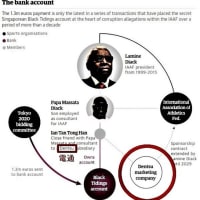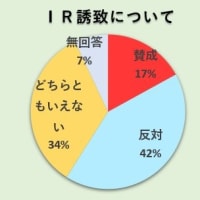国営諫早湾干拓事業ほど始めたら止まらない公共事業の悪しき典型はないでしょう。約50年以上も前の1952年に長崎大干拓構想として打ち出された諫早湾干拓事業は1997年4月の潮受け堤防の排水門締め切りによって、国内最大級で恵み豊かな諫早湾の干潟を干上がらせ、緩慢な死をもたらすという大罪を犯しました。潮受け堤防の着工前は福岡、佐賀、長崎、熊本の沿岸四県で、九万トン近くもあった年平均漁獲量が三割以下に激減。多くの専門家が「豊かな漁場をはぐくんでいた潮流などの異常な変化は、堤防などの事業工事が原因」と指摘しても、農水省は干拓農地面積を半減するなど目的変更までして事業にしがみついてきました。
諫早湾干拓事業は有明海の漁場環境を悪化させたとの多くの指摘がありながら、漁業被害と干拓事業との因果関係の科学的な立証は必ずしも容易ではありませんでした。このたび、長崎大学の西ノ首英之名誉教授と九州大学大学院の小松利光教授の研究グループによる長期にわたる観測結果によって、長崎県島原市沖の有明海の潮流の流速が、干拓事業による諫早湾閉め切り前後で約22%も減少していることがわかりました。農水省の干拓事業が漁業環境悪化に影響していることを示す貴重なデータといってよいでしょう。
西ノ首名誉教授は雲仙普賢岳の火山活動による漁業への影響を調べる一環として、92年―94年にかけて有明海を中心に二十六地点でそれぞれ一カ月間、流速の連続観測をしていました。九大の研究グループはこのデータと比較するために観測地点、時期、観測器具とも同じ条件で04年4月―5月の31日間、観測しました。その結果、観測地点ごとに20%強の流速減少が確認できたのです。
潮流の流速が減ることは、海洋環境の根幹にかかわるだけに、研究者も漁業者も重大な関心をもっています。
東幹夫・長崎大学名誉教授らは諫早湾を閉め切った1997年と2002年を比較し、閉め切り後の5年間に海底の砂地が泥化しているのは、流速の減少が原因と指摘していました。潮流の減少は、海洋をかき混ぜ酸素を供給する力を弱めます。実際に有明海では、諫早湾の閉め切り以降、貧酸素水塊(酸欠水域)が拡大したり、赤潮が頻発し、大規模化していることが観測されています。
国は、干拓事業と有明海異変との関連性について、検証を妨げてきました。2000年暮れから翌年春まで有明海全体に赤潮が発生し、ノリ養殖に壊滅的な被害が出たのを契機に、世論におされ、農水省はノリ不作等検討委員会(第三者委員会)を設置しました。同委員会は、2001年末、事業の検証に役立つとして、潮受け堤防の水門を開け、調整池内に海水を入れて、半年から数年にわたる中・長期の調査をするよう提言しました。しかし、農林水産省は、これを拒否し、工事完成を急いできました。
1986年の着工当初、1350億円だった国営諫早湾干拓事業の総事業費はすでに2533億円になっています。昨年12月20日に内示された2006年度予算の財務省原案では、さらに事業費50億円が追加計上されました。国はなにがなんでも来年度にほぼ完成にもちこむつもりです。
“農地拡大のための干拓”という当初の目的は、はるか昔に現実性も合理性もなくなっています。あとからわりこませた“防災目的のため”は先に干拓ありきで、防災計画について真剣に検討したものではありません。
諫早湾干拓事業は、土建国家日本の政官業の癒着が生み出した、事業の必要性・合理性を見いだせないまま、環境の破壊だけを残すという、無駄な大型公共事業の典型です。
国は、せめて中・長期の開門調査をはじめ、有明海再生にむけた取り組みを今からでも始めるべきです。
諫早湾干拓事業は有明海の漁場環境を悪化させたとの多くの指摘がありながら、漁業被害と干拓事業との因果関係の科学的な立証は必ずしも容易ではありませんでした。このたび、長崎大学の西ノ首英之名誉教授と九州大学大学院の小松利光教授の研究グループによる長期にわたる観測結果によって、長崎県島原市沖の有明海の潮流の流速が、干拓事業による諫早湾閉め切り前後で約22%も減少していることがわかりました。農水省の干拓事業が漁業環境悪化に影響していることを示す貴重なデータといってよいでしょう。
西ノ首名誉教授は雲仙普賢岳の火山活動による漁業への影響を調べる一環として、92年―94年にかけて有明海を中心に二十六地点でそれぞれ一カ月間、流速の連続観測をしていました。九大の研究グループはこのデータと比較するために観測地点、時期、観測器具とも同じ条件で04年4月―5月の31日間、観測しました。その結果、観測地点ごとに20%強の流速減少が確認できたのです。
潮流の流速が減ることは、海洋環境の根幹にかかわるだけに、研究者も漁業者も重大な関心をもっています。
東幹夫・長崎大学名誉教授らは諫早湾を閉め切った1997年と2002年を比較し、閉め切り後の5年間に海底の砂地が泥化しているのは、流速の減少が原因と指摘していました。潮流の減少は、海洋をかき混ぜ酸素を供給する力を弱めます。実際に有明海では、諫早湾の閉め切り以降、貧酸素水塊(酸欠水域)が拡大したり、赤潮が頻発し、大規模化していることが観測されています。
国は、干拓事業と有明海異変との関連性について、検証を妨げてきました。2000年暮れから翌年春まで有明海全体に赤潮が発生し、ノリ養殖に壊滅的な被害が出たのを契機に、世論におされ、農水省はノリ不作等検討委員会(第三者委員会)を設置しました。同委員会は、2001年末、事業の検証に役立つとして、潮受け堤防の水門を開け、調整池内に海水を入れて、半年から数年にわたる中・長期の調査をするよう提言しました。しかし、農林水産省は、これを拒否し、工事完成を急いできました。
1986年の着工当初、1350億円だった国営諫早湾干拓事業の総事業費はすでに2533億円になっています。昨年12月20日に内示された2006年度予算の財務省原案では、さらに事業費50億円が追加計上されました。国はなにがなんでも来年度にほぼ完成にもちこむつもりです。
“農地拡大のための干拓”という当初の目的は、はるか昔に現実性も合理性もなくなっています。あとからわりこませた“防災目的のため”は先に干拓ありきで、防災計画について真剣に検討したものではありません。
諫早湾干拓事業は、土建国家日本の政官業の癒着が生み出した、事業の必要性・合理性を見いだせないまま、環境の破壊だけを残すという、無駄な大型公共事業の典型です。
国は、せめて中・長期の開門調査をはじめ、有明海再生にむけた取り組みを今からでも始めるべきです。