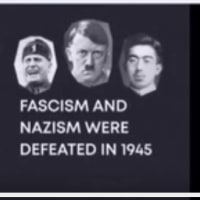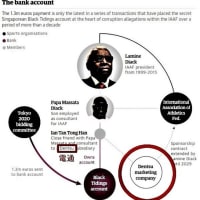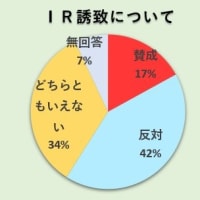民主、自民、公明の3党が政府案を「修正」する形で合意した復興基本法案が10日午後の衆院本会議で可決、衆院を通過した。二大政党が談合したのだから、参院で13日に審議入りし、17日にも成立する見通しである。3党による「修正」談合は、菅首相不信任案をめぐり政争を繰り広げていた1日に密かに行われた。これらの事実は、菅の後釜に誰が座るかにかかわりなく、民主・自民・公明の財界に従属した政策が継続されようとしていることを示している。東日本大震災の復旧復興問題をこれまでの財界主権政治で解決しようとすれば、早晩、被災者の思いとの間で矛盾を深めざるを得ない。被災者が主役である復旧復興を実現する道は、国民主権の新しい日本を切り拓く道でもある。
菅首相は、現代日本の典型的な伴食宰相(ばんしょくさいしょう)として、実に強運の持ち主である。「伴食」とは、主客のお供をしてご馳走になること。転じて、無能なのに要職にあって、実力の伴わない者をあざけっていう言葉である。伴食宰相は、そこで、他の引立て役の力を借りて権力の馳走に伴食できる機会、すなわち他力本願型で権力の地位にありつくことをめざす。これにならって菅政権は、その発足当初から、「小沢切り」の効果によって、すなわち「小沢効果」の他力によって存続してきたのである。一度目は鳩山首相からバトンを受けた10年6月、二度目は民主党代表選で小沢に勝利した10年9月、菅首相の人気があがったのは、この二度にわたる「小沢なき菅政権」「小沢切り菅政権」の誕生時だけであった(二宮厚美・神戸大教授「大連立ジレンマのなかの菅政権の迷走」『前衛』2011.7/No.872)。
そして3・11、菅・伴食宰相は九死に一生を得た。大地震が起こった金曜日、菅首相は国会で外国人政治献金問題の追及を受け、週明けには、辞任ないし不信任はほぼ間違いなし、という窮地に陥っていた。そこに3・11の「神風」が吹いたのである。直ちに政治休戦、ここ当分は解散総選挙なし、菅政権の存続が決まった。
3・11の天佑神助を活かすべく、菅首相はその延命をかけて、二つの行動に走った。一つは、菅首相自身、国民・世論の支持率の回復をめざして、パフォーマンスを演じることである。大地震の国難に立ち向かうトップリーダーとして、できるだけメディア等で目立つ行動に出た。しかし、所詮は伴食宰相。パフォーマンスを繰り返すほど、トップリーダーとしての無能を晒すことになった。
もう一つは、彼の切り札、他力本願カード、敵陣を味方に引き込む「救国大連立」カードである。3月19日、自民党谷垣総裁へ入閣要請をしたが、これは自民党に助力を乞うようなもので、ただちに自民党から足下を見られる結果となった。大連立を待望した財界、メディアの企図に反して、さすがの自民党も死にかけた菅政権に乗るわけにはいかなかったのである。
鳩山前首相が退陣表明してから1年、自民、公明両党などから提出された菅内閣不信任案は、6月2日の衆院本会議で反対多数で否決された。自民・公明などの言い分は、「菅内閣では東日本大震災に対応できない」「菅内閣では国難を打開できない」というだけで、論争の焦点は政策の違いなどでも何でもなく、もっぱら菅内閣の“政治手法”をあげつらうものだった。菅直人という「個人」の言動をめぐって、それが「気に食わない」「気に入らない」とかいった低レベルの話である。この点で象徴的だったのは、自民党の谷垣総裁、大島副総裁の発言だろう。大島氏は、「菅さんが首相を降りれば直ぐにでも超党派で新しい政治集団を作ることができる」といい、谷垣氏は、事前の野党党首会談で共産党の志位委員長に不信任決議後の政権構想を聞かれたとき、「確たる展望はない」と答えた。
菅首相の「小沢切り」によって、民主・自民2大政党間にはもはや政策の垣根はない。小沢・鳩山マニフェストにあった「対等な日米同盟」「国民生活第一」から日米同盟深化、消費税増税、TPP参加等の新自由主義的「構造改革」路線に回帰した菅首相にとって、「震災復興」の他力を借りて「菅延命」に走るのは、菅流のお家芸からして当然の帰結であった。しかし、その大連立に走る路線そのものが、国民生活との矛盾を深め、「政権交代」をもたらしたのではなかったのか。
日本は戦後一貫して対米従属と財界主権国家であった。財界の主流が重厚長大産業であった高度成長の時代には、国民経済循環が比較的順調のように見えたが、90年代以降、多国籍大企業が財界の主流になるにつれ、日本財界の恐るべき利益至上主義と非社会的体質、それを後押しすることしかできない民主・自民・公明などの政権政党のもとで、国民経済循環は破壊され、圧倒的多数の国民が生活不安、貧困に陥った。
民主・自民・公明3党が「修正」談合した復興基本法案は、復興の基本理念として「21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指す」ことや「国境を越えた社会経済活動の進展への対応等」を掲げて、被災者の生活基盤の回復より、「新成長戦略」と称して進めてきた財界・大企業主導の政策の優先を謳う。そして法案は、復興構想会議を法的に根拠付ける。復興構想会議は、財界の意向を忠実に反映して、自由貿易体制など政府がめざす「新成長戦略」を押し付け、復興財源について消費税を念頭に、復興を口実にした大増税の道をめざす。復興の進め方では、上からの計画を押し付ける。復興計画は住民合意でつくり、実施は国と自治体が連携し、国は財政に責任を持つことが基本なのに、3党案では国が復興の「基本的な方針」を定め、地方自治体はこれを踏まえ「措置を講ずる責務を有する」という逆立ちしたものとなっている。
東日本大震災における被災者の最大の不幸は、多くの国民が与野党さえ一致すれば被災者対策が前進すると誤解していることだ。しかしことの真相は、民主・自民両党の政策が財界主権で一致しているからこそ被災者対策が前進しないのである。この未曽有の国難に対して企業利益の一部も吐き出そうとしないような財界やそれに従属する民・自・公の財界主権政治は、早晩、被災者や国民の思いとの間で矛盾を深めざるを得ないだろう。被災者が主役である復旧復興を実現する道は、国民主権の新しい日本を切り拓く道でもあるのだ。