って、いっつも思う。
血管拡張という病態は、非常に高頻度に発生する。侵襲であったり、薬剤であったり。逆に、ICU患者で血管拡張の要素が無い人を探す方が難しいんじゃなかろうか。術後とか鎮痛・鎮静とか敗血症とか、これらの要素がない患者さんはそうはいないだろう。血管拡張は動脈だけじゃなくて容量血管にも発生する。そうすると前負荷が減少しうるので、見た感じは”ハイポ”になる。でもそれは見た目だけ。
最近、文献の世界では補液はしない方がいい、マイナスバランスの方が予後がいい、という話で溢れている。介入研究は少ないけれどね。でも、補液をした方がいい、という研究はほとんど見ない。正しいかどうかは分からないけど、少なくとも今の世界のトレンドはそっち。
補液をして血圧が上がると、”やっぱりハイポだったんだね”と言う人がいる。たくさんいる。違うでしょ。単にスターリングカーブの斜めのところにいただけでしょ。循環血液量が不足しているかどうかと、補液して血圧が上がるかどうかは、イコールじゃない。水は足りていても、血圧は上がりうる。
そもそも血圧の上昇は補液という介入に対するサロゲートマーカーでしかない。仮に患者さんが”ハイポ”で、補液で血圧が上がっても、もしかしたら患者さんの予後は悪くなっているかもしれない。
当然のことながら、補液は薬剤。たくさんの副作用がある。肺水腫、高クロール性アシドーシス、凝固成分の希釈などなど。なので、メリットとデメリットを天秤にかけないといけないのに、この”ハイポ”という安直な言葉のせいで、天秤に対する考慮なしに補液が行われることが少なくない気がしてしまう。
もちろん、補液をした方がいい患者さん、予後を改善できる患者さんはいるでしょう。ただ、その数は多くの人が思っているよりもすごく少ない可能性がある。
って、いっつも思う。
血管拡張という病態は、非常に高頻度に発生する。侵襲であったり、薬剤であったり。逆に、ICU患者で血管拡張の要素が無い人を探す方が難しいんじゃなかろうか。術後とか鎮痛・鎮静とか敗血症とか、これらの要素がない患者さんはそうはいないだろう。血管拡張は動脈だけじゃなくて容量血管にも発生する。そうすると前負荷が減少しうるので、見た感じは”ハイポ”になる。でもそれは見た目だけ。
最近、文献の世界では補液はしない方がいい、マイナスバランスの方が予後がいい、という話で溢れている。介入研究は少ないけれどね。でも、補液をした方がいい、という研究はほとんど見ない。正しいかどうかは分からないけど、少なくとも今の世界のトレンドはそっち。
補液をして血圧が上がると、”やっぱりハイポだったんだね”と言う人がいる。たくさんいる。違うでしょ。単にスターリングカーブの斜めのところにいただけでしょ。循環血液量が不足しているかどうかと、補液して血圧が上がるかどうかは、イコールじゃない。水は足りていても、血圧は上がりうる。
そもそも血圧の上昇は補液という介入に対するサロゲートマーカーでしかない。仮に患者さんが”ハイポ”で、補液で血圧が上がっても、もしかしたら患者さんの予後は悪くなっているかもしれない。
当然のことながら、補液は薬剤。たくさんの副作用がある。肺水腫、高クロール性アシドーシス、凝固成分の希釈などなど。なので、メリットとデメリットを天秤にかけないといけないのに、この”ハイポ”という安直な言葉のせいで、天秤に対する考慮なしに補液が行われることが少なくない気がしてしまう。
もちろん、補液をした方がいい患者さん、予後を改善できる患者さんはいるでしょう。ただ、その数は多くの人が思っているよりもすごく少ない可能性がある。
って、いっつも思う。











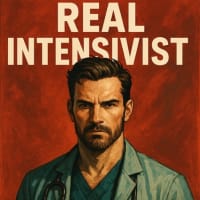














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます