The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
“ISOを活かす―71. 作業環境には、品質に影響するものと顧客満足に影響するものがある?”
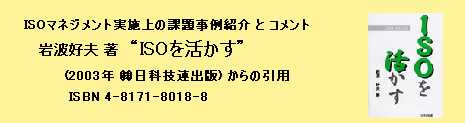
今回は、作業環境の確保がテーマです。
【組織の問題点】
電子部品メーカーのA社の手作業で精密部品を組み立てる工程には、十分な照度が必要です。そこで、その作業場には沢山の蛍光灯がつけられています。
たまたま定期審査の時、この作業場では 蛍光灯の一つが古くなって点滅していました。ところが、この蛍光灯は“作業が終わり手が空いたら交換する”との現場の話でした。
ISO9001マネジメントでは、このような管理水準が適切と言えるのか、という課題です。
【磯野及泉のコメント】
著者・岩波氏も 指摘しているようにISO9001では6.4項に“作業環境”の規定があります。

この事例の“精密部品の組立て工程”には“十分な照度が必要”とのことですが、そうならば その照度はどれくらいでなければならないのか、測定し、基準を決めて管理する必要がある訳です。(基準は当然 狙い値と上限値、下限値で決められるべきです。上限値、下限値を外れれば 直ちに是正するのが“管理”です。)
そして、この事例での“点滅”は 一般的には作業に悪影響を及ぼすと思われますが、現実にそうであるならば、直ちに交換するべきでしょう。
このISO9001:6.4項では、“製品要求事項への適合を達成するために” 作業環境の条件を整備するべきである、としていますので、作業者が気持ちよく仕事ができるようにすることが 品質確保に重要であると考えるならば、労働安全衛生上の問題とは考えずに 徹底的に 環境条件を整備するべきです。
労働安全衛生の基準は 作業する上での最低限の基準ですので、それが 必ずしも“十分に快適な環境水準”ではないことを肝に銘じておくべきだと思います。つまり、労働安全衛生の基準は、実際の 自分達の現場では有効でなく、不十分な場合があります。そのまま現地を見ずに適用すると 返って安全上の問題も出るようなことがあります。よく実態を把握した上で 適用するべき基準です。
ここでも 管理者が作業者の身になって、或いは 作業者自身が 主体的にどうあるべきかを 熟慮して自分達の管理基準を決定し、実施するべき問題です。安全を確保するために“自分達はこうする”という気構えが必要なのです。
この問題は 要するに 主体的に決めて、実施すれば 良く、決して複雑な問題ではありません。“主体的に決めて実施する”ことは ISO9001マネジメント全てに言える 基本姿勢です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « コラム記事“「... | 日本の裁判へ... » |
| コメント(10/1 コメント投稿終了予定) |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |




