The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
4月に見た映画の感想
♪流されて、流されて~流れ流れて何処どこ行くの?日本の政治家は最早、頭脳のないクラゲ?当てもなく流されて行く!もう国家漂流だ!
政治家は、政治的指導者のはず!指導者とは行き詰まった現状から人々を解放する人でなければならない。
そのためには、それは先読みができる人でなければならない。“先手、センテ”とはアホアホ政権の単なる掛け声ではない!
だが、全く残念なことに日本の政治家は先読みが全くできずに、現実に引きずり回されている。だから、♪流されて~・・・となる。流されたまま、それを止める決断すらできない。
そもそも、オリパラ開催期日と新型コロナ・ウィルス・ワクチンの接種スケジュールに矛盾があるのに、未だ気付いていないのだろうか。
これはワクチン接種担当御大臣様に、決してしてはならない質問だったのだろうか。ワクチン接種担当御大臣様に様々なメディアがインタビューを実施してきたが、こういった質問をした事例を私は知らない。まるで、口裏を合わせたような質問ばかりだった。結果として、政府に好都合な情報ばかりが流されたのではないか。
この戦略性のないスケジューリングの矛盾は遅くとも今年の2月頃に明確化していて、その時点で解消するべきものだった。しかも今や、オリパラのための保健衛生管理の医療態勢整備すらおぼつかない、どう考えてもムリッ!
“センテ、センテ”がアホアホ政権の掛け声にしか聞こえないためか、最近はそんな台詞すらなくなった。最早アホアホの極みなのだ!
結果として、アホアホ政権が最も恐れるオリパラは中止となる“さだめ”か?何よりアキレス腱として浮き上がったのが、オリパラに必要な医療従事者の確保ではないか。それが絶望的に不可能なのだ。イヨイヨ中止の決断が迫られる!?
それとも、完全無観客ならば、オリパラ医療態勢も何とかできるのか?新型コロナ・ウィルス対策には医師1人でも惜しい、遅れているワクチン接種にも医師は必要だから、ヤッパリダメか?
その上、オリパラ開催維持には参加選手にPCR検査を毎日実施する予定だという。そういう姿勢に矛盾を感じないか?一般人には十分なPCR検査をしていないにもかかわらず、参加選手には十分に実施するというのだ。それでいいのか?
機会不平等、それは五輪憲章に抵触しないのか?
だが、完全無観客開催ならば日本側は無収入となり、その赤字補填は巨額の国家財政負担となるのは必定!今更の中止でもそれは同じか?そうなれば、今後の公共サービスの低下も一層酷くなるであろう。年金も期待できなくなる。それは一層なけなしの貯蓄への傾斜となり、消費は落ち込む。消費が落ち込めば景気は良くならない!
そうなれば公共サービスの一般的低下どころか、今回の新型コロナ・ウィルス禍で破綻が明らかになった日本の感染症医療体制再構築すらおぼつかなくなるではないか。ところが感染症の世界的流行はこれから、もっと頻繁になると予想されている。すると感染症流行のたびに日本の景気だけは落ち込む。歴史的に巨大な負の連鎖に日本が落ち込む、そのとば口に居るのではないか。
その原因を作ったのは、今の与党アホアホ政治家達だ。アホアホ政治家には政治的理想や哲学、思想も何もあったものではない。だから原則がない。原則がないから危機に際して何をしたら良いのか、何を為すべきかが分からない。そして思考停止となり、目の前の権力闘争のみ、目先の利権争いのみとなる。
日本の政治家がクレバーならば、昨年のオリパラ延期時に既に、“ワクチンを日本に寄こせ!さもなければオリパラ開催不能ダゾ!”と世界に向けて啖呵を切るべきだった。そうすればさすがのIOCも驚いて必死になって他の国際機関に働きかける。米NBCも動き出してファイザーに圧力をかけたのではないか。だが、今となっては時すでに遅し。ボーっとしたノーテンキ・アホアホでは無理な話だったか?
こんなレベルの連中が日本の政治家なのだ。我々選挙民はそんな政治家を一生懸命選択してきた。よりましな選択肢は無かったか?情けない限りなのだ!
今や国家的漂流となり、♪流されて~・・・となる。結局、一般国民は今現在、医療体制の崩壊を見、近い将来、経済的地獄を見ることになる。
それにもかかわらず、金融市場は全般に結構暢気だ。米国と日本では、雲泥の差が客観情勢なのに、だ。日本の市場には巨大なブラックホールが身近に迫っているような気がするが、杞憂だろうか。
これもそれも、日本で新型コロナ・ウィルスのワクチンが作れなかったこともその一因になっている。
もし、日本が現段階でワクチン或いは特効薬開発に成功していれば、世界に大いに貢献出来、世界の多くの開発途上国からも尊敬を集めることができていたはずではないか。地道な基礎科学の開発が国家戦略上いかに重要なことか。それにもかかわらず、目先の利害で動くから、肝心な時に実力を発揮できないのだ。
中国製ワクチンは効果がないことは、中南米での実績が示している。もしやその中身は食塩水でプラセボ効果に期待するのみのものではないか。中国ならばやりかねないことだ。トコトン信じられない。それにもかかわらず、彼らは恩着せがましいのだ。
日本の開発ならばまだ信用はあっただろう。だが、日の丸ワクチンは無い!これが政府の言う“科学技術立国”の実態である。政治的原則無く、国家的戦略すら持てない国が国連の常任理事国に成れるはずがない。一時、外務省はそれを期待したというが、高望みもエエトコなのは明らかではないか。最早、日本は先進国から脱落し中進国へ、巨大な負の連鎖の中で途上国へと転落して行くのだろう。
一方、中国の科学技術、それには見せかけの部分が多々あるので、それには十分気を付けなければならない。
例えば、中国の大型ロケットの残骸がコントロール不能となり、何時何処に落下するか分からないという。それは中国が4月下旬に独自の宇宙ステーションの建設に向けて打ち上げた大型ロケット「長征5号B」の基幹部分22トンだという。本来、そのようになることを懸念して、宇宙ゴミになる可能性のものは大型にしないのが原則だという。そんな設計上の配慮はしないのが、あの国の特長だ。
もし、落下地点にいたとして、それが原因で死んだとしてもあの国のことしらばっくれて、責任を取らないのは火を見るよりはあきらか。何の補償も期待できまい。非常に迷惑で困った話だ。
結局、ロケット残骸は日本時間9日午前11時24分に大気圏に再突入。東経72.47度、北緯2.65度の地点に落下した。これはモルディブ諸島西方の海上に当たるとの発表があったという。
話は変わるが、このところテレビのワイドショウも、コロナ話ばかりでつまらないので、中国脅威論を話題にする。そこで、台湾有事を話題にして、他人事のように言っている。だが戦略・戦術論から言えば、それよりも先に沖縄が攻撃されるのは明らかだろう。
昨年中に既に“中国北西部のゴビ砂漠にある地上絵が嘉手納基地を再現している、との報道”がなされている。嘉手納基地の燃料タンク相当付近にミサイル着弾のクレータらしき跡があり、それは精度が高いものという。既に、実戦演習を行っていた証拠と考えられる。
それから見ても、他人事ではなく台湾有事の前に沖縄有事なのだ!決して暢気にしていられるものではない。
このように、台湾を攻撃し占領する布石として、米国軍の策源地としての沖縄の米軍基地を攻撃し、その機能を封殺することが作戦上の大前提となるのは常識なのだ。
だが、それも実は見せかけ!?中国は空母を持って、台湾攻撃の主力としたかのように見せかけているだけなのだ。その艦載戦闘機のエンジンが出力不足で、大型ミサイルを搭載して発艦できないと言われている。最近見た、中国の演習の映像でも小型のミサイルは搭載してはいたが、大型のものではなかった。どうやら小型の空対空ミサイルの武装だけなので、その戦力価値は大きく減殺される。つまり防空機能だけで攻撃力は無く、空母打撃群としての存在意義はない。
しかも、中国海軍の潜水艦への対処能力は未だに低いと思われ、南シナ海での海自の演習でも、海自の海上艦艇を追いかけまわしただが、それに随伴した潜水艦の存在は知らなかった、ようなのだ。これでは、中国海軍の海上艦隊群は海自の潜水艦一隻でも相当な打撃を加えられるはずなので、“見せかけ”、と言っても過言ではあるまい。その上に米海軍が加勢するとなると数では劣勢でも、質においてはるかに優勢となろう。
従って私の結論では、目下では中国には台湾有事を引起す海軍力はないものと見てよいのではないか。それにしても、ロケットの落下にはかなわない。
さて、今回投稿はGWによって一週間ぶりとなるが、家で自粛していてそれほど面白いことはなかった。当たり前か!?審査の仕事は、本来、時期的に少ないのだが、緊急事態下、顧客要望で延期にもなっている事例もある。
ネタが乏しいので、先月同様4月に見た映画の紹介としたい。このところ、NHK・BSプレミアムで見たBSシネマばかりではなく、地上波TVで放映された映画の録画もしていて、それが貯まってきているので、それも見始めている。最近はそれに加えてさらに、youtubeで無料の映画も見ている。これはむしろメジャーなものではなく、B級映画中心だが面白そうなものは見るようになった。それら、全てを今回は紹介したい。場合によってはネタバレもあるがお許しの程を・・・。
先月同様に鑑賞できた映画は、NHK・BSプレミアムのBSシネマで見たのが大半で、その内の洋画は次の通り。
①ネバダ・スミスNevada Smith 1966年・米、監督:ヘンリー・ハサウェイ、出演:スティーブ・マックイーン,カール・マルデン,ブライアン・キース,アーサー・ケネディ
②キリング・フィールドThe Killing Fields 1984年・英、監督:ローランド・ジョフィ、出演:サム・ウォーターストン,ハイン・S・ニョール
③ミネソタ大強盗団The Great Northfield Minnesota Raid 1972年・米、監督:フィリップ・カウフマン、出演:クリフ・ロバートソン、ロバート・デュヴァル
④ウェスト・サイド物語West Side Story 1961年・米、監督:ロバート・ワイズとジェローム・ロビンズ、出演:ナタリー・ウッド、リチャード・ベイマー、ジョージ・チャキリス
⑤追想Anastasia 1956年・米、監督:アナトール・リトヴァク、出演:ユル・ブリンナー、イングリッド・バーグマン、ヘレン・ヘイズ
⑥ムトゥ 踊るマハラジャ Muthu1995/2018・印、監督:K・S・ラヴィクマール、出演:ラジニカーント、ミーナ
⑦クォ・ヴァディスQuo Vadis 1951年・米、監督:マーヴィン・ルロイ、出演:ロバート・テイラー、デボラ・カー、ピーター・ユスティノフ
⑧グラディエーターGladiator 2000年・米、監督:リドリー・スコット、出演:ラッセル・クロウ、ホアキン・フェニックス、コニー・ニールセン、オリヴァー・リード、デレク・ジャコビ、ジャイモン・フンスー、リチャード・ハリス
⑨荒野の七人The Magnificent Seven 1960年・米、監督:ジョン・スタージェス、出演:ユル・ブリンナー、イーライ・ウォラック、スティーブ・マックイーン、チャールズ・ブロンソン、ロバート・ヴォーン、ジェームズ・コバーン
①、③、⑨は米西部劇。
⑨は日本の黒澤明の“七人の侍”が原作の有名な作品。実は、原作映画をつぶさに見たことはないのだが、原作では7人の得意な武器に刀ばかりではなく槍や弓など夫々個性があって面白いのだが、西部劇では拳銃とライフル銃に限られてしまうので、その点で7人の個性を出し辛く、面白みに欠ける。出演者は米男優のオールスター・キャストの印象である。特に、ロバート・ボーンのニヤケ顔はかつてTVシリーズ“0011ナポレオン・ソロ”以来、久しぶりで懐かしかった。Sマックイーンは①では主役。
③は、不覚にも途中で眠り込んで、始めと終わりで何とか“見た”つもりになっている。あくまでも“つもり”であった。
②はカンボジア内戦の話だが、あたかもその際の“虐殺”がメイン・テーマであるかのような印象を受けていた。日本での公開の時もそのように誤解させるようなPRでなかったろうか。恐いもの見たさに思っていたのだが、これまで見る機会を逃し、レンタル・ビデオでも見ることはなかった。絶好の機会とばかりに見たのだが、実際にはそうではなく、そのような惨劇の直前に逃亡し、その逃避行に成功した人の体験談である。
しかし何故、あのように残虐な行為が行われたかの原因についての追及や分析はこの映画の中では行われていない。私はその点に気になるのだが。
④はミュージカル映画として非常に有名だったが、私はミュージカルそのものにあまり興味ないので、これまで見ることはなかったが、この際、有名な映画として見た。作曲は佐渡裕氏の師匠レナード・バーンスタインである。
高校の最終学年の体育祭で、ピーターパンの仮装行列をやったが、その時に、誰がプロデュースしたのか今もって知らないのだが、このミュージカルのメインテーマのメロディを巧みに取り込んでいた。私はたまたまインディアンの娘・タイガー・リリー役を仰せつかってドンゴロスでできた衣装を着ていたのだった。そんな思い出と共に、懐かしく見てみようと思ったのだ。
だが、残念ながらストーリーそのものは大したものとは思えなかった。ニューヨーク下町の少々ぐれた高校生グループの闘争話、それだけのことのように思うのだが・・・。
⑤は、和訳の表題が見当違いの印象。現代の“アナスタシア”の方がはるかに分かり易い。
アナスタシアはロシアのロマノフ王朝の皇女。ロシア革命後、王朝の皇帝ら皇族はことごとく処刑されたはずだったが、皇女は行方不明となっていて、旧貴族たちはその行方を捜していた。それは皇帝のイングランド銀行に預金した1000万ポンド利子も含めて3600万ドルのロマノフ家の遺産目当てだった。ユル・ブリンナー演じるロシア帝国の元将軍ボーニンは街で見つけた記憶喪失の女性・イングリット・バーグマン演じるアンナ・ニコルをその王女に仕立てて遺産を手に入れようする話だ。バーグマンが気品と知性を体現していて、その魅力を発揮した映画だ。
ボーニンはデンマークに亡命した皇太后にアナスタシアを逢わせて、どうやら皇太后からは本当の皇女との心証を得て、アンナ自身も自分のアイデンティティに納得し、その後ボーニンとの恋に生きるため行方をくらましてしまう。全てを了解した皇太后は“芝居は終わった”と言って映画は終わる。
私はこれまで、あまりユル・ブリンナーという俳優を詳しくは知らなかった。しかし⑨のような西部劇の無頼漢役も⑤では貴族の将軍役も、或いは“王様と私”では王様役、“隊長ブーリバ”ではコサックの隊長、前回紹介した“ウェスト・ワールド”ではロボット役。極めて個性的な顔ながら、身のこなしが素晴らしく、これら全てを上手く演じている名優だとはじめて思い知った次第だ。
⑥はインドのミュージカル。インド映画は全てこのタイプのミュージカルのように聞いている。突然踊り出すのが面白いとか。
インド社会は古代からのカースト身分制が厳しいのが、社会発展のくびきになっていると聞いていたが、この映画ではその影響は見取れなかった。それよりも地主一家の話だったように思うので、古代からと言うよりも中世からの影響なのか?それにしても、未だに農本地主なのだろうか。
⑦は、イェスの亡くなった直後の直弟子ペトロによるキリスト教布教活動が背景にある話。ペトロは和訳すれば“いわお巌”。固い信念・信仰の象徴なのだ、と英語の先生からならったのを思い出す。英語ではピーター。
表題も和訳すれば“いずこへ”となる。その方が分かり易いが、まっラテン語のお勉強か。これは最近亡くなった吉本有名コメディアンのギャグだったのを思い出す。ストーリーは暴君ネロにまつわるモノ。詳しくは忘れかけているのが実態で、ネットで今もう一度確認している。ペトロはネロによって磔刑となり、その墓地の跡がバチカンの中心サン・ピエトロ大聖堂となっている。これはクリスチャンの常識。ここでは余計話で誤魔化す。
⑧は⑦と同じようにローマ帝国モノ。今となっては、⑦と混乱している印象。
見るのはこれが2度目で史実に基づいていると誤解していたが、創作話のようだ。だから、映画関係者には史実とは誤解されては困るとの苦情もあったかのようだ。確かに、ローマ皇帝のありようが、確固たる世襲制であるかのようなのも、チョット違うのではないかと、見ながら思ってはいたので、自分の感覚が確かであったとの自信を持ってしまった。
次にNHK・BSプレミアム・BSシネマで見た邦画は次の通り。
⑩どら平太 2000年、監督:市川崑、出演:役所広司、浅野ゆう子、宇崎竜童、片岡鶴太郎、菅原文太
⑪病院坂の首縊りの家 1979年、監督:市川崑、出演:石坂浩二、佐久間良子、桜田淳子
⑫女王蜂 1978年、監督:市川崑、出演:石坂浩二、高峰三枝子、中井貴恵、沖雅也、加藤武、大滝秀治、岸惠子、仲代達矢
⑬丹下左膳・百万両の壺 2004年、監督:津田豊滋、出演:豊川悦司、和久井映見、野村宏伸、麻生久美子
⑭聖の青春 2016年、監督:森義隆、出演:松山ケンイチ、東出昌大、リリー・フランキー、竹下景子
⑩は山本周五郎の“町奉行日記”を元にしたというが、大して感動も何もなかった。今でも印象は薄い。
ある小藩の国元では、財政難を補うために“壕外”と呼ばれる無法者の町から莫大な上納金を集めていた。それが原因で藩内が腐敗していた。それを一見隙だらけで“どら平太”と世間から呼ばれている一人の侍が殿の指示でやって来たと書付を見せて詐称して、藩内改革する話だが、十分にあり得ない内容だ。当時の小藩の侍達に上納金を集めるそんな金銭的才覚があるとは思えないからだ。何故ならば、侍には金銭自体に“汚い”という感覚があったということだからだ。だから反税制の改革は困難を極めたのだ。だから賄賂もバレ易く、バレれば即座に切腹。殿の指示を詐称するのも切腹となる時代のはずだからだ。二重の切腹を覚悟でできるものではない。厳密な話をすれば面白くはないが、それが現実。現代的には痛快サラリーマン話となるのだろうが、現実にはないのと同じレベルのストーリー。
⑪と⑫は、横溝正史の複雑なストーリー。これも話としては面白く、現実的可能性は皆無とは言い難いのだが・・・どうにも非現実的ではないか。
⑬は昔の大河内伝次郎の映画のリバイバル版。トヨエツが主役の左膳をやった。“百万両の壺”はいわゆる“コケざるの壺”。見ていてストーリーが中々核心に入らなかったように感じて、途中で眠ってしまった。
それらに対し⑭は現代の実話だ。将棋の関西棋院の棋士・村山聖(さとし)を題材としている。だから大阪の福島界隈が映画の始まりの舞台になる。これを本人の往時を知る人は、主役の松山ケンイチが本人と見まがうほどの好演だったという。羽生善治役の東出昌大も好演だった。私は羽生御本人が出演しているのかと、始めは思ったほどだ。村山は将棋公式戦でその羽生を破ったことのある、数少ない棋士の一人だという。だが、村山は幼い時から腎臓病ネフローゼに悩まされ、結局はそれが原因で若くして亡くなる。
映画の中で、羽生との名人位挑戦後村山は羽生を誘って二人で飲む場面がある。健康ハンディキャップを抱えながら村山は、そこで羽生に二つの夢があると告白する。一つは名人位であり、もう一つは恋人だという。羽生はその時結婚していて、その夢の二つとも既に手にしている。その立場でどのような表情で村山と対峙したのか。この難しい場面を東出は上手く演じていたように思う。五分五分の天才の両者だが、運命は過酷に二人を分けているのだ。これが厳しい人生の現実なのだ。神はあるのか?
聖は持病にもかかわらず、東京に出て母親の目の届かないところで不摂生を繰り返す。やがて泌尿器周辺に癌が発生し、切除手術で恋人獲得の夢も絶望。残る人生最後の数カ月、聖は負けなしで芸術的な棋譜を残したという。羽生はそんな聖が大好きで、その最期に寄り添い看取ったという。
BSシネマは地上波ではなく事情があって録画できないのだが、地上波のTV放映されたものは録画していて、これまでそのままだったが、自粛に伴い見て整理しようとしたのが次の6点。
⑮マッチポイントMatch Point 2005年、英、監督:ウッディ・アレン、出演:ジョナサン・リース・マイヤース、スカーレット・ヨハンソン
⑯英雄の条件Rules of Engagement 2000年、米、監督:ウィリアム・フリードキン、出演:トミー・リー・ジョーンズ、サミュエル・L・ジャクソン
⑰ジャッカルThe Jackal 1997年、米、監督:マイケル・ケイトン=ジョーンズ、出演:ブルース・ウィリス、リチャード・ギア
⑱ラストベガスLast Vegas 2013年、米、監督:ジョン・タートルトーブ、出演:マイケル・ダグラス、ロバート・デ・ニーロ、モーガン・フリーマン、ケビン・クライン
⑲ヘアースプレーHairspray 2007年、米、英、監督:アダム・シャンクマン、出演:ニッキー・ブロンスキー、ジョン・トラヴォルタ、ミシェル・ファイファー、クリストファー・ウォーケン、クイーン・ラティファ
⑳後妻業の女 2016年、日、監督:鶴橋康夫、出演:大竹しのぶ、豊川悦司、尾野真千子、笑福亭鶴瓶、津川雅彦、永瀬正敏
⑮見終わってウッディ・アレン調をジワリと感じるここには人生の理不尽があった。それが良い。象徴的画像に始まってアナロジー画像で終わる。事実を淡々と映像で追っていく語り口で分かり易かった。
“マッチポイント”とは“後1点で試合が終了するときのポイント”のことだが、テニス・ゲームでそれが、打ったボールが手前に落ちれば負け、相手側に落ちて相手が打ち返せなければ勝ちの運命の分かれ目を示している。映画の冒頭では無邪気なテニスでのそのシーンが流される。ラストでは重要な証拠の指輪を真犯人の主人公が川に投げ込んだつもりだったが、それがたまたま堤防の手摺に当たって跳ね返り、それを麻薬売人が偶然にも拾って持っていたので、その売人が殺人犯と警察官は断定する。しかも売人は殺されていたので捜査は終了。悪運の強い主人公という理不尽なのだ。小説“罪と罰”が下敷きなのか?
⑯の原題の“Rules of Engagement”は米海兵隊の“交戦規定”の意の由。イエメンで米国大使館包囲デモ事件が発生する。米国政府の要請で大使館員救出に向かった海兵隊は、暴徒と化した民衆に銃撃し、一般市民百数十人の死傷者を出した。この民衆銃撃を命令した大佐は軍法会議にかけられる。そんな大佐が、かつて厳しいベトナム戦で命を救われた戦友で、その後事務職で過ごした地味な人物に弁護を要請し、引き受けてもらう。
結局は陪審員の被告に対する心証が良かったのだろうか、決定的証拠無しに無罪となっている。決定的証拠の録画記録のテープは大佐を起訴した検察官が自らの出世のために故意に焼却した。厳重に保管されるべき国家の記録がきちんと保管できていないこと、毀損されたことが問われずに結審させているのが不思議だ。そのテープの存在は記録されているにも拘わらず、適切に法廷に提出されていないのだ。これでは今日本で裁判中の財務省の記録の毀損・隠滅・書き換えと同じではないのか。米国でも権力側の故意が通用するのか?法廷闘争上、被告に有利と思われる有力な証拠を検察が隠滅したと強く推定されるならば、明らかに起訴不当として無罪とさせるべきでないか。このシナリオに大いに不自然を感じるのだ。
知らなかったが、この作品はイェメン人を差別的に表現しているとの評価が米国にはあるようだ。どこがそうなのか私には直ちには分からないが、ひょっとして民衆が扇動されやすい烏合の衆であるかのような仕上がりであることに問題があるのだろうか。ならば事件が事実であれば問題ではなかったことになるのだろうか。創作であればなぜ場面設定をイェメンと特定したのだろうか。まぁそういう批判が人種差別の国であるのは結構、健全なことではないか。
⑰は1973年の映画“ジャッカルの日”のリメイクだという。残念ながら、その本作も見たいと思っていたが見きれていない。それは時の仏大統領ド・ゴール暗殺計画だったと思う。ここではブルース・ウィリスが追われるスナイパー役。リチャード・ギアはFBIの立場で追いつめて行く。ストーリーは今風で結構複雑。
⑱は現代の米名優が勢揃いして、引退した様々な“老後”を演じている。まっ、身につまされるが、微笑ましく面白いの一言か。
⑲はあまり有名ではないが、ミュージカル映画で、“ウェスト・サイド物語”よりもはるかに出色の作品だと思う。ジョン・トラヴォルタ、ミシェル・ファイファーと名優が脇を固めているが、主役はニッキー・ブロンスキーという背の低い見栄えのしない女優だ。だが歌唱力は確かに映画の冒頭からズーっと歌い上げていて上手い。あらゆる差別:身体的、性的、人種的差別反対を全編で明るい音楽であくまでも明るく主張!兎に角ぶっ飛んでいる。だから、そういう女優を起用したのだろう。
びっくりしたのは、ジョン・トラボルタだ。何と主人公の娘の母親役なのだ。最初、この母親は男ではないかと疑った。異様に大柄で太い手足。声も心なしか太い。だが、動きや身のこなしは完璧に女性。米国にはこんなオバサンも居るのかと思っていた。だがやっぱり、どう見ても顔の輪郭は男。その特徴的目付きから、後半になってひょっとしてトラボルタでは?とようやく気付く始末。配役で出ているのに一向に登場しないこともあった。しかし、彼は本来、“サタデー・ナイト・フィーバー”で踊りまくって有名になった俳優のハズなので、あの太い手足は役作りだったのだろうか。やはりハリウッドの一流の演技力はすごい!容易に騙されてしまう!
⑳このグループでたまたま唯一の邦画になったが、大竹しのぶの好演と役柄で尾野真千子との対立が面白い。これはこんな詐欺師やその集団がいるのかなぁと思わせるのが良い。まぁある種、“難波金融伝”を想起させる部分があって面白い。
この映画の前にTVドラマ化されていたようで、そんなことでもあるのか、映画ではシナリオ上省略されている部分があると感じるのが残念なところだ。
youtube無料動画で見たのは次の2点。
㉑チャタレイ夫人の恋人The Lover(L'amante) 1991年・伊・監督:フランク・デ・ニーロ、出演:ランバ・マル、マック・キラン、アンソニー・ステファン、バーバラ・ブラスコ
㉒レッド・エージェント 愛の亡命Despite the Falling Snow 2016年・英、加、監督:シャミム・サリフ、出演:レベッカ・ファーガソン、チャールズ・ダンス、サム・リード、アンチュ・トラウェ
㉑は表題の和訳がいい加減で、有名な“チャタレイ夫人の恋人”とは全く異なるようだ。むしろその“チャタレイ夫人の恋人”の内容を知らないので見ようと思ったのだ。騙された印象がある。主演は有名な女優らしい。その裸身を見るための映画か?監督はロバート・デ・ニーロではない、要注意。だが、映像は制作国がイタリアのためか明るく美しい。
㉒は、主演女優レベッカ・ファーガソンの1人二役で、演技は上手かった。映画評でみられたが、ここで1人二役にする必然性はあまりない。気付かなかったが、彼女はトム・クルーズの“ミッションインポッシブル”シリーズにもスパイ役で出演していたという。内容も、ソヴィエット社会の40年代頃と60年代を背景としていて必見とまでは言わないが見応えがあった。無料なので自粛でヒマな時にはお得感十分だ。
結局のところ、数えてみると4月は22の映画作品を見たが、印象に残るのは“追想(アナスタシア)”、“聖の青春”、“ヘアースプレイ”といったところであろうか。
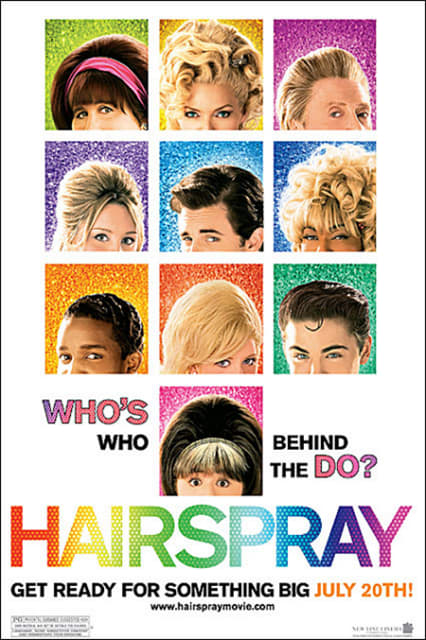
政治家は、政治的指導者のはず!指導者とは行き詰まった現状から人々を解放する人でなければならない。
そのためには、それは先読みができる人でなければならない。“先手、センテ”とはアホアホ政権の単なる掛け声ではない!
だが、全く残念なことに日本の政治家は先読みが全くできずに、現実に引きずり回されている。だから、♪流されて~・・・となる。流されたまま、それを止める決断すらできない。
そもそも、オリパラ開催期日と新型コロナ・ウィルス・ワクチンの接種スケジュールに矛盾があるのに、未だ気付いていないのだろうか。
これはワクチン接種担当御大臣様に、決してしてはならない質問だったのだろうか。ワクチン接種担当御大臣様に様々なメディアがインタビューを実施してきたが、こういった質問をした事例を私は知らない。まるで、口裏を合わせたような質問ばかりだった。結果として、政府に好都合な情報ばかりが流されたのではないか。
この戦略性のないスケジューリングの矛盾は遅くとも今年の2月頃に明確化していて、その時点で解消するべきものだった。しかも今や、オリパラのための保健衛生管理の医療態勢整備すらおぼつかない、どう考えてもムリッ!
“センテ、センテ”がアホアホ政権の掛け声にしか聞こえないためか、最近はそんな台詞すらなくなった。最早アホアホの極みなのだ!
結果として、アホアホ政権が最も恐れるオリパラは中止となる“さだめ”か?何よりアキレス腱として浮き上がったのが、オリパラに必要な医療従事者の確保ではないか。それが絶望的に不可能なのだ。イヨイヨ中止の決断が迫られる!?
それとも、完全無観客ならば、オリパラ医療態勢も何とかできるのか?新型コロナ・ウィルス対策には医師1人でも惜しい、遅れているワクチン接種にも医師は必要だから、ヤッパリダメか?
その上、オリパラ開催維持には参加選手にPCR検査を毎日実施する予定だという。そういう姿勢に矛盾を感じないか?一般人には十分なPCR検査をしていないにもかかわらず、参加選手には十分に実施するというのだ。それでいいのか?
機会不平等、それは五輪憲章に抵触しないのか?
だが、完全無観客開催ならば日本側は無収入となり、その赤字補填は巨額の国家財政負担となるのは必定!今更の中止でもそれは同じか?そうなれば、今後の公共サービスの低下も一層酷くなるであろう。年金も期待できなくなる。それは一層なけなしの貯蓄への傾斜となり、消費は落ち込む。消費が落ち込めば景気は良くならない!
そうなれば公共サービスの一般的低下どころか、今回の新型コロナ・ウィルス禍で破綻が明らかになった日本の感染症医療体制再構築すらおぼつかなくなるではないか。ところが感染症の世界的流行はこれから、もっと頻繁になると予想されている。すると感染症流行のたびに日本の景気だけは落ち込む。歴史的に巨大な負の連鎖に日本が落ち込む、そのとば口に居るのではないか。
その原因を作ったのは、今の与党アホアホ政治家達だ。アホアホ政治家には政治的理想や哲学、思想も何もあったものではない。だから原則がない。原則がないから危機に際して何をしたら良いのか、何を為すべきかが分からない。そして思考停止となり、目の前の権力闘争のみ、目先の利権争いのみとなる。
日本の政治家がクレバーならば、昨年のオリパラ延期時に既に、“ワクチンを日本に寄こせ!さもなければオリパラ開催不能ダゾ!”と世界に向けて啖呵を切るべきだった。そうすればさすがのIOCも驚いて必死になって他の国際機関に働きかける。米NBCも動き出してファイザーに圧力をかけたのではないか。だが、今となっては時すでに遅し。ボーっとしたノーテンキ・アホアホでは無理な話だったか?
こんなレベルの連中が日本の政治家なのだ。我々選挙民はそんな政治家を一生懸命選択してきた。よりましな選択肢は無かったか?情けない限りなのだ!
今や国家的漂流となり、♪流されて~・・・となる。結局、一般国民は今現在、医療体制の崩壊を見、近い将来、経済的地獄を見ることになる。
それにもかかわらず、金融市場は全般に結構暢気だ。米国と日本では、雲泥の差が客観情勢なのに、だ。日本の市場には巨大なブラックホールが身近に迫っているような気がするが、杞憂だろうか。
これもそれも、日本で新型コロナ・ウィルスのワクチンが作れなかったこともその一因になっている。
もし、日本が現段階でワクチン或いは特効薬開発に成功していれば、世界に大いに貢献出来、世界の多くの開発途上国からも尊敬を集めることができていたはずではないか。地道な基礎科学の開発が国家戦略上いかに重要なことか。それにもかかわらず、目先の利害で動くから、肝心な時に実力を発揮できないのだ。
中国製ワクチンは効果がないことは、中南米での実績が示している。もしやその中身は食塩水でプラセボ効果に期待するのみのものではないか。中国ならばやりかねないことだ。トコトン信じられない。それにもかかわらず、彼らは恩着せがましいのだ。
日本の開発ならばまだ信用はあっただろう。だが、日の丸ワクチンは無い!これが政府の言う“科学技術立国”の実態である。政治的原則無く、国家的戦略すら持てない国が国連の常任理事国に成れるはずがない。一時、外務省はそれを期待したというが、高望みもエエトコなのは明らかではないか。最早、日本は先進国から脱落し中進国へ、巨大な負の連鎖の中で途上国へと転落して行くのだろう。
一方、中国の科学技術、それには見せかけの部分が多々あるので、それには十分気を付けなければならない。
例えば、中国の大型ロケットの残骸がコントロール不能となり、何時何処に落下するか分からないという。それは中国が4月下旬に独自の宇宙ステーションの建設に向けて打ち上げた大型ロケット「長征5号B」の基幹部分22トンだという。本来、そのようになることを懸念して、宇宙ゴミになる可能性のものは大型にしないのが原則だという。そんな設計上の配慮はしないのが、あの国の特長だ。
もし、落下地点にいたとして、それが原因で死んだとしてもあの国のことしらばっくれて、責任を取らないのは火を見るよりはあきらか。何の補償も期待できまい。非常に迷惑で困った話だ。
結局、ロケット残骸は日本時間9日午前11時24分に大気圏に再突入。東経72.47度、北緯2.65度の地点に落下した。これはモルディブ諸島西方の海上に当たるとの発表があったという。
話は変わるが、このところテレビのワイドショウも、コロナ話ばかりでつまらないので、中国脅威論を話題にする。そこで、台湾有事を話題にして、他人事のように言っている。だが戦略・戦術論から言えば、それよりも先に沖縄が攻撃されるのは明らかだろう。
昨年中に既に“中国北西部のゴビ砂漠にある地上絵が嘉手納基地を再現している、との報道”がなされている。嘉手納基地の燃料タンク相当付近にミサイル着弾のクレータらしき跡があり、それは精度が高いものという。既に、実戦演習を行っていた証拠と考えられる。
それから見ても、他人事ではなく台湾有事の前に沖縄有事なのだ!決して暢気にしていられるものではない。
このように、台湾を攻撃し占領する布石として、米国軍の策源地としての沖縄の米軍基地を攻撃し、その機能を封殺することが作戦上の大前提となるのは常識なのだ。
だが、それも実は見せかけ!?中国は空母を持って、台湾攻撃の主力としたかのように見せかけているだけなのだ。その艦載戦闘機のエンジンが出力不足で、大型ミサイルを搭載して発艦できないと言われている。最近見た、中国の演習の映像でも小型のミサイルは搭載してはいたが、大型のものではなかった。どうやら小型の空対空ミサイルの武装だけなので、その戦力価値は大きく減殺される。つまり防空機能だけで攻撃力は無く、空母打撃群としての存在意義はない。
しかも、中国海軍の潜水艦への対処能力は未だに低いと思われ、南シナ海での海自の演習でも、海自の海上艦艇を追いかけまわしただが、それに随伴した潜水艦の存在は知らなかった、ようなのだ。これでは、中国海軍の海上艦隊群は海自の潜水艦一隻でも相当な打撃を加えられるはずなので、“見せかけ”、と言っても過言ではあるまい。その上に米海軍が加勢するとなると数では劣勢でも、質においてはるかに優勢となろう。
従って私の結論では、目下では中国には台湾有事を引起す海軍力はないものと見てよいのではないか。それにしても、ロケットの落下にはかなわない。
さて、今回投稿はGWによって一週間ぶりとなるが、家で自粛していてそれほど面白いことはなかった。当たり前か!?審査の仕事は、本来、時期的に少ないのだが、緊急事態下、顧客要望で延期にもなっている事例もある。
ネタが乏しいので、先月同様4月に見た映画の紹介としたい。このところ、NHK・BSプレミアムで見たBSシネマばかりではなく、地上波TVで放映された映画の録画もしていて、それが貯まってきているので、それも見始めている。最近はそれに加えてさらに、youtubeで無料の映画も見ている。これはむしろメジャーなものではなく、B級映画中心だが面白そうなものは見るようになった。それら、全てを今回は紹介したい。場合によってはネタバレもあるがお許しの程を・・・。
先月同様に鑑賞できた映画は、NHK・BSプレミアムのBSシネマで見たのが大半で、その内の洋画は次の通り。
①ネバダ・スミスNevada Smith 1966年・米、監督:ヘンリー・ハサウェイ、出演:スティーブ・マックイーン,カール・マルデン,ブライアン・キース,アーサー・ケネディ
②キリング・フィールドThe Killing Fields 1984年・英、監督:ローランド・ジョフィ、出演:サム・ウォーターストン,ハイン・S・ニョール
③ミネソタ大強盗団The Great Northfield Minnesota Raid 1972年・米、監督:フィリップ・カウフマン、出演:クリフ・ロバートソン、ロバート・デュヴァル
④ウェスト・サイド物語West Side Story 1961年・米、監督:ロバート・ワイズとジェローム・ロビンズ、出演:ナタリー・ウッド、リチャード・ベイマー、ジョージ・チャキリス
⑤追想Anastasia 1956年・米、監督:アナトール・リトヴァク、出演:ユル・ブリンナー、イングリッド・バーグマン、ヘレン・ヘイズ
⑥ムトゥ 踊るマハラジャ Muthu1995/2018・印、監督:K・S・ラヴィクマール、出演:ラジニカーント、ミーナ
⑦クォ・ヴァディスQuo Vadis 1951年・米、監督:マーヴィン・ルロイ、出演:ロバート・テイラー、デボラ・カー、ピーター・ユスティノフ
⑧グラディエーターGladiator 2000年・米、監督:リドリー・スコット、出演:ラッセル・クロウ、ホアキン・フェニックス、コニー・ニールセン、オリヴァー・リード、デレク・ジャコビ、ジャイモン・フンスー、リチャード・ハリス
⑨荒野の七人The Magnificent Seven 1960年・米、監督:ジョン・スタージェス、出演:ユル・ブリンナー、イーライ・ウォラック、スティーブ・マックイーン、チャールズ・ブロンソン、ロバート・ヴォーン、ジェームズ・コバーン
①、③、⑨は米西部劇。
⑨は日本の黒澤明の“七人の侍”が原作の有名な作品。実は、原作映画をつぶさに見たことはないのだが、原作では7人の得意な武器に刀ばかりではなく槍や弓など夫々個性があって面白いのだが、西部劇では拳銃とライフル銃に限られてしまうので、その点で7人の個性を出し辛く、面白みに欠ける。出演者は米男優のオールスター・キャストの印象である。特に、ロバート・ボーンのニヤケ顔はかつてTVシリーズ“0011ナポレオン・ソロ”以来、久しぶりで懐かしかった。Sマックイーンは①では主役。
③は、不覚にも途中で眠り込んで、始めと終わりで何とか“見た”つもりになっている。あくまでも“つもり”であった。
②はカンボジア内戦の話だが、あたかもその際の“虐殺”がメイン・テーマであるかのような印象を受けていた。日本での公開の時もそのように誤解させるようなPRでなかったろうか。恐いもの見たさに思っていたのだが、これまで見る機会を逃し、レンタル・ビデオでも見ることはなかった。絶好の機会とばかりに見たのだが、実際にはそうではなく、そのような惨劇の直前に逃亡し、その逃避行に成功した人の体験談である。
しかし何故、あのように残虐な行為が行われたかの原因についての追及や分析はこの映画の中では行われていない。私はその点に気になるのだが。
④はミュージカル映画として非常に有名だったが、私はミュージカルそのものにあまり興味ないので、これまで見ることはなかったが、この際、有名な映画として見た。作曲は佐渡裕氏の師匠レナード・バーンスタインである。
高校の最終学年の体育祭で、ピーターパンの仮装行列をやったが、その時に、誰がプロデュースしたのか今もって知らないのだが、このミュージカルのメインテーマのメロディを巧みに取り込んでいた。私はたまたまインディアンの娘・タイガー・リリー役を仰せつかってドンゴロスでできた衣装を着ていたのだった。そんな思い出と共に、懐かしく見てみようと思ったのだ。
だが、残念ながらストーリーそのものは大したものとは思えなかった。ニューヨーク下町の少々ぐれた高校生グループの闘争話、それだけのことのように思うのだが・・・。
⑤は、和訳の表題が見当違いの印象。現代の“アナスタシア”の方がはるかに分かり易い。
アナスタシアはロシアのロマノフ王朝の皇女。ロシア革命後、王朝の皇帝ら皇族はことごとく処刑されたはずだったが、皇女は行方不明となっていて、旧貴族たちはその行方を捜していた。それは皇帝のイングランド銀行に預金した1000万ポンド利子も含めて3600万ドルのロマノフ家の遺産目当てだった。ユル・ブリンナー演じるロシア帝国の元将軍ボーニンは街で見つけた記憶喪失の女性・イングリット・バーグマン演じるアンナ・ニコルをその王女に仕立てて遺産を手に入れようする話だ。バーグマンが気品と知性を体現していて、その魅力を発揮した映画だ。
ボーニンはデンマークに亡命した皇太后にアナスタシアを逢わせて、どうやら皇太后からは本当の皇女との心証を得て、アンナ自身も自分のアイデンティティに納得し、その後ボーニンとの恋に生きるため行方をくらましてしまう。全てを了解した皇太后は“芝居は終わった”と言って映画は終わる。
私はこれまで、あまりユル・ブリンナーという俳優を詳しくは知らなかった。しかし⑨のような西部劇の無頼漢役も⑤では貴族の将軍役も、或いは“王様と私”では王様役、“隊長ブーリバ”ではコサックの隊長、前回紹介した“ウェスト・ワールド”ではロボット役。極めて個性的な顔ながら、身のこなしが素晴らしく、これら全てを上手く演じている名優だとはじめて思い知った次第だ。
⑥はインドのミュージカル。インド映画は全てこのタイプのミュージカルのように聞いている。突然踊り出すのが面白いとか。
インド社会は古代からのカースト身分制が厳しいのが、社会発展のくびきになっていると聞いていたが、この映画ではその影響は見取れなかった。それよりも地主一家の話だったように思うので、古代からと言うよりも中世からの影響なのか?それにしても、未だに農本地主なのだろうか。
⑦は、イェスの亡くなった直後の直弟子ペトロによるキリスト教布教活動が背景にある話。ペトロは和訳すれば“いわお巌”。固い信念・信仰の象徴なのだ、と英語の先生からならったのを思い出す。英語ではピーター。
表題も和訳すれば“いずこへ”となる。その方が分かり易いが、まっラテン語のお勉強か。これは最近亡くなった吉本有名コメディアンのギャグだったのを思い出す。ストーリーは暴君ネロにまつわるモノ。詳しくは忘れかけているのが実態で、ネットで今もう一度確認している。ペトロはネロによって磔刑となり、その墓地の跡がバチカンの中心サン・ピエトロ大聖堂となっている。これはクリスチャンの常識。ここでは余計話で誤魔化す。
⑧は⑦と同じようにローマ帝国モノ。今となっては、⑦と混乱している印象。
見るのはこれが2度目で史実に基づいていると誤解していたが、創作話のようだ。だから、映画関係者には史実とは誤解されては困るとの苦情もあったかのようだ。確かに、ローマ皇帝のありようが、確固たる世襲制であるかのようなのも、チョット違うのではないかと、見ながら思ってはいたので、自分の感覚が確かであったとの自信を持ってしまった。
次にNHK・BSプレミアム・BSシネマで見た邦画は次の通り。
⑩どら平太 2000年、監督:市川崑、出演:役所広司、浅野ゆう子、宇崎竜童、片岡鶴太郎、菅原文太
⑪病院坂の首縊りの家 1979年、監督:市川崑、出演:石坂浩二、佐久間良子、桜田淳子
⑫女王蜂 1978年、監督:市川崑、出演:石坂浩二、高峰三枝子、中井貴恵、沖雅也、加藤武、大滝秀治、岸惠子、仲代達矢
⑬丹下左膳・百万両の壺 2004年、監督:津田豊滋、出演:豊川悦司、和久井映見、野村宏伸、麻生久美子
⑭聖の青春 2016年、監督:森義隆、出演:松山ケンイチ、東出昌大、リリー・フランキー、竹下景子
⑩は山本周五郎の“町奉行日記”を元にしたというが、大して感動も何もなかった。今でも印象は薄い。
ある小藩の国元では、財政難を補うために“壕外”と呼ばれる無法者の町から莫大な上納金を集めていた。それが原因で藩内が腐敗していた。それを一見隙だらけで“どら平太”と世間から呼ばれている一人の侍が殿の指示でやって来たと書付を見せて詐称して、藩内改革する話だが、十分にあり得ない内容だ。当時の小藩の侍達に上納金を集めるそんな金銭的才覚があるとは思えないからだ。何故ならば、侍には金銭自体に“汚い”という感覚があったということだからだ。だから反税制の改革は困難を極めたのだ。だから賄賂もバレ易く、バレれば即座に切腹。殿の指示を詐称するのも切腹となる時代のはずだからだ。二重の切腹を覚悟でできるものではない。厳密な話をすれば面白くはないが、それが現実。現代的には痛快サラリーマン話となるのだろうが、現実にはないのと同じレベルのストーリー。
⑪と⑫は、横溝正史の複雑なストーリー。これも話としては面白く、現実的可能性は皆無とは言い難いのだが・・・どうにも非現実的ではないか。
⑬は昔の大河内伝次郎の映画のリバイバル版。トヨエツが主役の左膳をやった。“百万両の壺”はいわゆる“コケざるの壺”。見ていてストーリーが中々核心に入らなかったように感じて、途中で眠ってしまった。
それらに対し⑭は現代の実話だ。将棋の関西棋院の棋士・村山聖(さとし)を題材としている。だから大阪の福島界隈が映画の始まりの舞台になる。これを本人の往時を知る人は、主役の松山ケンイチが本人と見まがうほどの好演だったという。羽生善治役の東出昌大も好演だった。私は羽生御本人が出演しているのかと、始めは思ったほどだ。村山は将棋公式戦でその羽生を破ったことのある、数少ない棋士の一人だという。だが、村山は幼い時から腎臓病ネフローゼに悩まされ、結局はそれが原因で若くして亡くなる。
映画の中で、羽生との名人位挑戦後村山は羽生を誘って二人で飲む場面がある。健康ハンディキャップを抱えながら村山は、そこで羽生に二つの夢があると告白する。一つは名人位であり、もう一つは恋人だという。羽生はその時結婚していて、その夢の二つとも既に手にしている。その立場でどのような表情で村山と対峙したのか。この難しい場面を東出は上手く演じていたように思う。五分五分の天才の両者だが、運命は過酷に二人を分けているのだ。これが厳しい人生の現実なのだ。神はあるのか?
聖は持病にもかかわらず、東京に出て母親の目の届かないところで不摂生を繰り返す。やがて泌尿器周辺に癌が発生し、切除手術で恋人獲得の夢も絶望。残る人生最後の数カ月、聖は負けなしで芸術的な棋譜を残したという。羽生はそんな聖が大好きで、その最期に寄り添い看取ったという。
BSシネマは地上波ではなく事情があって録画できないのだが、地上波のTV放映されたものは録画していて、これまでそのままだったが、自粛に伴い見て整理しようとしたのが次の6点。
⑮マッチポイントMatch Point 2005年、英、監督:ウッディ・アレン、出演:ジョナサン・リース・マイヤース、スカーレット・ヨハンソン
⑯英雄の条件Rules of Engagement 2000年、米、監督:ウィリアム・フリードキン、出演:トミー・リー・ジョーンズ、サミュエル・L・ジャクソン
⑰ジャッカルThe Jackal 1997年、米、監督:マイケル・ケイトン=ジョーンズ、出演:ブルース・ウィリス、リチャード・ギア
⑱ラストベガスLast Vegas 2013年、米、監督:ジョン・タートルトーブ、出演:マイケル・ダグラス、ロバート・デ・ニーロ、モーガン・フリーマン、ケビン・クライン
⑲ヘアースプレーHairspray 2007年、米、英、監督:アダム・シャンクマン、出演:ニッキー・ブロンスキー、ジョン・トラヴォルタ、ミシェル・ファイファー、クリストファー・ウォーケン、クイーン・ラティファ
⑳後妻業の女 2016年、日、監督:鶴橋康夫、出演:大竹しのぶ、豊川悦司、尾野真千子、笑福亭鶴瓶、津川雅彦、永瀬正敏
⑮見終わってウッディ・アレン調をジワリと感じるここには人生の理不尽があった。それが良い。象徴的画像に始まってアナロジー画像で終わる。事実を淡々と映像で追っていく語り口で分かり易かった。
“マッチポイント”とは“後1点で試合が終了するときのポイント”のことだが、テニス・ゲームでそれが、打ったボールが手前に落ちれば負け、相手側に落ちて相手が打ち返せなければ勝ちの運命の分かれ目を示している。映画の冒頭では無邪気なテニスでのそのシーンが流される。ラストでは重要な証拠の指輪を真犯人の主人公が川に投げ込んだつもりだったが、それがたまたま堤防の手摺に当たって跳ね返り、それを麻薬売人が偶然にも拾って持っていたので、その売人が殺人犯と警察官は断定する。しかも売人は殺されていたので捜査は終了。悪運の強い主人公という理不尽なのだ。小説“罪と罰”が下敷きなのか?
⑯の原題の“Rules of Engagement”は米海兵隊の“交戦規定”の意の由。イエメンで米国大使館包囲デモ事件が発生する。米国政府の要請で大使館員救出に向かった海兵隊は、暴徒と化した民衆に銃撃し、一般市民百数十人の死傷者を出した。この民衆銃撃を命令した大佐は軍法会議にかけられる。そんな大佐が、かつて厳しいベトナム戦で命を救われた戦友で、その後事務職で過ごした地味な人物に弁護を要請し、引き受けてもらう。
結局は陪審員の被告に対する心証が良かったのだろうか、決定的証拠無しに無罪となっている。決定的証拠の録画記録のテープは大佐を起訴した検察官が自らの出世のために故意に焼却した。厳重に保管されるべき国家の記録がきちんと保管できていないこと、毀損されたことが問われずに結審させているのが不思議だ。そのテープの存在は記録されているにも拘わらず、適切に法廷に提出されていないのだ。これでは今日本で裁判中の財務省の記録の毀損・隠滅・書き換えと同じではないのか。米国でも権力側の故意が通用するのか?法廷闘争上、被告に有利と思われる有力な証拠を検察が隠滅したと強く推定されるならば、明らかに起訴不当として無罪とさせるべきでないか。このシナリオに大いに不自然を感じるのだ。
知らなかったが、この作品はイェメン人を差別的に表現しているとの評価が米国にはあるようだ。どこがそうなのか私には直ちには分からないが、ひょっとして民衆が扇動されやすい烏合の衆であるかのような仕上がりであることに問題があるのだろうか。ならば事件が事実であれば問題ではなかったことになるのだろうか。創作であればなぜ場面設定をイェメンと特定したのだろうか。まぁそういう批判が人種差別の国であるのは結構、健全なことではないか。
⑰は1973年の映画“ジャッカルの日”のリメイクだという。残念ながら、その本作も見たいと思っていたが見きれていない。それは時の仏大統領ド・ゴール暗殺計画だったと思う。ここではブルース・ウィリスが追われるスナイパー役。リチャード・ギアはFBIの立場で追いつめて行く。ストーリーは今風で結構複雑。
⑱は現代の米名優が勢揃いして、引退した様々な“老後”を演じている。まっ、身につまされるが、微笑ましく面白いの一言か。
⑲はあまり有名ではないが、ミュージカル映画で、“ウェスト・サイド物語”よりもはるかに出色の作品だと思う。ジョン・トラヴォルタ、ミシェル・ファイファーと名優が脇を固めているが、主役はニッキー・ブロンスキーという背の低い見栄えのしない女優だ。だが歌唱力は確かに映画の冒頭からズーっと歌い上げていて上手い。あらゆる差別:身体的、性的、人種的差別反対を全編で明るい音楽であくまでも明るく主張!兎に角ぶっ飛んでいる。だから、そういう女優を起用したのだろう。
びっくりしたのは、ジョン・トラボルタだ。何と主人公の娘の母親役なのだ。最初、この母親は男ではないかと疑った。異様に大柄で太い手足。声も心なしか太い。だが、動きや身のこなしは完璧に女性。米国にはこんなオバサンも居るのかと思っていた。だがやっぱり、どう見ても顔の輪郭は男。その特徴的目付きから、後半になってひょっとしてトラボルタでは?とようやく気付く始末。配役で出ているのに一向に登場しないこともあった。しかし、彼は本来、“サタデー・ナイト・フィーバー”で踊りまくって有名になった俳優のハズなので、あの太い手足は役作りだったのだろうか。やはりハリウッドの一流の演技力はすごい!容易に騙されてしまう!
⑳このグループでたまたま唯一の邦画になったが、大竹しのぶの好演と役柄で尾野真千子との対立が面白い。これはこんな詐欺師やその集団がいるのかなぁと思わせるのが良い。まぁある種、“難波金融伝”を想起させる部分があって面白い。
この映画の前にTVドラマ化されていたようで、そんなことでもあるのか、映画ではシナリオ上省略されている部分があると感じるのが残念なところだ。
youtube無料動画で見たのは次の2点。
㉑チャタレイ夫人の恋人The Lover(L'amante) 1991年・伊・監督:フランク・デ・ニーロ、出演:ランバ・マル、マック・キラン、アンソニー・ステファン、バーバラ・ブラスコ
㉒レッド・エージェント 愛の亡命Despite the Falling Snow 2016年・英、加、監督:シャミム・サリフ、出演:レベッカ・ファーガソン、チャールズ・ダンス、サム・リード、アンチュ・トラウェ
㉑は表題の和訳がいい加減で、有名な“チャタレイ夫人の恋人”とは全く異なるようだ。むしろその“チャタレイ夫人の恋人”の内容を知らないので見ようと思ったのだ。騙された印象がある。主演は有名な女優らしい。その裸身を見るための映画か?監督はロバート・デ・ニーロではない、要注意。だが、映像は制作国がイタリアのためか明るく美しい。
㉒は、主演女優レベッカ・ファーガソンの1人二役で、演技は上手かった。映画評でみられたが、ここで1人二役にする必然性はあまりない。気付かなかったが、彼女はトム・クルーズの“ミッションインポッシブル”シリーズにもスパイ役で出演していたという。内容も、ソヴィエット社会の40年代頃と60年代を背景としていて必見とまでは言わないが見応えがあった。無料なので自粛でヒマな時にはお得感十分だ。
結局のところ、数えてみると4月は22の映画作品を見たが、印象に残るのは“追想(アナスタシア)”、“聖の青春”、“ヘアースプレイ”といったところであろうか。
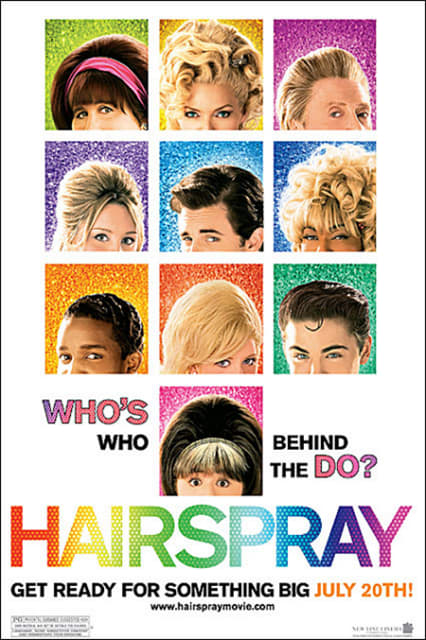
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « 並木伸一郎・... | 半藤一利・著“... » |
| コメント(10/1 コメント投稿終了予定) |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |




