馬が日本に渡ってきたのは、おそらく古墳時代の初め頃です。
そのへん、私は専門でないので結構いい加減かもしれません(笑)
馬は韓半島からきた渡来してきた人たちが、財産として持ち込んだのだろうと思います。
初期の古墳からはきらびやかな馬具が出土しており、それは韓半島でも同様な
状況です。
日本においては、馬は豪族の権勢を示す重要なアイテムだったようです。
今で言えば、たとえばロールズ・ロイスの様なものでしょうか。
財力とコネクションとステータスが無ければ持てないもの、それが馬です。
当然のことながら、公式の席では馬も正装です。なかなか当時の馬の
様子を伝えるものは多くはありませんが、権勢を示す威信財であっただけに、
豪族の古墳に供えられる埴輪は馬型のものが少なくありません。
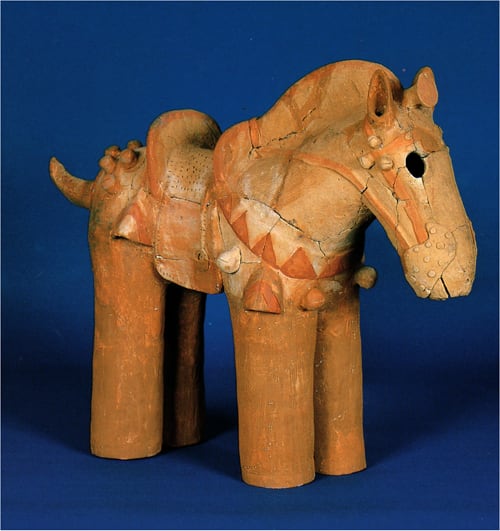
たてがみをたて、三角文の描かれた飾り帯をかけられ、
全身に鈴と飾り金具をちりばめた出で立ちです。
鞍とハミがつけられ、手綱が見えます。

旗を立てれば完璧な正装です。

そして、行列です。どうだっって感じでしょう。
きっと、地方の平民は馬を見ただけでひれ伏したに違いありません(爆)
そして、おそらく、馬は財産として徹底的に管理されたことと思います。
ところが、やはり本能のままに脱走する馬もいたようで、野馬が発生します。
つまり野生化した馬ですね。野良馬(笑)
これが旺盛に繁殖しているのを捕まえて、調教して輸出していた
のが陸奥の国は平泉ですね。平泉の文化を支えた財力は砂金と馬です。
また、福島の相馬ではこの野馬を捕まえることで、戦の訓練をしたり
したことが、相馬野馬追という祭礼の発端となっています。
ですから、少なくとも平安時代も半ば過ぎには馬は比較的
一般化していたのではないでしょうか?
ということは、当然家畜化してきているというわけですが、
家畜という部分では、まず乗り物として活用されはじめたようです。
ところでこの馬、なんかバランスが悪く見えません?

それは作った人間がへただったからなのかどうかは
次回のこころだ~~!
そのへん、私は専門でないので結構いい加減かもしれません(笑)
馬は韓半島からきた渡来してきた人たちが、財産として持ち込んだのだろうと思います。
初期の古墳からはきらびやかな馬具が出土しており、それは韓半島でも同様な
状況です。
日本においては、馬は豪族の権勢を示す重要なアイテムだったようです。
今で言えば、たとえばロールズ・ロイスの様なものでしょうか。
財力とコネクションとステータスが無ければ持てないもの、それが馬です。
当然のことながら、公式の席では馬も正装です。なかなか当時の馬の
様子を伝えるものは多くはありませんが、権勢を示す威信財であっただけに、
豪族の古墳に供えられる埴輪は馬型のものが少なくありません。
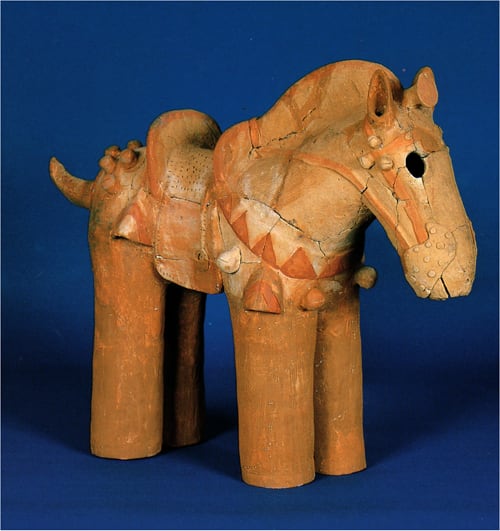
たてがみをたて、三角文の描かれた飾り帯をかけられ、
全身に鈴と飾り金具をちりばめた出で立ちです。
鞍とハミがつけられ、手綱が見えます。

旗を立てれば完璧な正装です。

そして、行列です。どうだっって感じでしょう。
きっと、地方の平民は馬を見ただけでひれ伏したに違いありません(爆)
そして、おそらく、馬は財産として徹底的に管理されたことと思います。
ところが、やはり本能のままに脱走する馬もいたようで、野馬が発生します。
つまり野生化した馬ですね。野良馬(笑)
これが旺盛に繁殖しているのを捕まえて、調教して輸出していた
のが陸奥の国は平泉ですね。平泉の文化を支えた財力は砂金と馬です。
また、福島の相馬ではこの野馬を捕まえることで、戦の訓練をしたり
したことが、相馬野馬追という祭礼の発端となっています。
ですから、少なくとも平安時代も半ば過ぎには馬は比較的
一般化していたのではないでしょうか?
ということは、当然家畜化してきているというわけですが、
家畜という部分では、まず乗り物として活用されはじめたようです。
ところでこの馬、なんかバランスが悪く見えません?

それは作った人間がへただったからなのかどうかは
次回のこころだ~~!

















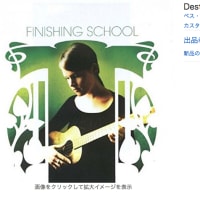
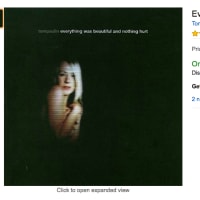

ましてやなじみがないものならば、おそろしい~!
こんにちは坊さん!
きっと、古代に船上で初めてこのウマを見た人たちは、腰を抜かして驚いたでしょうね!
ですので、実際以上に大きく見えて、
そのようなバランスになったのかも♪