
ひき続き、小杉泰氏の「ムハンマド・イスラームの源流をたずねて」のご紹介をさせていただきます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
ムハンマドが結婚し、長女が生まれたのは、結婚して5年が過ぎた頃である。
続いて女児3人、男児2人が産まれた。
男子2名は夭折した。
ムハンマドが35歳のころ、末娘が産まれ、4人の娘と妻とメッカで過ごした。
40才になる頃には、メッカ社会の現状を憂いて、度々ヒラーの洞窟に籠って瞑想にふけっていたとされるが、夫、父としての責務をおこたっていた様子はうかがえない。
しかし彼が「アラーの使徒」であると自覚するに至って、生活は大きな変化をとげる。
ムハンマドは、初めて「啓示」をうけた頃、定期的にメッカ郊外のヒラー山に籠って瞑想にふけっていたという。
この洞窟で天使ガブリエルの訪問をうけ、預言者としての暮らしが始まることになる。
40才のムハンマドは、メッカのクライシュ族の中で、指導者として必ずしも傑出していたわけではなかったが、信頼される人物であった。
彼の瞑想の本拠地ヒラー山は、徒歩小1時間で登れるほどの高さである。
今日では「光の山」と呼ばれ、洞窟が「ヒラーの洞窟」とされる。

「預言者伝」の中の描写を示す。
・・・
わたし(ムハンマド)が眠っている間に、天使ガブリエルが一冊の本を入れた錦織の手提げ袋を持って私のところにいらっしゃって、「朗読せよ」と私にお命じになりました。
わたしが「何を朗読するのですか?」とたずねると、彼はその手提げ袋で私を押さえつけたので、わたしは今にも死ぬかと思いました。
やがて彼はわたしを許し、また、「朗読せよ」とお命じになりました。
わたしが「何を朗読するのですか?」と尋ねると、彼はその手提げ袋でわたしを押さえつけたので、わたしは今にも死ぬかと思いました。
やがて彼はまた「朗読せよ」と言われました。
そしておっしゃいました、
「読め!
創造なされた汝の主の御名によって。
彼は、凝血から人間を創られた。
読め!
汝の主はもっとも尊貴なお方。
彼は、筆によってお教えになった方。
人間になることをお教えになった。
・・・
ムハンマドは誰もいないヒラーの洞窟で一人すごしていた。
誰も来るはずのない場所である。
そこに突然、誰かが現れた。
しかも唐突に「読め!」と命じる。
何のことか分からなかったに違いない。
そもそも当時のメッカの住民がほとんどそうであるように、彼は読み書きができなかった。
読み書きのできない自分に、読むものも無い洞窟で、「読め!」とはいったい何の話なのか?
「何を読めというのですか?」
ないしは「わたしは読むことができません」と彼は抗弁したのであろう。
相手は命令に従わないムハンマドに満足せず、実力行使に出た。
この時点では、相手が人間であるのか、天使や霊精の類であるのかも判然としない。
締め付けられたムハンマドが、殺されるのかと思っても、不思議はないであろう。
3度、死ぬ程苦しい目にあって、訳はわからないが言うことを聞くしかない、と思ったであろう。
神はムハンマドに、不思議の言葉を言い聞かせた。
ムハンマドは、恐れおののいて洞窟を後にした。
「預言者伝」の表現では、以下のようである。
・・・
山の中腹まで降りると、天から声が降ってきた。
「ムハンマドよ、汝はアラーの使徒なり。
そして、我はガブリエルなり」。
見上げると、両足で地平線をまたいだ巨大な男性の姿がそこにある。
その者はふたたび、
「ムハンマドよ、汝はアラーの使徒なり。
そして我はガブリエルなり」と呼ばわった。
・・・

天使は、ムハンマドが唯一神アラーによって人類への使徒として選ばれたことを宣言したわけである。
しかし、ムハンマドはその意味をまったく理解していなかったであろう。
ムハンマドはその姿を見つめて、動くこともままならなかったという。
かろうじて顔を動かして反対方向を見ると、どうやって移動したのか、そこにも天地の間に屹立する同じ姿が立っているのである。
あまりに帰宅が遅いので、妻が人をやって夫を探させるほど、時間が過ぎた。
そして震えながら家に帰ったムハンマドは、妻に「私に衣を被せてくれ。私に衣を被せてくれ」と叫んだ。
彼女に衣で覆ってもらった彼は、やがて愛妻の傍らで平静を取り戻し、事件を語った。
衣を被っている姿は、「コーラン」の次の章句に言及されている。
・・・
衣をかぶる者よ。夜は礼拝に立て。わずかの時を除いて。
夜の半分、あるいはそれより少しだけ少ない礼拝に立て(「衣を被る者」章1-3)
・・・
ムハンマドは妻に、率直に自分がおかしくなったのではないかとの恐れと不安を訴えたようである。
それに対して15才年上の妻は、夫への親愛をあらわにし、勇気づけた。
妻は「めっそうもない。アラーは決してあなたを辱めなでしょう。
あなたは身内の者に良くし、弱い者を支え、貧しい者に施しをし、旅人を暖かくもてなし、世の転変の犠牲となった人々を助けているのですから」と言った。
ちなみに彼女が挙げたムハンマドの美質は、当時のアラブ人の美徳観を示している。
これらはイスラームにも継承された。
弱者や貧者の救済、旅人へのもてなしなどは、今のアラブ世界でも人間味あふれる振る舞いとして、私たちは出逢うことができる。
妻は夫をなぐさめるだけでなく、いとこのもとに相談に行った。
彼は、当時のメッカには珍しいキリスト教徒だった。
彼は「ムハンマドを訪れたのは大天使にちがいない」と断定した、と伝えられる。
ムハンマドは、「啓示の器」たることを引き受けた。
(引用ここまで)
写真(中)はヒラー山。
写真(下)はヒラー山の洞窟を訪れる信徒たち。
いずれも同書より。
*****
この場面は非常に有名な場面であるようです。
たしかに一読すると、忘れられない強いインパクトがあります。
7世紀のアラビア半島で、このようなできごとがあったのだということを疑うことはできません。
しかし、なぜ、彼のもとを訪れた者が「大天使ガブリエル」なのか?ということは、率直に言って、今の私にはよく分かりません。
もし、ユダヤ教にもキリスト教にも関わりのない、土着の〝天使″であったなら、今の中東問題の混乱もなく、イスラム教徒たちだけの平穏な世界が保てたのではないかと思ってしまいます。
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「ユダヤ教徒の祈りの生活・・「旧約聖書」とつながる」
「地獄と申するは、昏き処にもろもろ天狗にまた天狗・・隠れキリシタンの信仰世界(3)」
「愛し子よ、愛で身を固めなさい・・長崎の原爆被害者・永井隆さんの遺言」
「ツングースのサマン(シャーマン)・・憑霊の人間学(3)」
「お前は宇宙霊の一部だ・・シュタイナーによる人智学的ゾロアスター論(3)」
 「エジプト・オリエント」カテゴリー全般
「エジプト・オリエント」カテゴリー全般「ブログ内検索」で
イスラム 15件
天使 15件
旧約聖書 15件
新約聖書 15件
などあります。(重複しています)











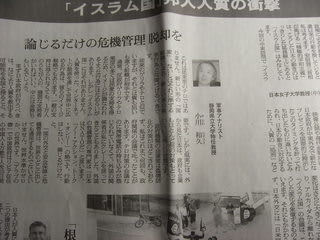
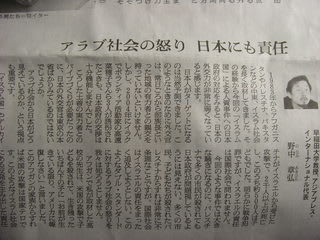
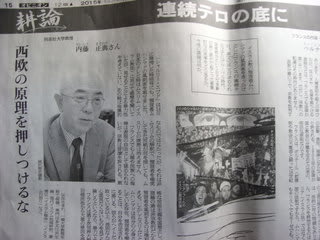




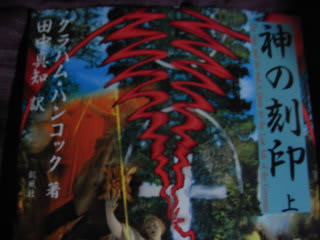


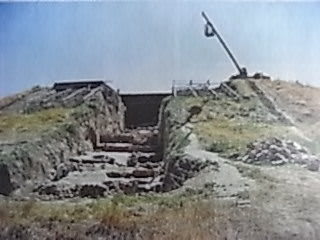
 「エジプト・オリエント」カテゴリー全般
「エジプト・オリエント」カテゴリー全般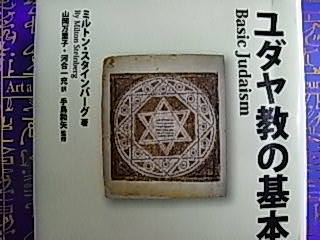
 wikipedia「過越」より
wikipedia「過越」より 「エジプト・オリエント」カテゴリー全般
「エジプト・オリエント」カテゴリー全般












