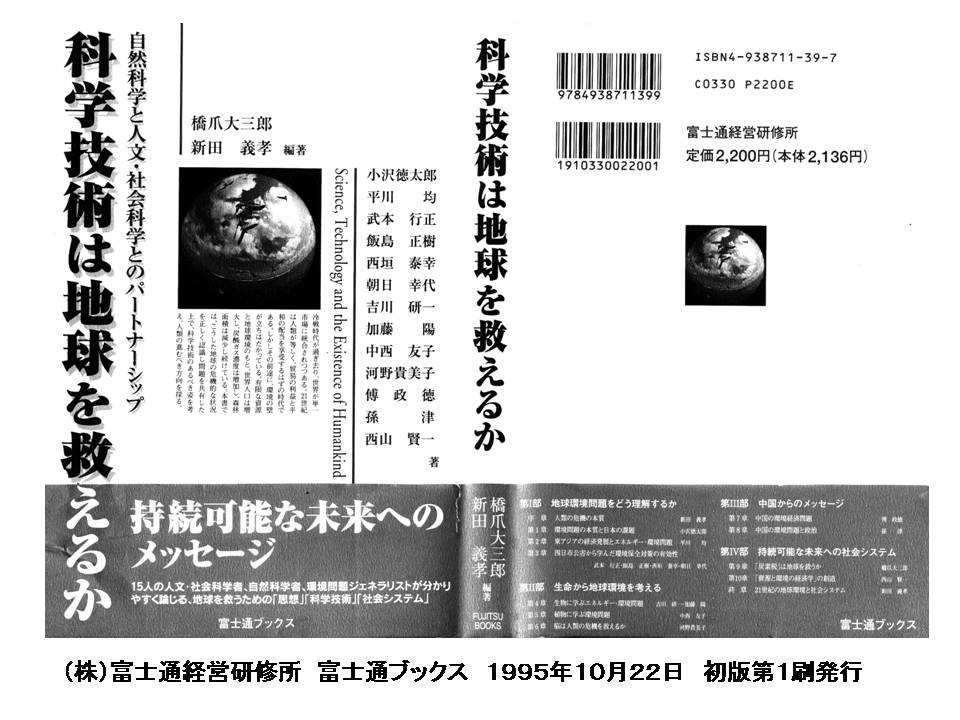みなさん、明けましておめでとうございます。
今日、2007年(平成19年)1月1日、私も「ブログ」を始めることにしました。
ブログを始めるにあたって、最初に何を書こうか考えました。無難なところは自己紹介からということでしょうか。
私のプロフィールや私の主張は私の公式HPを見ていただくことにして、昨年暮れに、底知れぬ「インターネット」という大海から
“バックキャスティング”で釣り上げた2つの成果(ゲット)を紹介することから、このブログを始めることにしましょう。
一つ目のゲット(私の肩書き)
初めてのブログへの挑戦ですので、ブログの現状を把握するために昨年暮れネットサーフィン(ブログサーフィン)を試みました。今となってはどのようなルートで到達したのか定かではないのですが、
塩見直紀さんという方の「21世紀の肩書研究所」というブログに遭遇しました。何となく興味をそそられたので、読み進むとなんと「私の肩書き」が次のように取り上げられていました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「環境問題スペシャリスト」(NO.0031)
テーマ:21世紀の肩書
ぼくは「21世紀の2大問題」として、環境問題と天職問題の2つをあげています。ぼくの「仮説」はあたるかな。問題の1つである環境問題。今年、2月、以下の本が出版されました。
日本が「失われた10年」を過ごしている間に、スウェーデンは年金制度改革、化石燃料の消費量の抑制、資源の再利用、廃棄物の削減といった施策を着々と進めてきた。
「国家の持続可能性ランキング」1位の国の挑戦から学ぶ。
『スウェーデンに学ぶ「持続可能な社会」
~安心と安全の国づくりとは何か~』
(朝日選書・2006年2月)。
さてさて、今日、「21世紀の肩書研究所」がご紹介する肩書は小沢徳太郎さんの肩書である「環境問題スペシャリスト」(NO.0031)です。
小沢徳太郎さんはスウェーデン大使館で科学技術部環境保護オブザーバーとして、環境・エネルギー問題を担当。退館後、「環境問題スペシャリスト」として独立。現在、執筆・講演等で、環境問題をテーマに東奔西走されています。他の著書に『いま、環境・エネルギー問題を考える』等があります。
この時代に、自分をどう位置づけるか。自分の役割はこれだとわかっている人にとっては21世紀はほんとうに刺激的だし、困難がいっぱいでもがんばれるのです。
2006.05.26 21世紀の肩書研究所 塩見直紀
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
特に最後の2行の塩見さんのコメントが新鮮だったので、今日、2007年1月1日に検索エンジン・グーグルに「21世紀の肩書き研究所」を入れて検索しますと、検索結果はなんと約105,000件が表示されました。
二つ目のゲット(環境問題ジェネラリストか環境問題スペシャリストか)
「21世紀の肩書き研究所」の検索結果が私の予測をはるかに超えていたので、試しに
私の以前の肩書き「環境問題ジェネラリスト」と
現在の肩書き「環境問題スペシャリスト」を同じようにグーグルで検索してみました。結果はこれまた、大変な驚きでした。
前者は今日午後7時現在で約28,800件、後者は約32,400件とこれまた私の予想をはるかに超える件数が表示されました。なぜこんなにたくさんの件数が表示されるのであろう、表示する判断基準は何か、さまざまな疑問が出てきます。
そして驚いたことに、「環境問題ジェネラリスト」約28,800件のトップに位置していたのが、東京工業大学の社会理工学研究科価値システム専攻ブログ「Cafe VALDES」でした。そして、なんと、
同大学の価値システム専攻「VALDESのHP」トップページには「せまりくる現実の問題は、文系、理系の学問的区別は持ってはくれません。
境界を越えたジェネラリスト、すなわち、現実問題へのスペシャリスト-これが私たちのねらいです」と謳われています。
これまた偶然ですが、私
はこのVALDESで橋爪大三郎教授の求めに応じて1997年、98年に非常勤で「私の環境論」を講じたことがあります。それがきっかけで、1995年3月1日から3日、奈良近郊のけいはんなプラザで、科学技術庁主催による「科学技術フォーラム:自然科学と人文・社会科学都のパートナーシップⅡ」(実施担当:財団法人日本科学技術振興財団、今回が14年目)という会合に参加することになりました。その第1分科会「人類の生存と科学技術」に参加したメンバーが、連日の討論を踏まえて書きおろした論文集が刊行されました。
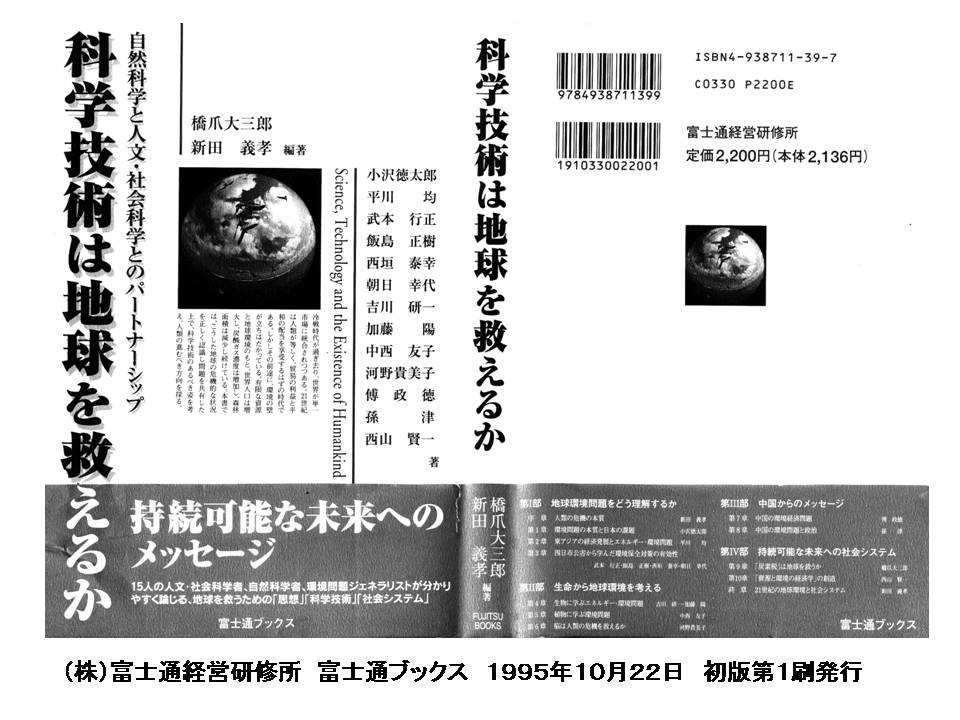
当時の私の肩書きは「環境問題ジェネラリスト」でした。ちなみに、「環境問題ジェネラリスト」の後に個人名として私の名前「小沢徳太郎」と入れて検索すると16件、「小澤徳太郎」と入れて検索すると1件が出てきました。つぎに、現在の肩書きである「環境問題スペシャリスト」の後に「小澤徳太郎」と入れて検索しますと約220件、「小沢徳太郎」と入れますと約96件出てきます。
私は1973年から95年までスウェーデン大使館科学技術部で環境問題、エネルギー問題、労働環境問題を担当してきました。
95年に独立して「環境問題ジェネラリスト 小沢徳太郎」の肩書きで、
2000年頃からは「環境問題スペシャリスト 小澤徳太郎」の肩書きで今まで仕事を続けてきました。私が10年以上前に独立したときの肩書きを「環境問題」のジェネラリストにするかスペシャリストにするか、迷いましたが、
同じような議論がいまなおネット上で熱く議論されているようです。
今回の塩見さんの「21世紀肩書き研究所」というブログに偶然出会い、触発され、調べた結果わかったことは、「環境問題ジェネラリスト」あるいは「環境問題スペシャリスト」という肩書きで仕事をしているのは、人口1億2千万人の世界第2位の経済大国
「日本」でどうやら私ひとりだけのようです。そうだとすれば、アジアでも、世界でもこのような肩書きで仕事をしているのは、もしかすると私だけかも・・・・・・
そして、このブログがめざすもの
このブログは「環境問題スペシャリスト 小澤徳太郎」が考える「環境論」と「その環境論に基づいて日本とスウェーデンの環境問題に対する対応の差」を検証することによって、
「環境問題の本質」に迫ろうとするものです。基本的なことは、昨年2月に朝日新聞社から出版した「スウェーデンに学ぶ『持続可能な社会』 安心と安全の国づくりとは何か」(前掲)に書いたつもりですが、この本に盛り込めなかったこと、その後の進展などをこのブログで書き続けて行こうと思います。
スウェーデンの人口は2005年4月に901万人。日本の団塊の世代はスウェーデンの人口の80%弱に相当する約700万人と推定されています。日本の21世紀前半社会を明るく豊かにするか貧しくするかはひとえに、
2007年から定年が始まる約700万人の団塊の世代の「環境問題に対する意識と行動」と、その子どもたちの行動にかかっています。
私がみなさんに期待したいのは、「環境問題」に対する私の考えや「スウェーデン」に関する私の観察と分析を、
ぜひ批判的な立場で検証し、日本の将来を「明るい希望の持てる社会」に変えていくために
それぞれの立場から日本の現状を真剣に考えてほしいことです。私たちの子どもや私たちの孫のために・・・・・・
 私は1973年から95年 までの22年間をスウェーデン大使館科学技術部で環境・エネルギー・労働環境問題を担当し 、これらの分野で日本とスウェーデンの対応を同時進行的にウオッチして来ました。このブログでは、 その体験から得た「私の環境論」に基づて、私が理解した日本と スウェーデンの現状を分析・検証したものです。ですから、別の方が別の視点で両国を分析すれば、別の姿を描くことも可能でしょう。
私は1973年から95年 までの22年間をスウェーデン大使館科学技術部で環境・エネルギー・労働環境問題を担当し 、これらの分野で日本とスウェーデンの対応を同時進行的にウオッチして来ました。このブログでは、 その体験から得た「私の環境論」に基づて、私が理解した日本と スウェーデンの現状を分析・検証したものです。ですから、別の方が別の視点で両国を分析すれば、別の姿を描くことも可能でしょう。
同じ資料を参考にしても判断基準が異なれば、結論が違ってきます。ですから、同じテーマに対して、みなさんの考えが私の考えと大きく異なるようであれば、大いに議論しましょう。議論を通して私自身の誤りを正すことができるし、「環境問題に対する共通の認識」と「持続可能な社会の構築の必要性」を分かち合うことができる と思うからです。