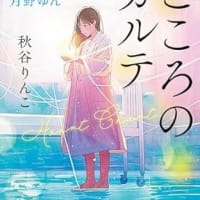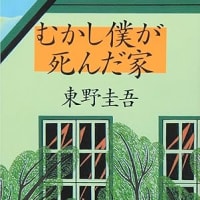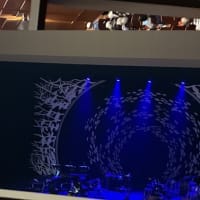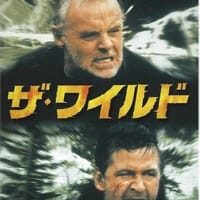2015年5月16日公開 143分
鎌倉にある東慶寺は、江戸幕府公認の駆込み寺だった。離縁を望む妻がここに駆け込めば問題解決に向け動く拠り所だった。駆け込んだからといってすぐには入れず、まずは御用宿で仔細の聞き取りがされる。御用宿の柏屋に居候する劇作者に憧れる見習い医者の信次郎(大泉洋)は、柏屋の主人・源兵衛(樹木希林)とともに、離婚調停人よろしく、口八丁手八丁、奇抜なアイディアと戦術で男と女のもつれた糸を解き放ち、ワケあり女たちの再出発を手助けしていく。
劇作家・井上ひさしが晩年に11年をかけて執筆した時代小説「東慶寺花だより」の映画化です。
昔、グレープの「縁切寺」という曲で東慶寺を知った身にはなんだか懐かしいような気持ちになり選択
質素倹約例が発せられた江戸時代後期が舞台。
日本橋の豪商・堀切屋三郎衛門(堤真一)の愛人お吟(満島ひかり)は夫の身上に不信感を持ち東慶寺に駆け込む途中で夫の暴力から逃げ出してきた鉄練りの女じょご(戸田恵梨香)と出会って共に駆け込みを果たします。この時追っ手を間違えて信次郎に下駄をぶつけちゃうんですね~ (じょごの顔は鉄練りの際の火ぶくれで醜くなっていますが、信次郎の薬で綺麗に治ります。)
(じょごの顔は鉄練りの際の火ぶくれで醜くなっていますが、信次郎の薬で綺麗に治ります。)
この信二郎、江戸で騒ぎを起こして(お上に楯突く発言をして)親戚を頼って逃げ込んだのですが、叔父と思っていた源兵衛さんは女性だった、というところから笑いが起こります。権力を笠にきる連中が嫌いというのは甥とよく似ているね 番頭の利平(木場勝巳)やその妻お勝(キムラ緑子)との掛け合いも楽しく、おせんを取り戻そうと押しかけてきたヤクザ相手に信二郎が得意の弁舌で煙に巻くエピソードも
番頭の利平(木場勝巳)やその妻お勝(キムラ緑子)との掛け合いも楽しく、おせんを取り戻そうと押しかけてきたヤクザ相手に信二郎が得意の弁舌で煙に巻くエピソードも です。
です。
ただ、少し早口で進む会話はときに聞き取りにくい部分もあったのがちょっと残念かも
東慶寺に入るにも持参金により優雅に生活できる者から下働きまでランクがあったとは知りませんでした。
足を挫いた自分を一緒に連れてきてくれたじょごの分も出そうとするお吟の好意を断り下働きの最低ランクを希望したじょごは、根っから働くことが性に合ってる感じ。火傷を治療してくれた信次郎とは薬草集めを通じて互いに好意を抱くようになっていきます。 渓流のあちら側とこちら側でこっそり顔を合わせる二人の様子は初心な恋人たちのよう
渓流のあちら側とこちら側でこっそり顔を合わせる二人の様子は初心な恋人たちのよう 見つかればえらいことになるのですがねぇ
見つかればえらいことになるのですがねぇ
駆け込んだ時には柏屋の吟味にまともに話もできずに口ごもるじょごでしたが、信二郎や薬草との出会いが彼女を逞しく自分の意思をはっきり持った女性に変えていったのね。
寺には他にも夫を殺したゴロツキに無理やり妻にされた女侍のゆう(内山理名)や、吉原から逃げ出すために姉夫婦を巻き込んだ大芝居を打ったおせん(玄里)など大勢の女たちが暮らしています。
寺の中には男性は原則として入れませんが、医者は別。でも診察は直接肌に触れてはいけないとか目を合わせてはいけないとか、その辺の事情を映画ではコミカルに描いています。演じているのが大泉さんですからその効果は絶大
おゆき(神野三鈴)が想像妊娠で腹が膨らんだ時には、その原因を推理し理路整然と説き聞かせてこれを直すあたりは立派な名医です
寺を潰す口実を見つけるため鳥居が送った間者は、院代の法秀尼(陽月華)の隠し部屋にあった禁書を見つけて、隠れキリシタンとして苦しんできた身の置き所を見つけ寝返るの もっと騒動があるのかと身構えていた割には、あっさり終わってしまった感がありました。
もっと騒動があるのかと身構えていた割には、あっさり終わってしまった感がありました。 尤もこの数年で老中や鳥居は失脚するし、歴史としても東慶寺は残っているのですからこれ以上広げられなかったのかな
尤もこの数年で老中や鳥居は失脚するし、歴史としても東慶寺は残っているのですからこれ以上広げられなかったのかな
実はお吟は自分が治らない病気と悟り、愛する男に最期を見られたくないという矜持から駆け込みをしたということが明らかになっていきます。それを知らない堀切屋は、信二郎を捕まえてお吟の意図を探ろうとするのですが、彼女の本心を聞かされて・・・彼の素性は大泥棒で、町奉行の鳥居(北村有起哉)から目を付けられているという伏線もあるのですが、質素倹約を押し付ける権力者に抗う町人の代表のような扱いで、ちょっとカッコ良すぎだぞ~堤さん
宿下がりしていたお吟が息を引き取った時、柏屋の門口で念仏を唱えていたのは、間違いなく堀切屋 この二人は愛しているが故に添い遂げられない悲しさを背負っていました
この二人は愛しているが故に添い遂げられない悲しさを背負っていました
一方、なまじ腕が立つだけに厄介なのはゆうの夫。前夫の敵討ちのために弓や薙刀の稽古を積んだゆうが、二年が経って仇討より静かに暮らすことを希望したのと対照的に、夫は無理やり連れ戻そうと暴れます。それを抑えようとして結果的に仇討を成したゆうに心の中で でした。
でした。
じょごの夫の重蔵(武田真治)は、二年の間に改心して仕事にも身を入れる男になっていました。詫びて復縁を願う重蔵でしたが彼女の心は決まっていました。長崎に医者の修行に行くという信二郎に、すでに立派な医者なのだから、今なすべきは劇作者として江戸に行くことだと諭すじょごが頼もしい!!信二郎が憧れる八犬伝の作者・馬琴(山崎努)を昔祖父が助けた縁でじょごと繋がりがあるという設定からは、江戸に戻った二人が身を寄せるのが馬琴宅であることが自然な流れとして受け入れられます。
鎌倉にある東慶寺は、江戸幕府公認の駆込み寺だった。離縁を望む妻がここに駆け込めば問題解決に向け動く拠り所だった。駆け込んだからといってすぐには入れず、まずは御用宿で仔細の聞き取りがされる。御用宿の柏屋に居候する劇作者に憧れる見習い医者の信次郎(大泉洋)は、柏屋の主人・源兵衛(樹木希林)とともに、離婚調停人よろしく、口八丁手八丁、奇抜なアイディアと戦術で男と女のもつれた糸を解き放ち、ワケあり女たちの再出発を手助けしていく。
劇作家・井上ひさしが晩年に11年をかけて執筆した時代小説「東慶寺花だより」の映画化です。
昔、グレープの「縁切寺」という曲で東慶寺を知った身にはなんだか懐かしいような気持ちになり選択

質素倹約例が発せられた江戸時代後期が舞台。
日本橋の豪商・堀切屋三郎衛門(堤真一)の愛人お吟(満島ひかり)は夫の身上に不信感を持ち東慶寺に駆け込む途中で夫の暴力から逃げ出してきた鉄練りの女じょご(戸田恵梨香)と出会って共に駆け込みを果たします。この時追っ手を間違えて信次郎に下駄をぶつけちゃうんですね~
 (じょごの顔は鉄練りの際の火ぶくれで醜くなっていますが、信次郎の薬で綺麗に治ります。)
(じょごの顔は鉄練りの際の火ぶくれで醜くなっていますが、信次郎の薬で綺麗に治ります。)この信二郎、江戸で騒ぎを起こして(お上に楯突く発言をして)親戚を頼って逃げ込んだのですが、叔父と思っていた源兵衛さんは女性だった、というところから笑いが起こります。権力を笠にきる連中が嫌いというのは甥とよく似ているね
 番頭の利平(木場勝巳)やその妻お勝(キムラ緑子)との掛け合いも楽しく、おせんを取り戻そうと押しかけてきたヤクザ相手に信二郎が得意の弁舌で煙に巻くエピソードも
番頭の利平(木場勝巳)やその妻お勝(キムラ緑子)との掛け合いも楽しく、おせんを取り戻そうと押しかけてきたヤクザ相手に信二郎が得意の弁舌で煙に巻くエピソードも です。
です。ただ、少し早口で進む会話はときに聞き取りにくい部分もあったのがちょっと残念かも

東慶寺に入るにも持参金により優雅に生活できる者から下働きまでランクがあったとは知りませんでした。

足を挫いた自分を一緒に連れてきてくれたじょごの分も出そうとするお吟の好意を断り下働きの最低ランクを希望したじょごは、根っから働くことが性に合ってる感じ。火傷を治療してくれた信次郎とは薬草集めを通じて互いに好意を抱くようになっていきます。
 渓流のあちら側とこちら側でこっそり顔を合わせる二人の様子は初心な恋人たちのよう
渓流のあちら側とこちら側でこっそり顔を合わせる二人の様子は初心な恋人たちのよう 見つかればえらいことになるのですがねぇ
見つかればえらいことになるのですがねぇ
駆け込んだ時には柏屋の吟味にまともに話もできずに口ごもるじょごでしたが、信二郎や薬草との出会いが彼女を逞しく自分の意思をはっきり持った女性に変えていったのね。

寺には他にも夫を殺したゴロツキに無理やり妻にされた女侍のゆう(内山理名)や、吉原から逃げ出すために姉夫婦を巻き込んだ大芝居を打ったおせん(玄里)など大勢の女たちが暮らしています。
寺の中には男性は原則として入れませんが、医者は別。でも診察は直接肌に触れてはいけないとか目を合わせてはいけないとか、その辺の事情を映画ではコミカルに描いています。演じているのが大泉さんですからその効果は絶大

おゆき(神野三鈴)が想像妊娠で腹が膨らんだ時には、その原因を推理し理路整然と説き聞かせてこれを直すあたりは立派な名医です

寺を潰す口実を見つけるため鳥居が送った間者は、院代の法秀尼(陽月華)の隠し部屋にあった禁書を見つけて、隠れキリシタンとして苦しんできた身の置き所を見つけ寝返るの
 もっと騒動があるのかと身構えていた割には、あっさり終わってしまった感がありました。
もっと騒動があるのかと身構えていた割には、あっさり終わってしまった感がありました。 尤もこの数年で老中や鳥居は失脚するし、歴史としても東慶寺は残っているのですからこれ以上広げられなかったのかな
尤もこの数年で老中や鳥居は失脚するし、歴史としても東慶寺は残っているのですからこれ以上広げられなかったのかな
実はお吟は自分が治らない病気と悟り、愛する男に最期を見られたくないという矜持から駆け込みをしたということが明らかになっていきます。それを知らない堀切屋は、信二郎を捕まえてお吟の意図を探ろうとするのですが、彼女の本心を聞かされて・・・彼の素性は大泥棒で、町奉行の鳥居(北村有起哉)から目を付けられているという伏線もあるのですが、質素倹約を押し付ける権力者に抗う町人の代表のような扱いで、ちょっとカッコ良すぎだぞ~堤さん

宿下がりしていたお吟が息を引き取った時、柏屋の門口で念仏を唱えていたのは、間違いなく堀切屋
 この二人は愛しているが故に添い遂げられない悲しさを背負っていました
この二人は愛しているが故に添い遂げられない悲しさを背負っていました
一方、なまじ腕が立つだけに厄介なのはゆうの夫。前夫の敵討ちのために弓や薙刀の稽古を積んだゆうが、二年が経って仇討より静かに暮らすことを希望したのと対照的に、夫は無理やり連れ戻そうと暴れます。それを抑えようとして結果的に仇討を成したゆうに心の中で
 でした。
でした。じょごの夫の重蔵(武田真治)は、二年の間に改心して仕事にも身を入れる男になっていました。詫びて復縁を願う重蔵でしたが彼女の心は決まっていました。長崎に医者の修行に行くという信二郎に、すでに立派な医者なのだから、今なすべきは劇作者として江戸に行くことだと諭すじょごが頼もしい!!信二郎が憧れる八犬伝の作者・馬琴(山崎努)を昔祖父が助けた縁でじょごと繋がりがあるという設定からは、江戸に戻った二人が身を寄せるのが馬琴宅であることが自然な流れとして受け入れられます。