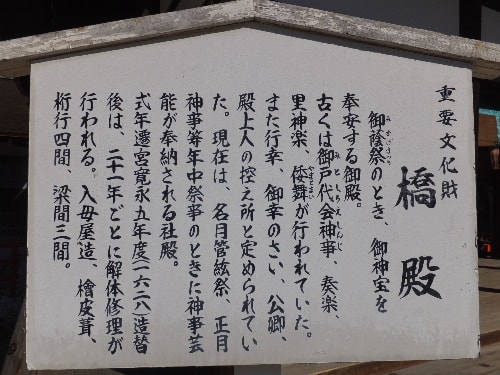今日は阿倍野ハルカスで東芝の商談会があるので、
国道25号線を走る。
偶然、大念佛寺の真横で赤信号で停まったら、
本堂の屋根が見えた。
吸い寄せられるかのように車は寺へ向かったのであった。(笑)
こちらは約3年半振りの参拝となります。
【山門】

【本堂】

相変わらず立派な本堂です。
ちょうど本堂内で納骨の法要が行われていて、
御本尊の厨子が御開帳されました。
今日は時間が無かったので本堂のみ参拝しましたので、
詳しくは2011年7月30日のブログをご確認ください。
決して手抜きではない。(笑)
<2011月7月30日>
http://blog.goo.ne.jp/05100625/e/1bb7badb4da49caae397a405f2ceb3d7
【御朱印】

【阿倍野ハルカス遠望】


ハルカス30階から見た大阪の街並み。
それにしても緑が少ないですね。

天王寺公園の辺りは緑がありました。
【キューズモール】

ここでよくアイドルさんのイベントが行われているようです。
もうここで充分な高さなんで、
高いお金を払ってまで最上階まで登ることは無いでしょう。(笑)
国道25号線を走る。
偶然、大念佛寺の真横で赤信号で停まったら、
本堂の屋根が見えた。
吸い寄せられるかのように車は寺へ向かったのであった。(笑)
こちらは約3年半振りの参拝となります。
【山門】

【本堂】

相変わらず立派な本堂です。
ちょうど本堂内で納骨の法要が行われていて、
御本尊の厨子が御開帳されました。
今日は時間が無かったので本堂のみ参拝しましたので、
詳しくは2011年7月30日のブログをご確認ください。
決して手抜きではない。(笑)
<2011月7月30日>
http://blog.goo.ne.jp/05100625/e/1bb7badb4da49caae397a405f2ceb3d7
【御朱印】

【阿倍野ハルカス遠望】


ハルカス30階から見た大阪の街並み。
それにしても緑が少ないですね。

天王寺公園の辺りは緑がありました。
【キューズモール】

ここでよくアイドルさんのイベントが行われているようです。
もうここで充分な高さなんで、
高いお金を払ってまで最上階まで登ることは無いでしょう。(笑)