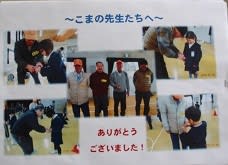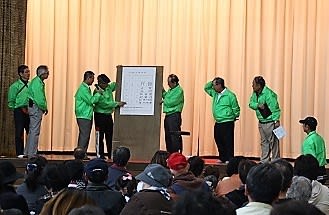ビフォー アフター
「運命の7月」などとはちょっと大袈裟だな~ と思いながら書いて来た地域活動「瀬戸内海環境保全大作戦」。
西日本を襲った豪雨によって、錦川の上流から流れ出た大木や竹などの長尺物。その量は半端ではない。
これを毎年の恒例事業としてボランティ参加を募り、海岸清掃作業を行う主催者側の一人としては、ただただ無事終了を祈って、神頼み仏頼みをしたくなる活動の一つではある。
大雨による大量の漂着物に加えて、連日連夜の猛暑酷暑。午前7時とは言え、今年の暑さはまさしく「念力がゆるめば死ぬる暑さかな」。
何が何でも熱中症で救急搬送などを出してはならない。この至上命題を胸に「安全に妥協無し」を叫び対策に熱中した。
7月16日「海の日」午前7時。子供から大人まで、今年も約600人の参加を得た。
言うに及ばず朝早くても日差しは強い。そんな中約90分の作業で約8.5㌧という大量の漂着物を回収した。
そんな成果を挙げる中で、終わってみれば誰一人熱中症状も見せず、小さなケガの一つもなく無事終了。これは有り難かった。
プロボラ(プロフェッショナルボランティア)看護師さん3名で救護班を設置。ベッドを備え、AEDも置いた。
地形の関係で、いざという時の救急搬送は漁船による海上輸送に頼るしかない。そこで一隻の漁船はゴミの搬送はせずに、パトロール専用に回した。給水所も昨年の倍に増やし、冷たい水の他、塩飴や経口補水液も設置した。言うなれば熱中症対策のおまじないの品々である。
周到な準備と言えるかどうか定かではないが、あらゆる準備はしたつもり。その結果が完璧な無事終了につながったとすれば、事前にあれこれ声を上げた役回りも救われたというものである。枕を高く、何日ぶりかの高いびきであったような(笑)
中学生と教職員で200人。高校生、小学校の教職員、児童保護者。米軍岩国基地から屈強な海兵隊員、官公庁や企業からの団体参加そして、何より地元の人たちの熱い協力体制等々。
中には、地元の少年ソフトボールチームの男女がユニフォーム姿で参加して、周囲の微笑みを誘う。
誰かがやらなきゃならないことを誰かがやる。単純にそう思いみんなで力を出し合う地域活動。
周到な準備と優しい声かけ、時々無理なお願い。そんな繰り返しで、地域はゆっくりと動いていくのかもしれないね~。
兎に角、皆さんのやる気とパワーで、あれほど大量であった海岸漂着物があっと言う間にきれいな砂浜に戻った。まさにビフォー・アフター、見て頂いた通り。そして執行部の一人として、大いに心配したビフォー・アフター無事終えてホッと一息。さー次の計画が・・・。