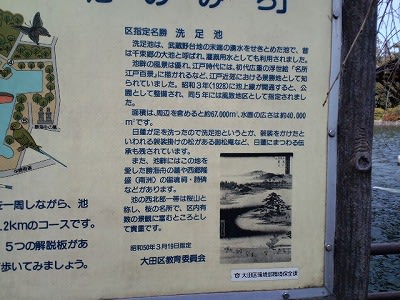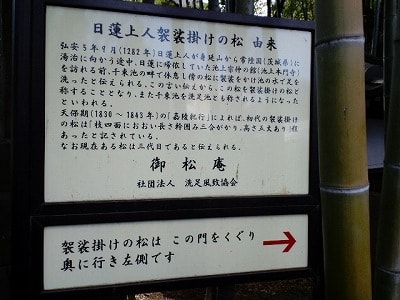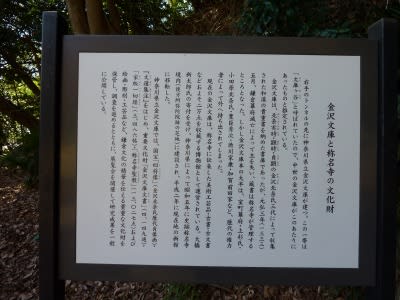小石川後楽園 @文京区後楽一丁目



江戸時代初期、寛永6年(1629年)に水戸徳川家の祖である頼房が、江戸の上屋敷の庭として造ったもので、二代藩主の光圀の代に完成した庭園。
現在は、東京ドームに隠れてしまったような存在だが、水戸藩の上屋敷はドームの場所も含め広大な敷地だった。
池を中心にした「回遊式泉水庭園」で、随所に中国の名所の名前をつけた景観を配し、中国趣味豊かなものになっている。

シダレザクラ
門を入って直ぐ、池の傍。

得仁堂
光圀が創建した時代の建物で、残っているのはこれだけ。
伯夷、叔斉の木像を安置した堂。
得仁堂の名前は孔子が伯夷・叔斉を評して「求仁得仁」と語ったことによる。

円月橋
明の儒学者朱舜水が設計したといわれる石橋。
石工は日本人だが、中国の様式を良く伝えている。


護岸工事が進行中
創建以来の池の石垣の損傷が激しく、修復工事が進んでいる。

西行堂跡



江戸時代初期、寛永6年(1629年)に水戸徳川家の祖である頼房が、江戸の上屋敷の庭として造ったもので、二代藩主の光圀の代に完成した庭園。
現在は、東京ドームに隠れてしまったような存在だが、水戸藩の上屋敷はドームの場所も含め広大な敷地だった。
池を中心にした「回遊式泉水庭園」で、随所に中国の名所の名前をつけた景観を配し、中国趣味豊かなものになっている。

シダレザクラ
門を入って直ぐ、池の傍。

得仁堂
光圀が創建した時代の建物で、残っているのはこれだけ。
伯夷、叔斉の木像を安置した堂。
得仁堂の名前は孔子が伯夷・叔斉を評して「求仁得仁」と語ったことによる。

円月橋
明の儒学者朱舜水が設計したといわれる石橋。
石工は日本人だが、中国の様式を良く伝えている。


護岸工事が進行中
創建以来の池の石垣の損傷が激しく、修復工事が進んでいる。

西行堂跡