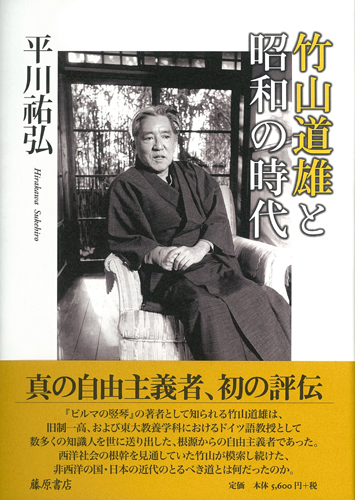「日本美術院の作家たちと五浦の風景」@水戸市立博物館


図書館に『ヘンな日本美術史』を借りに行って、博物館に立ち寄った。
天心・波山記念事業関連展示として、「日本美術院の作家たちと五浦の風景」と題する展示が行われていた。

隣の部屋では、その人たちに関連する作家の展示も在った。


その中に、小又光さんの「五浦海岸」と題する作品もあった。
小又光(おまたひかる・1919-1978)は創元会会員で日本舞踊の踊り子などを描いた画家で、骨董愛好家だった。
お宅には何度もお邪魔して話蒐集談を伺ったり、トランプゲームに興じたことがあった。
1973年没とあったから、40年も前の出来事か。
それほど昔のこととは思われない。
友人のUさん宅を訪ねる際、旧居の脇を通る。
今では更地となってしまい、コスモスの花が咲いているが、当時は趣味を凝らした素晴らしい住まいで、この様な家に住みたいと憧れた。


図書館に『ヘンな日本美術史』を借りに行って、博物館に立ち寄った。
天心・波山記念事業関連展示として、「日本美術院の作家たちと五浦の風景」と題する展示が行われていた。

隣の部屋では、その人たちに関連する作家の展示も在った。


その中に、小又光さんの「五浦海岸」と題する作品もあった。
小又光(おまたひかる・1919-1978)は創元会会員で日本舞踊の踊り子などを描いた画家で、骨董愛好家だった。
お宅には何度もお邪魔して話蒐集談を伺ったり、トランプゲームに興じたことがあった。
1973年没とあったから、40年も前の出来事か。
それほど昔のこととは思われない。
友人のUさん宅を訪ねる際、旧居の脇を通る。
今では更地となってしまい、コスモスの花が咲いているが、当時は趣味を凝らした素晴らしい住まいで、この様な家に住みたいと憧れた。