中谷宇吉郎の森羅万象帖 展@LIXILギャラリー


東京には大学や企業の運営する美術館や博物館やギャラリーが沢山ある。
それぞれ独自の視点で蒐集・運営されている。
入場料も無料か或いは心づけ程度の値段だから有り難い。
中央区京橋の「INAXギャラリー」が改装され「LIXILギャラリー」と名前も変った。
これまでも、陶器、絵画、彫刻、映像表現と多様な企画展や、斬新な作品が紹介されてきた。新たになっても、これまでの運営方針は変わらないようだ。
散歩のついでに立ち寄るには格好の場所だ。
鹿島アントラーズの胸のロゴ「LIXIL」の会社で、トステム・INAX・ 新日軽・
.サンウエーブ等住まいと暮らしのトップブランドが一つになって生まれた会社とのことだが、専門外だから詳しくは分からないが、鹿島の応援をはじめとして発展することを期待している。
「雪は天から送られた手紙である」という有名な言葉で知られる科学者・中谷宇吉郎(1900~62年)自然現象を捉えた写真、スケッチ、科学映画など宇吉郎や彼の研究室が残した貴重な資料が展示されている。
火花放電や雪の結晶など、当時のカメラでよく撮影できたと思う映像が張り付けられた研究ノートが沢山展示されている。
研究の内容は理解できなくとも、中谷宇吉郎の科学に対する姿勢や自然に対する眼差しをくみ取れ、ただ、感心するばかりだった。


東京には大学や企業の運営する美術館や博物館やギャラリーが沢山ある。
それぞれ独自の視点で蒐集・運営されている。
入場料も無料か或いは心づけ程度の値段だから有り難い。
中央区京橋の「INAXギャラリー」が改装され「LIXILギャラリー」と名前も変った。
これまでも、陶器、絵画、彫刻、映像表現と多様な企画展や、斬新な作品が紹介されてきた。新たになっても、これまでの運営方針は変わらないようだ。
散歩のついでに立ち寄るには格好の場所だ。
鹿島アントラーズの胸のロゴ「LIXIL」の会社で、トステム・INAX・ 新日軽・
.サンウエーブ等住まいと暮らしのトップブランドが一つになって生まれた会社とのことだが、専門外だから詳しくは分からないが、鹿島の応援をはじめとして発展することを期待している。
「雪は天から送られた手紙である」という有名な言葉で知られる科学者・中谷宇吉郎(1900~62年)自然現象を捉えた写真、スケッチ、科学映画など宇吉郎や彼の研究室が残した貴重な資料が展示されている。
火花放電や雪の結晶など、当時のカメラでよく撮影できたと思う映像が張り付けられた研究ノートが沢山展示されている。
研究の内容は理解できなくとも、中谷宇吉郎の科学に対する姿勢や自然に対する眼差しをくみ取れ、ただ、感心するばかりだった。














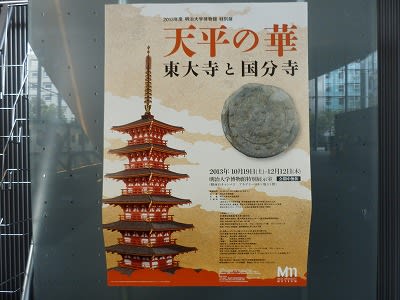

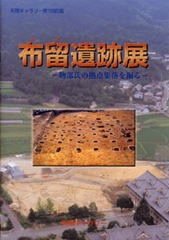

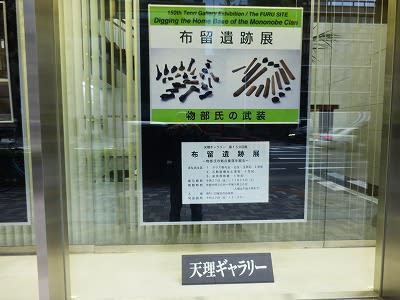


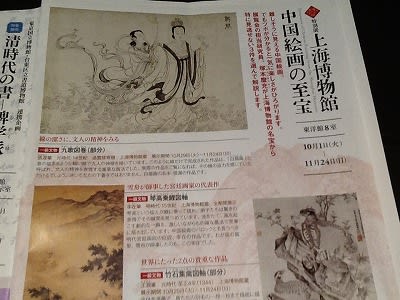






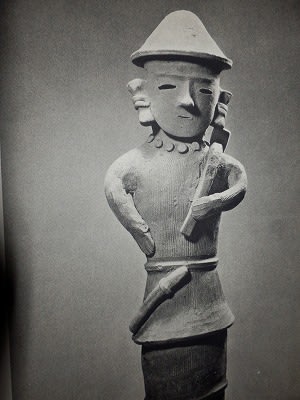
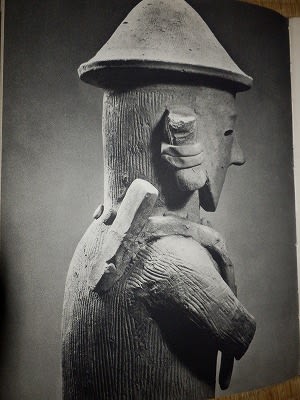
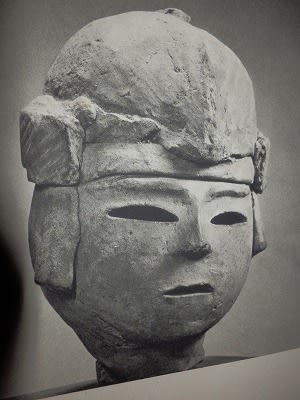
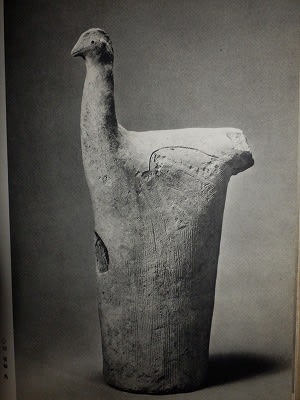

















![コラボTシャツ2013[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2e/44/fe5881f7f6b1d77f2be64249284796e9.jpg)























