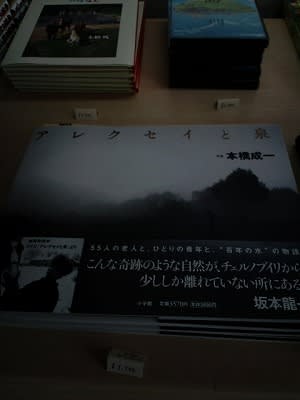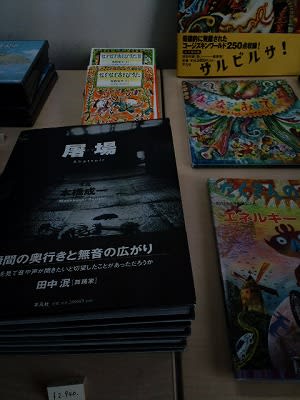本橋 成一さん @ギャラリー・しえる

「スズキコージさんが僕の事務所にあらわれ、チェルノブイリノ写真お借りできますか?と言うことで渡したら、徹底的に切り刻まれまして。作者としては、つらい出来事でしたが、出来上っ作品を見て、良かったな、と思いました。」
と本橋 成一さんは話し始めた。
それから1時間以上、ロシアでの体験を話された。
終了後、何かいくらい訪れたのですか、とのし質問に30回以上と思います。
とのこと「初めの数回は、とても写真など写す心境になれなかった」抗がん剤で頭の毛が失われてしまった少女に対面すれば、自分がしたことではなくとも責任を感じてしまった。と体験の一端を語った。
その後の話は、感動的。
とても、僕の言葉では表現しようも無い。
戻ってからネットで検索したら、以下のような方、
世の中にはすごい人がいるものだと思った。
1963年 自由学園卒業。東京綜合写真専門学校入学。
1965年 筑豊文庫の上野英信を訪ね、その後 九州・北海道の炭鉱の人々を撮り始める。
1965年 報道写真家岡村昭彦と出会い1年半アシスタントをする。岡村の代わりに連絡係としてベトナムに赴く。
1968年 作品「炭鉱〈ヤマ〉」で、第5回太陽賞受賞。
1971年 『太陽』の仕事でユーラシア大陸を6ヶ月かけて横断する。
1972年 色川大吉『ユーラシア大陸思索行』でデンマーク、オーストリア、ギリシャ、トルコ、インドなどを撮影。
1972年 小沢昭一『諸國藝能旅鞄』(写真/本橋成一)6回連載。
1973年 フジテレビ『動物家族』のムービーカメラマンとして羽仁進と9ヶ月間東アフリカに滞在。
1974年 仲間と共同事務所JPU(ジャーナリスティック・フォトグラファー・ユニオン)を構える。
1976年 小沢昭一編集『藝能東西』の仕事で初めてサーカスを撮る。
1977年 日産自動車新聞広告の仕事で再びユーラシア大陸を3ヶ月で横断。
1980年 上野駅を撮り始める。個展『サーカスの時間』(新宿・ニコンサロン)写真集『サーカスの時間』(筑摩書房)刊行。
1983年 写真集『上野駅の幕間』(現代書館)刊行。
1985年 画家丸木位里・丸木俊のスライド集『ひろしまを見たひと』(監督・土本典昭)の作品を撮影。
1987年 独立して「ポレポレ坐」を立ち上げる。
1988年 写真集『魚河岸 ひとの町』(晶文社)刊行。
1989年 立松和平に同行して、パリ・ダカールラリーを撮影する。
1990年 『砂の水平線』共著・立松和平(平凡社)刊行。正式に事務所「ポレポレタイムス社」を設立。
1991年 チェルノブイリ原発とその被災地ベラルーシに通い始め、汚染地域で暮らす人々を撮影。
1993年 写真絵本『チェルノブイリからの風』(影書房)刊行。写真集『サーカスの詩』(影書房)刊行。
1994年 写真集『無限抱擁』(リトル・モア)刊行。
1995年 写真集『無限抱擁』で日本写真協会年度賞、写真の会賞を受賞。
1998年 写真集『ナージャの村』で第17回土門拳賞受賞。ドキュメンタリー映画『ナージャの村』を初監督。 ベルリン国際映画祭に出品。
2002年 二作目映画『アレクセイと泉』で52回ベルリン国際映画祭にてベルリナー新聞賞及び国際シネクラブ賞受賞。第12回サンクトペテルブルク映画祭でグランプリなど受賞多数。
2002年 雑誌の連載で開戦前のイラク国内を旅する。翌年『イラクの小さな橋を渡って』(池澤夏樹との共著)を緊急刊行。
2003年 毎日新聞にて“生命の旋律”を一年間連載し、翌年、写真集『生命の旋律の旋律~本橋成一が撮る人間の生き様集~』を刊行。
2006年 歌と三線一本で流浪の人生を送ってきた石垣島のおばあを描いた映画『ナミイと唄えば』を公開。
2007年 徳山ダムに沈んだ岐阜県徳山村に最後まで住み続けた村人たちの暮らしを15年追った映画「水になった村」を初プロデュース。
2009年 ドキュメンタリー映画『バオバブの記憶』公開。
2010年 プロデュース作品『祝の島』公開。
2010年 個展『昭和藝能東西』(銀座・ニコンサロン)写真集『昭和藝能東西』(オフィスエム)刊行

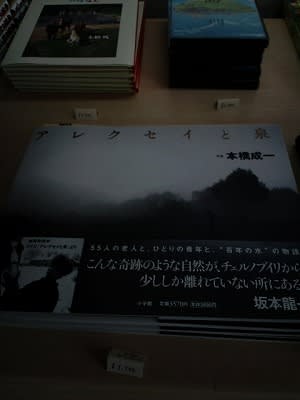
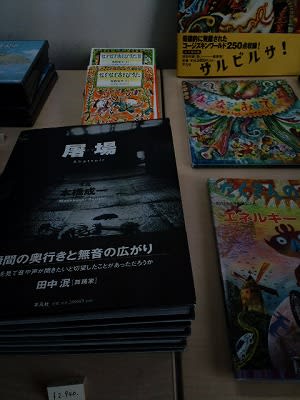
写真集
『炭鉱〈ヤマ〉』1968年(現代書館)
『サーカスの時間』1980年(筑摩書房)
『上野駅の幕間』1983年(現代書館)
『ふたりの画家 丸木位里・丸木俊の世界』1987年(晶文社)
『魚河岸 ひとの町』1988年(晶文社)
『サーカスが来る日』1989年(リブロポート)
『老人と海』1990年(朝日新聞社)
『サーカスの詩』1993年(影書房)
『無限抱擁』1995年(リトル・モア)
『ナージャの村』1998年(平凡社)
『アレクセイと泉』2002年(小学館)
『生命(いのち)の旋律~本橋成一が撮る人間の生き様集~』2004年(毎日新聞社)
『バオバブの記憶』2009年(平凡社)
『昭和藝能東西』2010年(オフィスエム)
『屠場』2011年(平凡社)
単行本
『パリのお菓子屋さん』共著・山本益博 1980年(文化出版局)
『砂の水平線』共著・立松和平 1990年(平凡社)
『砂の旅人』共著・立松和平 1993年(駸々堂)
『ナージャ希望の村』2000年(学習研究社)
『イラクの小さな橋を渡って』共著・池澤夏樹
写真絵本
『チェルノブイリからの風』1993年(影書房)
『アレクセイと泉のはなし』2004年(アリス館)
文庫
『サーカスがやってくる』共著・西田敬一 1982年(旺文社)
映画
『ナージャの村』1997年(監督)
『アレクセイと泉』2002年(監督)
『ナミイと唄えば』2006年(監督)
『水になった村』2007年(プロデューサー)監督・大西暢夫
『バオバブの記憶』2009年(監督