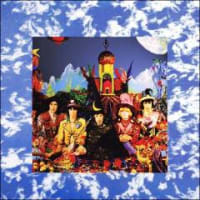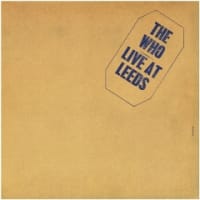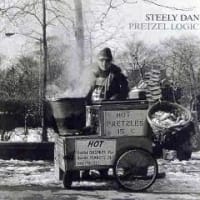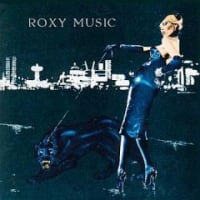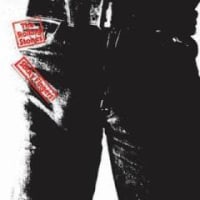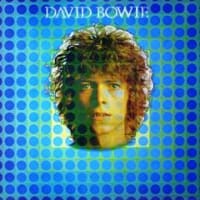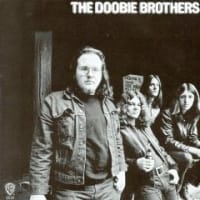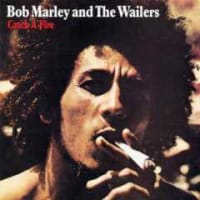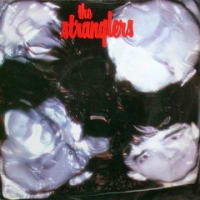1983年という年は、1967年や1977年ほどではないが色々な意味でポップミュージックの転換年でもあった。特にロック音楽に関していえば1977年に起こったロンドンパンクを皮切りにしたポスト・パンクとニューウェーブのムーブメントが、略、終焉した年でもあった。だが、新たなる出発をロックという領域でスタートさせた年でもあった、前者の代表がポリスの「シンクロニシティー」で、後者の代表がU2の「WAR~闘」であろう。しかし、私にとっては前者の影響はものすごく大きい。1982年に既にジャムが解散していたし、ポリスも実はこの作品を出した時点では解散を表明していなかった。しかし(結果論で申し訳ないが)私は、これ以上ポリスというバンドがニューウェーブ・ロックという領域で何かやることがあるのだろうかと思ってしまうほど、当時の彼ら、及び、彼らを取り巻くポップミュージックの世界では最高の出来であったといえよう。また、ポール・ウェラーのジャム解散後の動きはスティングを十二分に刺激してしまうであろうという事も・・・。そんな年の翌年、このプリンスの新作はなんとサウンド・トラック盤として発売になった。実は私はこの作品が発売された当時は、私が注目してきたプリンスが一挙にこんなに世間に認められ大ヒットしてしまってとても嬉しいという反面、プリンスをデビュー以来ずっと注目してきた音楽ファンの一人としては、なんでこんなにヒットしてしまうのだよという複雑なファン心理であったし、少なくとも「ダーティーマインド」、「戦慄の貴公子」がプリンスの一番面白い時代なんだよって一人で知ったかぶりをして、無論レコードも買ったし映画もみたが、この当時はあまりこの作品に関してはそこそこの出来だという簡単な評価、及び「随分ロック寄りになったなぁ」という感じでそれ以上のものを探求しなかったが、最近それが大きな誤りだったと気がついた。
前作「1999」のレビューでも書いたが、プリンスはこのソウル音楽の変革時にヒップ・ホップを選ばなかった。それは恐らくリリックの面白さは既に実績があるという自負があったに違いない。一方で、ロックはニューウェーブが終わった一方で空洞化になりつつあった。アメリカのロックには既に聴くべき価値もあるものは何一つなかったが、頼りのイギリスも本来のロックは鳴りを潜め、ギターロックへ回帰するミュージシャンが続々と出始めたが、前述のU2の如く、ロンドンではなくアイルランドで政治的にも問題意識を掲げた連中はその思いを音楽に込め、ロック音楽が一面的に持っていたメッセージ性を強く打ち出すことでファンに応えていったのである。プリンスも全く同じでそういうファンの受け皿になっていった。だからロックとファンクの融合から更にロックなっていった。だが、この作品の中でとても面白いのがバラッド曲である。”The Beautiful Ones”やタイトル曲でもある”Purple Rain”などは、実はロックではなくソウルのバラッド(というか正しい音楽分類でいうとバラード)なのである。ここは最近になって注目し、聴きこんでわかった部分である。この辺りは流石に黒人ミュージシャンで、自身が培ったルーツは簡単には変えられないということであるし、また、意図的に彼は黒人音楽の誇りを残したというのが正答かもしれない。個人的にはこのバラードを聴いて、プリンスに残っている根本的なソウル音楽の支柱に関して安堵したし、それは私だけではなかった筈だ。
この作品は前述の様にサウンド・トラック(といっても全編にわたりプリンス&ザ・レボリューションの演奏しか入っていないが)盤ということもあってか、この時点ではプリンスがロックとファンクを融合させ可也ロックよりになったことに関してはこの作品だけかもしれないという憶測が流れた(私はそうは思わなかったが)。そしてその回答は意外に早く翌年発表の新作で解明される。うーん、やはり次作のレビューも書かなくては終わらないな・・・。
こちらから試聴できます。