表題の2語、ご存知の方も多いと思いますが、
漢字で表した数の単位で、無量大数は最大、涅槃寂静は最小です。
大きい数の方は、
一、十、百、千、万、億、兆、京(けい)、垓(がい)、𥝱(秭)(じょ)、穣(じょう)、
溝(こう)、澗(かん)、正(せい)、載(さい)、極(ごく)、恒河沙(こうがしゃ)、
阿僧祇(あそうぎ)、那由他(なゆた)、不可思議(ふかしぎ)、
そして無量大数(むりょうだいすう)となり、21単位あります。
次の単位への上がり方について、
時代によって万で進む場合と万万で進む場合がありましたが、
現在は万進方で落ち着いています。
1無量大数は、10の68乗となります。
0を68個書かなければならないのですが、長くなりますから止めておきます^^
具体的な例として使うと、
太陽の質量は、約198穣kg、天の川銀河の直径は約9垓4600京mになります。
小さい方の数は、
分、厘、毛、糸、忽(こつ)、微(び)、繊(せん)、沙(しゃ)、塵(じん)、埃(あい)、
渺(びょう)、漠(ばく)、模糊(もこ)、逡巡(しゅんじゅう)、須臾(しゅせ)、
瞬息(しゅんそく)、弾指(だんし)、刹那(せつな)、六徳(りっとく)、虚空(こくう)、
清浄(せいじょう)、阿頼耶(あらや)、阿摩羅(あまら)、
そして涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)となり、24単位あります。
次の単位への下がり方は、それぞれ0.1倍ですので、
1涅槃寂静は、10のマイナス24乗になります。
小数点以下、0を23個書かなくてはいけないので、これも省略します。
具体的には、
ウィルスの大きさは約2沙m、中性子の直径は約1須臾7瞬息mとなります。
望遠鏡も顕微鏡もなく、宇宙や物質の世界の知識もない時代に、
このような単位を考えた人の壮大な想像力を思うと、感嘆せずにはいられません。
漢字で表した数の単位で、無量大数は最大、涅槃寂静は最小です。
大きい数の方は、
一、十、百、千、万、億、兆、京(けい)、垓(がい)、𥝱(秭)(じょ)、穣(じょう)、
溝(こう)、澗(かん)、正(せい)、載(さい)、極(ごく)、恒河沙(こうがしゃ)、
阿僧祇(あそうぎ)、那由他(なゆた)、不可思議(ふかしぎ)、
そして無量大数(むりょうだいすう)となり、21単位あります。
次の単位への上がり方について、
時代によって万で進む場合と万万で進む場合がありましたが、
現在は万進方で落ち着いています。
1無量大数は、10の68乗となります。
0を68個書かなければならないのですが、長くなりますから止めておきます^^
具体的な例として使うと、
太陽の質量は、約198穣kg、天の川銀河の直径は約9垓4600京mになります。
小さい方の数は、
分、厘、毛、糸、忽(こつ)、微(び)、繊(せん)、沙(しゃ)、塵(じん)、埃(あい)、
渺(びょう)、漠(ばく)、模糊(もこ)、逡巡(しゅんじゅう)、須臾(しゅせ)、
瞬息(しゅんそく)、弾指(だんし)、刹那(せつな)、六徳(りっとく)、虚空(こくう)、
清浄(せいじょう)、阿頼耶(あらや)、阿摩羅(あまら)、
そして涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)となり、24単位あります。
次の単位への下がり方は、それぞれ0.1倍ですので、
1涅槃寂静は、10のマイナス24乗になります。
小数点以下、0を23個書かなくてはいけないので、これも省略します。
具体的には、
ウィルスの大きさは約2沙m、中性子の直径は約1須臾7瞬息mとなります。
望遠鏡も顕微鏡もなく、宇宙や物質の世界の知識もない時代に、
このような単位を考えた人の壮大な想像力を思うと、感嘆せずにはいられません。














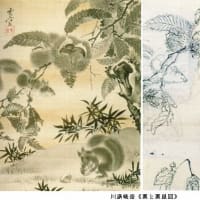







多分中国の人が付けたのだと思いますが、
壮大な感覚の持ち主だったのかも知れませんね。
最後が涅槃寂静なのも仏教の世界観なのでしょうね。
なるほど。
確かに発祥の地はインドだったかも知れませんね。
そのようなスケールの大きさを感じます。
釈迦も孔子もソクラテスも紀元前500年から400年位の間の人だったと思います。
人類の知能は、その頃が最高でそれ以降は進歩がない、
あるいは若干低下しているのではないかと聞いた事があります。
知識が増え過ぎているのかも知れませんね。
なるほど。
人間満腹だと、好奇心を失うのかも知れませんね。
ハングリー精神と言いますが、向上を目指すためには、ある程度の空腹は必要なのかも知れません。
現代のような情報過多の時代には、
ネットで簡単に調べられるので、それ以上進まないようにも感じています。
本当に調べるのには、やはり書物でないとダメかなとも思っています。
人間って分かっているもんなんですかね。
そうでしたか。
そこまで考えてみませんでしたが、やはり人間の英知なのでしょうかね。