玉音放送の約2週間後、GHQ最高司令官マッカーサーが、丸腰でコーンパイプを片手に専用機バターン号から日本に降り立った。その日から、日本人の心理状態は精神医学上極めて興味ある状況に陥る。バターン号とはマッカーサーが日本軍に惨敗したバターン半島での戦いとそれに続くバターン死の行進へマッカーサーの執念を物語ている。 マッカ―サーはフィリピンの戦闘で自分の戦歴に「敗北の屈辱」を与えた日本に、復讐のためやってきた。 二度と日本が立ち上がれないように、大日本帝国を解体するために。
だが戦時中、鬼畜米英と恐れられたアメリカ軍は意外と紳士的だった。
戦勝国の軍隊が敗戦国の住民に接する場合、略奪と女性への暴行は国により国民性に差が出てくる。
日ソ不可侵条約を踏みにじって満州に侵略したソ連兵の日本人に対する暴虐やベルリン陥落でソ連兵が行った女性への性的暴行は今でも語り草である。
その点、占領軍のアメリカ兵が日本の国民に接した対応は、比較的紳士的だった。 少なくとも、ソ連兵が満州で行った日本国民に対する乱暴狼藉にくらべたら、はるかに米兵は紳士的だった。(この原稿を書いている2022年のウクライナ戦争におけるロシア兵のウクライナ住民への虐殺行為を見れば夫々の国の国民性の違いを知るだろう。)
あくまでも比較の問題だが、日本を占領した軍隊がソ連兵ではなく、米兵であったことはラッキーと言えなくもない。
日本を占領した米兵は先ず、ガムとチョコレートで、子供たちの心を鷲づかみにした。
それだけではない。マッカーサーは、これまで日本には無いと思われていた「自由と民主主義」を手土産に持ってきた。
以後マッカーサーは、7年の間、占領下という閉鎖空間で日本人と共に暮らすこととなる。ここに日本人は、後に精神医学用語となる「ストックホルム症候群」を全国的に体験することになる。
ストックホルム症候群とは、1973年、ストックホルムで起きた銀行強盗による人質を盾にした銀行立てこもり事件に由来する。
4人の人質の犯人に対する複雑な人間の心理状態を指すための言葉で、人質は被害者であったにも関わらず長期間犯人と時間を共にすることによって、最終的には犯人に対して連帯感、親近感、同情を感じるようになる。 そして犯人逮捕の際彼らは感謝すべき警察を非難し、非難すべき犯人を支持した。この人質の心理状況が後にストックホルム症候群と言われるようになる。
米軍の日本占領時で例えれば、凶悪犯人は鬼畜と思った米軍の総大将マッカーサーであり、人質は敗戦国民の日本人、そして人質現場の銀行は、米軍占領下の日本にあたる。
見た目が強面で昔ヤンキーだったという男が、普通に接していても「優しい」と感じる心理状態も同じと考えられる。
「ストックホルム症候群」は特に「鉄の暴風」と呼ばれる地上戦の激しかった沖縄戦で顕著に現れた。
沖縄でも終戦を待たず米軍の捕虜になった人は価値観の逆転を味わった。
鬼畜のはずの米兵が食料を与え怪我人の治療をしてくれた。
敗戦直後、沖縄戦のバイブルと言われた『鉄の暴風』(沖縄タイムス刊)の初版には、米軍のヒューマニズムが賞賛された。
同書の序文にこうある。
「この動乱を通し、われわれが、おそらく終生忘れ得ないのは、米軍の高いヒューマニズムであった。 国境と民族を超えた彼らの人類愛によって、生き残りの沖縄人は生命を保護され、あらゆる支援を与えられて、更生第一歩を踏み出すことができた。 このことを特筆しておきたい」。(1950年版から一言の言及もなく削除されている)
たしかに、戦場の各所で、多くの住民が米軍に救出され、その救出劇を見た住民が米軍に暖かいイメージを抱いたとしても不思議ではない。 当時の沖縄住民は日本の敗残兵に見離され、米国の被保護者に転落していたのだから。
県民を守るはずの日本兵は、武器・弾薬を持たず食糧補給もままならず、無残な姿で逃げ回っていた。県民を壕から追い出して自決する日本軍は「敵」になった。少なくとも敵に見えた。この瞬間米軍は解放軍になった。
更に沖縄を日本から永久分断するための米軍の心理作戦、そしてそのため善意を強調する米軍との共同生活は、沖縄でも「人道的米軍」という心理状態に陥った。
この辺の複雑な心境を、後に「集団自決」の証人となった宮城晴美氏は次のように書き残している
≪米軍に保護された住民にとって、それまでの『兵隊さん』は、いつしか『日本兵』という“敵”に変わっていた。住民は、すっかり”親米派”になっていたのである。『お国のために』と信じ、日本軍と行動をともにしてきた私の母・宮城初枝も、大けがをして投降したものの、島の人たちからあらぬ噂をたてられ、日本軍に加担したとして批判の的にされていた。
戦争は終わった。しかし母にとっての”戦争”は終わらなかった。さまざまなできごとが戦後に尾を引き、母はその当事者になってしまうのである。≫
(宮城晴美著 「母の遺したもの」)
創業したのは奄美群島出身の故・元山嘉志富さん。
アメリカ統治下の沖縄には、米軍相手にひと山当てようと、沖縄の外からも大勢の人が集まり、基地の周辺は活況を呈していました。
元山さんもそうした1人で、故郷から親族や若手を呼び寄せ、従業員として雇いました。
 左側の白髪の男性が元山さん
左側の白髪の男性が元山さん
「ニューヨークレストラン」の経営は、すぐに軌道に乗りました。
元山さんに呼び寄せられた1人が、おいの徳富清次さん(77)。
2008年まで「ニューヨークレストラン」を経営しました。
沖縄に「アメリカンドリーム」を夢見て海を渡った当時、徳富さんはまだ小学生でした。
レストランで働き始めた徳富さんに任された仕事のひとつが、ステーキを焼くためのまき割り作業でした。
沖縄本島北部、深い森が広がる通称「やんばる」からトラックで運ばれてくる丸太を必死に割ってまきを作った作業が今でも忘れられない思い出だと言います。
憧れのライフスタイル
レストランで徳富さんが目の当たりにしたのは、豊かなアメリカ人の姿でした。
当時のコザの街はアメリカ兵であふれていました。
女性を連れ、毎晩のように店を訪れる兵士たちは、300グラムのステーキを勢いよくぺろりと平らげ、気前よく大量のドルを落としていきました。
店で売るハンバーガーも、サンドイッチも、コーラも、飛ぶように売れに売れました。
当時、立派な家が建つのに必要だった2000ドルを、たった1日で売り上げた日もあったというほど、街は好景気に沸いていました。
徳富さんの目に映る米兵はみな“紳士”でした。
「兵士が歩くときには必ずボタンをきっちり締めて、きれいな姿で歩く。飲みに行くときには、床屋で髪を整える。その頃の兵隊は、紳士だった」
戦時に作られた文書、写真等が国策、或いは軍の作戦に沿ったプロパガンダ的要素に満ちていることはよく知られている。
後世これらの文書や写真を検証する場合、これらがどのような意図を持って製作されたか、その背景を検証しないとせっかくの資料が時代を見誤る有害物にもなりかねない。
沖縄戦といえば、日本軍が住民を壕から追い出したとか、凄惨な集団自決に追いこんだとか住民を守らない残虐な日本軍のイメージが強調されて来た。
他方、「アメリカ軍は人道的であり、沖縄住民を残酷な日本軍から救うためにやって来た平和と民主主義の守護者、“解放者”である」かのような、アメリカが作った情報がまかり通ってきた。
■戦場カメラマンが同行した沖縄戦
アメリカ軍は沖縄侵攻作戦を、「アイスバーグ作戦」と名付け、それまでの太平洋戦争ではみられなかったカメラマン部隊を投入し、沖縄戦の様子を克明に記録している。
それらの記録映像には老女を壕から助け出したり、赤ん坊を抱いてミルクを飲ませたり或いは住民の負傷者に手当てをしているヒューマニズム溢れる米兵の姿を記録した。写っている米兵は気のせいかハンサムで体格のいい白人が多い。
実際に沖縄に上陸した米軍は白人、黒人それにフィリピン人や日系二世も混じっていたが、プロパガンダとして残す人道的米兵としてはハンサムな白人の若者が適役だったのだろう。
それらの映像記録は、未編集のまま米国国立公文書館に保存されているが、「1フィート運動の会」によってその大部分は収集されている。
だが、スチール写真等は、沖縄の米軍統治時代に「琉米親善」のプロパガンダに利用された。
米軍の従軍カメラマンの中には、有名なアーニーパイルも含まれていた。
彼の名は70歳代以上の人なら東京の「アーニーパイル劇場」として記憶にあるだろう。
だが、アーニーパイルは米軍占領下の沖縄で小学校時代を過ごした人なら、沖縄戦で日本兵の狙撃により非業の最期を遂げた英雄として学校で教えられていたのを思い出すだろう。
イメージとしては沖縄を解放しに来た“解放軍”の従軍記者が、侵略者・日本軍の狙撃により非業の戦死をしたという英雄物語である。

(沖縄の伊江島にあるアーニーパイル記念碑)
終戦当時ルーズベルト米大統領の名は知らなくともアーニーパイルの名は知っている小学生、中学生は沖縄には多数いたくらいだ。
アーニーパイルは第二次世界大戦に従軍記者として同行し、1944年にピューリッツァー賞を受賞するなど、第二次世界大戦期のアメリカの従軍記者を代表する存在の1人となったが、翌年4月に従軍先の沖縄県伊江島にて日本軍の機関銃から射撃を受け戦死した。遺体は一度現地に埋葬されたのち米軍基地に移され、1949年にハワイ・ホノルルの国立太平洋記念墓地に埋葬された。毎年4月18日に最期の地となった伊江村で慰霊祭が行われる。
戦後、日本を占領下においたGHQが東京宝塚劇場を接収した際、アメリカ軍の強い要望により「アーニー・パイル劇場」と名付けられた。
アメリカ軍統治時代の那覇の国際通りにも、米軍政府と琉球政府の協力で「アーニーパイル国際劇場」という映画館が建設された。「アーニーパイル国際劇場がある通り」から現在「国際通り」と呼ばれるようになった。
■マッカーサーの沖縄領土化計画と「太平洋の要石」
マッカサ―は沖縄をを本土と分離し、アメリカの領土にする計画だった。
その最大の根拠は、アメリカが中国、アジア支配の戦略のために、そして沖縄を共産主義の防波堤として気兼ねなく使うためであった。
マッカーサーが沖縄をアメリカの領土にする意図を持っていた証拠は、沖縄戦後史の研究家R・エルドリッジ博士が、その著書『沖縄問題の起源』で「マッカーサー覚書」として紹介している。この「マッカーサー覚書」については後で詳述する。
アメリカは、沖縄戦が終結する前に沖縄について綿密な調査研究をしていた。
マッカーサーは、沖縄人と日本人は違う民族であり、沖縄人は明治期以降武力で日本の植民地とされた被支配民族と言う捉えていた。
そのため収容された捕虜収容所でもはじめから本土兵と沖縄兵を分離するなど、本土と沖縄の対立を意図的に組織した。
このアメリカの意識的な本土・沖縄分断策は成功し、施政権返還後も一部のグループに受け継がれている。
以下に引用する大田前沖縄県知事の著書「沖縄の決断」の紹介文にこれが凝縮されている。
≪まぎれもなく、沖縄はかつて日本国の植民地であった。
古くは薩摩の過酷な搾取に支配され、太平洋戦争で沖縄県民は軍務に活用され、やがて切り捨てられ、そして卑劣にも虐待された歴史がある。
その意味では、沖縄戦のあとに上陸してきたアメリカ軍は沖縄にとって解放軍のはずだった。≫
(大田昌秀著「沖縄の決断」朝日新聞社刊)
米軍が沖縄に上陸した時点で米軍の侵攻作戦には、密かに分類した三つのカテゴリーがあった。
①「解放者」は、米軍であり正義と民主主義の伝道者。
②「侵略者」(沖縄を異民族として侵略)は、日本軍であり、独裁・侵略国家の先鋒
③「被侵略者」は、沖縄住民であり、残忍な日本軍の被害者
■掌返しの日本国民
マッカーサーが7年後日本を去るとき「鬼畜」は「親愛なるマッカーサー様」に様変わりしていた。
マッカーサーのもとには日本国中から感謝と惜別の念に満ちた数万通の手紙と贈り物が届けられていたと言う。
当時のNHKはその模様を次のように報じている。
「4月16日午前6時半、マッカーサー元帥は夫人、令息同伴でアメリカ大使館を出発、帰国の途に就きました。朝早くから詰めかけた人々が20万を超え、沿道をうずめ尽くしました。19発の礼砲とどろくうちを、車は羽田空港に到着。吉田首相と堅く握手を交わすマッカーサー元帥。手を振っていつまでも別れを惜しむ元帥夫人。いよいよ出発の時刻が迫りました。見送るリッジウェイ総司令官。愛機バターン号は静かに日本を離れ、一路アメリカに向かいました。」
マッカーサーに対する掌返しが最も甚だしかったのは朝日新聞だった。
「鬼畜米英」など日本国民を煽った朝日新聞は、マッカーサーの日本上陸と共にマッカーサー教徒に変身した。
マッカ―サの帰国時、朝日新聞は「われわれに民主主義、平和主義のよさを教え、日本国民をこの明るい道へ親切に導いてくれたのはマ元帥だった」(昭和26年4月12日)と報じた。 そして驚いたことには、朝日新聞社の長谷部忠社長は、マッカーサーをご神体にした「マッカーサー神社」を作ろうとしていた。
結局「マッカーサー神社」の建設は不首尾に終わったが、今考えると建設して欲しかった。 そして「平和憲法」と並んで世界遺産に登録して欲しかった。
■マッカーサーの置き土産-焚書坑儒
だが、マッカーサーが日本に残したものは「民主主義」や「言論の自由」の他に、秦の始皇帝並みの「焚書坑儒」があった。「焚書」では文字通りGHQにとって不都合な書籍が没収・処分されたが、「坑儒」とは、戦前からの知識人を震え上がらせた「公職追放」のことである。
特に戦後日本の言論界や思想界に悪影響を与えた「坑儒」は、教育追放である。
■マッカーサーの功罪
マッカーサーは当時のアメリカでも実施していなかった男女平等を始めとする数々の民主主義の理想を持ち込んだが、軍人でありながら何故このよう、現在でも類のない理想主義に満ちていたたのか。
その鍵をとく為に彼が日本に第一歩を印すまでの足跡を辿ってみる。
バターンの復讐
マッカーサー、この誇り高きエリート軍人はフィリピンでは日本軍に敗走の屈辱を味合わされた。
挌下と見下していた黄色民族の軍隊に敗走する事は彼の辞書には無かった。
ダグラス・マッカーサーは1880年1月26日アーカンソー州リトルロック生まれる。父親のアーサー・マッカーサー・ジュニア中将は南北戦争の退役軍人であり名誉勲章を受章している職業軍人家系だった。
1898年、アメリカ陸軍士官学校に入学し、1903年に陸軍少尉になり卒業した。その成績はアメリカ陸軍士官学校史上最高で、マッカーサーの取った成績以上の成績で卒業したものは未だに現れていない。
1942年5月7日、その誇り高きマッカーサーがフィリピン・コレヒドールで日本軍本間中将との戦いに敗れてオーストラリアに敗走する。
この屈辱の負け惜しみに「I shall return」(必ず戻る)という有名な言葉を残した。
彼の屈辱の敗走の2年後、彼より10歳若いアイゼンハワーがヨーロッパ戦線でノルマンディ作戦を指揮して世界的英雄になった。
後に米大統領となるアイゼンハワーは、一時マッカーサーの部下として補佐官を務めた時期もあり、軍人として必ずしもエリートコースを歩んでおらず一時は閑職で燻っていた時期もあった。
一方、マッカーサーは軍人のエリートコースを歩みながら、その巧みな雄弁術はむしろ政治家を志向し、戦後大統領候補にもなっている。
かつての部下のアイゼンハワーが連合国遠征軍最高司令官として「ノルマンディ作戦」を指揮し大成功を収めたニュースを忸怩たる思いで聞いていた。 そしてアイゼンハワーが戦後、アメリカ大統領になろうとは夢想もしていなかった。
日本占領までのマッカーサーはフィリピンでの屈辱を晴らす復讐の念に燃えていた。
それには日本の軍隊を徹底的に壊滅させる必要があった。
日本を手足のもぎ取られた子羊のように、二度と米国に反抗できない状態にしておく意図に燃えていた。
そのためには日本国憲法の設定、その中でも交戦権の否認は不可欠であった。
■マッカーサー 皇居を睥睨しながら執務をした■
マッカーサーは皇居に面した第一生命ビルの6階に占領軍の本部を構えた。
そこから皇居を見下ろして天皇の権威の上に君臨する全能の権力者となった。
日本の歴史上権力と権威を1人で独占して日本を統治した者は彼をおいて他に例が無い。
日本の歴史では朝廷の権威と幕府の権力は常に補完しあってきた。
マッカーサーと言えば日本に「自由と民主主義」を普及させた恩人とと見られている。
しかし彼が日本で最初に行ったことは「自由と民主主義」とは逆の「焚書坑儒」であった。
「焚書坑儒」とは中国の専売特許かと思ったらマッカーサーもこれを行った。
秦の始皇帝にも劣らぬ絶大な権力を振るったマッカーサーなら「焚書坑儒」もけして不思議ではない。
マッカーサー司令部は昭和21年3月に一通の覚え書きを出して、戦時中の日本の特定の書物を書物の存在すべきあらゆる場所から没収し、廃棄することを日本政府に指示した。
書物没収のためのこの措置は時間とともに次第に大がかりとなる。
昭和23年文部省の所管に移って、各都道府県に担当者が置かれ、大規模に、しかし、秘密裏に行わた。
没収対象の図書は7千7百余種に及んだという。
そのとき処理し易いように作成されたチェックリストが分厚い一冊の本として公開されている。
戦後のWar Guilt Informasion Programの一環であった私信にまで及ぶ『検閲』の実態はかなり知られている。
だが、数千冊の書物の『焚書』の事実はほとんどまったく知られていない。
チェックリストは、昭和57年に文部省社会教育局編として復刻され、やっと公開されるようになった。
失われた書物の内容を、殆んどの日本人は知らない。
つまり、先の大戦に関して、戦後の日本人は偏った情報を与え続けられ現在もそれが継続していることになる。
■「三年殺し」に潰された安倍政権■
マッカ―サーの「焚書」という荒業は彼の予想を遥かに越えて、60年経った現在でも日本の内部組織を破壊しつづけている。
マッカーサーの負の遺産である「戦後レジーム」。
それは「戦後民主主義」という形で今でも左翼マスコミの中に奥深く染み込んでいる。
その解消に果敢に挑んだ安倍前首相は、「戦後レジーム」そのものともいえるマスコミと左翼官僚によって見事に潰されてしまった。
復帰を阻止せよ!」~アメリカ軍 宣撫工作~ (2007年5月15日放映)
QAB琉球朝日放送http://www.qab.co.jp/okinawa-reversion/index.html
<沖縄が本土復帰した1972年5月。13年間、毎月発刊されてきた月刊誌がその歴史に幕を閉じました。その月刊誌は『守礼の光』。 沖縄の産業や文化、アメリカの文化などを紹介したカラー写真付きの雑誌で学校や公民館などに無料で配布されました。 『守礼の光』には、琉球の昔話も掲載されました。運玉義留、野底マーペー、空を飛んだ男・・・各地に伝わる昔話を集め、記事にしたのは沖縄のひとりの女性でした。女性は琉球文化を誇りに精力的に仕事を続け、各地を回っては口承されてきた物語を掘り起こしました。 雑誌を発行したのは、米国琉球列島高等弁務官府。しかし、それは表向きの発行元で、実際は「アメリカ陸軍・第7心理作戦部隊」が編集発行を行っていたのです。当時「第7心理作戦部隊」を知る者は殆どおらず、その存在はこれまでベールに包まれたままです。 部隊の任務はビラや放送などでアメリカ軍のアジア戦略をスムーズにする事。沖縄での仕事のひとつが『守礼の光』の発行でした。アメリカ軍は、琉球文化が色濃く表現されたその昔話の数々を大いに評価します。実はアメリカ軍にはある狙いがあったのです。 「沖縄は日本にあらず」ーアメリカ軍は日本とは違う独特の琉球文化を強調して、沖縄の人達の日本復帰への思いを逸らせようとしたのです。 >
第7心理作戦部隊が行った事は今で言えば広報活動のようなことだが、戦火で荒らされた沖縄にとっては「宣撫工作」としての効果は充分あったのだろう。
先ず食い物を食わしてモノを与え、それから飴と鞭で洗脳するのは情報戦の常道。
洗脳については「撫順戦犯管理所」からの帰還兵が有名である。
1950年にシベリアで捕虜となっていた日本人のうち約1100人が中国にひきわたされ、撫順、および太原で収容された。この施設の一つが撫順戦犯管理所である。
問題点
日本人が釈放されたのは1956年以降であったが、釈放された日本人捕虜はみな中国を賛美するようになっていた。これが「撫順の奇蹟」と中国では称されている。しかし釈放された人々の言動から、洗脳行為が行われたのではないかという疑いがもたれている。
(ウィキペディア)
沖縄人をあえて琉球人と呼び、<日本は琉球を侵略した異民族>と、沖縄人を洗脳した。
これらアメリカの工作は現在も一部ウチナンチュに受け継がれ、琉球独立という幻想は今でも息づいている。
アメリカが最も嫌ったサヨクの反日工作に琉球独立が利用されている事実は歴史の皮肉とも言えよう。
アメリカが沖縄を日本から分断する作戦だったことは沖縄上陸時から実行されていた。
これについては下記エントリで詳しく述べている。
さらに「洗脳工作」は現在でも県知事が記者の引っ掛け質問にあえて「ウチナンチュは日本人」と答えねばならぬほどねじれた形で後を引いている。
沖縄戦で、米軍は上陸の前、沖縄中に「鉄の暴風」を吹き荒れさせ、沖縄住民の生命と肉体に壊滅的打撃を与えた。
米軍が上陸した後、降り注ぐ砲弾の合間に空から舞い降りてきたのは、膨大な数の「鉄の爆弾」ならぬ「紙の爆弾」であった。
炸裂する砲弾に替わる「紙爆弾」は、今度は沖縄住民の心を破壊していった。
沖縄戦で米軍は沖縄住民の身体のみならず心も共に破壊したのだ。
太田昌秀著『沖縄戦下の米日心理作戦』は、米軍が沖縄戦で行った心理作戦ついて、次のように述べている。
<さる太平洋戦争末期の沖縄戦では、米軍が空から撒いた一枚の宣伝ビラ読んで命が助かった人もいれば、それを所持していただけでスパイの汚名を着せられ命を落としたものもいた。このように戦時中、軍人も民間人も一枚の宣伝ビラの対応いかんによって文字どおり、生死を分かったのである。 一片の紙片は、まさに「紙爆弾」そのものだった。 沖縄戦で日本軍は、敵が散布した宣伝ビラを拾ったまま警察や憲兵に届けないで所持しているものは「銃殺に処す」と厳命を下していた。>(『沖縄戦下の米日心理作戦』太田昌秀 岩波書店)
「紙爆弾」といわれる宣伝ビラは、60数万枚にも及ぶ膨大な数量が、小さな島にばら撒かれた。
その種類も日本軍用、沖縄住民用と内容が別れ、
目的別に更に20種類に細分されるという徹底ぶりだった。
だが、米軍の心理作戦部隊が最も重要視したのは、
本土出身の将兵と地元住民との仲を疑心暗鬼の状態にして、
お互い離反させることであった。
沖縄住民と日本兵との間に楔を打ち込むことを目的にした宣伝ビラの例には、次のようなものがある。
沖縄住民用ビラ
<この戦争は、沖縄の皆さんの戦争ではありません。貴方たち沖縄人は、内地人の手先に使われているのです。皆さんは、彼ら内地人の犠牲になっているのではありませんか。(略)>(『沖縄戦した米日心理作戦」)
このような沖縄人用の宣伝ビラを読むと、60数年前に米軍が書いたビラながら、その呪縛は現在の沖縄にも生きており、今でもどこかで良く見るアジ文である。














 ⇒最初にクリックお願いします
⇒最初にクリックお願いします



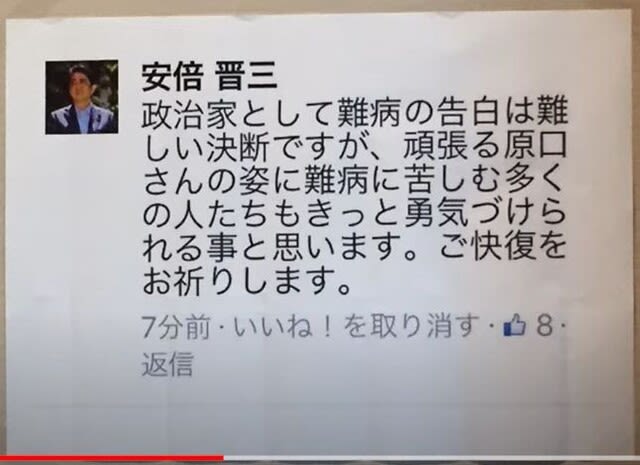











志位さんがコクソ―に反対しようが、志位さんが個クソ―を食らおうが個人の勝手だが、
こんな多様性、いやだ!
78星雲 M