映画祭の初日に見る映画は、初めて入った食堂で注文した料理を食べるようなものだ。これが、うまいかまずいかは、この食堂の善悪を印象付けてしまいがちである。だから、よほどプログラム構成も慎重さを必要とするように思う。いや、観客の反応にいちいち神経を使って観客に媚びる必要はないといいう姿勢も大事なことかもしれない。ただ、見るほうにとっては、おもしろい映画に当たりたいという意識は強い。そこで、タイムテーブルを眺め、上映作品のかんたんな説明を見て、それぞれのタイトルを眺めたり、解説を読む。それで選ぶべき映画を選択をする。しかし、当たるも当たらないもわからない。当たればラッキーということとなる。もろに解説に沿って内容を想像すると、まったく別のものだったりする。解説は、この選択ではむしろ、邪魔になる。どうも過去18年の映画祭体験から、解説を信じるな、それがベターだと思うようになってきた。とくに近年の邦画のタイトルで、内容を想像することは間違いの元になる。料理は食ってみる、映画は見てみるしか、ぼくにっとっておもしろいか、つまらないかはわからない。プログラムで選んではみても、当たるも八卦、当たらぬも八卦の運次第ということになりがちだ。しかし、解説は後でもう一度かならず読む。その映画成立を知ることや、内容の記憶や、理解をするのに有効であるからだ。とくに小冊子して、入館時に配布されるプログラムは、資料としても貴重である。タイムテーブルもプログラムも、その点では実行委員会の努力に感銘している。
ということで、最初に選んだ映画は「ミケランジェロの暗号」であった。このときに「愛の勝利をムッソリーニを愛した女」でなくて良かった。両作品とも、ヒットラーとムッソリーニのファシストの時代を背景にした物語であるが、前者がはるかにおもしろい。後者は、おもしろくない。なぜおもしろくないのか、これは後で述べる。
だが、「ミケランジェロの暗号」のおもしろさも、ストリーとしては、オーストリア映画というけれども、ハリウッド映画のようなサスペンション・アクション映画であった。ストリーも展開も明快・単純なもので、ネタも途中でわかる。おそらくハリウッド映画の一作だとしたら、平凡な三流作品にすぎない映画であったろうと思う。これが、ハリウッド映画でなかったところが、おおいに興味をそそったのである。物語が、深みをたたえてくる。それがヨーロッパの風土である。暗い空に爆音が響く。夜空に航空機が接近してくる。どういうわけか、双眼鏡で追跡している男がいる。と男は撃てと叫ぶ。レジスタンスが、野原に待ち伏せしていたのだ。かれらの小銃が、いっせいに火を吹く。すぐに飛行機は撃墜される。1940年代、飛行機は小銃で落せたのだと、不思議な感慨がぼくをつつみこんた冒頭シーンであった。これがハリウッド映画であったら、紙芝居になるのだが、ヨーロッパの風土では、あの陰鬱さが、現実感を生み出してくる。ナチ、ユダヤ人迫害、レジスタンスと、生々しいレアル感と戦争の傷跡が観客を惹き付ける。それに登場人物を演じる俳優たちが、名もしられてないから、かえって登場人物に存在感がある。これらが一体となってこの平凡な内容にある重さと深さを与えて、かつエンターテイメントの愉しみをも満喫させてくれる。石像の画廊、石畳の光、服装、彫像、絵画と、その歴史の重さ伝統などがもたらす、各シーンの映像美に、ぼくはストリー展開よりも惹かれていたのである。
これがヨーロッパで、ハリウッドでないのだと再認識しながら、どこかで、この典型的ヨーロッパ的雰囲気には、飽きも感じるのであった。今やアジア諸国より慣れ親しんで、新鮮度が薄れてきる。別に珍しくも無いように思えだした。年金生活者でも、シーズンごとにイタリア、スペインの南欧からドイツ、デンマーク、イギリスの北欧まで旅行をひんぱんにするようになった。そして、北欧から南欧まで何処に行っても変わらない市街、石づくりであるがゆえに重々しい住居、孤立して閉鎖的な家並み、あらゆる場所に、リアルな肉体をもつ裸体彫刻や、幾何学模様の庭園、これらが、どうにかならぬのかと
重苦しくてしかたがないようになってきているのだ。
イタリア映画、フランス映画、ドイツ映画、英国映画と、1960年代ころまでは、ヨーロッパ映画はそれぞれに忘れがたい名作の数々をぼくらに提供してきた。映画産業が衰退してきて、ヨーロッパでは映画の製作が衰亡していき、やたら閉鎖的で芸術と言う名の難解な映画が製作されだした。この映画はその範疇でなくて、ハリウッド的なものをヨーロッパで制作したもので、マカロニーウエスタンか、ヨーロッパ寿司の類になっている。これを越えるものではないのだ。解説によると、昨年のベルリン国際映画祭(第61回)で大好評を博したとあるが、こんな程度でよろこべるとは、ヨーロッパでの映画の意識の古さを、思えてならない。このままでは、映画の復活はまだまだヨーロッパでは遠いのかもしれない。
つぎに、おもしろくないといった「愛の勝利を ムッソリーニを愛した女」を話してみよう。この映画でおもしろくない点である。まずなによりも、この映画でいいたいことはなんなのかがわからないということである。したがって、ムッソリーニに人目ぼれして、すべてを捧げてしまったヒロインの愛がなんのかがわからないのだ。つまり人間が描かれていない。それは人間として、共感を感じることができないのである。冒頭、反政府のデモ決行の集会で演説する、過激なそして、哲学的な理性主義、神は存在しないというメッセージに、魂を吸い取られた若き美貌のヒロインがスポットを浴びる。その後の
ムッソリーニとイーダの恋の進行も、葛藤も無ければ、深まりも展開しない。すべては冒頭の衝撃的迫力の革命家の存在だけが、彼女を支配しつつけていく。
この映画の主題をあえて探そうとしていくと、辛うじて主題と思えるのは、ファッシズムという魔力の真実を描こうとしてのであろうかとも思える。そうだとしたら、主人公の若きムッソリーニは、人間というより、怒号を張り上げて大衆煽動を繰り返す、ロボットのような役割にしかみえない。おまけに
その情念を性的魅力に変える肉体は、ほんもののムッソリーニとは、天と地ほどに違う。ほんものは不細工で狆のようなのに、この二枚目ぶりが、どこでどう狆になるのかがわからない。イーダの愛は、精神的な愛というより、抑えがたい性的魅力、情欲への抗しがたい衝動に貫かれている。彼女は偉大な首相という言葉を、離別の後で回りに語りつづける。それは、オームの女が麻原 彰晃にとりつかれたのとどう違うのかと思えたりする。あるいは、性的衝動を制御できない、ストーカーかとも思える。こういうようにヒロイン・ベニートの人間像が決められない。主人公はブッソリーニはたんなる機械にしかかじられないのであった。だから、そこに悲劇もないし、「愛の勝利を」とは、たいした意味はない。男を情欲で捕らえるという程度のことである。この映画は成人指定になっている意味もわかる。しかし、この程度で成人指定とは、なんか時代錯誤の感じさへするのである。どこをつついてもおもしろくないえいがであったのだ。イタリアもアメリカもなぜ批評家賞を浴びせたのか、欧米の映画評のつまらなさをあらためて感じさせる。
ということで、最初に選んだ映画は「ミケランジェロの暗号」であった。このときに「愛の勝利をムッソリーニを愛した女」でなくて良かった。両作品とも、ヒットラーとムッソリーニのファシストの時代を背景にした物語であるが、前者がはるかにおもしろい。後者は、おもしろくない。なぜおもしろくないのか、これは後で述べる。
だが、「ミケランジェロの暗号」のおもしろさも、ストリーとしては、オーストリア映画というけれども、ハリウッド映画のようなサスペンション・アクション映画であった。ストリーも展開も明快・単純なもので、ネタも途中でわかる。おそらくハリウッド映画の一作だとしたら、平凡な三流作品にすぎない映画であったろうと思う。これが、ハリウッド映画でなかったところが、おおいに興味をそそったのである。物語が、深みをたたえてくる。それがヨーロッパの風土である。暗い空に爆音が響く。夜空に航空機が接近してくる。どういうわけか、双眼鏡で追跡している男がいる。と男は撃てと叫ぶ。レジスタンスが、野原に待ち伏せしていたのだ。かれらの小銃が、いっせいに火を吹く。すぐに飛行機は撃墜される。1940年代、飛行機は小銃で落せたのだと、不思議な感慨がぼくをつつみこんた冒頭シーンであった。これがハリウッド映画であったら、紙芝居になるのだが、ヨーロッパの風土では、あの陰鬱さが、現実感を生み出してくる。ナチ、ユダヤ人迫害、レジスタンスと、生々しいレアル感と戦争の傷跡が観客を惹き付ける。それに登場人物を演じる俳優たちが、名もしられてないから、かえって登場人物に存在感がある。これらが一体となってこの平凡な内容にある重さと深さを与えて、かつエンターテイメントの愉しみをも満喫させてくれる。石像の画廊、石畳の光、服装、彫像、絵画と、その歴史の重さ伝統などがもたらす、各シーンの映像美に、ぼくはストリー展開よりも惹かれていたのである。
これがヨーロッパで、ハリウッドでないのだと再認識しながら、どこかで、この典型的ヨーロッパ的雰囲気には、飽きも感じるのであった。今やアジア諸国より慣れ親しんで、新鮮度が薄れてきる。別に珍しくも無いように思えだした。年金生活者でも、シーズンごとにイタリア、スペインの南欧からドイツ、デンマーク、イギリスの北欧まで旅行をひんぱんにするようになった。そして、北欧から南欧まで何処に行っても変わらない市街、石づくりであるがゆえに重々しい住居、孤立して閉鎖的な家並み、あらゆる場所に、リアルな肉体をもつ裸体彫刻や、幾何学模様の庭園、これらが、どうにかならぬのかと
重苦しくてしかたがないようになってきているのだ。
イタリア映画、フランス映画、ドイツ映画、英国映画と、1960年代ころまでは、ヨーロッパ映画はそれぞれに忘れがたい名作の数々をぼくらに提供してきた。映画産業が衰退してきて、ヨーロッパでは映画の製作が衰亡していき、やたら閉鎖的で芸術と言う名の難解な映画が製作されだした。この映画はその範疇でなくて、ハリウッド的なものをヨーロッパで制作したもので、マカロニーウエスタンか、ヨーロッパ寿司の類になっている。これを越えるものではないのだ。解説によると、昨年のベルリン国際映画祭(第61回)で大好評を博したとあるが、こんな程度でよろこべるとは、ヨーロッパでの映画の意識の古さを、思えてならない。このままでは、映画の復活はまだまだヨーロッパでは遠いのかもしれない。
つぎに、おもしろくないといった「愛の勝利を ムッソリーニを愛した女」を話してみよう。この映画でおもしろくない点である。まずなによりも、この映画でいいたいことはなんなのかがわからないということである。したがって、ムッソリーニに人目ぼれして、すべてを捧げてしまったヒロインの愛がなんのかがわからないのだ。つまり人間が描かれていない。それは人間として、共感を感じることができないのである。冒頭、反政府のデモ決行の集会で演説する、過激なそして、哲学的な理性主義、神は存在しないというメッセージに、魂を吸い取られた若き美貌のヒロインがスポットを浴びる。その後の
ムッソリーニとイーダの恋の進行も、葛藤も無ければ、深まりも展開しない。すべては冒頭の衝撃的迫力の革命家の存在だけが、彼女を支配しつつけていく。
この映画の主題をあえて探そうとしていくと、辛うじて主題と思えるのは、ファッシズムという魔力の真実を描こうとしてのであろうかとも思える。そうだとしたら、主人公の若きムッソリーニは、人間というより、怒号を張り上げて大衆煽動を繰り返す、ロボットのような役割にしかみえない。おまけに
その情念を性的魅力に変える肉体は、ほんもののムッソリーニとは、天と地ほどに違う。ほんものは不細工で狆のようなのに、この二枚目ぶりが、どこでどう狆になるのかがわからない。イーダの愛は、精神的な愛というより、抑えがたい性的魅力、情欲への抗しがたい衝動に貫かれている。彼女は偉大な首相という言葉を、離別の後で回りに語りつづける。それは、オームの女が麻原 彰晃にとりつかれたのとどう違うのかと思えたりする。あるいは、性的衝動を制御できない、ストーカーかとも思える。こういうようにヒロイン・ベニートの人間像が決められない。主人公はブッソリーニはたんなる機械にしかかじられないのであった。だから、そこに悲劇もないし、「愛の勝利を」とは、たいした意味はない。男を情欲で捕らえるという程度のことである。この映画は成人指定になっている意味もわかる。しかし、この程度で成人指定とは、なんか時代錯誤の感じさへするのである。どこをつついてもおもしろくないえいがであったのだ。イタリアもアメリカもなぜ批評家賞を浴びせたのか、欧米の映画評のつまらなさをあらためて感じさせる。











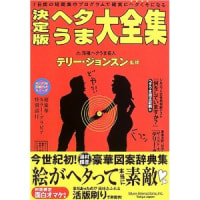












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます